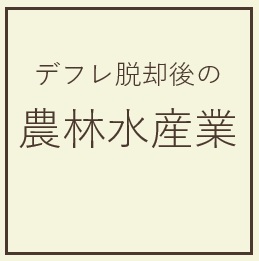この記事は、Gemini Deep Research にリサーチして執筆してもらったレポートです。
生成AIの書いた記事を修正すること無く、そのまま掲載しています。
一般常識として、「生成AIの書く記事には、ハルシネーションによる間違いが含まれている可能性がある」事を踏まえて記事を読んでください。
生成AIは完璧ではありません。
この記事の prompt は以下の文書になります。
現在の日本の農林水産業における、デフレ脱却と人手不足による経営状況をリサーチしてください。
特に、収益率の変化、商流変更や事業再編・経営統合や、人材確保の方法の変更、倒産状況などの動向も知りたいです。
また、人手不足を受けての設備投資・IT活用などの動向もリサーチしてください。
わからない事は、わからないと回答してください。
ハルシネーションは避けてください。
以降は、全て Gemini Deep Research の書いたレポートです。
岐路に立つ日本の第一次産業:経営危機と戦略的適応に関する調査報告
要旨
日本の第一次産業は、デフレ脱却に伴うコストインフレと、深刻化する構造的な人手不足という二つの巨大な圧力に挟まれ、重大な転換点に立たされている。本報告書は、この二つのマクロ経済的要因が農業、林業、水産業の各分野に与える深刻な影響を分析し、倒産件数の増加や収益性の圧迫といった厳しい経営実態を明らかにする。同時に、この危機的状況に対応すべく、強靭な事業者たちが進める戦略的な転換についても詳述する。具体的には、スマート技術の導入による生産性向上、事業承継と規模拡大を目的としたM&Aによる事業再編、そして多様な人材活用モデルの構築といった適応戦略である。分析の結果、これらの戦略的投資と変革を遂行できる事業者と、そうでない事業者との間で構造的な二極化が進行しており、日本の食料および資源生産の未来像が根本から再構築されつつあることが示唆される。
第1章 二重の圧力:デフレ脱却後のコスト高騰と労働力減少の構造
本章では、日本の第一次産業が直面する経営環境を規定する二つの根本的な要因、すなわちコスト構造のインフレ圧力と、不可逆的な人口動態に起因する労働力不足について分析する。これら二つの力は独立して存在するのではなく、相互に作用し合い、コストと収益の両面から事業者を圧迫する「収益性のはさみ(プロフィタビリティ・シザーズ)」とも呼ぶべき状況を生み出している。
1.1 デフレ脱却とコストインフレの波及
長年のデフレ経済からの転換は、日本経済全体にとっては好機である一方、第一次産業の経営者にとっては、生産コストの急激な上昇という形で直接的な打撃となっている。特に、燃料、肥料、飼料といった生産に不可欠な資材の価格高騰は、収益構造を根底から揺るがしている。
政府もこの問題を重視しており、農林水産省が公表した「令和6年度 食料・農業・農村白書」では、「合理的な価格の形成」が特集テーマの一つとして掲げられた 1。これは、生産コストの上昇分を製品価格へ適切に転嫁することが、もはや個々の事業者の経営努力の問題ではなく、国家的な戦略課題として認識されていることを示している。
しかし、政策目標と現場の実態には大きな乖離が存在する。ある調査によれば、農業事業者の55%がコスト上昇分を価格に転嫁できておらず、価格改定を実施した事業者の中でも約9割がコスト上昇分を完全にはカバーできていないと回答している 4。この価格転嫁の困難さが、経営体力を直接的に削り取っている。
その結果は、倒産件数の増加という形で明確に表れている。帝国データバンクの調査によると、物価高を直接的な要因とする「物価高倒産」は全産業で増加傾向にあり、2024年には過去最多の933件に達した 6。この傾向は農業分野で特に顕著であり、2023年度の農業関連事業者の倒産件数は過去最多の81件を記録。その背景には、肥料、飼料、そしてきのこ栽培におけるおがくずなどの原材料費、施設維持に関わる燃料費の高騰が主要因として挙げられている 8。さらに、コロナ禍で導入された実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)の返済が本格化し、多くの事業者にとって新たな資金繰りの重荷となっていることも、この苦境に拍車をかけている 6。
1.2 人口動態の崖:労働力危機の定量分析
コストインフレと並行して、日本の第一次産業はより構造的で深刻な問題、すなわち労働力の絶対的な不足に直面している。これは単なる景気循環による人手不足ではなく、少子高齢化という不可逆的な人口動態に根差した構造的危機である。
統計データはこの危機的状況を明確に示している。基幹的農業従事者数は、2010年の205.1万人から2020年には136.3万人へと、わずか10年で34%も減少した 11。この減少傾向は止まらず、2021年には130.2万人となっている 12。労働市場の需給も極めて逼迫しており、2023年度の農林漁業における有効求人倍率は1.22倍と、全産業平均の1.12倍を上回り、求人数が求職者数を大幅に超過する「売り手市場」が常態化している 13。
この問題は、就業者の高齢化と後継者不足によってさらに深刻化している。多くの農家が70歳以上の高齢者によって運営され、一人で作業を担うケースも少なくない 14。事業を継承する人材が見つからないことは、事業者の高齢化や不測の事態(病気・死亡)が発生した際に、事業継続を断念せざるを得ない状況を直接的に引き起こす。これが「後継者難倒産」であり、全産業で過去最高水準で推移している 6。農林水産業においては、事業承継問題が廃業やM&Aの最も主要な動機の一つとなっている 18。
これらの要因が複合的に絡み合い、労働力の確保が困難であることを直接の原因とする「人手不足倒産」も急増しており、2024年には初めて300件を超え、過去最多を更新した 6。
これら二つの圧力、すなわちコストインフレと労働力不足は、第一次産業の経営を両側から締め付ける「はさみ」のように機能している。コスト上昇が利益を圧迫する一方で、労働力不足は生産規模の拡大を阻み、ひいては売上向上の機会を奪う。この二重の圧力下で、事業者はかつてないほどの経営判断を迫られている。さらに、これらの問題は相互に連関し、悪循環を生み出している。コスト高騰で収益性が悪化した事業は、後継者にとって魅力的な継承先とはならず、「後継者難」を助長する。そして、後継者や働き手が見つからない「人手不足」の状態では、コスト高を吸収するための規模拡大や省力化投資もままならず、結果として「物価高倒産」のリスクが高まる。このように、「物価高」「人手不足」「後継者難」を要因とする倒産は、それぞれが独立した事象ではなく、密接に絡み合った構造的な問題の現れなのである。
表1:日本の第一次産業における労働力統計の比較(2021年-2023年頃)
| 項目 | 農業 | 林業 | 水産業 |
|---|---|---|---|
| 基幹的就業者数 | 130.2万人 (2021年) 12 | 3,333人 (2023年新規就業者) 21 | 15.1万人 (2018年) 22 |
| 平均年齢 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 65歳以上の割合 | 約70% 23 | 不明 | 不明 |
| 新規就業者数(年間) | 約5.2万人 (2021年) | 778人 (2023年、「緑の雇用」事業経由) 21 | 約70%が他産業からの新規参入者 25 |
| 外国人材(特定技能・技能実習) | 約5.4万人 (2023年末時点) | 234人 (2024年10月末時点) 21 | 増加傾向 27 |
注:各統計は調査年や定義が異なるため、直接的な比較には注意が必要。林業の就業者数は新規就業者数のみ記載。水産業の就業者数は2018年のデータ。
第2章 農業分野:経営不振とデジタル化による再生の狭間で
本章では、第1章で提示したマクロ環境の分析を農業分野に特化して適用し、収益性や事業継続性への具体的な影響をデータに基づいて検証する。その上で、この厳しい環境を乗り越えるために事業者が採用している三つの主要な生存戦略、すなわち「ビジネスモデルの転換」「労働力確保の革新」「テクノロジーの活用」について、詳細に分析する。
2.1 圧迫される利益:農業経営の収益性分析
生産コストの高騰は、農業経営の収益性を直接的に圧迫している。農林水産省の「農業経営統計調査」によれば、2022年の全農業経営体において、農業粗収益は前年比8.2%増加したものの、農業経営費は飼料費や光熱動力費の高騰により12.2%とそれを上回るペースで増加した。その結果、農業所得は21.7%もの大幅な減少に見舞われた 29。2023年には作物価格の上昇などにより所得は16.3%回復したが、経営費も依然として6.2%増加しており、収益性が外部環境の変動に極めて脆弱であることが示されている 30。
この影響は、特に畜産経営において深刻である。例えば、肉用牛肥育経営では、2023年に飼料費が過去最高を記録し、黒毛和種の場合、総生産コストの33.4%を占めるに至った。生産コストが上昇する一方で販売価格は下落し、利益幅は著しく圧縮された 31。その結果、2023年には肉用牛農家の42%が赤字経営に陥るという異常事態となった 32。酪農経営においても、2022年に赤字経営体の割合が急増するなど、同様の傾向が見られる 32。
2.2 倒産件数の急増とその背景
収益性の悪化は、事業継続の断念、すなわち倒産の増加に直結している。帝国データバンクの調査によれば、2023年度の農業関連事業者の倒産は81件に達し、前年度の64件を大幅に上回り過去最多を更新した 8。
その主要因は、肥料、飼料、燃料といった生産資材価格の高騰であると明確に指摘されている 8。特に、暖房や照明などのエネルギーコストへの依存度が高い施設野菜農業(きのこ栽培含む)では、倒産がそれぞれ118.2%、160.0%と爆発的に増加しており、コスト構造の脆弱性が浮き彫りとなった 8。
注目すべきは、倒産した事業者のうち27.2%が業歴5年~10年未満の比較的新しい事業者であった点である 8。これは、コロナ禍やコスト高騰の危機が到来する直前に創業した事業者が、十分な財務基盤を構築する前に外部からの連続的なショックとゼロゼロ融資などの支援策の終了に直面し、持ちこたえられなかったことを示唆している。
表2:農業および水産業における倒産の要因分析(2023年度-2024年度の動向)
| 項目 | 農業 | 水産業・養殖業 |
|---|---|---|
| 倒産件数 | 81件 (2023年度、前年度比26.6%増) | 27件 (2025年1-8月、前年比1.5倍ペース) 33 |
| 主要因の内訳 | ||
| コスト高騰 | 主要因。特に肥料、燃料、原材料費 8 | 主要因。特に燃料費、飼料費 35 |
| 人手不足 | 全産業で過去最多を更新しており、農業も影響大 6 | 深刻な課題。特に外国人材への依存度が高い |
| 後継者難 | 倒産・廃業の主要因の一つ | M&Aの主要な動機 18 |
| その他 | ゼロゼロ融資の返済負担 8 | 赤潮などの環境変動による被害 25 |
注:データは異なる調査機関・期間に基づいているため、直接的な比較には限界がある。
2.3 生存への道筋 I:ビジネスモデルの転換
このような厳しい環境下で、事業者は生き残りをかけてビジネスモデルそのものの変革を迫られている。その動きは主に「事業再編による規模拡大」と「流通チャネルの変革」の二つの方向に集約される。
2.3.1 事業再編と承継(M&A)
後継者不足と規模の経済の追求という二つの課題を同時に解決する手段として、M&A(合併・買収)の活用が活発化している。農業を含む食品関連分野のM&A市場は盛況であり、2025年の取引件数は既に前年を上回るペースで推移している 38。その主な動機は「後継者不足」と「経営の安定化」である 23。
具体的な事例としては、業務用食品卸が野菜農家を買収して生産から販売までの一貫体制(垂直統合)を構築するケース 39、IT企業がブランドトマト農園を買収し、テクノロジーを注入して生産性の向上を図るケース 40、野菜苗生産大手が競合他社を買収して事業基盤を強化し、シナジーを追求するケース 38 などが挙げられる。これらの事例は、M&Aが単なる高齢経営者の出口戦略ではなく、異業種の知見を取り込み、事業を近代化・成長させるための戦略的な手段として機能していることを示している。
2.3.2 中間流通の排除(D2C Eコマースとブランディング)
従来の卸売市場経由の流通では価格決定権が弱く、コスト上昇分を転嫁しにくい。この構造から脱却するため、生産者が消費者に直接販売するD2C(Direct-to-Consumer)モデルへの移行が進んでいる。「ポケットマルシェ」や「食べチョク」といったオンラインプラットフォームの利用が拡大している 41。
しかし、単にオンラインストアを開設するだけでは成功はおぼつかない。成功事例に共通するのは、巧みなブランディングとコミュニケーション戦略である。
- **「しあわせスイカ農園」**は、独自品種のスイカを開発し、その栽培への情熱やこだわりをウェブサイトやSNSで物語として発信。発売前に消費者の期待感を醸成することで、発売と同時に完売するほどの人気を獲得している 41。
- **「沖縄かんな農園」**は、Facebookを活用して3人家族で営む農園のストーリーを伝え、消費者とのコミュニティを形成。このダイレクトなエンゲージメントが奏功し、SNSを開始した初年度に売上を218%増加させた 43。
これらの成功戦略の核心は、SNS(視覚に訴えるInstagram、速報性のあるX(旧Twitter)、深い物語を伝えるYouTubeなど)を駆使してブランドを構築し、消費者との個人的なつながりを築くことにある 44。これにより、価格以上の価値を伝え、従来の流通構造がもたらす利益圧迫から脱却することが可能となる。
2.4 生存への道筋 II:労働力の再創造
労働力の絶対数が減少する中で、事業者は従来の雇用形態にとらわれない、新たな労働力確保の道を模索している。
2.4.1 外国人材への依存構造
外国人労働力への依存は年々高まっている。技能実習制度と特定技能制度を合わせた農業分野の外国人材の総数は、2023年12月末時点で約54,000人に上り、特に特定技能外国人数は2024年6月には約28,000人へと急増している 2。これはもはや一時的な労働力の補完ではなく、農業労働力の中核をなす構造的な要素となっていることを示している。一方で、技能実習制度から新たな「育成就労制度」への移行が予定されており、受入コストの増加や、転籍要件の緩和による人材流出リスクの増大といった新たな課題も懸念されている 49。
2.4.2 「農福連携」による新たな担い手確保
地域の労働力を確保する新たなモデルとして「農福連携」(農業と福祉の連携)が注目を集めている。農福連携に取り組む主体数は増加傾向にあり、2022年度には前年度から938増加し、総数5,509に達した 50。
その成功事例として、静岡県の京丸園株式会社が挙げられる。同社は20年以上にわたり、現在25名の障害を持つ従業員を通年雇用している。成功の鍵は、障害を持つ従業員に単純作業を割り当てるのではなく、個々の能力や特性に合わせて作業プロセスを再設計し、専用の治具を開発したり、補助機械を導入したりする点にある。これにより、障害を持つ従業員が難易度の高い作業を担うことが可能となり、農園全体の生産性が向上、毎年黒字を計上する優良経営を実現している 51。他の事例でも、種まきのような反復作業や、いちごの葉かきのような細やかな作業など、障害の特性と作業内容を緻密にマッチングさせることで、障害者が貴重な戦力となっていることが示されている 53。
2.5 生存への道筋 III:テクノロジーによる生産性革命
労働力不足を補い、生産性を向上させるための切り札として、スマート農業への投資が加速している。
2.5.1 市場の拡大と導入状況
日本のスマート農業市場は急速に拡大しており、2024年度の331億円から2029年度には708億円規模に達すると予測されている 54。世界市場も年平均成長率12%以上での成長が見込まれており 56、強力な投資と導入のモメンタムを示している。日本国内では、2023年時点で全農業経営体の26.1%が何らかの形でデータを活用した農業を実践しており、その割合は着実に増加している 55。
2.5.2 導入事例と投資対効果(ROI)
- 水管理の自動化:水田の水門管理システムを導入したある農家では、見回りのための労働時間が大幅に削減されただけでなく、最適な水管理によって雑草が減少し、初年度の収量が1割以上増加した 58。
- データ駆動型栽培:宮崎県の施設園芸農家では、ハウス内の温度や湿度をセンサーで管理し、データを活用することで、平均単収が大幅に増加。投資コストを約1年で回収する成果を上げた。また、熟練者でも10年かかるとされる収量を、新規就農者がデータを活用することで数年で達成した事例も報告されている 58。
- 作業の自動化:ドローンによる農薬散布や、GPSを搭載した自動運転トラクターの導入が進んでおり、一人の作業者がより広大な面積を管理することを可能にし、人手不足に直接的に対応している 12。
- 投資回収:初期投資は大きな障壁となるが、ある試算では500万円の投資が人件費削減と収量増加によって約4年で回収可能とされている 59。政府も補助金や税制優遇措置によってこれらの投資を後押ししている 60。
農業分野の現状を俯瞰すると、均一な衰退ではなく、明らかな「二極化」が進行していることがわかる。一方では、コスト圧力に耐えきれず倒産に至る小規模・新規事業者が過去最多を記録している。他方では、テクノロジーへの大型投資、M&Aによる戦略的な規模拡大、そして洗練されたブランディングによるD2C市場の開拓といった手段を駆使して成功を収める、新たな農業経営体の姿が浮かび上がる。この二極化は、伝統的な家族経営モデルから、より大規模で、技術集約的、かつ市場志向の企業的経営モデルへの構造転換が加速していることを示唆している。
さらに、これらの生存戦略は個別に存在するのではなく、相互に連関している。例えば、スマート農業技術を導入するための高額な初期投資を賄うために、M&Aによる規模拡大や外部資本の導入が必要となる場合がある。そして、その技術によって生産された高品質な農産物の価値を最大化するために、独自のブランドを構築し、D2Cチャネルで販売するという流れが生まれる。このように、事業再編、技術革新、ビジネスモデル変革は、しばしば一つの統合された成長戦略として実行されており、成功のためには断片的な対応ではなく、全体最適を目指す包括的なアプローチが不可欠となっている。
第3章 林業分野:根深い構造問題への挑戦
林業分野は、農業以上に根深い構造的課題を抱えている。長い投資回収期間、険しい地形での作業、そして極めて深刻な労働力不足といった問題が、セクター全体の収益性を圧迫している。ここでは、林業が直面する特有の困難と、その打開策として期待されるテクノロジー活用や事業再編の動向について分析する。
3.1 困難な事業環境
林野庁の「令和6年度 森林・林業白書」によれば、林業は極めて小規模かつ細分化された所有構造が特徴であり、林家(山林所有世帯)の88%が10ha未満の山林しか保有していない 21。このような所有構造は、効率的な大規模施業の展開を著しく困難にしている。
労働力不足は他のどの産業よりも深刻かもしれない。政府は「緑の雇用」事業などを通じて新規就業者の確保に努めているが、2023年度の実績は778人にとどまり、急速に高齢化する労働人口を補うには程遠い 21。そのため、特定技能や技能実習制度を通じた外国人材への期待が高まっている 21。
収益性の低さも大きな課題である。20ha以上の山林を保有する個人経営体の年間林業所得は平均でわずか145万円、法人経営体でも営業利益は平均279万円と、再投資や人材確保に必要な収益を確保できているとは言い難い状況にある 21。林業に関連する建設業などでは、資材高や人手不足を背景とした倒産が増加しており、林業経営体も同様の圧力に晒されていると考えられる 6。
3.2 事業継続に向けた再編(M&A)
高い後継者不在率と細分化された所有構造という背景から、M&Aや事業承継は、事業の継続と成長のための不可欠なツールとなっている。
具体的な事例を見ると、その動機は多様である。あるホールディングスはサプライチェーン確保のために林業経営体を買収し 62、エネルギー関連企業は木質バイオマス発電事業を強化するために林業会社を傘下に収めた 63。また、ある投資会社は経営戦略の見直しの一環として、30年以上運営してきた林業事業を土地開発会社へ譲渡した 64。これらの事例は、同業間での水平統合だけでなく、エネルギーや建設といった川下産業との垂直統合を目的としたM&Aが活発に行われていることを示している。
3.3 近代化への挑戦:スマート林業の推進
政府は、生産性と安全性を向上させ、減少する労働力にとって魅力ある産業へと転換させるため、「スマート林業」の推進を明確な目標として掲げている 65。
その具体的な取り組みは、森林管理から伐採・搬出に至る全プロセスに及んでいる。
- 森林調査(ドローン・レーザー測量):従来、多大な労力と危険を伴った人手による森林調査に代わり、レーザー測量機(LiDAR)を搭載したドローンが活用されている。上空から森林の三次元データを精密に取得することで、立木一本一本の位置や樹高、材積を正確に把握できる。これにより、最適な伐採計画や搬出経路(架線集材など)の策定が可能となり、計画策定にかかる労力を大幅に削減し、精度を向上させている 67。
- 伐採・搬出(高性能林業機械):ハーベスタやフォワーダといった高性能林業機械の導入は、労働生産性向上の中心的な役割を担う。ある実証事業では、タワーヤーダ(集材機)を用いた作業システムが、隣接する従来型作業地の生産性(5.6 $m^3$/人日)を大幅に上回る10.3 $m^3$/人日を達成した 67。さらに、ICTを搭載したハーベスタは、丸太の価値が最大になるよう自動で採材(バリューバッキング)することができ、1立方メートルあたりの販売単価を引き上げる効果も報告されている 72。
- 経営管理(ICT・データプラットフォーム):クラウドベースのプラットフォームを活用し、森林情報をデジタルで一元管理する動きも進んでいる。これにより、多数の小規模な森林所有者とのコミュニケーションを効率化し、小規模な森林を集約して経済的に成立する単位で管理することが可能になる。また、こうしたプラットフォームは、J-クレジット(森林由来のカーボンクレジット)の創出・販売管理にも活用されている 73。
表3:日本の第一次産業におけるスマート技術マトリクス
| 技術分類 | 農業 | 林業 | 水産業 |
|---|---|---|---|
| ドローン/リモートセンシング | 応用例: 農薬・肥料散布、生育状況のモニタリング | 応用例: レーザー測量による森林資源量調査、3D地形データ作成 | 応用例: 赤潮の早期発見、漁場探索 |
| IoT/センサー | 応用例: 水田の水位・水温センサー、ハウス内の環境(温度・湿度・CO2)制御 58 目的: 遠隔管理による省力化、品質・収量の安定化 | 応用例: 林業機械の稼働状況モニタリング、作業員の安全管理 67 目的: メンテナンス効率化、労働災害防止 | 応用例: 養殖いけすの水温・溶存酸素・塩分濃度等のリアルタイム監視 80 目的: 最適な生育環境の維持、斃死リスクの低減、省力化 |
| AI/データ分析 | 応用例: 病害虫の画像診断、市場データに基づく生産計画、生育データに基づく収量予測 | 応用例: レーザーデータからの立木自動認識・材積計算、J-クレジットのCO2吸収量算定 | 応用例: 魚の食欲を画像解析し給餌量を自動制御、衛星データ等から漁場を予測 |
| ロボット/自動化 | 応用例: 自動運転トラクター・田植え機、自動収穫ロボット(ピーマン等) | 応用例: 自動運転下刈り機(開発中)、遠隔操作式林業機械 21 目的: 危険・過酷作業の代替、省力化、安全性向上 | 応用例: 自動給餌機、自動網掃除ロボット、自動魚種選別機 |
林業における技術導入は、単なるコスト削減や効率化にとどまらない、新たなビジネスモデル創出の起爆剤としての側面を持つ。スマート林業の第一歩は、ドローンによるレーザー測量など、正確な森林データの取得から始まる。このデジタル化された精密な森林データは、伐採計画の最適化という直接的な目的を超えた価値を持つ。例えば、このデータを用いることで、森林が吸収するCO2量を科学的に算定し、J-クレジットとして市場で販売することが可能になる 73。これは、森林の持つ環境的価値を金融資産に転換する新たな収益モデルである。さらに、詳細な地形や植生データは、エコツーリズムや「森林サウナ」といった体験型サービスなど、木材生産以外の事業を計画・展開するための基礎情報ともなる 85。このように、スマート林業への初期投資は、伝統的な林業経営を、多様な収益源を持つデータ駆動型の「森林資産マネジメント事業」へと変貌させる戦略的な一歩となり得るのである。
第4章 水産業分野:海の変動と陸の課題への対応
水産業は、コストや労働力といった陸上の経営課題に加え、海洋環境の変動という予測困難な自然のリスクに常に晒されている。本章では、漁業および養殖業が直面するこの二重の課題を分析し、特に労働力不足とコスト高騰への対応策として、テクノロジーを活用した「スマート水産業」への戦略的転換がどのように進んでいるかを詳述する。
4.1 変動の海:生産と収益性の動向
日本の漁業・養殖業の生産量は、1984年のピーク以降、長期的な減少傾向が続いている。2023年の総生産量は383万トンであった 25。しかし一方で、生産額は前年比5%増の1兆6,800億円と、2003年以来の高水準を記録した。これは、魚粉価格高騰を背景としたイワシ類の価格上昇や、不作による海苔の価格上昇など、供給側の要因に強く支えられたものであり、安定した需要に裏打ちされた成長とは言い難い 25。
経営は、生産資材価格の変動に極めて脆弱である。燃料油価格は依然として高止まりしており 25、特に養殖業においては、経営費の8割を占めることもある飼料価格が、世界的な魚粉需給や為替レートによって大きく変動するリスクを抱えている 25。
収益性も業態によって大きく異なる。2022年のデータでは、沿岸漁船漁業を営む個人経営体の平均漁労所得が252万円であったのに対し、海面養殖業を営む個人経営体の所得は1,062万円と、管理された環境下での生産がより高い収益性を生む可能性を示している 87。
4.2 再編による強靭化:倒産とM&Aの動向
厳しい経営環境は、倒産や事業再編の動きを加速させている。特に養殖業では、2025年1月から8月までの倒産・休廃業件数が前年の1.5倍のペースで推移し、過去10年で最多となる可能性が指摘されている 33。水産業全体で見ても、2023年には4年ぶりに倒産件数が増加に転じ、事業者の2割以上が赤字経営であったと報告されている 35。
このような状況下で、M&Aは規模の経済を追求し、経営の安定化を図るための重要な戦略となっている。マルハニチロのような大手企業は、養殖事業者や卸売業者を積極的に買収し、サプライチェーンの確保と業界再編を進めている 23。その狙いは、コスト構造を最適化し、地域に根差した漁業権や伝統的なノウハウを獲得することにある 88。
4.3 船員と担い手の確保という至上命題
水産業は、労働力不足、特に外国人材への依存が極めて深刻な産業である。漁業・養殖業における外国人技能実習生の数は年々増加しており 27、特に体力を要する船上作業などでは、もはや補助的な労働力ではなく、操業に不可欠な中核的存在となっている 36。この過度な依存は、新型コロナウイルス禍で見られたような入国制限など、外部要因によってサプライチェーンが寸断されるリスクを内包している 22。
長時間労働や過酷な労働環境は、国内の若年層を惹きつける上での大きな障壁となっている 90。この状況を改善するため、「働き方改革」の一環として、週休制の導入や給与水準の引き上げといった労働条件の改善に取り組む動きも見られる。一部の水産加工場では、労働時間の短縮と高い賃金水準を提示することで、人材確保に成功した事例も報告されている 91。
4.4 デジタルの波:スマート水産業の導入
政府は、資源の持続可能性と産業としての成長を両立させるため、「スマート水産業」の導入を強力に推進している 78。その取り組みは、特に管理・予測が可能な養殖業において目覚ましい進展を見せている。
データ駆動型養殖業:
- AIによる自動給餌:回転寿司チェーンのくら寿司などは、いけす内の魚の行動をカメラで解析し、食欲旺盛な時にのみ最適な量の餌を自動で与えるAIシステムを導入している。これにより、最大のコスト要因である飼料の無駄を削減し、成長率を向上させ、環境負荷も低減している 79。
- IoTによる環境モニタリング:スタートアップ企業などは、カキなどの養殖いかだにIoTセンサーを設置し、水温、塩分濃度、海流などをリアルタイムで監視している。このデータが、従来は漁師の「経験と勘」に頼っていた管理を代替し、斃死リスクを低減させ、初心者でも高品質な養殖を可能にする再現性の高い生産モデルを構築している 80。
- AIによるリスク管理:ドローンとAI画像解析を組み合わせ、赤潮の発生を早期に検知するシステムが開発されている。これにより、クロマグロのような高価な養殖魚の大量斃死を未然に防ぐことが可能となる 79。
天然魚漁業の効率化:
- AIによる漁場予測:人工衛星が観測する海水温やクロロフィル濃度といったデータと、過去の漁獲データをAIが解析し、魚群の存在確率が高い海域を予測するサービスが提供されている。これにより、漁船の探索時間を短縮し、燃料消費を最大15%削減した事例もある 82。
- 情報のデジタル化と共有:漁獲データを船上でデジタル化し、陸上の市場とリアルタイムで共有するシステムも導入されている。これにより、水揚げ前に需要と供給をマッチングさせ、物流の効率化や魚価の向上につなげる取り組みが進められている 83。
水産業全体で見られるこれらの動きは、産業構造の根本的な転換を示唆している。資源量の変動や燃料価格の高騰といった予測不能なリスクに常に晒される伝統的な天然魚漁業(「狩猟型」モデル)は、投資や新規参入の対象として魅力を失いつつある。対照的に、テクノロジーによって管理・制御され、より予測可能で拡張性のあるビジネスモデルを構築できる養殖業(「農耕型」モデル)の戦略的重要性が増している。スマート技術は、この「狩猟」から「農耕」への歴史的な転換を可能にする重要な触媒であり、水産業をより強靭で収益性の高い、そして次世代の担い手や投資家にとって魅力的な産業へと変貌させる可能性を秘めている。
第5章 総括と戦略的展望
本報告書の分析を通じて、日本の農業、林業、水産業が、デフレ脱却後のコストインフレと深刻な労働力不足という二重の圧力に直面し、重大な経営危機にあることが明らかになった。この「収益性のはさみ」とも言える状況は、特に体力の乏しい中小・零細事業者や新規参入者を直撃し、倒産件数の増加という形で産業の新陳代謝を促している。しかし、この危機は同時に、産業構造の変革を加速させる強力なドライバーともなっている。
各産業は、それぞれの事業特性に応じた戦略的適応を進めているが、その方向性には明確な共通項が見られる。それは、「事業再編による規模の追求」「テクノロジーによる生産性の飛躍」「労働力モデルの革新」という三つの柱である。
- 規模の追求(M&Aによる再編):後継者不足は、もはや個々の事業者の問題ではなく、産業全体の構造問題となっている。これに対し、M&Aは単なる事業承継の手段にとどまらず、細分化された経営資源を集約し、テクノロジー投資や市場競争に必要な「規模」を確保するための戦略的ツールとして不可欠な存在となっている。異業種からの参入を含むM&Aは、新たな資本と経営ノウハウを産業に注入し、近代化を促進する役割も担っている。
- 生産性の飛躍(スマート技術の導入):労働人口の減少が不可逆である以上、一人当たりの生産性を飛躍的に向上させる以外に、国内の生産基盤を維持する道はない。AI、IoT、ドローン、ロボットといったスマート技術は、この課題に対する最も直接的かつ効果的な解決策である。本報告書で示した事例のように、スマート技術は省力化やコスト削減に貢献するだけでなく、データ駆動型の精密な管理を可能にし、品質や収益性を向上させ、さらにはJ-クレジットのような新たな価値創出の源泉ともなり得る。
- 労働力モデルの革新:テクノロジーが全ての労働を代替するわけではない。将来にわたって持続可能な産業であるためには、多様な人材が活躍できる環境の構築が急務である。これには、外国人材を技能実習生という一時的な存在としてではなく、中長期的なキャリアパスを描けるパートナーとして統合していく制度設計が求められる。同時に、農福連携のような国内の多様な担い手を発掘・育成する取り組みや、週休二日制の導入や福利厚生の充実といった「働き方改革」を通じて、産業のイメージを刷新し、若者や女性を含む国内人材を惹きつける努力が不可欠である。
今後の10年は、日本の第一次産業にとって、淘汰と変革が同時進行する激動の時代となるであろう。この三つの戦略的柱を統合し、実行できた事業者のみが生き残り、成長していく。その結果、事業体数は減少する一方で、一事業者あたりの規模は拡大し、生産性は向上する。最終的に現れるのは、より少数精鋭で、技術集約的、そして市場への対応力に優れた、新たな第一次産業の姿である。ただし、この変革には、高額な初期投資(ROIの問題) 96 や、新たな技術を使いこなすデジタル人材の育成・確保という大きな課題も伴う 98。これらの課題に官民一体で取り組み、変革を支援していくことが、将来の日本の食料安全保障と国土保全の鍵を握っている。
引用文献
- 令和6年度食料・農業・農村白書を本日公表 | 農林水産省のプレスリリース, 11月 2, 2025にアクセス、 https://kyodonewsprwire.jp/release/202505309759
- 令和6年度 食料・農業・農村白書(令和7年5月30日公表):農林 …, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r6/index.html
- 令和6年度 料・農業・農村 書 概要 – 農林水産省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.maff.go.jp/j/wpaper/w_maff/r6/pdf/r6_gaiyou_all.pdf
- 【プレスリリース】第2回 コスト高騰緊急アンケート結果を公表しました。, 11月 2, 2025にアクセス、 https://hojin.or.jp/information/2022costup2/
- 農産物の価格はなぜあげられない?(前編)食料安全保障と農業のキホンの「キ」(6), 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mri.co.jp/knowledge/column/20230925.html
- 2024 年報 – 帝国データバンク, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tdb.co.jp/resource/files/assets/d4b8e8ee91d1489c9a2abd23a4bb5219/787079408f28464f8eeef6f74c8bccd5/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%80%92%E7%94%A3%E9%9B%86%E8%A8%882024%E5%B9%B4%E5%A0%B1%E3%83%BB12%E6%9C%88%E5%A0%B1.pdf
- 2024年の企業倒産は9901件、年間件数3年連続で大幅増 1万件に迫る – PR TIMES, 11月 2, 2025にアクセス、 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001000.000043465.html
- 「農業」の倒産動向 2023年度は81件で過去最多 帝国データバンク, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.jacom.or.jp/ryutsu/news/2024/06/240610-74639.php
- 「農業」の倒産、2023年度は過去最多81件 肥料価格や原材料高を背景に急増 – PR TIMES, 11月 2, 2025にアクセス、 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000875.000043465.html
- 農業の倒産、2023年度は過去最多81件に 急増の背景は? TDB調査 – ECのミカタ, 11月 2, 2025にアクセス、 https://ecnomikata.com/ecnews/43326/
- 農業現場の人手不足対策の取組み – JA共済総合研究所, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.jkri.or.jp/PDF/2022/Rep180ueda.pdf
- 農業の人手不足はこうやって解決する!解決に向けた取り組みをご紹介 – 自然電力株式会社, 11月 2, 2025にアクセス、 https://shizenenergy.net/re-plus/column/agriculture/labor_shortage/
- 農業・畜産業の人手不足|現状データと解決策・対策を徹底解説 – Jinzai Plus, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.jinzaiplus.jp/posts/218
- 農家における人手不足の現状とは?主な原因や解決策 – 株式会社 グローバルヒューマニー・テック, 11月 2, 2025にアクセス、 https://gh-tec.co.jp/column/farmer-labor-shortage/
- 後継者難倒産の動向調査(2024年度)|株式会社 帝国データバンク
, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tdb.co.jp/report/economic/20250407-succession-br24fy/ - 2024年度の後継者難倒産、500件超の高水準続く 止まらぬ社長の高齢化 – PR TIMES, 11月 2, 2025にアクセス、 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001054.000043465.html
- 2024年上半期の「後継者難」倒産 過去最多の254件 労働集約型の産業では、人手だけでなく、後継者不足も顕著 | TSRデータインサイト | 東京商工リサーチ, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1198742_1527.html
- 『上場企業M&A動向調査レポート(水産・農林業界版)』を発表 | M&A総合研究所, 11月 2, 2025にアクセス、 https://masouken.com/news_releases/1007
- 2025 年 8 月報 – 帝国データバンク, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tdb.co.jp/resource/files/assets/d4b8e8ee91d1489c9a2abd23a4bb5219/10348eb294ff40ee8cfda3c541dc12e5/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%80%92%E7%94%A3%E9%9B%86%E8%A8%882025%E5%B9%B48%E6%9C%88%E5%A0%B1%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%AA%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B9.pdf
- 帝国データバンク発表 過去最多の人手不足倒産 – ファクトリージャーナル, 11月 2, 2025にアクセス、 https://factoryjournal.jp/44533/
- 令和6年度 森林・林業白書 全文:林野庁, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/r6hakusyo/zenbun.html
- 水産業の外国人依存と持続性問題 | Ocean Newsletter | 海洋政策研究所, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.spf.org/opri/newsletter/497_1.html
- 農林水産業界のM&Aと事業承継の動向・2025年最新, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.nihon-ma.co.jp/sector/agriculture.php
- 令和6年度 水産白書 全文:水産庁, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/R6/250606_1.html
- 農業分野における外国人材の受け入れ – 農林水産省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/attach/pdf/250828-5.pdf
- (3)水産業の就業者をめぐる動向 – 水産庁, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/r02_h/trend/1/t1_2_3.html
- (3)水産業の就業者をめぐる動向 – 水産庁, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/r03_h/trend/1/t1_2_3.html
- 農業経営統計調査 令和4年 農業経営体の経営収支 – 農林水産省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/noukei/einou/attach/pdf/einou_22.pdf
- 農業経営統計調査(営農類型別経営統計) 令和5年 農業経営体の経営収支 – 農林水産省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/noukei/einou/pdf/einou_23.pdf
- 令和5年の「畜産物生産費統計」について, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.alic.go.jp/joho-c/joho05_003588.html
- 2024年の畜産経営は 物価高騰の厳しい時期を乗り越えることができたのか?, 11月 2, 2025にアクセス、 https://nougyorieki-lab.or.jp/kind/14682/
- 1~8月倒産・休廃業27件 水産養殖業者、過去最多ペース 帝国データバンク, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.suikei.co.jp/archives/67112
- 「水産養殖業者」の倒産・休廃業解散動向(2025年1-8月) – 帝国データバンク, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tdb.co.jp/report/industry/250906-yousyoku25y1-8/
- 国内の水産事業者 業績回復も2割強が赤字 倒産は4年ぶりに増加、燃料や物価高の影響大 | TSRデータインサイト | 東京商工リサーチ, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1197951_1527.html
- 水産業における外国人労働力の導入実態と今後の展望 – 水産振興ONLINE, 11月 2, 2025にアクセス、 https://lib.suisan-shinkou.or.jp/ssw625/ssw625-04.html
- 2025年9月の事業承継M&Aマーケット概況 ~食品関連業種(食品、農林水産, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.recof.co.jp/information/detail/640.html
- 農業の事業承継とは?注目される背景や種類、流れや成功のポイントを解説 – fundbook, 11月 2, 2025にアクセス、 https://fundbook.co.jp/column/industries-ma/agriculture/
- 「農業×IT」の異業種M&Aで、食や環境の課題に挑戦 – fundbook, 11月 2, 2025にアクセス、 https://fundbook.co.jp/cases/interview/20230728-2/
- 農家直送の「オンラインマルシェ」が販路拡大の鍵。成功事例や …, 11月 2, 2025にアクセス、 https://minorasu.basf.co.jp/80525
- コロナに負けるな!農家マーケティングのプチ成功事例 | FOOD FIELD CREARIVE, 11月 2, 2025にアクセス、 https://ffcnippon.com/2020/11/04/%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%81%AB%E8%B2%A0%E3%81%91%E3%82%8B%E3%81%AA%EF%BC%81%E8%BE%B2%E5%AE%B6%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%81%AE%E3%83%97%E3%83%81%E6%88%90/
- Facebookで売上が218%に「沖縄かんな農園の事例」【農家のSNS活用法vol.1】 – マイナビ農業, 11月 2, 2025にアクセス、 https://agri.mynavi.jp/2017_07_29_2054/
- 農家さんが農業経営にSNSを活用すべき理由と運用方法を解説! – ファームコネクト, 11月 2, 2025にアクセス、 https://farm-connect.org/agricultural-management/sns/
- SNSを活用して農業経営を強化!販路拡大・ブランド力向上の成功術 – 株式会社シュビヒロ, 11月 2, 2025にアクセス、 https://shubihiro.com/column/sns-agriculture/
- 農家が取り組むべきブランディングとSNS活用 | フードビジネス.com, 11月 2, 2025にアクセス、 https://food-business.funaisoken.co.jp/biz_farm/biz_farm_consulting/sns_attracting/sns_attracting_column/9934/
- 農業の人手不足|深刻な現状とデータでわかる原因と対策, 11月 2, 2025にアクセス、 https://aseanbc.co.jp/tips/%E8%BE%B2%E6%A5%AD%E3%81%AE%E4%BA%BA%E6%89%8B%E4%B8%8D%E8%B6%B3%EF%BD%9C%E6%B7%B1%E5%88%BB%E3%81%AA%E7%8F%BE%E7%8A%B6%E3%81%A8%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%A7%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8B%E5%8E%9F/
- 農業分野における外国人材の受け入れ – 農林水産省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/attach/pdf/index-189.pdf
- 【2025】育成就労制度における問題点とは?4つの課題をわかりやすく解説 – MEIKOGLOBAL, 11月 2, 2025にアクセス、 https://meikoglobal.jp/magazine/problems-with-fostered-work-system/
- 農福連携とは?現状やメリット・デメリットを解説 | コラム – イノチオグループ, 11月 2, 2025にアクセス、 https://inochio.co.jp/column/48/
- 農福連携で人材不足を解決!導入の流れや活用事例を紹介, 11月 2, 2025にアクセス、 https://minorasu.basf.co.jp/81108
- 農福連携をめぐる情勢 – 厚生労働省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mhlw.go.jp/content/001446707.pdf
- 農福連携取組事例集, 11月 2, 2025にアクセス、 https://noufuku.or.jp/wp-content/uploads/2025/03/7379e1e2d1f465e1dbe759fcffb7c35b.pdf
- スマート農業に関する調査を実施(2024年) | 市場調査とマーケティングの矢野経済研究所, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3740
- スマート農業とは?IT化の事例と気になる将来性を簡単に解説!|Y media – Yanmar, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.yanmar.com/jp/about/ymedia/article/smart_agri.html
- 世界のスマート農業市場(2025年~2033年):農業タイプ別、提供サービス別、その他, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.marketresearch.co.jp/insights/smart-agriculture-market-stra/
- スマート農業が普及しない理由とは?課題と現状をプロが解説! – イノチオグループ, 11月 2, 2025にアクセス、 https://inochio.co.jp/column/127/
- 農業DXとは?目指すべき方向性と事例4選 – ユーザックシステム, 11月 2, 2025にアクセス、 https://usknet.com/dxgo/contents/dx-industory/what-is-agriculture-dx/
- AIで農業経営を革新!導入メリットからコスト、成功事例まで完全ガイド – TRYETING, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tryeting.jp/column/8337/
- 省力化投資促進プラン ―農林水産業(農業)― (案), 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai34/shiryou16-12.pdf
- 帝国データバンク – 住宅産業新聞, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.housenews.jp/tag/tdb
- 綿半ホールディングス<3199>、林業経営を手掛ける須江林産の全株式を取得し子会社化, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.ma-cp.com/news/9827/
- M&Aニュース TREホールディングス、泉山林業を子会社化し木質バイオマス発電事業を強化, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.ma-cp.com/news/9629/
- 広大なヒノキの山林をM&A。30年続いた林業を引き継いだ決め手は、知見と人柄だった – バトンズ, 11月 2, 2025にアクセス、 https://batonz.jp/learn/13942/
- 令和3年度スマート林業構築 普及展開事業 報告書 – 林野庁, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/smartforest/attach/pdf/smart_forestry-73.pdf
- 令和4年度スマート林業構築 普及展開事業 報告書 – 林野庁, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/smartforest/attach/pdf/smart_forestry-5.pdf
- 林業イノベーション推進 スマート林業技術等実証業務 報 告 書 – 富山県, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.pref.toyama.jp/documents/40197/r6houkokusyo.pdf
- UAV写真を活用した森林資源把握マニュアル概要版 – 地方独立行政法人 青森県産業技術センター, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.aomori-itc.or.jp/_files/00183895/UAVP_manual_202212.pdf
- スマート林業オンライン講座3【2-1森林構造の画像化・森林解析2】 – YouTube, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=SPEDNFaEGqc
- 森林の測量でドローンを活用する方法や事例を紹介, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.skysurvey-navi.com/by-application/forest.html
- ドローンレーザ測量による森林調査を事例をもとに解説, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.dronesurvey-navi.com/case/forest.html
- スマート林業の実現に向けた取組について @静岡県林業先端技術展示会, 11月 2, 2025にアクセス、 http://www.pref.shizuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/044/287/rinya.pdf
- 森林クレジットの今がわかる! – 林野庁, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/ondanka/attach/pdf/J-credit-2.pdf
- 森林・林業DXによる民有林集約化を通じた – 農林水産省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.rinya.maff.go.jp/j/sin_riyou/ondanka/attach/pdf/J-credit-1.pdf
- 栃木県塩谷町の私有林を集約しJ-クレジット創出・販売で連携協定締結 – NTTドコモビジネス, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.ntt.com/about-us/press-releases/news/article/2025/1017.html
- 日本初、GISで森林由来J‐クレジットの創出者・審査機関・購入者の3者を支援する『森林価値創造プラットフォーム』を提供開始 | 住友林業, 11月 2, 2025にアクセス、 https://sfc.jp/information/news/2024/2024-08-27.html
- スマート水産業:水産庁, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.jfa.maff.go.jp/j/kenkyu/smart/
- 漁業におけるAIの活用事例9選!漁獲量UPや流通・品質管理改善など | ニューラルオプト, 11月 2, 2025にアクセス、 https://neural-opt.com/fishery-ai-cases/
- IoT活用事例 世界一おもしろい水産業へ 牡蠣スマート養殖プロジェクト – KDDI Business, 11月 2, 2025にアクセス、 https://biz.kddi.com/beconnected/feature/2022/220525/
- スマート漁業とは?水産業でのAI活用事例5選!導入時の課題は?【2025年最新】, 11月 2, 2025にアクセス、 https://ai-market.jp/industry/fishing_ai/
- (5)スマート水産業の推進等に向けた技術の開発・活用 – 水産庁, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/r06_h/trend/1/t1_2_5.html
- J-クレジットの制度概要と活用事例 – 京都府地球温暖化防止活動推進センター, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.kcfca.or.jp/wp-content/uploads/2024/12/250214_3.pdf
- 森林・林業の分野で 地域おこし協力隊制度を活用して 地域を盛り上げましょう! – 総務省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.soumu.go.jp/main_content/000900205.pdf
- 山村地域のコミュニティの活性化① – 林野庁, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.rinya.maff.go.jp/j/rinsei/singikai/attach/pdf/201113si-1.pdf
- (2)漁業・養殖業の経営の動向 – 水産庁, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/r05_h/trend/1/t1_2_2.html
- 漁業のM&A動向(2025年)メリットデメリット/事例/成功のポイントを解説 – CINC Capital, 11月 2, 2025にアクセス、 https://cinc-capital.co.jp/column/industry/fishing-industry-ma
- 水産業界のM&A動向 市場規模や買収・売却事例について解説, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.ma-cp.com/about-ma/industry/agriculture-forestry-fisheries/3/
- 漁業における技能実習生受け入れのメリットと課題 – 協同組合Keep on Heart, 11月 2, 2025にアクセス、 https://koh-cooperative.com/fisheries/
- 〜優良な取組事例と考えるヒント〜 – 全国漁業就業者確保育成センター, 11月 2, 2025にアクセス、 https://ryoushi.jp/wp-content/uploads/2022/10/dc17b791e4c2e4d0b9650181af5238d9.pdf
- 漁業の人手不足を解決|最新技術と外国人の活用事例を紹介 – Hakky Handbook, 11月 2, 2025にアクセス、 https://book.st-hakky.com/industry/solving-labor-shortage-in-fisheries-what-are-the-specific-methods-for-securing-human-resources-in-fishing-villages
- 水産加工工場の人材不足を解決!効果的な対策を考える – 株式会社グローバルハーモニー, 11月 2, 2025にアクセス、 https://global-harmony.co.jp/column/d02f6d4f-35a6-4441-82b4-ff1b96eed07c
- メリット・デメリット付き!スマート漁業のAI活用事例を紹介 – ContactEARTH for Expert, 11月 2, 2025にアクセス、 https://dx-consultant.co.jp/smart_fisheries_ai_case/
- (5)スマート水産業の推進等に向けた技術の開発・活用 – 水産庁, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.jfa.maff.go.jp/j/kikaku/wpaper/r05_h/trend/1/t1_2_5.html
- 自動化導入のコストを回収するまでの目安と計画の立て方, 11月 2, 2025にアクセス、 https://fa-match.jp/archives/251
- スマート林業を実現する産業用ドローン導入ガイド, 11月 2, 2025にアクセス、 https://mazex.jp/blog/smart-forestry-drones.html
- デジタル水産業戦略拠点検討会 とりまとめ – 水産庁, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.jfa.maff.go.jp/j/study/attach/pdf/degitaru_kentokai-31.pdf
- 漁業DXの現状と未来を語る:水産業デジタル化の課題、国内外事例と将来展望 – note, 11月 2, 2025にアクセス、 https://note.com/mudnesspartners/n/n059350c67541
- スマート漁業の人材不足を解決するには?必要スキル・育成3ステップ・最新求人動向を解説, 11月 2, 2025にアクセス、 https://ai-keiei.shift-ai.co.jp/smart-fishery-human-resource/