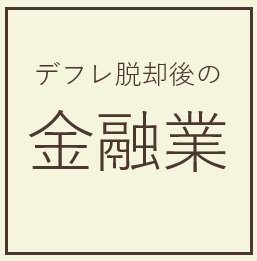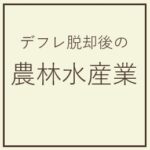この記事は、Gemini Deep Research にリサーチして執筆してもらったレポートです。
生成AIの書いた記事を修正すること無く、そのまま掲載しています。
一般常識として、「生成AIの書く記事には、ハルシネーションによる間違いが含まれている可能性がある」事を踏まえて記事を読んでください。
生成AIは完璧ではありません。
この記事の prompt は以下の文書になります。
現在の日本の金融保険業界における、デフレ脱却と人手不足による経営状況をリサーチしてください。
特に、収益率の変化、商流変更や事業再編・経営統合や、人材確保の方法の変更、倒産状況などの動向も知りたいです。
また、人手不足を受けての設備投資・IT活用などの動向もリサーチしてください。
わからない事は、わからないと回答してください。
ハルシネーションは避けてください。
以降は、全て Gemini Deep Research の書いたレポートです。
日本の金融・保険業界の変革期:デフレ脱却と人手不足がもたらす経営環境の構造変化と戦略的対応
第1章:序論 – 日本の金融・保険業界が直面する二つの構造的課題
日本の金融・保険業界は、歴史的な転換点に立たされている。数十年にわたるデフレ経済と超低金利時代の終焉、そして社会構造に根差した深刻な人手不足という、二つの巨大な構造変化の波が同時に押し寄せているからである。これらは単なる外部環境の変化ではなく、業界のビジネスモデル、収益構造、競争原理、さらには存在意義そのものを根底から揺るがす地殻変動と言える。本レポートでは、この二つの構造的課題が金融・保険業界の経営に与える多面的な影響を分析し、各社が生き残りと持続的成長のために迫られている戦略的対応の全体像を明らかにする。
1.1 「金利のある世界」への回帰
長らく続いたデフレ経済からの脱却は、日本の金融政策の正常化を促し、「金利のある世界」への回帰を現実のものとした。日本銀行は、2025年1月には政策金利を0.25%から0.5%へと引き上げると予測されており、さらに2025年度末までには1%への段階的な利上げも視野に入っている 1。この変化は、金融・保険業界にとって両刃の剣である。
一方では、伝統的な金融仲介機能の収益機会が復活することを意味する。銀行にとっては預貸金利鞘の改善が期待され、保険会社にとっては資産運用の利回り向上が見込まれる。これは、長年の収益低迷に苦しんできた業界にとって、まさに待望の追い風である。
しかし、他方では、これまで経験したことのない新たなリスクに直面することも意味する。金利上昇は、保有する債券の評価損を発生させ、企業の資金調達コストを増加させることで貸出先の信用リスクを高める可能性がある。また、預金獲得競争の激化は資金調達コストの上昇を招く。金融機関も保険会社も、この新しい金利環境下でリスクとリターンのバランスを再計算し、事業運営の舵を切り直すことが求められている。
1.2 深刻化する人手不足という「静かなる危機」
もう一つの構造的課題は、日本経済全体を覆う深刻な人手不足である。これは、金融・保険業界にとっても「静かなる危機」として経営に重くのしかかっている。業界の人手不足感を示す指数は、前年の-24ポイントから-31ポイントへと悪化しており、危機感が増していることがうかがえる 5。
この問題の根は深い。少子高齢化による生産年齢人口の減少というマクロ的な要因に加え、金融業界自体の就職先としての人気の低下、そしてデジタルトランスフォーメーション(DX)やリスク管理の高度化に対応できる専門人材(特にIT人材)の決定的な不足といった複合的な要因が絡み合っている 6。
人手不足が経営に与える影響は二重である。第一に、人材獲得競争の激化による賃金上昇は、人件費という固定費を押し上げ、収益を圧迫する。第二に、必要な人材を確保できないことは、事業拡大や新たなサービス開発の直接的な制約となり、企業の成長機会を奪う。
この二つのメガトレンド、すなわち「金利のある世界」への回帰と「深刻な人手不足」は、独立した事象としてではなく、相互に影響を及ぼし合う複合的な課題として捉える必要がある。金利上昇による収益改善の可能性は、賃上げや生産性向上のためのDX投資といった人手不足対策の原資となり得る点で、二つの課題は補完的な関係にある 1。一方で、人手不足を背景とした賃金上昇は、金利上昇による利鞘改善効果を相殺する圧力となる。また、金利上昇はDX投資に必要な資金の調達コストを引き上げるため、二つの課題は対立的な関係にもある。
この複雑な経営環境は、金融・保険機関の経営陣に対して、これまで以上に高度で緻密な戦略的意思決定を要求する。単に金利上昇の恩恵を待つだけでは生き残れず、コスト管理、生産性向上、人材戦略、事業再編といったあらゆる経営課題に同時並行で、かつ高いレベルで対応することが不可欠となっている。
第2章:金融機関(銀行・信用金庫)の経営変革
デフレ脱却と人手不足は、特に地域経済に深く根差す銀行や信用金庫のビジネスモデルに根本的な変革を迫っている。金利環境の変化は収益構造に光と影を落とし、生き残りをかけた再編・提携の動きを加速させている。
2.1 収益構造の変化:「金利のある世界」の光と影
長年のゼロ金利政策からの転換は、銀行の根幹ビジネスである預貸業務に大きな影響を及ぼすが、その恩恵は一様ではない。競争環境や事業構造の違いが、各金融機関の収益性に格差をもたらし始めている。
貸出収益の展望と課題
金利上昇は、理論上、貸出金利と預金金利の差である預貸利鞘(よたいりざや)を拡大させ、銀行の収益を押し上げる。特に、貸出ポートフォリオに占める変動金利の割合が高い大手銀行は、市場金利の上昇が比較的速やかに貸出金利に反映されるため、収益改善の恩恵を受けやすい構造にある 13。
しかし、地域金融機関が直面する現実はより厳しい。大手銀行や低コストを武器とするネット銀行との競争が激化しており、貸出金利を十分に引き上げることが困難な状況にある 8。金利上昇局面で預金金利の引き上げが先行し、貸出金利の引き上げが追いつかなければ、むしろ利鞘が縮小するリスクさえ存在する。このため、多くの地域金融機関にとって、金利上昇が必ずしも収益の増加に直結するとは限らない。
預金獲得競争の激化
金利が上昇するにつれて、預金者はより有利な金利を求めて金融機関を選ぶようになる。これにより、金融機関の間で預金獲得競争が激化し、預金金利の引き上げ圧力が強まる 8。競争力のある金利を提示できない金融機関からは預金が流出するリスクが高まり、資金調達コストの上昇が収益を圧迫する。特に、地域経済の縮小に直面する地方圏の地域金融機関にとっては、相続などを通じた域外への預金流出も深刻な懸念材料となっている 13。
有価証券運用リスクの顕在化
金利上昇は、銀行が保有する既存の有価証券ポートフォリオ、特に長期国債などに大きなリスクをもたらす。金利が上昇すると債券価格は下落するため、多額の評価損(含み損)が発生する可能性がある 14。これまで安定的な収益源と見なされてきた有価証券運用が、一転して収益の変動要因となり、財務の健全性を脅かすリスクが顕在化している。
手数料ビジネスへの注力
預貸業務の収益性の先行きが不透明であることから、多くの金融機関は金利に依存しない手数料ビジネスの強化に活路を見出そうとしている。具体的には、M&Aや事業承継に関するコンサルティング、資産運用アドバイス、ビジネスマッチングといった、取引先の経営課題解決に踏み込んだ付加価値の高いサービスを提供し、その対価として手数料を得るモデルへの転換である 16。しかし、現状では手数料収益の伸びは全体として横ばいにとどまっており、金利収益の変動を補うほどの収益の柱には育っていないのが実情である 18。
2.2 生き残り戦略としての再編・提携
厳しい経営環境を背景に、金融機関、特に地方銀行(地銀)の間で合併や経営統合といった再編の動きが加速している。これは、個々の金融機関の経営判断というだけでなく、金融システムの安定を企図する金融庁の後押しも受けた大きな潮流となっている。
金融庁が後押しする地銀再編
金融庁は、地域金融機関の経営基盤強化と地域経済への貢献能力向上を目的として、再編を積極的に後押ししている。その一環として、合併時のシステム統合費用などを補助する交付金の申請期限を2026年3月末から延長し、補助上限額も現行の30億円から引き上げる方針を明らかにしている 19。さらに、2020年11月には、同一県内の地銀同士の合併に独占禁止法の適用を除外する特例法が施行され、再編の大きな障害が取り除かれた 20。こうした制度的支援が、再編の動きを加速させる要因となっている。実際に、2025年1月には愛知銀行と中京銀行が合併して「あいち銀行」が、青森銀行とみちのく銀行が合併して「青森みちのく銀行」が誕生するなど、具体的な動きが活発化している 21。
再編の動向とパターン
地銀の数は、1990年の132行から2025年には97行へと減少し、特に第二地方銀行の集約が進んでいる 22。M&A市場全体も活況を呈しており、2024年の日本企業関連のM&A取引総額は前年比で40%増加した 23。金融業界においても、福井銀行による福邦銀行の吸収合併や、三十三フィナンシャルグループによる子会社の売却など、具体的な再編事例が相次いでいる 24。
これらの動きは、地域金融機関が重大な戦略的岐路に立たされていることを示唆している。限られた利鞘改善効果、人手不足に伴う人件費の上昇、そして不可欠なDX投資という三重の圧力に直面する中で、旧来のビジネスモデルを維持することは困難になりつつある。その結果、金融機関は「規模の経済」を追求する道か、「専門性」を追求する道のいずれかを選択せざるを得なくなっている。
前者の「規模」を追求する戦略は、M&Aを通じて経営統合を図り、本部機能やITシステム、店舗網といった重複コストを削減することで、経営効率を高めるアプローチである。金融庁の再編支援策は、まさにこの道を後押しするものと言える 19。これは、コスト効率を武器に収益性を確保しようとする防御的な戦略である。
後者の「専門性」を追求する戦略は、預貸業務への依存から脱却し、取引先である地域の中小企業が直面する人手不足、事業承継、デジタル化といった経営課題に対し、専門的なソリューションを提供するアドバイザリーモデルへと舵を切るアプローチである。人材紹介やDX導入支援、M&A仲介といったサービスを提供し、そこから得られる手数料収入を新たな収益の柱とする 12。これは、新たな付加価値を創造することで成長を目指す攻撃的な戦略である。
今後、地域金融機関の業界地図は、この二つの戦略軸に沿って大きく塗り替えられていくだろう。経営統合によって誕生する大規模な「スーパーリージョナルバンク」と、規模は小さくとも特定の分野で高い専門性を発揮する「ブティック型金融機関」へと二極化が進む可能性が高い。いずれの道も選択できず、高コスト構造と差別化できないサービスに甘んじる金融機関は、淘汰の波にのまれるか、吸収される側になるリスクが高まっている。
第3章:保険業界(生命保険・損害保険)の事業動向
保険業界もまた、金利環境の変化と構造的な課題への対応を迫られている。生命保険、損害保険、そして販売チャネルである保険代理店、それぞれのセクターで収益構造の変化と事業再編の動きが顕著になっている。
3.1 生命保険業界の収益性分析
2023年度の生命保険業界の決算は、基礎利益の大幅な回復という明るい結果を示した。しかし、その内訳を見ると、資産運用環境の変化がもたらす複雑な影響が浮かび上がってくる。
基礎利益の大幅な回復
2023年度の生命保険業界全体の基礎利益は、対前年度比で41.5%という大幅な増加を記録した 26。この好業績の最大の要因は、前年度に急増していた新型コロナウイルス関連の入院給付金などの支払いが大幅に減少したことにある。これにより、保険本来の収支を示す危険差益・費差益が正常化し、利益水準が回復した 26。大手生保9社の保険関係収支は、実に60.7%もの増加となっている 26。これは、一過性の特殊要因が剥落したことによるものであり、業界の収益力が本質的に向上したというよりは、平時の水準に戻ったと解釈するのが適切である。
資産運用環境の変化
金利のある世界への回帰は、生命保険会社の資産運用に複雑な影響を及ぼしている。プラスの側面としては、新規に投資する資金の運用利回りが改善し、将来的な収益基盤の強化につながる点が挙げられる。金利上昇を背景に、一時払個人年金保険などの貯蓄性商品の販売が好調に推移したことも、収益に貢献した 26。大手生保の利息及び配当金等収入(利差益)も4.0%増加している 26。
一方で、マイナスの側面も無視できない。特に、海外資産への投資に伴う為替ヘッジコストが高止まりしており、これが運用収益を圧迫する要因となっている 29。さらに、2025年以降に導入が予定されている新たな国際的な資本規制(ICS)は、保険会社に対してより精緻なリスク管理と資本配分の最適化を求めるものであり、今後の経営戦略に大きな影響を与えることが予想される 1。
3.2 損害保険業界の収益性分析
損害保険業界も2023年度は好調な決算となった。その背景には、保険引受業務の改善と良好な資産運用環境がある。
収益改善の主要因
大手損保グループであるSOMPOホールディングスは、2023年度に過去最高となる2,910億円の修正連結利益を計上し、前年度から1,388億円の大幅な増益となった 31。この収益改善には、主に三つの要因が寄与している。
第一に、火災保険の収益性改善である。過去数年間にわたる保険料率の適正化の取り組みが効果を発揮し、ベースとなる収支が大きく改善した 31。第二に、前年度に比べて大規模な自然災害による保険金支払いが減少したことである 31。第三に、海外保険事業の好調である。世界的な金利上昇の恩恵を受け、海外での資産運用収益が大きく伸びたことが、全体の利益を押し上げた 31。
3.3 保険代理店業界の再編加速
保険商品の主要な販売チャネルである保険代理店業界では、経営環境の厳しさが増す中で、M&Aによる再編が急速に進んでいる。
M&Aの活発化とその背景
損害保険代理店の数は減少傾向にあり、業界の集約が進んでいることがうかがえる 33。この再編を促している背景には、中小規模の代理店が直面する深刻な経営課題がある。
第一に、経営者の高齢化と後継者不足の問題である。多くの代理店が事業承継の課題を抱えており、M&Aが事業継続のための有力な選択肢となっている 37。第二に、デジタル化への対応の遅れである。オンラインでの相談や契約が一般化する中で、デジタル化への投資が追いつかない小規模代理店は競争力を失いつつある 38。第三に、コンプライアンス体制の強化など、規制対応の負担増である。顧客本位の業務運営を徹底するための研修や体制整備には相応のコストがかかり、これも規模の大きい代理店に有利に働く 40。
こうした要因から、大手保険代理店や商社、さらには投資ファンドなどが、規模の拡大や優秀な人材の確保を目的として、中小代理店の買収を活発化させている 37。M&Aは、買い手にとっては迅速な事業拡大の手段であり、売り手にとっては事業承継問題の解決策として、双方にとって合理的な選択となっている。
【表1】主要生命保険・損害保険会社の2023年度決算概要比較
| 会社名 | セクター | 主要収益指標 | 前年度比変化率 (%) | 収益変動の主な要因 |
|---|---|---|---|---|
| 生命保険各社(41社合計) | 生命保険 | 基礎利益 | +41.5 | 新型コロナ関連の給付金支払いが大幅に減少したことによる保険関係収支の正常化 26 |
| 日本生命保険 | 生命保険 | 基礎利益 | +61.5 | 新型コロナ関連の支払減少、一時払商品の販売増 |
| 住友生命保険 | 生命保険 | 基礎利益(グループ) | +16.9 | 新型コロナ関連の支払減少、海外事業(シメトラ)の収支悪化が一部相殺 |
| アクサ生命保険 | 生命保険 | 基礎利益 | +42.5 | (詳細な要因は資料に記載なし) |
| SOMPOホールディングス | 損害保険 | 修正連結利益 | +89.9 | 国内損保事業における火災保険の収支改善、自然災害の減少。海外保険事業の資産運用収益増 31 |
| 損害保険ジャパン | 損害保険 | 当期純利益(親会社株主帰属) | +95.7 | 自動車保険の保険金増加の一方、火災保険の収益改善、自然災害・大口事故の減少、新型コロナ影響の剥落 |
注:各社の会計基準や指標の定義が異なるため、単純な横並び比較には留意が必要。
第4章:人手不足への戦略的対応
金融・保険業界は、知識集約型の産業であり、その競争力は人材の質に大きく依存する。深刻化する人手不足は、事業継続を脅かす喫緊の課題であり、各社は人材の確保・定着と生産性向上の両面から、従来の枠組みを超える戦略的な対応を迫られている。
4.1 人材確保と定着:賃上げと採用の多様化
人材獲得競争が激化する中で、金融機関は魅力的な労働条件を提示する必要に迫られている。その最も直接的な手段が、賃金の引き上げである。
金融界の「賃上げ」ラッシュ
物価上昇と人材市場の逼迫を背景に、金融業界では異例とも言える賃上げの動きが広がっている。特に地域金融機関では、人材の流出を防ぎ、新たな人材を惹きつけるために、大幅な賃金改定に踏み切る例が相次いでいる。例えば、滋賀銀行は平均5.38%の賃上げと35,000円の初任給引き上げを、群馬銀行も平均3.5%のベースアップと30,000円の初任給引き上げを実施した 9。産業界全体としても、2025年の春闘賃上げ率は4.6%と高水準を維持する見込みであり 45、2024年には7割以上の企業がベースアップを実施するなど、賃上げは社会全体の大きな潮流となっている 11。金融業界もこの流れに乗り遅れることはできず、人件費の上昇は避けられない経営課題となっている。
新たな人材獲得チャネル
伝統的な新卒一括採用だけでは、多様化・専門化するニーズに対応できなくなっている。そのため、金融機関は人材獲得のチャネルを多様化させている。注目すべき動きとして、地域金融機関や信用金庫が、人材紹介を事業として手がけるケースが増えている点が挙げられる。これらは、自社の採用ニーズを満たすだけでなく、人手不足に悩む地域の取引先企業を支援する新たな手数料ビジネスとしても機能している 12。また、DXや資産運用などの特定分野における高度な専門性を持つプロフェッショナル人材を、中途採用や「副業・兼業」といった柔軟な契約形態で確保する動きも活発化している 25。
4.2 働き方改革と生産性向上
人材の定着率を高め、一人ひとりの生産性を向上させるためには、賃金だけでなく、働きがいのある職場環境の整備が不可欠である。
旧来型営業モデルからの脱却
特に営業部門では、旧来の働き方を見直す動きが出ている。保険代理店業界では、個人の販売ノルマを課さない「ノルマなし」の制度を導入する企業が増えている 49。これは、短期的な契約件数を追うのではなく、顧客との長期的な信頼関係の構築や、質の高いコンサルティングを重視する姿勢への転換を意味する。こうした取り組みは、営業職員の過度なプレッシャーを軽減し、働きがいを高めることで、人材の定着とサービスの質向上を目指すものである。
DE&Iとエンゲージメント
多様な人材がその能力を最大限に発揮できる職場環境の構築も重要な課題である。柔軟な勤務形態の導入や、DE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)の推進、従業員のウェルビーイング向上への取り組みは、優秀な人材を惹きつけ、組織全体の活力を高める上で不可欠となっている 49。
これらの動きの背景には、金融機関、特に地域金融機関の役割そのものが変化しているという、より本質的な地殻変動がある。かつて地域金融機関は、地域経済における数ある雇用主の一つとして、他の企業と人材獲得を競う「競争者」であった。しかし、地域全体が人手不足という共通の課題に直面する中で、その役割は、地域の人材市場を活性化させ、最適配置を促す「プラットフォーム」へと進化しつつある。
この進化のプロセスは段階的に進行している。第一段階は、自社の賃金を引き上げて人材を確保するという内向きの対応である 9。しかし、これは地域内での人材の奪い合いに過ぎない。第二段階として、金融機関は自らが持つ広範なネットワークと信用力を活かし、取引先である中小企業に対して人材紹介やコンサルティングといったサービスを提供するようになる 12。これは、顧客の経営課題解決に貢献する新たなビジネスモデルである。
そして最終的に、金融機関は地域経済における「人材プラットフォーム」としての役割を担うことになる。例えば、閉鎖される工場の従業員の再就職を地域内の成長企業と連携して支援したり、専門スキルを持つ人材とそれを必要とする中小企業をマッチングさせたりすることで、地域全体の人材の流動性を高め、人的資本の最適化を図る 12。これは、単なる手数料ビジネスを超えた、地域経済の持続可能性に直接貢献する活動である。金融機関は、取引先の最大の経営課題である人手不足を解決する中核的な存在となることで、融資以外の面でも不可欠なパートナーとなり、自らの競争優位性と存在意義を再定義しているのである。
【表2】主要地域銀行の賃上げ・初任給改定状況(2024-2025年)
| 銀行名 | 発表時期 | 平均賃上げ率(ベースアップ等) | 大卒初任給(改定前) | 大卒初任給(改定後) | 引き上げ額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滋賀銀行 | 2024年 | 5.38% | 225,000円 | 260,000円 | +35,000円 |
| 群馬銀行 | 2024年 | 3.5% (人事制度改定と合わせ6.2%) | 220,000円 | 250,000円 | +30,000円 |
| 山陰合同銀行 | 2024年 | (ベースアップ実施) | – | – | – |
| 全国企業平均(2024年度実績) | 2024年9月調査 | 3.03% (ベースアップ率) | – | – | – |
出典:
9
第5章:テクノロジー活用による生産性革命と事業モデル革新
人手不足という制約と、金利上昇下でのコスト管理の必要性は、金融・保険業界にデジタルトランスフォーメーション(DX)の加速を強いている。テクノロジーの活用は、もはや単なる業務効率化の手段ではなく、生産性を飛躍的に高め、新たなビジネスモデルを創出するための競争力の源泉となっている。
5.1 業務効率化の切り札となるDX
各社は、RPA(Robotic Process Automation)やAI(人工知能)といった技術を導入し、人手を介していた業務の自動化・高度化を推進している。
RPAによる定型業務の自動化
RPAは、ルールに基づいて行われる定型的な事務作業を自動化する技術であり、人手不足対策の切り札として広く導入されている。三菱UFJ銀行では、RPAを活用して、これまでシステム開発に多額の費用と時間を要していたシステム間のデータ転記作業などを自動化し、累計で数十万時間もの作業時間を削減した 52。これにより、従業員は単純作業から解放され、より付加価値の高いコンサルティング業務や企画業務に集中することが可能になった 54。
AI活用による業務の高度化
AIの活用は、単純な自動化の域を超え、専門的な判断が求められるコア業務の変革にまで及んでいる。保険業界では、引受査定や保険金支払査定にAIを導入する動きが活発化している。損害保険ジャパンは、自動車事故の損傷写真と修理見積書をAIが照合し、修理内容や金額の妥当性をチェックするシステムを導入しており、2025年までに車両損害調査の40%をAIで自動化することを目指している 56。第一生命保険は、1,700万件もの保障設計データをAIに学習させ、顧客の意向に最適な保険プランを推奨するシステムを開発した 57。これらの取り組みは、査定プロセスの劇的な迅速化と標準化を実現し、顧客満足度の向上と業務効率化に大きく貢献している。銀行業務においても、AIは与信審査、不正検知、チャットボットによる顧客対応など、幅広い分野で活用が進んでいる。
オンライン手続きの普及
顧客接点のデジタル化も急速に進んでいる。従来は書面でのやり取りが中心だった各種手続きがオンラインで完結できるようになり、顧客の利便性が向上するとともに、金融機関側の事務負担も大幅に軽減されている 58。
5.2 新たな顧客体験とビジネスモデル
テクノロジーは、既存業務の効率化にとどまらず、これまでにない顧客体験やビジネスモデルの創出を可能にしている。
フィンテックとエンベデッドファイナンス
金融サービスと非金融サービスの垣根はますます低くなっている。特に「エンベデッドファイナンス(組込型金融)」は、今後の金融サービスの主流になると目されている 60。これは、非金融事業者のアプリやサービスの中に、決済、融資、保険といった金融機能を部品のように組み込むモデルである。例えば、ユニクロが提供する決済サービス「UNIQLO Pay」は三井住友銀行の決済基盤を、NTTドコモの「dスマートバンク」は三菱UFJ銀行のBaaS(Banking as a Service)基盤を活用している 61。金融機関にとって、エンベデッドファイナンスは、自社のサービスを顧客の日常生活やビジネスの動線の中に自然な形で届け、新たな顧客接点を獲得するための強力な戦略となる。
Insurtech(インシュアテック)の進化
保険(Insurance)とテクノロジー(Technology)を融合させたInsurtechも進化を続けている。自動車の走行データを基に保険料を個別に設定する「テレマティクス保険」や、必要な時に必要な分だけ加入できる「オンデマンド保険」など、顧客のニーズにきめ細かく対応した新しい保険商品が生まれている 64。また、米国のLemonade社のように、AIチャットボットを活用して保険の申し込みから保険金請求まで、すべてのプロセスをスマートフォン上で完結させる革新的なサービスも登場している 66。これらの動きは、保険をよりパーソナルで、利便性の高いものへと変えつつある。
こうしたテクノロジー活用の進展は、金融・保険業界内に明確な「デジタル格差」を生み出している。これは単なる効率性の差ではなく、企業の競争力そのものを左右する決定的な要因となりつつある。
三菱UFJ銀行のRPAによる大規模な業務削減 54、損害保険ジャパンのAIを活用した先進的な保険金査定 56、大手銀行によるエンベデッドファイナンスへの積極的な展開 61 などは、デジタル化の「先進企業」が、いかにしてコスト構造を変革し、新たな顧客価値を創造しているかを示す好例である。これらの取り組みは、もはや実験的なものではなく、事業運営の中核をなすものとなっている。
一方で、多くの地域金融機関や中小保険代理店は、レガシーシステムの刷新の遅れ、デジタル人材の不足、投資余力の欠如といった課題に直面し、デジタル化の波に乗り遅れている 38。紙ベースの業務や対面中心のサービスモデルへの依存は、コスト面でもサービス面でも大きなビハインドとなっている。
この「先進企業」と「遅滞企業」の間の能力格差は、今後ますます拡大していくだろう。デジタル先進企業は、低いコストで優れた顧客体験を提供し、創出された人的リソースを高度なアドバイザリー業務に再配分することで、さらなる競争優位を築く。一方で、デジタル化に遅れた企業は、高コスト構造と陳腐化したサービスから抜け出せず、人材獲得競争でも不利な立場に置かれる。この格差こそが、第2章や第3章で述べたM&Aや業界再編を加速させる根本的な駆動力となっているのである。DXは、もはや選択肢ではなく、業界の勝者と敗者を分ける分水嶺なのである。
第6章:倒産動向に見る日本経済と金融業界の健全性
企業の倒産動向は、経済全体の健全性を測るバロメーターであると同時に、金融機関が直面する信用リスクの動向を示す重要な指標である。全産業で倒産が増加する中、金融・保険業界自体の倒産は抑制されており、リスクの所在が変化していることがうかがえる。
6.1 全産業における倒産件数の増加
コロナ禍での各種支援策が縮小・終了し、日本経済が平時へと移行する中で、企業の倒産件数は明確な増加トレンドに転じている。2024年度の倒産件数は10,070件に達し、11年ぶりに1万件の大台を超えた 70。
この倒産増加の背景には、複数の構造的な要因がある。
- 人手不足倒産: 2024年度は過去最多の350件を記録。特に建設業や運輸・通信業で深刻化しており、受注があっても人手が足りずに事業継続が困難になるケースが多発している 70。
- 物価高倒産: 原材料価格やエネルギーコストの上昇を販売価格に十分に転嫁できず、収益が悪化したことによる倒産も925件と過去最多を更新した 70。
- 後継者難倒産: 経営者の高齢化と後継者不在による事業承継の失敗も、507件と高水準で推移している 70。
これらの要因は、特に体力の乏しい中小零細企業を直撃しており、倒産の増加は当面続くと見られる。
6.2 金融・保険業界の倒産状況
全産業で倒産が増加しているのとは対照的に、金融・保険業界自体の経営破綻は極めて少ない水準で推移している。東京商工リサーチの調査によると、2024年の「金融・保険業」の倒産件数は25件で、前年比28.5%の減少となった 72。2024年度上半期(4-9月)も13件で、前年同期比27.7%減と、同様の傾向が続いている 73。
このデータは、金融・保険業界全体として、自己資本は充実しており、経営基盤が安定していることを示している。しかし、これは金融機関が安泰であることを意味しない。むしろ、リスクの性質が変化していることを示唆している。金融機関自身の経営破綻リスクは低いものの、その取引先である中小企業の倒産が増加することで、金融機関が保有する貸出債権が焦げ付く「信用リスク」が高まっているのである。
この状況は、金融セクターが直面するリスクが、過去の金融危機のように金融機関自身の破綻が連鎖する「システミック・リスク」から、経済全体の企業業績悪化が金融機関の資産の質を劣化させる「システムワイドな信用リスク」へと移行していることを物語っている。
このリスク構造の変化を理解することは、今後の金融行政や各金融機関のリスク管理のあり方を考える上で極めて重要である。過去の危機では、金融機関自体の資本増強や流動性確保が最優先課題であった。しかし、現在の課題は、金融機関の貸出ポートフォリオの健全性をいかに維持するかという点にある。
この文脈において、第2章で提示した地域金融機関の「専門性」追求戦略の重要性が改めて浮き彫りになる。単に融資先の財務状況を監視する受動的なリスク管理にとどまらず、人材紹介やDX支援といったコンサルティング機能を通じて、取引先企業の経営改善や事業継続を能動的に支援すること。それは、単なる新事業の展開ではなく、自らのバランスシートを劣化から守るための、最も効果的なリスク管理策そのものなのである。金融機関の安定は、もはや取引先の企業の安定と不可分一体となっている。この認識こそが、新しい時代における金融機関の役割と戦略の根幹をなすべきである。
【表3】倒産動向の業種別比較(2024年度)
| 業種 | 倒産件数(件) | 前年度比変化率 (%) | 人手不足倒産(件) | 物価高倒産(件) |
|---|---|---|---|---|
| 全産業 | 10,070 | +13.4 | 350 | 925 |
| 建設業 | 1,932 | +10.5 | 111 | 254 |
| サービス業 | 2,638 | +20.6 | 101 | (データなし) |
| 小売業 | 2,109 | +12.5 | (データなし) | 165 |
| 金融・保険業 | 25* | -28.5* | (データなし) | (データなし) |
出典:
70*金融・保険業のデータは2024年(暦年)のものであり、他業種の2024年度(4月-3月)データとは集計期間が異なる点に留意。
第7章:総括と今後の展望
日本の金融・保険業界は、デフレ経済からの脱却と深刻な人手不足という二つの構造変化に直面し、かつてない規模の変革期を迎えている。本レポートで分析してきたように、これらの変化は業界の収益構造、競争環境、そして求められる役割を根本から変えつつある。今後の持続的な成長を実現するためには、環境変化への適応と、ビジネスモデルそのものの再構築が不可欠である。
7.1 環境変化への適応戦略
これまでの分析を総括すると、各セクターが取るべき戦略的対応の方向性は明確である。
銀行業界、特に地域金融機関は、もはや旧来の預貸業務を中心としたビジネスモデルでは立ち行かなくなっている。生き残りの道は、「規模の経済」を追求するM&Aによる経営効率化か、あるいは地域経済に深く入り込み、取引先の経営課題を解決する「専門性」を追求するアドバイザリーモデルへの転換か、そのいずれかに大きく振れるだろう。中途半端な立ち位置の金融機関は、淘汰の対象となる可能性が高い。
保険業界は、金利上昇という新たな資産運用環境を的確に捉え、リスク管理を高度化させることが求められる。同時に、AIやIoTといったテクノロジーを駆使して、保険引受や支払査定のプロセスを抜本的に効率化・高度化し、顧客ニーズの多様化に対応したパーソナルな商品・サービスを開発することが競争力の鍵となる。
そして、業界全体に共通する最大の経営課題は、人材戦略とデジタル変革である。賃上げによる人材の確保・定着は必須の投資であり、同時にRPAやAIの活用による生産性の飛躍的な向上がなければ、コスト増を吸収し、持続的な成長を遂げることはできない。DXは、もはや選択肢ではなく、企業の生存をかけた必達目標である。
7.2 持続的成長に向けたビジネスモデルの再構築
今後の金融・保険サービスの姿は、より「エンベデッド(組込型)」で、「パーソナル」で、「データ駆動型」のものになるだろう。金融機能は、独立したサービスとして提供されるだけでなく、顧客の日常生活や企業のサプライチェーンといった様々なプラットフォームにシームレスに組み込まれていく。
この大きな潮流の中で、金融・保険機関に求められる役割も変化する。単に資金や保険商品を提供する「供給者」から、顧客が直面する複雑な経営課題、特に本レポートで焦点化した人手不足やデジタル化といった問題に対して、共に解決策を探る「総合的なパートナー」へと進化することが求められる。
結論として、この変革期を乗り越え、未来の勝者となるのは、二つの変革を同時に成し遂げた企業である。一つは、テクノロジーを徹底的に活用して自社のコスト構造をスリム化し、生産性を極限まで高める「内部変革」。もう一つは、その過程で生み出された人的・経済的リソースを、顧客の最も差し迫った課題を解決する新たな付加価値の創造へと振り向ける「外部変革」である。この両輪を力強く回すことができた企業のみが、金利上昇と人手不足がもたらす「収益性の圧搾(プロフィタビリティ・スクイーズ)」を克服し、持続的な成長軌道を描くことができるだろう。日本の金融・保険業界は、まさにその真価が問われる時代に突入したのである。
引用文献
- 「2025年の必須課題」トップ10 – PwC, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/2025/assets/pdf/insurance-issue2025.pdf
- 「金利のある世界」へ踏み出す日本経済 – みずほリサーチ&テクノロジーズ, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mizuho-rt.co.jp/publication/2025/pdf/report250220.pdf?rt_bn=msg-tweet
- 銀行 銀行株の持続性が問われる年になるだろう – SBI証券, 11月 2, 2025にアクセス、 https://go.sbisec.co.jp/prd/common/newyear_forecast_2025_report_bank.html
- 「金利のある世界」に戻る日本 – 三菱UFJ信託銀行, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tr.mufg.jp/new_assets/houjin/jutaku/pdf/unyou_jyoho_202503_no154.pdf
- マイナビキャリアリサーチLab 金融・保険業レポート(2024年5月), 11月 2, 2025にアクセス、 https://career-research.mynavi.jp/wp-content/uploads/2024/05/2024-5-kinyugyo.pdf
- 金融業界の人材不足を解消!銀行が活用する人材派遣会社とは? – パーソルマーケティング, 11月 2, 2025にアクセス、 https://sales.persol-mk.co.jp/column/talent-shortage-financial-industry/
- 2030年問題とは?2040年問題との違いや金融業界のDX活用をわかりやすく解説, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/sp/contents/column/20250516_2030_problem.html
- 金利上昇の“副作用”:邦銀の金利競争激化の行方 – ピクテ・ジャパン, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.pictet.co.jp/investment-information/market/deep-insight/20250825.html
- 賃上げおよび初任給引き上げを実施 | ニュースリリース – 滋賀銀行, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.shigagin.com/news/topix/3198
- ベースアップの実施および初任給の引上げについて – 群馬銀行, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.gunmabank.co.jp/info/news/20240318a.html
- 地域企業における賃上げ等の動向について (特別調査) – 財務省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mof.go.jp/about_mof/zaimu/kannai/202401/tokubetsu.pdf
- 人手不足を受けた地域金融機関の取り組み – 日本銀行, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.boj.or.jp/finsys/c_aft/data/aft240305a.pdf
- 金利上昇下における預金基盤の 重要性の高まり – 大和総研, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/it/20250724_030167.pdf
- 「金利のある世界」で顕在化する 地銀の金利リスクと今後求められる対応 – 日本総研, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.jri.co.jp/file/report/researchfocus/pdf/15151.pdf
- 金融レポート, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.fsa.go.jp/news/29/Report2017.pdf
- データから見る地銀「手数料ビジネス」の収益実態 – きんざいOnline, 11月 2, 2025にアクセス、 https://kinzai-online.jp/node/7941
- 融資推進・手数料強化, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.scbri.jp/publication/.assets/geppo-2024-6-3.pdf
- 厳しさが増す地域銀行のビジネス環境と 求められる収益基盤の強化 – 日本総研, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/report/researchfocus/pdf/13430.pdf
- 地銀再編を後押し、交付金拡充 金融庁、改正案を提示, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.47news.jp/13372702.html
- 地銀再編とは? (予想される変化と今後の動向を解説) – Frontier Eyes Online, 11月 2, 2025にアクセス、 https://frontier-eyes.online/regional-banks-reorganization/
- 地方銀行に求められる「攻め」の再編戦略 – 日本総研, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.jri.co.jp/page.jsp?id=110941
- 地方銀行の越境再編 – 大和総研, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/it/20250711_025199.pdf
- 日本M&Aレビュー – 東京フィナンシャル・アドバイザーズ, 11月 2, 2025にアクセス、 https://tfa.co.jp/docs/lseg_2024-p3.pdf
- 銀行業界のM&Aニュース一覧, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.nihon-ma.co.jp/news/gyokai.php/?gcode%5B%5D=g0620&gname=%E9%8A%80%E8%A1%8C
- 人材支援 – しののめ信用金庫, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.shinonome-shinkin.jp/business/solution/main-biz/human_resource.html
- 2023年度 生命保険会社決算の概要 | ニッセイ基礎研究所, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=79561?site=nli
- 2023年度 生命保険会社決算の概要(全社集計確報と、トピックス追加版) | ニッセイ基礎研究所, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=79222?site=nli
- 2023年度 業績の概要 – 日本生命, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.nissay.co.jp/kaisha/annai/gyoseki/pdf/kessan202405/gaiyo.pdf
- 2023年度上半期 業績の概要 – 日本生命, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.nissay.co.jp/news/2023/pdf/kessan202311/gaiyo.pdf
- 2023年度決算(案)説明用資料 – 住友生命, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.sumitomolife.co.jp/about/company/ir/settlement/pdf/240523.pdf
- 2023年度通期決算説明資料 – SOMPOホールディングス, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.sompo-hd.com/-/media/hd/files/doc/pdf/ir/2024/ir_20240520.pdf?la=ja-JP
- 1.2023年度の事業概況 – 損保ジャパン, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.sompo-japan.co.jp/-/media/SJNK/files/company/disclosure/2024/sj_disc2024_07.pdf
- 損保代理店数等統計 | VALUEMAN’S Blog, 11月 2, 2025にアクセス、 https://value-agent.co.jp/wp/%E6%90%8D%E4%BF%9D%E4%BB%A3%E7%90%86%E5%BA%97%E6%95%B0%E7%AD%89%E7%B5%B1%E8%A8%88/
- 損保協会集計 2024年度損害保険代理店統計 代理店実在数が14万店に減少 1年で1万4848店が廃止 – 保険毎日新聞, 11月 2, 2025にアクセス、 https://homai.co.jp/news/28196/
- 2024.08.22 損保協会集計 2023年度損害保険代理店統計 代理店実在数15万店で減少続く 募集従事者数の減少率は鈍化 | 保険ニュース, 11月 2, 2025にアクセス、 https://hoken.ne.jp/news_wp/2024/08/22/2024-08-22-%E6%90%8D%E4%BF%9D%E5%8D%94%E4%BC%9A%E9%9B%86%E8%A8%88%E3%80%80%EF%BC%92%EF%BC%90%EF%BC%92%EF%BC%93%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%90%8D%E5%AE%B3%E4%BF%9D%E9%99%BA%E4%BB%A3%E7%90%86%E5%BA%97%E7%B5%B1/
- 保険代理店のM&Aの動向とは?費用相場や事例20選も紹介, 11月 2, 2025にアクセス、 https://leveragesma.jp/article/705/
- 保険代理店のM&Aとは?メリットや流れを解説 | マネーフォワード クラウド, 11月 2, 2025にアクセス、 https://biz.moneyforward.com/ma/basic/1281/
- 【2025年】保険代理店のM&A動向は?メリットやデメリットから事例・成功のポイントまで解説, 11月 2, 2025にアクセス、 https://cinc-capital.co.jp/column/industry/ma-insurance-agency
- 保険代理店の未来図共有:2035年、進化する業界が描く新たな常識 – KOTORA JOURNAL, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.kotora.jp/c/81700-2/
- ー2024 保険代理店の直面する課題と展望, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.nihondaikyo.or.jp/wp-content/uploads/2024/11/nakazaki.pdf
- 生命保険代理店の大型化は今後進んでいくのか? 中小保険代理店が生き残るための戦略とは?, 11月 2, 2025にアクセス、 https://fp-wanted.com/column/642
- 保険代理店業界のM&A動向!流れや注意点と事例を解説【2025年最新】, 11月 2, 2025にアクセス、 https://mastory.jp/%E4%BF%9D%E9%99%BA%E4%BB%A3%E7%90%86%E5%BA%97%E3%81%AEM&A
- 保険代理店の売却・M&A動向2024|メリット・相場・注意点, 11月 2, 2025にアクセス、 https://co-ad.jp/blog/ma_trends/3934/
- 2025 年も高水準の賃上げ継続へ – みずほリサーチ&テクノロジーズ, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mizuho-rt.co.jp/publication/2025/pdf/insight-jp250109.pdf
- 人材を紹介してほしい|関信用金庫, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.shinkin.co.jp/seki1534/about/promotion_plan/zinzai.html
- 人材支援サービス|西尾信用金庫, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.shinkin.co.jp/nishio/hojin/keieikadai/jinzai/
- 人材採用|ちょうししんきん – 銚子信用金庫, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.choshi-shinkin.co.jp/hojin/keiei/recruit-biz.html
- 保険代理店で営業ノルマなしの会社が急増中!インセンティブへの影響は? – R&C, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.randcins.jp/recruit/no-quota/
- 株式会社hokanが実現する保険業界改革。自由な働き方と使命感の融合, 11月 2, 2025にアクセス、 https://morejob.co.jp/mirai/hokan/
- 2024年度賃上げ結果 および 2025年度賃上げ意向調査 – 山陰合同銀行, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.gogin.co.jp/common/chingin202409.pdf
- 三菱東京UFJ銀行が可能性を拡げる、金融機関でのRPA導入による業務効率化, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mufg.jp/profile/strategy/dx/articles/0020/index.html
- 三菱UFJ信託銀行におけるRPA導入事例, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.boj.or.jp/finsys/c_aft/basic_seminar/data/rel180305a2.pdf
- RPAで銀行・金融業界の業務効率化!自動化のメリットや活用事例を解説|BizteX robop, 11月 2, 2025にアクセス、 https://service.biztex.co.jp/dx-hacker/rpa/bank-finance/
- 金融業界でRPAが導入される理由は?大手金融業の事例4選とRPA導入の注意点, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.usknet.com/rpa/rpa_automation/31007/
- デジタル技術を活用した商品・サービス提供 – SOMPOホールディングス, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.sompo-hd.com/csr/action/customer/content4/
- 保険業界における生成AIの活用事例16選!現状やメリット・導入における課題も解説, 11月 2, 2025にアクセス、 https://n1-inc.co.jp/hoken-ai/
- 保険業界のDXとは?国内外の生命保険会社でのDX推進事例 – 株式会社プリマジェスト, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.primagest.co.jp/column/1826/
- 保険業界のDXの課題は?メリットやデメリット、推進するための方法, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp/column/business/article26.html
- 2025年は「フィンテックが日常に溶け込む年」 – インフキュリオン・インサイト, 11月 2, 2025にアクセス、 https://insight.infcurion.com/business/trends-and-prospects-2025/
- 【今さら聞けない金融IT用語】エンベデッドファイナンス – digital FIT, 11月 2, 2025にアクセス、 https://fit.nikkin.co.jp/post/detail/tb046
- 組み込み型 融の事例と動向, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.boj.or.jp/paym/outline/mirai_forum/data/rel220608a2.pdf
- エンベデッド・ファイナンスの新潮流。NTTドコモの取り組みに見る金融体験の近未来 | DATA INSIGHT, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.nttdata.com/jp/ja/trends/data-insight/2023/0509/
- 【保険DX】国内外の生保・損保における成功事例を徹底調査 | CASE …, 11月 2, 2025にアクセス、 https://case-search.jp/case-by-theme-dx-insurance/
- インシュアテックとは?保険業界のAI活用・DX化のトレンドについて事例やポイントを解説, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.persol-bd.co.jp/service/bpo/s-bpo/column/insurtech/
- 【DX事例3選】海外の保険業界DXの状況とは?デジタル化の成功事例を会社別にわかりやすく紹介 | ContactEARTH for Expert, 11月 2, 2025にアクセス、 https://dx-consultant.co.jp/overseas-insurance-industry-dx-case/
- 保険業界のDXとは?国内外の先行事例や海外トレンドをもとに解説 – 株式会社モンスターラボ, 11月 2, 2025にアクセス、 https://monstar-lab.com/dx/about/dx-insurance/
- 地域金融機関における企業DX支援の現状と課題 – 日本銀行, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.boj.or.jp/finsys/c_aft/data/aft251010a1.pdf
- 地方銀行の越境再編 2025年07月11日 | 大和総研 | 鈴木 文彦, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/it/20250711_025199.html
- 倒産集計 2024年度報(2024年4月~2025年3月) – 帝国データバンク, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tdb.co.jp/report/bankruptcy/aggregation/g2-5yfk9w/
- 2024年度の企業倒産は1万70件、11年ぶりに1万件超える 人手不足、物価高が中小企業の経営を直撃 ― 全国企業倒産集計2024年度報 | 株式会社帝国データバンクのプレスリリース – PR TIMES, 11月 2, 2025にアクセス、 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001055.000043465.html
- 2024年(令和6年)の全国企業倒産1万6件, 11月 2, 2025にアクセス、 https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/content/contents/002312866.pdf
- 2024年度上半期(4-9月)の全国企業倒産5,095件 | 株式会社東京商工リサーチのプレスリリース, 11月 2, 2025にアクセス、 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000019.000126976.html