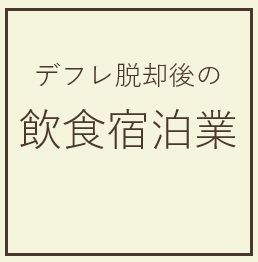この記事は、Gemini Deep Research にリサーチして執筆してもらったレポートです。
生成AIの書いた記事を修正すること無く、そのまま掲載しています。
一般常識として、「生成AIの書く記事には、ハルシネーションによる間違いが含まれている可能性がある」事を踏まえて記事を読んでください。
生成AIは完璧ではありません。
この記事の prompt は以下の文書になります。
現在の日本の飲食宿泊旅行サービス業界における、デフレ脱却と人手不足による経営状況をリサーチしてください。
特に、収益率の変化、商流変更や事業再編・経営統合や、人材確保の方法の変更、倒産状況などの動向も知りたいです。
また、人手不足を受けての設備投資・IT活用などの動向もリサーチしてください。
わからない事は、わからないと回答してください。
ハルシネーションは避けてください。
以降は、全て Gemini Deep Research の書いたレポートです。
デフレ脱却と人手不足の交差点:日本の飲食・宿泊・旅行サービス業界の経営変革と将来展望
エグゼクティブ・サマリー
日本の飲食・宿泊・旅行サービス業界は、歴史的な転換期を迎えている。記録的なインバウンド需要という強力な追い風を受け、市場は回復基調にある一方で、国内ではデフレからの脱却に伴う物価・人件費の高騰と、構造的かつ深刻な人手不足という未曾有の逆風に同時に直面している。この二つの巨大な力が交差する中で、業界の経営環境は複雑性を増し、企業は従来の成功モデルからの根本的な変革を迫られている。
本レポートは、この複合的な課題に対し、企業が如何なる戦略的対応を進めているかを多角的に分析するものである。分析の結果、企業の対応は以下の三つの戦略的方向に集約されることが明らかになった。第一に、人手不足を補い、コスト上昇を吸収するための「DX(デジタルトランスフォーメーション)による生産性革命」。第二に、人材の獲得競争を勝ち抜き、従業員の定着を図るための「人材戦略の根本的再構築」。そして第三に、成長機会の獲得と経営効率の向上を同時に実現するための「M&Aによる業界再編」である。
これらの変革への適応能力の差は、企業間の二極化を急速に加速させている。資本力と戦略実行力を持ち、新たな経営モデルへ迅速に移行できる企業が収益を拡大する一方で、旧来の労働集約型・低価格モデルから脱却できない企業は淘汰されるという厳しい現実が、倒産件数の増加という形で顕在化している。
結論として、本業界の今後の持続的な成長は、テクノロジーを駆使した生産性の飛躍的な向上と、従業員をコストではなく価値創造の源泉と捉える新しい労働力モデルの構築にかかっている。この歴史的転換期を乗り越え、次代の勝者となるための要件を本レポートでは提示する。
第1章 市場環境の構造変化と新たな潮流
本章では、飲食・宿泊・旅行サービス業界全体の経営状況を左右するマクロ環境を分析する。特に、記録的なインバウンド需要が市場を牽引する一方で、物価高騰下で国内需要が変容するという「二つの市場」が併存する現状を、各種データに基づき明らかにする。
1.1. インバウンド主導の回復と国内需要の停滞
2024年の日本の宿泊市場は、その回復構造において顕著な特徴を示した。観光庁の宿泊旅行統計調査によると、年間の延べ宿泊者数は6億5,906万人泊に達し、統計が比較可能な2010年以降で過去最高を記録した 1。これはコロナ禍前の2019年比で10.6%増という高い水準であり、市場が完全に回復軌道に乗ったことを示している 2。
しかし、この成長の内実を詳細に分析すると、その原動力が極めて偏っていることがわかる。成長を牽引したのは、訪日外国人旅行者数の急増である。外国人延べ宿泊者数は1億6,447万人泊と、前年比で+39.7%、2019年比では+42.2%という驚異的な伸びを記録した 2。円安が海外からの旅行者にとって強い追い風となり、インバウンド需要が市場全体を力強く底上げした構図だ 3。
その一方で、市場の基盤であるべき日本人の国内旅行需要は停滞感を強めている。日本人延べ宿泊者数は4億9,460万人泊と、前年比で1.0%の減少となった 2。2019年比では+3.0%とコロナ禍前の水準を僅かに上回ってはいるものの、物価高による実質所得の低下や、インバウンド需要に引きずられる形でのホテル宿泊料金の高騰が、国内旅行への意欲を削いでいる状況がうかがえる 3。
このインバウンド需要と国内需要の乖離は、業界の成長が円安という外部要因に大きく依存する脆弱な構造となっていることを示唆している。為替の変動や国際情勢の変化といった外部からの衝撃に対して、業界の収益基盤が揺らぎやすいリスクを内包していると言える。また、インバウンドの恩恵が限定的な地方の中小事業者にとっては、国内市場の停滞が直接的な経営圧力となっており、依然として厳しい経営環境が続いている。
1.2. 物価上昇がもたらす消費者行動の変化:外食における「コスパ」重視と旅行消費の二極化
物価上昇は、特に国内消費者の行動に大きな変化をもたらしている。外食市場においては、消費者の節約志向が一段と強まり、「高単価の外食を控え、低価格帯の食事を頻繁に楽しむ」という傾向が顕著になっている 5。この消費行動の変化は、業態別の売上動向に明確な差となって表れている。
日本フードサービス協会の調査によると、ファストフード業態はテイクアウトやデリバリー需要の定着に加え、その価格帯の手頃さからコロナ禍以前を超える成長を記録している 5。一方で、比較的高単価なディナーレストランや、宴会需要が中心であった居酒屋・パブレストランは、回復基調にはあるものの、消費者の支出抑制の影響を受け、回復ペースは相対的に緩やかである 6。
浜銀総合研究所の分析では、外食需要が新年会などの「ハレの日」需要と、日常的な外食需要とで二極化している可能性が指摘されている 8。消費者は、特別な機会には支出を惜しまないものの、普段の食事については価格に対して極めて敏感になっている。これは、企業に対して、単なる「安さ」ではなく、「価格に見合う価値」、すなわちコストパフォーマンスを厳しく問いかけていることを意味する。このトレンドは、メニュー開発、価格設定、業態戦略の全てにおいて、「価値の明確な伝達」が不可欠であることを示している。
1.3. 2024-2025年の市場規模と業況感
こうした複雑な市場環境の中、業界全体の業況感は回復を示している。日本銀行の短観によれば、「宿泊・飲食サービス」の業況判断DIは2022年12月以降プラス圏で推移し、2024年6月時点でも+24と良好な水準を維持している 9。これは、インバウンド需要に支えられた売上回復が、経営者のマインドをポジティブに転じさせていることを反映している。
市場規模の予測も、この回復基調が継続することを示唆している。矢野経済研究所の予測では、2024年度の国内外食市場規模(中食含む)は、前年度比2.9%増の32兆1,423億円に達すると見込まれている 7。来店客数の増加に加え、後述するコスト上昇を背景とした価格改定が客単価を押し上げることが主な要因である。
しかし、この良好な業況感や市場規模の拡大予測の裏では、深刻な人手不足とコスト上昇という構造的な問題が進行している。売上が増加しても、それ以上にコストが増加すれば利益は圧迫される。多くの企業が、需要はあるのに人手が足りずサービスを提供できない、あるいは提供できても利益が出ないという「儲からない繁忙」に陥るリスクを内包しており、経営環境は決して楽観視できるものではない。
インバウンドの活況が、国内市場の構造的問題(実質賃金の伸び悩みによる消費停滞)を覆い隠す「マスキング効果」を生み出している点には、特に注意が必要である。見かけ上の「好調」は、主に外部要因に支えられたものであり、国内の基盤市場が脆弱なままである限り、持続的な成長への道筋は不透明と言わざるを得ない。
【表1】飲食・宿泊・旅行業界 主要経営指標(2024年 vs 2023年, 2019年)
| 指標 | 2019年実績 | 2023年実績 | 2024年実績 | 2024年 vs 2023年比 | 2024年 vs 2019年比 | 典拠 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 延べ宿泊者数 (全体) | 5億9,592万人泊 | 6億1,765万人泊 | 6億5,906万人泊 | +6.7% | +10.6% | |
| 延べ宿泊者数 (日本人) | 4億8,019万人泊 | 4億9,960万人泊 | 4億9,460万人泊 | -1.0% | +3.0% | 2 |
| 延べ宿泊者数 (外国人) | 1億1,573万人泊 | 1億1,785万人泊 | 1億6,446万人泊 | +39.7% | +42.2% | 2 |
| 客室稼働率 (全体) | 62.7% | 57.0% | 59.6% | +2.6 pt | -3.1 pt | 2 |
| 客室稼働率 (旅館) | 39.6% | 36.7% | 36.1% | -0.6 pt | -3.5 pt | |
| 客室稼働率 (ビジネスホテル) | 75.8% | 69.2% | 73.7% | +4.5 pt | -2.1 pt | |
| 外食産業売上高 (全体) | N/A | N/A | 前年比 +8.4% | +8.4% | N/A | |
| 外食産業売上高 (ファストフード) | N/A | N/A | 前年比 +8.1% | +8.1% | N/A | |
| 外食産業売上高 (居酒屋) | N/A | N/A | 前年比 +5.5% | +5.5% | N/A |
注: 外食産業売上高は日本フードサービス協会会員社対象の調査結果であり、市場全体の規模とは異なる。2019年比のデータは提供されていない。
第2章 深刻化する労働力不足:業界最大の経営制約
本章では、飲食・宿泊・旅行サービス業界の成長を根本から揺るがす人手不足問題に焦点を当てる。その深刻度、構造的要因、そして事業運営への具体的な影響を分析し、これが単なる景気循環の問題ではなく、業界のビジネスモデルそのものに関わる構造的な課題であることを論証する。
2.1. 人手不足の現状と構造的要因
現在の飲食・宿泊サービス業界が直面する人手不足は、あらゆる指標が示す通り、極めて深刻なレベルに達している。日銀短観における雇用人員判断DIは-65という数値を示し、企業が感じる人員不足感が危機的な状況にあることを物語っている 9。帝国データバンクの調査では、「旅館・ホテル」の約8割が正社員の人手不足を感じており、これは全業種の中で最も高い割合である 10。また、厚生労働省の統計でも、宿泊業の欠員率は他業種と比較して突出して高く、構造的な労働力不足に陥っていることが確認されている 12。
この深刻な人手不足の根源には、一過性ではない、業界が長年抱えてきた構造的な問題が存在する。コロナ禍以前から、飲食・宿泊サービス業は「低賃金」「労働環境の厳しさ(休日・休暇の少なさ、不規則な勤務時間)」「非正規雇用比率の高さ」といった課題を抱え、その結果として他産業よりも高い離職率が常態化していた 13。これらの問題は、労働生産性が低いままであったこととも密接に関連している 13。
デフレ経済下では、コストを極限まで圧縮し、需要の変動に非正規雇用で柔軟に対応するという経営モデルが一定の合理性を持っていた。しかし、経済がデフレから脱却し、労働市場全体で賃金上昇の機運が高まる中、このモデルは限界を迎えている。より良い労働条件を求めて労働者が他産業へ移動しやすくなった結果、旧来の低賃金・高負荷モデルに依存していた飲食・宿泊サービス業は、熾烈な人材獲得競争において劣勢に立たされている。
さらに、コロナ禍がこの構造的問題を決定的に悪化させた。観光需要の蒸発に伴う大規模な雇用調整により、多くの労働者が業界を離れざるを得なかった。そして、需要が回復した現在も、一度離れた人材の多くは業界に戻ってきていない。経団連の調査によれば、離職した観光業の雇用者のうち、宿泊業・飲食サービス業へ復帰したのは4割未満に留まっている 14。これは、コロナ禍を経て、多くの労働者がこの産業の安定性や将来性に対して強い懸念を抱くようになったことを示唆している 13。
2.2. 供給能力への影響:機会損失の実態と潜在的リスク
人手不足は、もはや単なるコスト増や管理上の問題ではなく、売上機会そのものを喪失させる「供給制約」という形で、企業の経営を直接的に脅かしている。需要が回復しても、それに応えるサービスを提供するための人員を確保できないという「機会損失」が、全国の現場で現実のものとなっている。
三井住友トラスト基礎研究所の分析によれば、宿泊業において現在の雇用者数とコロナ禍前の生産性から供給能力の上限を試算すると、平均的な月の需要には対応可能であるものの、夏休みシーズンなどの繁忙期には供給が需要に追い付かず、客室稼働率に深刻な影響を及ぼす可能性が高いと指摘されている 10。ある試算では、2019年のピーク時と比較して、平均的な月の20%程度の宿泊需要を失う可能性があるとされている 10。これは、目の前にあるビジネスチャンスを、人手がいないという理由だけでみすみす逃しているに等しい。
この供給制約は、業界の成長の最大の足枷となっている。インバウンド観光客が過去最高を記録し、消費意欲も旺盛であるにもかかわらず、その受け皿となるべき宿泊施設や飲食店が満員を理由に予約を断らざるを得ない状況は、個社のみならず日本経済全体にとっても大きな損失である。
2.3. 地方部における特に深刻な状況
人手不足の問題は、全国一律ではなく、地域によってその深刻度に差がある。特に、もともと労働力人口が少ない地方の観光地において、問題はより先鋭化している。観光庁の調査では、事業者自身が「人手不足は地方の観光に特化した施設で特に課題が大きい」と認識していることが示されている 15。
地方では、若年層の都市部への流出が続く一方で、従業員の高齢化が進んでおり、新たな労働力の確保が都市部以上に困難である 15。また、地方の旅館などでは、従業員のスキルアップや定着に繋がる研修の実施率が低い傾向にあり、人材育成の面でも課題を抱えている 15。
国策としてインバウンドの地方誘客が推進される中、その受け皿となるべき地方の宿泊・飲食サービス業が供給能力の限界に達しているという構造的な矛盾が生じている。これは、観光を通じた地方創生の実現に向けた、極めて大きな障壁となっている。この問題を解決せずして、持続可能な地方観光の発展はあり得ない。
第3章 収益性の実態:コストプッシュ圧力との攻防
本章では、売上回復の裏で進行するコスト上昇の実態を分析し、企業の収益性がどのような圧力を受けているかを明らかにする。価格戦略の難しさと、それが利益率に与える影響を掘り下げていく。
3.1. 売上回復とコスト構造の変化
市場の回復に伴い、多くの企業の売上高は増加傾向にある。しかし、その一方で、損益計算書(P/L)の費用項目はかつてない上昇圧力に晒されている。原材料費、エネルギー費、物流費といった事業運営に不可欠なコストが、世界的なインフレや円安を背景に高騰を続けている 7。
中でも特に深刻なのが、人件費の上昇である。第2章で詳述した慢性的な人手不足は、人材を確保するための時給引き上げを不可避なものにしている 7。従業員の賃金を引き上げなければ、他産業や競合他社に人材が流出し、事業の継続すら困難になる。このため、多くの企業にとって賃上げは、もはや選択肢ではなく必須の経営課題となっている。
この結果、企業のコスト構造は大きく変化した。売上増というプラス要因と、売上原価および販売管理費の増というマイナス要因が激しく綱引きする状況となっており、コスト上昇分を販売価格に適切に転嫁できなければ、売上は伸びても利益は減少するという「増収減益」に陥るリスクが常に付きまとっている。
3.2. 価格戦略の動向:値上げと顧客維持のジレンマ
コスト上昇圧力に対応するため、多くの企業が価格改定、すなわち「値上げ」に踏み切らざるを得ない状況にある。矢野経済研究所のレポートによると、外食チェーンの中には、年に1〜2回というハイペースで定期的に価格改定を実施している企業も少なくない 7。
しかし、価格戦略は極めて難しい舵取りを要求される。第1章で分析した通り、特に国内の消費者は物価高騰に対して強い防衛意識を持っており、単純な値上げは即座に客離れを引き起こすリスクがある 5。そのため、企業は値上げの際に、消費者の納得感を得るための工夫を凝らしている。例えば、単に価格を上げるだけでなく、食材の品質を向上させたり、メニューの価値を高めたりすることで、価格上昇に見合う付加価値を提供しようと努めている 7。
さらに、より精緻な価格設定への取り組みも見られる。人件費が割高になる深夜帯に限定して追加料金を課す「深夜料金」の導入や、賃料や最低賃金水準が異なる地域ごとに価格を変える「地域別価格制度」の導入などがその例である 7。これは、コスト構造の違いを価格に反映させ、収益性を確保しようとする合理的な試みである。
このように、現代の価格戦略は、コストを転嫁するという守りの側面と、ブランド価値を訴求し顧客を維持するという攻りの側面の両方が求められる、極めて高度な経営課題となっている。
3.3. 業態別・企業規模別にみる営業利益率の動向
こうした厳しい環境下で、業界の収益性はどのように推移しているのだろうか。総務省の個人企業経済調査によると、「宿泊業,飲食サービス業」の1企業当たりの年間営業利益は、前年に大幅な減少を記録した後、2024年には7.2%の増加に転じ、最悪期を脱したことが示されている 16。
しかし、その水準は依然として楽観できるものではない。財務総合政策研究所の法人企業統計調査によれば、宿泊業の売上高営業利益率は、コロナ禍以前から全産業の平均を下回る水準にあり、構造的に収益性が低い産業であることが指摘されている 18。現在のコストプッシュ圧力は、この構造的な課題をさらに悪化させている可能性がある。
特に、価格転嫁や後述するDXによる効率化投資の余力が乏しい中小企業ほど、利益率の圧迫は深刻であると推察される。仕入れ量の少なさから原材料コストの削減が難しく、ブランド力も限定的であるため大胆な価格改定も打ち出しにくい。結果として、資本力のある大手企業と中小企業との間で、収益性の格差がさらに拡大している可能性が高い。
この状況は、業界が従来の「規模の経済(スケールメリット)」に加え、テクノロジー活用による「効率の経済(エコノミー・オブ・エフィシエンシー)」を追求しなければ生き残れない時代に突入したことを意味する。売上規模だけでなく、単位労働時間あたりの付加価値、すなわち労働生産性を最大化する経営が不可欠となっている。そして、そのための投資を実行できる企業とそうでない企業との間で、収益性の差、ひいては企業の存続可能性そのものの差が、明確に現れ始めている。
第4章 生存と成長に向けた戦略的転換
本章では、前章までで明らかになった厳しい経営環境に対し、企業が具体的にどのような戦略を講じているかを詳述する。「人材」「DX」「事業再編」の3つの切り口から、業界の変革に向けた能動的な動きを捉える。これらの戦略は個別に存在するのではなく、相互に連携し、人手不足という根本課題を解決するための「三位一体の変革パッケージ」として機能している。
4.1. 人材戦略の再構築
労働力供給の絶対量が減少する中、企業は人材戦略の根本的な見直しを迫られている。その動きは、「新たな労働力の活用」と「既存従業員の定着」という二つの側面に大別できる。
4.1.1. 採用チャネルの多様化と新たな労働力の活用
従来の若年層中心の採用ターゲットに固執するだけでは、必要な人員を確保することはもはや不可能である。そのため、多くの企業がシニア層、主婦・主夫層、外国人材など、多様なバックグラウンドを持つ人材に積極的に門戸を広げている 19。
特に、外国人材の活用は、人手不足解消の重要な鍵となっている。中でも、2019年に導入された在留資格「特定技能」は、フロント業務、接客、レストランサービス、客室清掃など、宿泊・飲食業における幅広い現場業務への従事が可能であり、即戦力として期待されている 20。実際に、特定技能ビザで来日した外国人材が、インバウンド顧客への多言語対応で貢献するだけでなく、日本人スタッフにも良い刺激を与えるなど、組織の活性化に繋がっている事例が報告されている 21。これは、企業が画一的な雇用管理から、個々の事情や文化に合わせた柔軟なマネジメントへと移行する必要性を示している。
4.1.2. 労働環境改善とリテンション戦略
人材獲得競争の激化を受け、企業の戦略の力点は「採用(いかに採るか)」から「定着(リテンション:いかに辞めさせないか)」へと明確にシフトしている。観光庁の調査では、宿泊事業者が人手不足対策として最も注力したい項目として、「働きやすい労働時間・休日等の労働条件の整備」と「給料の引き上げ」を挙げている 15。
具体的には、かつての飲食業界で一般的だった長時間・固定シフトを見直し、「1日1時間から」「週末限定」といった短時間・柔軟な勤務体系を導入する動きが広がっている 23。これにより、育児や介護、学業など、個々のライフスタイルに合わせた働き方が可能となり、これまで労働市場に参加しにくかった層を取り込むことが可能になる。賃金という金銭的報酬だけでなく、働きやすさや働きがいといった非金銭的報酬の重要性が、かつてなく高まっている。
4.2. デジタルトランスフォーメーション(DX)による生産性革命
人手不足という供給制約を乗り越え、生産性を向上させるための最も強力な武器がDXである。業界のDXは、単なる業務効率化に留まらず、顧客体験の向上や新たな収益機会の創出を目指す「攻めのDX」へと進化している。
4.2.1. 宿泊業:フロント業務の自動化からデータ駆動型経営へ
宿泊業のDXは、最も定型的な業務であるフロント業務の自動化から急速に進展している。専用端末や顧客自身のスマートフォンを用いたスマートチェックイン/アウト、顔認証によるキーレスエントリー、QRコード決済などが大手ホテルチェーンを中心に普及し、フロントスタッフの業務負荷を大幅に軽減している 24。また、客室へのアメニティ配送やレストランでの配膳にロボットを導入し、月間で十数万円相当の労働力削減効果を上げた事例も報告されている 26。
さらに、DXはバックオフィス業務にも浸透している。クラウドベースの宿泊管理システム(PMS)や顧客関係管理(CRM)を導入することで、予約情報や顧客データを一元管理し、データに基づいた経営戦略の立案が可能になる 24。星野リゾートのように、AIを活用して需要を予測し、宿泊料金をリアルタイムで変動させるダイナミックプライシングを導入して収益の最大化を図る先進的な取り組みも始まっている 28。
4.2.2. 飲食業:省人化テクノロジーの導入と業務効率化
飲食業では、特にホール業務の自動化がDXの主戦場となっている。ファミリーレストランなどを中心に、客席に設置されたタブレット端末や顧客のスマートフォンから注文するセルフオーダーシステムが広く普及した 7。これにより、注文取りの業務が削減され、従業員は調理や配膳、より付加価値の高い接客に集中できるようになった。配膳ロボットや、POSレジと連動したキャッシュレス決済端末の導入も進んでおり、会計業務の効率化にも貢献している 29。これらの投資は、労働生産性の向上に直結する重要な施策となっている。
4.2.3. 旅行業:デジタル技術が創出する新たな顧客体験
旅行業におけるDXは、業務効率化に加えて、旅行者の体験価値を向上させる方向で進化している。例えば、携帯電話の位置情報などから得られる人流データを分析し、観光地の混雑状況をリアルタイムで可視化することで、オーバーツーリズムを回避しつつ周遊を促す取り組みが神奈川県箱根町などで実施されている 30。
また、生成AIを活用した24時間対応の多言語観光案内チャットボット(山口県美祢市)や、VR(仮想現実)技術を用いて現地の魅力を疑似体験できるバーチャルツアー(アムステルダム)など、新たなテクノロジーが旅行の「マエ(計画段階)」から「ナカ(旅行中)」の体験を豊かにしている 30。長野県志賀高原では、地域の観光協会が独自の予約・決済サイトを構築し、オンライン旅行代理店(OTA)に支払う手数料を削減すると同時に、得られた顧客データをマーケティングに活用してリピーター獲得に繋げるという、データ駆動型の地域経営を実践している 31。
【表2】セクター別DX・IT活用ソリューションと戦略的目的
| セクター | 目的(省人化・コスト削減) | 目的(顧客体験向上・売上増) | 代表的ソリューション | 導入事例企業(一部) |
|---|---|---|---|---|
| 宿泊業 | フロント業務の自動化、清掃・配膳業務のロボット化、バックオフィス業務の効率化 | データに基づくパーソナライズドサービス、待ち時間の削減、非接触での手続き完了、収益の最大化 | スマートチェックイン機、顔認証システム、配膳ロボット、クラウドPMS/CRM、AIダイナミックプライシング | アパホテル、星野リゾート、プリンスホテル、東急ホテルズ |
| 飲食業 | ホール業務(注文・配膳・会計)の自動化、発注・在庫管理の効率化 | 注文の待ち時間短縮、メニュー情報の多言語化、キャッシュレスによる利便性向上 | セルフオーダーシステム(タブレット/モバイル)、配膳ロボット、POS連動キャッシュレス決済 | ファミリーレストラン各社、すかいらーくHD |
| 旅行業 | 定型的な問い合わせ対応の自動化、予約・決済プロセスの効率化 | 混雑回避による快適な周遊、パーソナライズされた情報提供、新たな観光体験の創出 | 人流データ分析、生成AIチャットボット、VR/ARコンテンツ、地域独自予約サイト(直販) | 神奈川県箱根町、長野県志賀高原、山口県美祢市 |
4.3. 業界再編の加速:M&Aと事業ポートフォリオの最適化
人手不足とコスト上昇という厳しい環境は、業界再編の動きを加速させている。自社単独での成長や課題解決が困難になる中、M&A(合併・買収)は企業が生き残り、成長するための極めて重要な戦略的選択肢となっている。
4.3.1. M&Aの主要動向と戦略的意図
近年のM&Aは、単なる規模拡大を目的としたものだけではない。複合的な戦略的意図が背景にある。
- 戦略補完型のM&A: 大手企業が、自社の弱みを補完するために他社を買収するケースが目立つ。例えば、ファミリーレストランを主力とするすかいらーくホールディングスが、西日本で強い地盤を持つうどんチェーン「資さんうどん」を買収した事例は、未進出エリアへの迅速な展開と、和食という新たな業態ポートフォリオの獲得を同時に狙ったものである 33。また、居酒屋大手のワタミが、健康志向のサンドイッチチェーン「サブウェイ」の日本法人を買収したのも、自社にないブランドとフランチャイズ展開のノウハウを獲得する戦略的な動きと言える 33。
- インバウンド需要の獲得: 宿泊業では、旺盛なインバウンド需要や2025年の大阪・関西万博を見据え、ホテルの取得競争が活発化している。既存のホテルを買収し、自社のブランドに転換(リブランド)する動きや、外資系ブランドの新規開業ラッシュが続いている 35。これにより、優良な立地の物件とそれに付随する人材を効率的に確保することが可能になる。
- 事業承継問題の解決: 地方の旅館や個人経営の飲食店では、経営者の高齢化と後継者不足が深刻な問題となっている。こうした企業にとって、M&Aは事業と従業員の雇用を存続させるための有効な手段となっている。
4.3.2. 不採算事業の整理と「選択と集中」
M&Aによる事業拡大と並行して、自社の強みが発揮できない不採算事業を売却し、経営資源を中核事業に集中させる「選択と集中」の動きも活発化している。コロナ禍で体力の低下した多くの企業が、不採算店舗を閉鎖することで財務体質を改善し、残った優良店舗の収益性を高める戦略をとった 7。また、大手企業グループが、本業とのシナジーが薄い子会社を売却する事例も見られる 37。
M&Aによる事業の「購入」と、不採算事業の「売却」は、表裏一体のポートフォリオ最適化戦略である。限られた経営資源を、最も成長が見込める領域に再配分することで、企業全体の競争力を高めようとする動きが、業界全体で加速している。
第5章 企業淘汰の現実:倒産動向とその背景
業界の構造変化は、成長や変革といったポジティブな側面だけでなく、適応できない企業が市場から退出を余儀なくされるという厳しい側面ももたらしている。本章では、企業倒産の動向を分析し、その背景にある現代的な要因を明らかにすることで、事業継続の分岐点がどこにあるのかを考察する。
5.1. 2024-2025年における倒産件数の推移と特徴
帝国データバンクの調査によると、企業倒産件数は前年同月を33カ月連続で上回るなど、明確な増加傾向を示している 39。2025年7月単月では、飲食業の倒産が105件、宿泊業が6件報告されている 40。
この背景には、コロナ禍で導入された実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)をはじめとする各種支援策が縮小・終了したことがある。これらの支援策によって一時的に延命されてきた企業が、需要回復局面で待ち受けていた原材料費の高騰、人件費の上昇、そして深刻な人手不足という新たな試練に耐えきれず、事業継続を断念するケースが増加している。これは、市場が正常な新陳代謝の過程に入り、競争力の低い企業が淘汰されるフェーズに移行したことを示している。
5.2. 「人手不足倒産」「物価高倒産」の分析
近年の倒産動向で特筆すべきは、その要因の変化である。従来の倒産が主に「販売不振」、すなわち需要サイドの問題に起因していたのに対し、現在は供給サイド・コストサイドの問題に起因する倒産が急増している。
- 人手不足倒産: 「求人を出しても応募がない」「従業員が退職して事業が回らない」「人件費の高騰に耐えられない」といった、人手不足に直接関連する倒産が高水準で推移している。2025年7月には、月間の件数が過去最多の41件を記録した 39。これは、需要があってもサービスを提供する担い手がいないために事業継続が不可能になるという、極めて現代的な経営課題が企業の存続そのものを脅かしていることを示している。
- 物価高倒産: 原材料費やエネルギー価格の高騰分を、販売価格へ十分に転嫁できずに採算が悪化し、倒産に至るケースも増加している 40。特に、価格競争が激しい業態や、価格決定力の弱い中小企業がこの影響を強く受けている。
これらの倒産の増加は、本レポートで一貫して指摘してきた構造変化が、もはや単なる経営環境の変化ではなく、企業の生死を分けるレベルに達していることを示す動かぬ証拠である。低価格・労働集約型というデフレ時代のビジネスモデルから脱却し、生産性を高め、付加価値を価格に転嫁できる経営モデルへと転換できなかった企業から、市場からの退出を迫られている。
この一連の動きは、短期的には痛みを伴うものの、長期的な視点で見れば、業界が「高付加価値・高生産性モデル」へと移行する過程で生じる必然的な「創造的破壊」の一側面と捉えることもできる。生産性の低い企業が市場から退出することで、残された労働力や顧客が、より生産性の高い企業へと再配分される。結果として、業界全体の平均的な生産性や収益性が向上し、産業構造がより健全で持続可能なものへと転換していく可能性がある。
第6章 結論と将来展望
本章では、全章の分析を総括し、日本の飲食・宿泊・旅行サービス業界の今後の展望と、企業が持続的に成長するための要件を提言する。
6.1. 主要な調査結果の総括
本レポートの分析から、日本の飲食・宿泊・旅行サービス業界が直面する経営環境の全体像が明らかになった。
- 市場の二重構造: 経営状況は、円安を背景とした記録的なインバウンド需要に牽引される形で回復している。しかしその裏で、国内市場は物価高による実質賃金の伸び悩みを背景に停滞・変容しており、市場は外需と内需の二重構造を呈している。
- 構造的逆風: デフレ時代の終焉は、深刻な人手不足と恒常的なコスト上昇圧力という、業界にとって構造的な逆風をもたらした。これは、安価な労働力に依存した従来のビジネスモデルの限界を露呈させている。
- 三位一体の戦略転換: この構造変化に対応するため、先進的な企業は「人材戦略の再構築」「DXによる生産性革命」「M&Aによる業界再編」を三位一体で推進している。これらは個別の戦術ではなく、相互に連携した包括的な経営変革パッケージとして機能している。
- 二極化と新陳代謝: 変革への適応能力の差は、企業間の収益格差を拡大させ、二極化を加速させている。適応できない企業は「人手不足倒産」や「物価高倒産」という形で市場から退出を余儀なくされており、業界の新陳代謝が進行している。
6.2. 業界が直面する構造的課題と持続的成長への提言
これらの調査結果を踏まえ、業界が持続的に成長するために取り組むべき課題と、そのための提言を以下に示す。
- 提言1:ビジネスモデルの再定義
安価な労働力に依存した労働集約型モデルからの完全な脱却が急務である。今後は、テクノロジーの活用を前提とし、少ない人員でも高い付加価値を生み出せる高生産性・高付加価値モデルへの転換を、経営の最優先課題として設定する必要がある。これは、単なる設備投資に留まらず、業務プロセス、組織構造、収益モデルの全てを見直すことを意味する。 - 提言2:人的資本経営への本格移行
従業員を変動費としての「コスト」と見なす旧来の考え方を捨て、持続的な価値創造の源泉である「人的資本」として捉え直す経営への本格移行が求められる。単に市場に合わせて賃金を引き上げるだけでなく、体系的な研修によるスキル開発、明確なキャリアパスの提示、そして多様な働き方を許容する柔軟な労働環境の整備を通じて、従業員エンゲージメントを高め、選ばれる企業となることが不可欠である。 - 提言3:データ駆動型経営の徹底
経営者の勘や過去の経験だけに頼る経営から、客観的なデータに基づいて意思決定を行うデータ駆動型経営への転換を徹底すべきである。顧客データ、販売データ、業務データを収集・分析し、価格設定、マーケティング戦略、新サービス開発、人員配置など、あらゆる経営判断の精度を高めることが、競争優位性を確立する上での鍵となる。
6.3. 今後注目すべき主要トレンドと成功企業の要件
最後に、業界の未来を形作るであろう主要なトレンドと、その中で成功を収める企業に共通する要件を提示する。
今後注目すべきトレンド:
- インバウンド需要の質的変化: 単なる「爆買い」から、地方でのユニークな文化体験や自然体験を求める「コト消費」への深化がさらに進む。これに対応できる、地域に根差した魅力的なコンテンツの造成が重要となる。
- 国内市場の価値志向: 国内消費者は、価格だけでなく、健康や環境配慮(サステナビリティ)といった新たな価値基準で商品・サービスを選ぶ傾向が強まる。
- テクノロジーのさらなる進化: 生成AIなどの新たな技術が、顧客一人ひとりに最適化されたパーソナルな体験の提供を可能にし、顧客満足度のレベルを一段と引き上げる。
成功企業の要件:
これらのトレンドと構造変化の中で勝ち抜く企業は、以下の3つの要素を兼ね備えているだろう。- 俊敏性(アジリティ): 市場の変化や新たなテクノロジーの登場に迅速に対応し、ビジネスモデルを柔軟に変革できる組織的な能力。
- 投資能力: DXや人材育成、M&Aといった未来への投資を、継続的に実行できるだけの財務基盤と資本力。
- 組織文化: 多様なバックグラウンドを持つ人材を惹きつけ、その能力を最大限に引き出し、従業員一人ひとりが主体的に変革に参加できる、オープンで魅力的な組織文化。
日本の飲食・宿泊・旅行サービス業界は、厳しい試練の時代にあると同時に、過去の慣習を断ち切り、新たな成長モデルを構築する絶好の機会にも直面している。この歴史的な転換点を乗り越え、未来を切り拓くことができるか否かは、各企業の変革への意志と実行力にかかっている。
引用文献
- 最多の6.6億人泊 日本人は1%減 観光庁宿泊旅行統計調査2024年確定値, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.kankokeizai.com/2507250630kks/
- 宿泊旅行統計調査 (2024年・年間値(確定値)) – 国土交通省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001905698.pdf
- 宿泊旅行統計調査2024年12月~中国人延べ宿泊者数がコロナ禍前を回復, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=80996?site=nli
- 宿泊旅行統計調査2024年6月~国内旅行は弱い動きだが、インバウンド需要は好調~ | ニッセイ基礎研究所, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=79241?site=nli
- 2024年12月の外食市場動向:飲食店が今取り組むべき戦略とは?, 11月 2, 2025にアクセス、 https://fs-ring.jp/news_trend/1163/
- 日本フードサービス協会、2024年年間の外食市場動向調査結果を発表 – サッポロビール, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.sapporobeer.jp/hanjo/gyokai/topics/post5662.html
- 外食市場に関する調査を実施(2024年) | ニュース・トピックス …, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3642
- 外食需要動向(2024年1月), 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.yokohama-ri.co.jp/html/report/pdf/gaishoku2401.pdf
- マイナビキャリアリサーチLab 宿泊業レポート(2024年8月), 11月 2, 2025にアクセス、 https://career-research.mynavi.jp/wp-content/uploads/2024/08/2024-8-syukuhaku.pdf
- 人手不足が宿泊施設の稼働に与える影響の試算 – 三井住友トラスト …, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.smtri.jp/report_column/report/pdf/report_20230419_1.pdf
- 経済分析レポート 需要高まる宿泊飲食サービス業の動向 – 帝国データバンク, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tdb.co.jp/resource/files/assets/d4b8e8ee91d1489c9a2abd23a4bb5219/41e205618dbf425298c33701fb3e4d28/e2024072901.pdf
- 省力化投資促進プラン ―宿泊業―, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/shouryokukatousi/02.pdf
- コロナ禍後を見据えた観光業の雇用改革に向けた課題, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.jri.co.jp/file/report/jrireview/pdf/13942.pdf
- 観光業の雇用改革に向けた課題 (2024年9月5日 No.3650) | 週刊 経団連タイムス, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.keidanren.or.jp/journal/times/2024/0905_07.html
- 令和6年度「宿泊業の人材確保・育成の状況に関する … – 国土交通省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001891438.pdf
- 2024 年(令和6年)個人企業経済調査 結果の概要, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.stat.go.jp/data/kojinke/kekka/pdf/2024gaiyou.pdf
- 2023 年(令和5年)個人企業経済調査 結果の概要, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.stat.go.jp/data/kojinke/pdf/2023gaiyou.pdf
- 宿泊業の 高付加価値化のための 経営ガイドライン – 国土交通省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001583232.pdf
- 【2025年最新】小売業界の人手不足を解消する採用戦略と成功事例|少子高齢化・シフト問題への実践対応, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.saiyoutantou.com/saiyou-seikou-jirei/9838/
- 『特定技能』と『技術・人文知識・国際業務』―ホテル業界での外国人雇用に適した在留資格とは?, 11月 2, 2025にアクセス、 https://tlg-visa.law/case/%E3%80%8E%E7%89%B9%E5%AE%9A%E6%8A%80%E8%83%BD%E3%80%8F%E3%81%A8%E3%80%8E%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%83%BB%E4%BA%BA%E6%96%87%E7%9F%A5%E8%AD%98%E3%83%BB%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%A5%AD%E5%8B%99%E3%80%8F%E2%80%95/
- 宿泊分野における特定技能外国人等の受入れ事例①, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/810002193.pdf
- 宿泊分野の特定技能外国人材受入れ成功要因, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001582319.pdf
- 飲食店の人手不足はどうなる!?アルバイト市場動向から見る採用戦略 – ネオキャリア, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.neo-career.co.jp/humanresource/knowhow/b-contents-parttime-insyokuhitodebusoku-190213/
- 宿泊業界DX完全ガイド|導入メリット・課題・成功事例まで一挙公開 – リスキリングナビ, 11月 2, 2025にアクセス、 https://reskilling-navi.com/column/shukuhakugyo_dx
- 宿泊業界の人手不足は【ホテルDX】で解決!成功事例と導入メリットをご紹介 – cmkPLUS, 11月 2, 2025にアクセス、 https://plus.cmknet.co.jp/hotel-dx/
- ホテルのDX成功事例15選!収益UPや人手不足解消、顧客満足度UPなど | ニューラルオプト, 11月 2, 2025にアクセス、 https://neural-opt.com/hotel-dx-cases/
- ホテルDXとは?導入のメリット・成功事例・注意点を徹底解説, 11月 2, 2025にアクセス、 https://relohotel-solutions.com/column/dx-introduction/
- ホテル業界におけるDXの成功事例5選 – Yopaz, 11月 2, 2025にアクセス、 https://yopaz.jp/trend/successful-dx-hotel-industry/
- 飲食施設における IT 活用と生産性との関連分析 – 経済社会総合研究所, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.esri.cao.go.jp/jp/esri/archive/e_rnote/e_rnote060/e_rnote060.pdf
- 観光DXの成功事例5選!メリットや推進のポイントを徹底解説 – ゼンリンデータコム, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.zenrin-datacom.net/solution/blog/tourism-DX-case-studies
- 観光分野の DX推進に向けた優良事例集 – 国土交通省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001736089.pdf
- 観光DXの事例を紹介 観光DX企業の選び方や推進する上での課題も解説, 11月 2, 2025にアクセス、 https://social.tobutoptours.co.jp/column/sightseeing_dx/
- 【飲食M&A連載 #04】2024年外食M&A総まとめ 件数増加と多様化が進んだ一年, 11月 2, 2025にアクセス、 https://food-dx.com/article/2024M_A
- 2025年 外食M&Aを読む ― 5つの視点と最新事例|照井久雄 – note, 11月 2, 2025にアクセス、 https://note.com/teruhisa10/n/ne4694f204814
- インバウンド特需を追い風にしたホテル・旅館・民泊M&Aの最新動向, 11月 2, 2025にアクセス、 https://info.manda.bz/2025/08/11/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%90%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%83%89%E7%89%B9%E9%9C%80%E3%82%92%E8%BF%BD%E3%81%84%E9%A2%A8%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%9F%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E3%83%BB%E6%97%85%E9%A4%A8%E3%83%BB/
- ホテル・旅館業界のM&A事例や最新動向を解説 | マネーフォワード クラウド, 11月 2, 2025にアクセス、 https://biz.moneyforward.com/ma/basic/810/
- 【2025年版】外食・飲食業界のM&A・事業承継の動向と実態, 11月 2, 2025にアクセス、 https://ma.sharemall.co.jp/columns/restaurant-industry-ma
- 【2025年最新】飲食業界のM&A動向!相場や成功事例、メリット・デメリットを解説, 11月 2, 2025にアクセス、 https://ma-navigator.com/columns/innsyokutenn_ma
- 倒産件数は830件 33カ月連続で前年同月を上回り戦後最長に2024年度は11年ぶりの1万件台へ ― 全国企業倒産集計2025年1月報 | 株式会社帝国データバンクのプレスリリース – PR TIMES, 11月 2, 2025にアクセス、 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001021.000043465.html
- 東京商工リサーチ 令和7年7月の全国企業倒産状況 負債総額1670億3500万円, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.hoteresonline.com/articles/14452