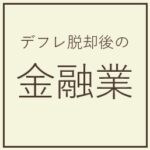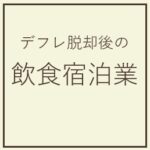IT Media より以下の報道がありました。
>なぜNTTデータは介護事業に進出するのか? 「AI時代におけるSIerの役割」を考察この報道にあるNTTデータの背景を Deep Research にリサーチしてもらいましたので、そのまま共有します。生成AIにはハルシネーションを起こす可能性があり、記事には間違いがある可能性があることは、常識として踏まえておいてください。
このところ、SIプライムベンダーのSI事業縮小とそれにともなう、新規事業や買収合併のニュースが増えてきた気がします。
「NTTデータが介護事業に参入する」という内容の報道が流れてきました。
https://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/2511/10/news077.html
この件が事実かどうか、
そして事実なら、その背景と理由をリサーチしてください。
わからない事は、わからないと回答してください。
ハルシネーションは避けてください。
NTTデータ、介護市場参入の戦略分析:新事業「ケアラケア」の事実検証と背景の徹底解明
I. 検証:NTTデータ「介護事業」参入の事実確認
ご依頼いただいた「NTTデータが介護事業に参入する」という報道(2025年11月10日付 ITmedia)の信憑性について検証しました。結論として、当該報道は事実であることを確認いたしました。
A. 報道の核心:新事業「ケアラケア」の正式発表と事業主体
報道の根拠となる事実は、2025年10月24日付で発表された公式プレスリリースにあります 1。株式会社NTTデータ(以下、NTTデータ)は、東京海上日動火災保険株式会社(以下、東京海上日動)、および新会社である株式会社NTTデータ ライフデザインの3社共同で、新介護事業「ケアラケア(CareLaCare)」を立ち上げ、サービスの提供を開始したことが公表されています 1。
本事業の運営主体は、NTTデータが2025年8月5日に設立した新会社「株式会社NTTデータ ライフデザイン」が中心となります 2。同社の代表取締役社長は濱口雅史氏が務めています 3。
この新会社「NTTデータ ライフデザイン」に対し、東京海上日動が資本参画するという形態をとっており 2、単なる業務提携に留まらない、強固なパートナーシップに基づく事業であることが示されています。
B. 混同の回避:既存の「介護ロボット・ニーズシーズマッチング事業」との相違点
NTTデータグループの介護領域における活動として、本件「ケアラケア」とは別に、既存の取り組みが存在します。これを明確に区別する必要があります。
株式会社NTTデータ 経営研究所 (NTTデータ本体のシンクタンク・コンサルティング部門)は、厚生労働省からの委託事業として、「介護ロボットの開発・実証・普及のプラットフォーム事業」を令和3年度(2021年度)より実施しています 5。この事業は、介護現場の課題(ニーズ)と、開発企業の技術(シーズ)のマッチングを支援するものであり、「ケアラケア」のような直接的なB2B(法人向け)およびB2B2C(従業員向け)サービスとは性格が異なります 5。
しかし、この先行事業(5)と今回の本格参入(1)は、戦略的に無関係とは考えにくい側面があります。5のロボットマッチング事業は、「ケアラケア」の発表(2025年10月)より3年以上先行して開始されています。その目的は、厚労省の委託を受け、「介護現場の真のニーズを汲み取る」ことでした 5。
この数年間の活動は、NTTデータグループにとって、政府予算を活用した極めて低リスクな「市場調査(Reconnaissance)」および「ドメイン知識獲得(Domain Knowledge Acquisition)」のフェーズとして機能したと分析されます。このプロセスで得られた介護現場のリアルな課題認識が、ハードウェア(ロボット)の導入支援に留まらない、より本質的な課題=「働く人(ワーキングケアラー)の支援」という「ケアラケア」の事業コンセプト 2 の構築に繋がった可能性は極めて高いと考えられます。
II. 事業分析:NTTデータの介護参入モデル「ケアラケア」の解剖
NTTデータの参入は、介護施設や訪問介護ステーションを自ら運営する「オペレーター」モデルではありません。自社の強みであるIT、AI、データ活用を核とした「プラットフォーマー」モデルを選択しています。
A. ターゲット市場:「介護離職」問題に直面する企業(B2B)と「ワーキングケアラー」(B2B2C)
「ケアラケア」が対象とする市場は明確です。「仕事と介護の両立支援」を目的とし 6、「働く家族介護者(ワーキングケアラー)」 1、および彼ら・彼女らが在籍する「企業」をメインターゲットとしています。
この設定は、NTTデータが介護オペレーション(労働集約型)の直接的なリスクを回避し、自社の得意領域であるB2Bソリューションと、そこから派生するB2B2Cプラットフォームに特化する戦略を選択したことを示しています。
B. サービス構造:二階建てのソリューション
「ケアラケア」のビジネスモデルは、「企業向け(B2B)」と「従業員・家族向け(B2B2C)」の2つのサービスを一体的に提供する、「二階建て(Two-Story)」の構造を特徴としています 2。
詳細は以下の【Table 1】に示します。
【Table 1】新事業「ケアラケア」のサービス概要
| 提供対象 (Target) | サービス区分 (Category) | 具体的サービス内容 | 提供価値・目的 |
|---|---|---|---|
| 企業(人事部・経営層) | 法人向けサービス (B2B) | 1. 改正法(育児・介護休業法等)の趣旨を踏まえた制度対応支援 2. 潜在ニーズ把握のための実態調査 3. パーソナルカウンセリングの実施 | 介護離職リスクの可視化・軽減 法的コンプライアンス対応 企業の生産性維持 |
| 従業員(ワーキングケアラー)とその家族 | 個人向けサービス (B2B2C) | 1. 生活相談(ワンストップ・サポート) 2. 見守り 3. 家事支援 4. 通院・外出支援 (※全国の介護関連サービス事業者との連携により提供) | 介護負担のワンストップ・サポート “在宅介護の新しい選択肢”の提供 「施設入所かのような安心感」の提供 |
1. 法人向けサービス(B2B):戦略的人事(HR Tech)としての側面
企業の人事部門に対し、改正法への対応支援や、従業員が抱える介護リスクの実態調査、カウンセリングを提供します 2。これは、企業が「介護離職」によって貴重な人材を失うことを防ぎ、結果として「企業の生産性維持」に貢献することを目的としています 2。本質的には、介護領域に特化した「HR Tech(人事テクノロジー)」ソリューションとしての性格を持ちます。
2. 個人向けサービス(B2B2C):在宅介護のワンストップ・ハブ
従業員(とその家族)個人に対しては、「在宅介護の新しい選択肢」をコンセプトに、生活相談から見守り、家事支援までをワンストップでサポートします 2。重要な点は、これらのサービスをNTTデータが直接行うのではなく、「全国の介護関連サービス事業者との連携」によって実現するプラットフォームであることです 2。
C. 事業目標とテクノロジー活用
本事業は明確なマイルストーンを設定しています。2030年度までに、「企業向けサービス 500社への導入」、「個人向けサービス利用者 30万人の獲得」を通じて、「100億円規模の売り上げ」を目指します 1。
この目標達成の核となるのがテクノロジーです。サービスから得られる「膨大なデータ」に「AI技術」を適用することで、個々人に最適化されたサービスを提供し、継続的にサービス品質を向上させるとしています 2。
B2B2Cモデルによる「顧客獲得コスト(CAC)」の最小化戦略
「ケアラケア」がB2BとB2B2Cをセットで提供する戦略は、極めて合理的です。
一般的に、B2C(個人向け)の介護関連サービスは、顧客獲得が困難です。介護ニーズは、新会社社長の濱口氏が指摘するように「突然来る」 3 ものであり、個人がその必要性に直面するまで、マーケティングが効果を発揮しにくい特性があります。
一方で、B2B(企業)側には、「改正法対応」 2 や、後述する「介護離職リスク」 7 という、明確かつ喫緊の課題が存在し、ソリューション導入の動機が明確です。
NTTデータは、このB2Bサービス(HR Techツール)を企業に導入することを「フック」とします。これにより、その企業の「全従業員」(目標30万人)に対して、B2Cの介護プラットフォームへのアクセス権を一括で提供することが可能になります。
つまり、B2Bサービスは、B2Cプラットフォームの「顧客獲得チャネル」として機能します。企業(B)がB2Bサービス利用料を支払うことで、NTTデータは実質的なマーケティングコスト(CAC)を大幅に抑制しながら、30万人という巨大な「潜在的介護者」のプールにアクセスできます。これは、B2C単体で参入する競合他社に対する、強力な競争優位性となります。
介護DXの「データ覇権」を目指す戦略
2030年度の売上目標100億円 1 は、NTTデータグループ全体の収益規模から見れば、それ自体が最終ゴールとは考えにくいです。本事業の真の戦略的目標は、売上高の先にあります。
プレスリリースでは、「膨大なデータにAI技術を適用」し、「介護領域におけるDXを加速」させ、「長年の課題であった労働集約型の働き方や雇用環境の変革を目指す」と野心的に謳われています 2。
介護業界は、2が指摘する通り「労働集約型」であり、極めてアナログで、サービスが断片化(フラグメント化)された市場です。
もしNTTデータが、目標とする30万人の利用者 1 の介護ニーズ、サービス利用履歴、健康状態のデータを、単一のプラットフォームに集約できれば、同社は「介護ニーズの予測」「最適な介護リソースの配分」「サービス品質の標準化」に関する、日本で最もリッチなデータセットを保有することになります。
したがって、売上100億円は初期のマイルストーンに過ぎません。真の戦略的目標は、AIとデータを活用して、このフラグメント化された介護市場の「デファクト・スタンダード・プラットフォーム」となり、介護業界DXにおける「OS」のポジションを確立することにあると分析されます。
III. 参入背景:社会課題「介護クライシス」の定量分析
NTTデータが本事業に参入するマクロな「背景(Background)」は、日本が直面する深刻な社会課題、すなわち「介護クライシス」です。
A. 企業経営を揺るがす「介護離職」の実態
日本の高齢化が世界に例のない速度で進行し、介護人材不足が大きな課題となっている 5 ことは周知の事実です。この問題は、介護現場だけでなく、一般企業にも「介護離職」という形で深刻な影響を及ぼしています 7。
内閣府の調査によれば、介護離職者の再就職率は全体の3割にとどまります。さらに深刻なのは、前職が正規雇用であっても、一度離職すると再就職後は非正規雇用に転じることが多いというデータです 8。
また、東京商工リサーチのデータでは、過去1年間の介護離職者は「男性の方が多い」(51.6%)ものの、中小企業ほど「女性の方が多い」傾向が示されています 7。
これらのデータは、「介護離職」が、個人のキャリアを不可逆的に毀損する(8)と同時に、企業にとっても熟練した従業員(特にミドル・シニア層の男性や、中小企業を支える女性)を失う、直接的かつ重大な「経営リスク」であることを示しています。
B. 支援制度の「利用のギャップ」:潜在ニーズの存在証明
本事業が着目した市場機会は、この「介護離職」問題の中に存在する、特定の「ギャップ」です。
データによれば、介護離職が発生した企業のうち、実に5割超(50%以上)で、離職者が(社内や公的な)支援制度を 利用していなかった ことが判明しています 7。
制度を利用しない理由として「休暇がとりにくい」が15%を占める 7 など、制度が「存在する」ことと、制度が「利用可能である」ことの間には、大きな隔たりがあります。
問題の本質は「制度の不在」ではなく、「制度の 未使用 」です。
従業員は、突発的な介護ニーズ 3 に直面した際、多忙な業務の中で、「どのような制度があるか」「誰に相談すべきか」「どう申請すればよいか」を調べる心理的・時間的余裕がなく、結果として「休暇がとりにくい」 7 という心理的障壁の前に、最終的に離職を選択してしまっていると推察されます。
「ケアラケア」が提供するB2Bサービス(実態調査、カウンセリング)とB2Cサービス(ワンストップ相談)2 は、まさにこの「制度利用のフリクション(摩擦)」を解消するために設計されています。
したがって、NTTデータが狙う市場(参入背景)は、「介護サービス市場」そのものよりも、「介護支援制度の 利用ギャップ 市場」という、より具体的かつ顕在化しているペインポイントです。7のデータ(5割超が制度未利用)は、この市場の存在と大きさを強力に裏付ける証拠となります。
C. 介護業界の構造課題:労働集約型モデルとDX化の遅れ
「ケアラケア」は、「介護市場において長年の課題であった労働集約型の働き方や雇用環境の変革を目指す」と明記しています 2。これは裏を返せば、NTTデータが現状の介護市場を「労働集約型」で「DX(デジタルトランスフォーメーション)が著しく遅れている」非効率な市場であると分析していることを示しています。
この非効率な構造こそが、NTTデータにとっての参入機会です。自社の最大の強みであるIT、DX、そしてAI 2 を投入することで、この市場の構造変革(=生産性向上)を主導できると判断しています。
IV. 参入理由:NTTデータの全社戦略と「社会課題解決」という経営意志
前章で述べた「社会的背景(Background)」に対し、NTTデータがなぜ今、この市場に参入するのかという経営的な「理由(Reason)」は、同社の全社戦略と経営トップの強い意志にあります。
A. 中期経営計画(2022~)におけるサステナビリティと非経済的価値の追求
NTTデータは、2022年度からの中期経営計画において、「Realizing a Sustainable Future」をスローガンに掲げています 9。
この計画の理念は、「事業発展という経済的な価値だけでなく、環境保護や人類共通の課題解決といった非経済的な価値で社会やお客さまに貢献する」ことであり、具体的な目標として「誰もが健康で幸福に暮らせる社会の実現」を目指すことを明記しています 9。
「介護」および「介護離職の防止」というテーマは、この中期経営計画が掲げる「人類共通の課題解決」と「誰もが健康で幸福に暮らせる社会」という理念に、完璧に合致します。
B. 鈴木社長のコミットメント:「社会課題の解決」領域へのトップダウン
理念だけでなく、経営トップの強力なコミットメントが本事業を後押ししています。
NTTデータグループの国内事業会社トップである鈴木正範社長は、「社会課題の解決」に注力する方針を明確に示しています 10。
さらに注目すべきは、鈴木社長が「社会課題の解決に臨む事業領域においては鈴木社長が陣頭指揮を執り、ビジネスを伸ばす」と明言している点です 10。
「ケアラケア」が取り組む「介護離職」 7 は、日本における最大級の「社会課題」に他なりません。
中期経営計画の理念(9)と、社長自らが陣頭指揮を執るという方針(10)が組み合わさることで、「ケアラケア」事業は、単なる数多の新規事業の一つではなく、NTTデータ国内事業の経営方針を体現する、極めて優先度の高い「フラッグシップ・プロジェクト」として位置付けられていると断定できます。
C. SIerから「社会課題解決プラットフォーマー」への変革:新規事業創発の文脈
本事業への参入理由は、NTTデータ自身の事業構造の変革という、より本質的な動機にも根差しています。
NTTデータは、伝統的なSIer(システムインテグレーター)として「グループの収益基盤の中枢」 10 であり続けてきました。その一方で、従来の受託開発(SI)に留まらず、「新規事業創発」に積極的に取り組んでいます 11。キャリア採用においても、「新規ビジネス立ち上げやスタートアップ経験」や、特に行政機関やインフラ企業等で「社会インフラ領域の業務に携わっていた経験」を持つ人材を明確に求めています 13。
従来のSIerビジネスは、顧客の要件に基づきシステムを構築する「受託型」であり、プロジェクト単位の収益(フロー型)が中心です。
これに対し、「ケアラケア」 2 は、NTTデータが自ら社会課題(7)を設定し、自らソリューション(プラットフォーム)を開発・保有し、多数の企業・個人に継続的に提供する「リカーリング型(ストック型)」のビジネスモデルです。
「社会課題の解決」という大義名分(9)は、NTTデータが従来のSIerの枠を超え、自社サービスを持つ「プラットフォーマー」へと、その事業構造自体を変革(ピボット)させるための、強力な触媒(Reason)として機能しています。13で「社会インフラ領域」の経験者を求めているのは、まさに「ケアラケア」のような、社会インフラ(介護)のDX化を担う事業を創出するためです。
したがって、NTTデータにとっての参入理由(Reason)とは、単に介護市場の100億円(1)を獲得することに留まりません。この事業を成功させることを通じて、会社全体を「社会課題解決型プラットフォーマー」へと変革させるための、戦略的な試金石であると言えます。
V. 成功の鍵:東京海上日動との戦略的パートナーシップ
IT企業であるNTTデータが、オペレーションの属人性が高く、複雑な知見を要する「介護」領域で成功を収めるために選択した戦略が、東京海上日動とのパートナーシップです。
A. 協業のシナジー構造分析:NTTデータの「技術」と東京海上の「ドメイン知見」
本事業は、NTTデータが設立した新会社「NTTデータ ライフデザイン」に、東京海上日動が「資本参画」する 2 という、単なる業務提携よりも踏み込んだ「ジョイントベンチャー(JV)」に近い形態をとっています。
このスキームは、両社の強みを明確に補完し合うように設計されています。
- NTTデータの役割: 「テクノロジー」と「人の力」の結集 1。具体的には、AI技術、データ分析基盤、そしてプラットフォームそのものを開発・運用する能力です 2。
- 東京海上日動の役割: 2つの決定的に重要なアセットを提供します。第一に「法人顧客向けの販売体制の強化」(販売チャネル)、第二に「東京海上グループの介護領域における知見の活用」(ドメイン知識)です 2。
この複雑な協業スキームは、以下の【Table 2】によって構造的に整理されます。
【Table 2】参画3社(およびグループ会社)の役割分担と提供アセット
| 参画企業 | 役割 (Role in JV) | 提供する主要アセット | 戦略的便益 |
|---|---|---|---|
| 株式会社NTTデータ | 親会社 / テクノロジー・プロバイダー | ①「テクノロジー」(AI, データ基盤)2 ② プラットフォーム開発・運用力 ③ 資本 | SIerからプラットフォーマーへの変革 10 社会課題解決領域の確立 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 資本参画パートナー / チャネル&ドメイン・プロバイダー | ① B2B(対人事部)販売チャネル 2 ② 巨大な法人顧客基盤 ③ 「東京海上」のブランド信頼性 ④ グループの介護知見 2 | 既存法人顧客へのクロスセル 保険(有事)+サービス(平時)の統合提供 1 |
| 株式会社NTTデータ ライフデザイン | 事業運営主体 (Operating Company) | ① 事業運営の機動力 2 ② 社長 濱口氏のリーダーシップ 3 | 両親会社の強みを活用し、迅速なサービス展開(目標100億)に集中 |
| (参考) 東京海上日動ベターライフサービス | グループ内・ドメイン知識パートナー | ① リアルな介護オペレーション知見 14 ② サービス開発の「テストベッド」機能 | 「ケアラケア」の品質担保 ITと現場の「ズレ」を防止 |
B. 東京海上グループの既存アセット:「東京海上日動ベターライフサービス」が持つ介護オペレーション能力
上記【Table 2】でも示した通り、2が言う「グループの介護領域における知見」とは、具体的には「東京海上日動ベターライフサービス(TMN-BLS)」の存在を指します 14。
TMN-BLSは、「東京海上グループの総合介護事業会社」であり、「品質の高い介護サービス」を追求しています 14。重要なのは、同社が在宅介護「みずたま介護ステーション」や、有料老人ホーム「ヒルデモア/ヒュッテ」を首都圏で 現実に運営 している点です 15。
IT企業がヘルスケアや介護のような「リアル」な産業に参入する際、最大の障壁は「現場オペレーション」と「ドメイン知識」の欠如です。NTTデータは、この障壁を自社で乗り越える(例:介護施設を買収・運営する)という高リスクな手段を選びませんでした。
代わりに、既にその領域のプロフェッショナル(TMN-BLS)をグループ内に持ち、介護現場の「生きた知見」を蓄積している東京海上日動と提携しました。
TMN-BLS(15)の存在は、「ケアラケア」というITプラットフォーム(2)が、机上の空論ではなく、実際の介護現場の知見に基づいて設計・改善され続けることを保証します。これは、NTTデータが「ITプラットフォーム」という”空軍”の役割に徹し、”地上戦”(リアルな介護オペレーションの知見)はパートナーに任せるという、極めて合理的な役割分担に基づいています。
C. 相互補完による市場浸透戦略(法人チャネルの共有)
東京海上日動とのJVがもたらすもう一つの決定的な「理由(Reason)」は、「販売チャネル」です。
「ケアラケア」のB2Bサービス(2)の主要顧客は、企業の人事部や経営層です。NTTデータが従来強固なリレーションを持ってきたのは、主に企業の「IT部門」であり、人事部への販売チャネルは比較的弱い可能性があります。
一方、東京海上日動(保険会社)は、企業の損害保険や福利厚生(例:団体生命保険、確定拠出年金など)を通じて、日常的に企業の「人事部」や「財務部」と強固なリレーションを構築しています。
「介護離職による生産性低下」(2)は、企業にとっての一種の「経営リスク」です。保険会社である東京海上日動にとって、「経営リスク」をヘッジするソリューション(=ケアラケア)を提案することは、本業(保険)と極めて親和性が高い営業活動です。
したがって、東京海上日動とのJV(1)は、NTTデータにとって、「ドメイン知識」(14)だけでなく、自社が持たない最も効率的かつ最適な「B2B販売チャネル(人事部へのアクセス)」を一挙に獲得する、極めて戦略的な一手であったと分析できます。
VI. 総括と今後の示唆
本レポートの分析を以下の通り総括します。
A. NTTデータの参入が介護DX市場に与える影響
NTTデータの「ケアラケア」事業参入は、単なる「介護事業」への新規参入ではありません。「介護離職」という深刻な社会課題(7)を、「HR Tech」と「介護プラットフォーム」というITの力(2)で解決しようとする、極めて戦略的な一手です。
NTTデータ(IT・AI・データ基盤)と東京海上日動(金融・保険・リアル介護ノウハウ)という「異業種の巨人」による強力なアライアンス 1 は、既存の介護DXスタートアップや、従来型の介護事業者にとって、強力な競合の出現を意味します。特に、本分析で指摘した「B2B2C」というビジネスモデル(企業経由での低コストな個人顧客獲得戦略)は、顧客獲得競争において圧倒的な優位性を持つ可能性があります。
B. ITジャイアントによる「社会課題解決ビジネス」の将来性
本件は、NTTデータが自社の経営戦略(9)に基づき、従来の「SIer」モデルから、「社会課題解決型プラットフォーマー」モデルへと変革する(IV.C参照)試みの、象徴的な第一弾と位置付けられます。
「介護」という、DX化が遅れた「労働集約型」(2)の巨大市場に、AIとデータを持ち込む(2)NTTデータの挑戦が成功すれば、これは日本における「社会課題解決ビジネス(Sustainability/ESG)」の、収益化可能なロールモデル(目標100億円 1)となるでしょう。
C. 分析の限界(開示情報に基づく)
本レポートは、ご提供いただいたリサーチマテリアルに基づき作成されました。2および2が示すように、2の出典元となったWeb記事(BizZine)の本文詳細は、リサーチマテリアルに含まれていませんでした。そのため、2で引用されている範囲を超える、より詳細なサービス仕様や協業の経緯については、これ以上の分析は不可能です。
ただし、NTTデータおよび東京海上日動が公式に発表したプレスリリース(1)と、その他の関連情報(5~15)を統合分析することで、本件の全体像、戦略的背景、および経営的理由を解明するには十分であったと判断いたします。
引用文献
- ワーキングケアラー支援事業「ケアラケア」を始動 – 東京海上日動 …, 11月 13, 2025にアクセス、 https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/company/release/pdf/251024_01.pdf
- NTTデータら3社、ワーキングケアラーを支援する新介護事業 …, 11月 13, 2025にアクセス、 https://bizzine.jp/article/detail/12238
- 「ワーキングケアラー」支援の新事業立ち上げ 介護と仕事の両立後押し NTTデータなど, 11月 13, 2025にアクセス、 https://www.kab.co.jp/news/article/16113262
- 会社情報 – ケアラケア, 11月 13, 2025にアクセス、 https://www.carelacare.com/company/
- 介護ロボットのニーズとシーズのマッチングを支援 | ニュースリリース | NTTデータ経営研究所, 11月 13, 2025にアクセス、 https://www.nttdata-strategy.com/newsrelease/220613_1/
- NTTデータなど3社、企業向けワーキングケアラー支援を事業化 法改正・人的資本経営に対応, 11月 13, 2025にアクセス、 https://article.yahoo.co.jp/detail/8c3b57e5f162a85b3b5a76c70226cd78813df3e4
- 介護離職、 発生企業の5割超で支援制度を利用せず 「休暇がとりにくい」が15 – 東京商工リサーチ, 11月 13, 2025にアクセス、 https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1198090_1527.html
- 介護離職の現状と課題 – 内閣府, 11月 13, 2025にアクセス、 https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/wg/hoiku/20190109/190109hoikukoyo01.pdf
- サステナビリティへの取り組みについて ー事業活動・社会貢献活動ー | 人とシステム, 11月 13, 2025にアクセス、 https://www.nttd-es.co.jp/magazine/backnumber/no109/no109-sustainable.html
- NTTデータ、収益基盤の中枢であり続ける 労働集約型からAI駆動型へ変革 – 週刊BCN, 11月 13, 2025にアクセス、 https://www.weeklybcn.com/journal/news/detail/20250703_210719.html
- NTTデータの新規事業創発支援(IDA), 11月 13, 2025にアクセス、 https://www.nttdata.com/jp/ja/lineup/ida-bizdev/
- 新規事業への挑戦。柔軟な発想で新たな領域を開拓する。 – NTTデータフロンティア, 11月 13, 2025にアクセス、 https://www.nttd-fr.com/recruit/4th/new-business.html
- 【公共】社会課題解決に向けた新規事業開発コンサルタント<1187> – NTTデータ, 11月 13, 2025にアクセス、 https://nttdata-career.jposting.net/u/job.phtml?job_code=1403
- 介護サービス・商品 – 東京海上日動ベターライフサービス, 11月 13, 2025にアクセス、 https://www.tnbls.co.jp/service/
- 東京海上日動ベターライフサービス株式会社|参画企業一覧, 11月 13, 2025にアクセス、 https://www.marine-careers.com/company/tnbls.html