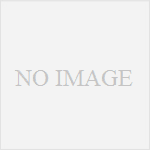(2023年10月27日、為替変動により日本円の価格を変更しました)
Visual Studioの販売価格は以下のMicrosoftの公式サイトにドル価格で掲載されている。
しかし、これを見ても価格パッケージの種類が多すぎて、自分に合ったパッケージはどれなのか直ぐには判断できない。
正直、私も理解するのに少し時間が掛かった。
そこで、簡単に解説記事を書こうと思う。
人に説明するとき、この記事を見せれば済むように。
個人や小規模事業者は無料版が使える
個人や小規模事業者は条件付きでVisual Studio Communityという無料版を使用する事ができる。
これは、ライセンス数が5つ以下、つまりユーザー数が5人以下で、エンタープライズではない場合はこのVisual Studio Communityを使用する事ができる。
エンタープライズの定義は以下の条件の何れかを満たす組織である。
「組織内の合計でPC数が250台を超える。
又は、250人以上のユーザー(従業員や派遣や外注など)が居る。
又は、年間収益が100万ドル(150円/ドルで1億5000万円)を超える」
詳しくは以下の公式情報を参照されたし。
Visual Studio Communityは以下のサイトから入手できる。
ライセンスの基準は「ユーザー単位」
Visual Studio のライセンスには様々な種類があるが、全て「ユーザー単位」のライセンスになっている。
つまり、ユーザー1人に1ライセンスを購入する必要がある。
購入したソフトウェアの1ライセンスで複数台のPCやサーバー機にソフトウェアをインストールして使用する事が可能だ。
一人のユーザーが直接使用するのならば、何台のPCやサーバー機を使用しても構わない。
Visual Studioをインストールするハードウェアの台数に制限はない。
ライセンスは「買い取り」と「サブスクリプション」がある
ライセンスの種類には大きく分けて、買い取り と サブスクリプションがある。
買い取りは、従来のソフトウェア・ライセンス販売と同じだ。
買い取りライセンスはスタンドアロン・ライセンスとして提供される。
サブスクリプションは、月単位と年単位がある。
月単位と年単位それぞれに、また種類がある。
サブスクリプションは大きく分けて二種類
ライセンス提供方法には大きく分けて以下の三種類ある。
クラウド・サブスクリプション
標準サブスクリプション
スタンドアロン・ライセンス
クラウド・サブスクリプション
月単位のサブスクリプションだけが提供される。
Visual Studio ProfessionalとVisual Studio Enterpriseの二種類がある。
長期契約は必要なく、課金は Microsoft Azure サブスクリプションで行う。
Azureサブスクリプションは、クラウド・コンピュータAzureの様々なサービスのライセンス管理に使用しているシステムで、クラウドのAzure同様に従量課金や月額定額制などの料金体系を管理する。
Visual Studioのクラウド・サブスクリプションとは、Azureサブスクリプションのシステムを使用して、Azureと同様に簡潔にVisual Studioライセンスの管理を行う仕組みの事である。
クラウド ソリューション プロバイダー (CSP) から提供される。
Azure portalによりライセンスを閲覧し一元管理することができる。
Azureと併用する場合に便利なライセンス形態である。
また、プログラマーの出入りが多い場合にも便利である。
標準サブスクリプション
昔は「with MSDN」と呼ばれていたライセンス形態である。
年単位のサブスクリプション契約であり、初年に高めの新規ライセンス料を支払い、その後は毎年更新ライセンス料を支払う形態である。
更新しなくても36ヶ月間ライセンスは有効である。
新バージョンへアップグレードしないのなら、購入したライセンスは永続的に有効で、使い続けることができる。
リセラー(小売り販売店)から提供される。
Visual Studio Professionalと
Visual Studio Enterpriseと
MSDN Platformsと
Visual Studio Test Professionalの
の四種類がある。
IDEのVisual Studioが付いているのは前者二つの開発用ライセンスだけで、後者二つはテストや運用専用のライセンスである。
スタンドアロン・ライセンス
もっとも単純で安価なライセンス形態である。
提供される製品はVisual Studio IDEだけで、他のクラウドやサーバー製品は含まない。
買い切りなので、購入したVisual Studioは永続的に使用している。
将来、新バージョンが販売されたら、その都度購入する必要がある。
Microsoftの公式サイトでは「短期間のみ使用するならクラウド・サブスクリプションのVisual Studio Professionalと価格は変わらないよー、買ってねー」という内容の売り込みが書かれているが、紛らわしいので無視した方が良い。
Visual Studio Professionalのスタンドアロン・ライセンスはVisual Studio IDEだけの買い切りである。
サブスクリプションではない。
サブスクリプションに追加される製品
ライセンス形態を分かり難くしているのは、サブスクリプションに追加されるVisual Studio以外の製品である。
サブスクリプション・ライセンスには全て、以下の三つの製品が付属している。
Azure DevOps
Azure DevOps Server
Team Foundation Server
スタンドアロン・ライセンスには、これらは付属していない。
Azure DevOpsとは開発しているソフトウェアのバージョン管理・要件管理・プロジェクト管理・自動ビルド・テスト・リリース管理を行うMicrosoft製品群のパッケージである。
Azure DevOpsはGitも使用できるので、別製品となっている。
標準サブスクリプションには「特典」が付いている
更にややこしい事に、標準サブスクリプションには、「特典」が沢山付いている。
テストと学習に利用を制限されたAzureの利用権。
Microsoft365 Developerのサブスクリプション利用権。
WindowsやWindows Server, SQL Server, Office, Visio, Exchangeなど開発に必要なソフトウェア製品。
トレーニングサービス。
テクニカルサポートや開発者コミュニティなどサポートサービス。
など、かなり盛り沢山である。
ITベンダーが購入するなら標準サブスクリプションでOSやサーバーソフトウェアと纏めてライセンス契約した方が良いかも知れない。
繰り返すが、標準サブスクリプションは、新バージョンへアップグレードしない場合も、購入したライセンスは永続的に有効で、使い続けることができる。
価格は全てドル換算
以上の解説を踏まえて、以下のMicrosoftの公式サイトで、それぞれの価格を確認して欲しい。
解説前より、かなり読みやすくなっているはずだ。
価格は全てドル換算で書かれているので、為替レートを確認して電卓片手に円価格を計算する必要がある。
日本円の価格をざっくり一覧する
為替レートを、1ドル150円として、日本円の価格を以下に一覧しておく。(2023年10月27日更新)
円価格はドル価格を為替レートに従って変換しただけで、小売り販売価格を示しているわけではない。
クラウド・サブスクリプション
| 製品名 | ドル価格 | 円価格 |
| Visual Studio Enterprise | 250ドル/月 | 37,500円/月 |
| Visual Studio Professional | 45ドル/月 | 6,750円/月 |
標準サブスクリプション
| 製品名 | 新規・更新 | ドル価格 | 円価格 |
| Visual Studio Enterprise | 初年新規 | 5,999ドル/年 | 899,850円/年 |
| 更新 | 2,569ドル/年 | 385,350円/年 | |
| Visual Studio Professional | 初年新規 | 1,199ドル/年 | 179,850円/年 |
| 更新 | 799ドル/年 | 119,850円/年 | |
| MSDN Platforms | なし | なし | なし |
| Visual Studio Test Professional | 初年新規 | 2,169ドル/年 | 325,350円/年 |
| 更新 | 899ドル/年 | 134,850円/年 |
スタンドアロン・ライセンス
| 製品名 | ドル価格 | 円価格 |
| Visual Studio Professional | 499ドル | 74,850円 |
ライセンス選択の簡単なアドバイス
ライセンス形態の選択について簡単にアドバイスする。
会社員の個人開発や個人事業主や従業員250人以下の企業などが、売上1億5000万円以下の事業を営んでいて、Visual Studioの利用者が5人以下なら、Visual Studio Community一択である。
その売上が伸びて1億5000万円を超えてもスタンドアロン・ライセンスで充分だと思う。
Visual Studioのバージョンアップはだいたい2年か3年に一度なので、多くても2年に一度499ドル=74,850円支払えば最新のVisual Studioを使い続けることができる。
Visual Studioの利用者5人以上でソフトウェア開発を本業にする事業を営んでいるならば、必要なソフトウェアはVisual Studioだけというわけにもいかないと思う。
Windows, Windows Server, SQL Server, Microsoft365, MS-Office, Visio, Exchange, バージョン管理ソフトなど開発業務に必要なソフトウェアは沢山ある。
これらMicrosoft製品を多数必要とするなら、まとめて標準サブスクリプション・ライセンスを購入した方が良いだろう。
標準サブスクリプションの価格は一見高価に見えるが、Visual Studioだけの価格ではない。
タイムスケールも年単位で計算する。
ITベンダーのように長期的にソフトウェア開発計画を立てる企業に向いたライセンス形態だ。
ITベンダーではないユーザー企業が、社内システムを新規構築する場合、新規開発期間だけ外注先などから技術者など人材を集めてきて、開発が終了したらプロジェクトチームを解散して、運用フェーズに移行するような、プロジェクト体制でVisual Studioを導入するならクラウド・サブスクリプションが適していると思う。
契約が月単位のサブスクリプションなので、短期的な人員の増減に対応し易い。
Azure DevOpsも付いているので、バージョン管理や要件管理・テスト・リリースの管理ソフトウェアも付属している。
Oracle, PostgreSQL, LinuxなどMicrosoft製品以外の製品を組み合わせて、Visual Studioを使用する場合を考える。
この場合Visual Studioを使用するのはフロントエンドだけであり、自社製品であるなら開発環境のバージョンアップは長期的には行わないことが多い。
パッケージソフトウェアの場合、古いバージョンの .NETやWindowsへの対応を長期的に継続しなければならないので、開発環境のバージョンアップの周期が長い。
2020年の時点で、.NET Framework 3.5や4.0を使用していたりする。
Windows7のサポート終了や、.NET Frameworkのサポート終了などのタイミングでマイグレーションすることが多い。
だから、この場合はスタンドアロン・ライセンスで開発者の人数分のライセンスを買い揃え、長期的にそのVisual Studioを使い続けることになる。
サブスクリプション契約は無駄に毎年バージョンアップするので、コストの無駄となる。
開発者によって、適したライセンスは違う。
様々なライセンス形態が用意されているのは「便利」というよりは「必須」と考えた方が良いかも知れない。
以上、Visual Studioライセンス形態の簡単な解説でした。