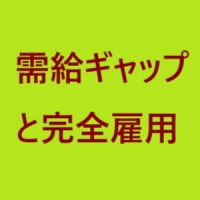この記事は、Gemini Deep Research に「最新の日本のマクロ経済状況」を問い合わせて調査・レポートしてもらったものです。
全てDeep Researchの作成した文章を、そのまま掲載しています。
日本のマクロ経済の岐路:構造転換の只中でデフレからの移行を舵取りする
I. エグゼクティブ・サマリー
本レポートは、現在の日本経済が直面する複雑なマクロ経済状況について、専門的見地から詳細な分析を提供するものである。分析の結果、日本は物価が持続的に上昇する環境への移行には成功したものの、需要主導の持続可能な成長モデルへの転換は未だ途上にあり、その基盤は脆弱であることが明らかになった。現在の日本経済を象徴するのは、歴史的な労働市場の逼迫と実質賃金の停滞という中心的なパラドックスであり、この現象は根深い構造的問題に起因している。
特に、経済の総需要と総供給の差を示す需給ギャップ(GDPギャップ)を巡る議論は、現状認識の鍵を握る。政府や日本銀行の公式推計が依然として需要不足(マイナスのギャップ)を示唆する一方で、市場では広範な人手不足や供給制約が観測されており、両者の間に著しい乖離が見られる。
今後の見通しについては、緩やかな成長が続くと予測されるものの、その実現は米国の通商政策をはじめとする外部リスクをいかに乗り切るかに大きく依存している。本稿では、デフレ脱却政策の進捗、需給ギャップの構造、雇用情勢、そして将来展望という4つの相互に関連する領域を深く掘り下げ、データに基づいた多角的な分析を行う。
II. 現在のマクロ経済概観:脆弱性を内包した回復
A. 成長のダイナミクス:緩慢かつ不均一な拡大
日本経済は、緩やかではあるものの、持続的な成長を示し、底堅さを見せている。直近の2025年のデータでは、第2四半期の実質GDPが前期比0.3%増となり、5四半期連続のプラス成長を記録した。この数値は市場予想の0.1%を上回るものであった 1。政府は2024年度の実績見込みを0.4%とし、2025年度については1.2%の実質GDP成長を見込んでいる 2。この成長を支える一因として、比較的堅調な設備投資が挙げられる。これは、将来の金利引き上げを見越した企業による投資の前倒しが含まれている可能性が指摘されている 1。
しかし、この成長ペースは、日本の過去の平均と比較すると依然として低い水準にある。1980年から2025年までの四半期ごとの平均成長率は0.42%であった 1。現在の成長局面は、新型コロナウイルス感染症のパンデミック期に見られた極端な変動(2020年第2四半期の-7.60%という記録的な落ち込みと、同第3四半期の5.30%という急反発)を経た正常化の過程にあると解釈できる 1。しかし、民間シンクタンクによる2025年第2四半期の成長率予測が年率換算で+0.7%程度にとどまるなど、経済の根本的な勢いは力強さを欠いているとの見方も存在する 4。
B. インフレ圧力:コストプッシュから需要プルへの萌芽か?
物価動向は、日本経済が新たな局面に入ったことを最も明確に示している。消費者物価指数(CPI)は、日本銀行(以下、日銀)が目標とする2%を大幅に上回る水準で推移している 6。2025年6月の最新データでは、総合指数(2020年=100)が111.7となり、前年同月比で3.3%の上昇を記録した 7。より重要なのは、天候に左右されやすい生鮮食品と、価格変動の激しいエネルギーを除いた「コアコアCPI」が前年同月比で3.4%上昇したことである 7。これは、インフレが特定の品目だけでなく、より広範な財・サービスに浸透し始めていることを示唆しており、物価上昇の基調が強まっている証左と言える。
この状況は、約30年間にわたってゼロ近傍のインフレ、あるいはデフレに苦しんできた日本経済にとって、決定的な転換点である 6。日銀や国際通貨基金(IMF)などの国際機関も、日本が2%の物価目標を持続的に達成できる可能性が高まっているとの見解を示している 10。しかし、この新たな物価上昇の傾向が、一過性のものでなく、持続可能なものであるかどうかが、今後の最大の焦点となる。
現在の経済状況は、いわば「二層構造」の回復によって特徴づけられる。一方では、企業部門、特に大手製造業は好調である。経常利益は過去最高水準にあり 11、設備投資も成長の牽引役となっている 1。他方で、家計部門は依然として厳しい状況に置かれている。名目賃金の上昇が物価上昇に追いつかず、実質賃金がマイナス圏で推移しているため、国民の購買力は実質的に低下している。この企業部門と家計部門の乖離が、日本経済の回復の足枷となっている。企業の好業績が、力強い賃金上昇を通じて家計の所得を増やし、それが国内消費を活性化させるという経済の好循環がいまだ確立されていない。この循環の欠如こそが、現在の回復が「脆弱」であると評価される根本的な理由であり、経済が外部からの衝撃に対して弱い構造を維持している原因となっている。
表1:主要マクロ経済指標(直近データと予測)
| 指標 | 最新期/値 | 参照期間 | 2025年度予測(コンセンサス) |
|---|---|---|---|
| 実質GDP成長率(前期比) | 0.3% | 2025年4-6月期 | – |
| 実質GDP成長率(前年比) | 1.2% | 2025年4-6月期 | 1.2% (政府見通し) |
| 消費者物価指数(総合、前年比) | 3.3% | 2025年6月 | 2%台後半 |
| コアコアCPI(前年比) | 3.4% | 2025年6月 | – |
| 完全失業率(季節調整値) | 2.6% | 2024年4月 | 2%台半ば |
| 有効求人倍率(季節調整値) | 1.26倍 | 2024年4月 | 1.3倍前後 |
| 現金給与総額(名目、前年比) | 2.3% | 2025年5月 | 3%前後 |
| 実質賃金(前年比) | -1.7% | 2025年5月 | マイナス圏での推移 |
注:予測値は各種資料を基に分析者が作成。
出典:1
III. デフレ脱却への道:進捗と根強い課題
A. 政策の変遷:「異次元緩和」から慎重な正常化へ
現在のインフレ環境の土台を築いたのは、日銀が長年にわたり推進してきた「量的・質的金融緩和(QQE)」である。この政策は、人々のデフレマインドを転換させ、予想物価上昇率を引き上げることを明確な目的としていた 14。政府との連携の下で進められたこの政策は 16、企業の物価見通しを引き上げることに成功した 11。2%を超える物価上昇が定着したことを受け、日銀は歴史的な政策転換に着手した。2024年にはマイナス金利政策を解除し、その後も段階的な利上げを実施している 17。直近の利上げにより、政策金利は0.50%となり、今後も緩やかなペースでの追加利上げが見込まれている 17。
この金融政策の正常化は、極めて慎重な舵取りが求められるプロセスである。日銀は公式見解として、「賃金と物価の好循環」が確固たるものになるのを見極めるまで、性急な金融引き締めは避ける方針を繰り返し表明している 19。これは、デフレへの逆戻りを防ぎたいという強い意志の表れである。
B. アキレス腱:名目賃金と実質賃金の乖離
デフレ脱却に向けた最大の課題は、名目賃金と実質賃金の乖離に集約される。これは日本経済の「アキレス腱」と言っても過言ではない。2025年5月のデータでは、名目賃金である現金給与総額は前年同月比で2.3%増加したものの、同期間の物価上昇率が高かったため、実質賃金は1.7%の減少となった。これで5ヶ月連続のマイナスであり、賃金の伸びが物価上昇に追いつかない状況が続いている 13。
毎春の労働組合と経営側の交渉(春闘)では歴史的に高い賃上げ率が妥結されているが、その恩恵が大企業から中小・零細企業へと波及するペースは遅く、不完全である 13。長期的な視点で見ても、この問題の根深さは明らかである。2014年以降、名目賃金は緩やかな上昇傾向にある一方で、実質賃金は一貫して低下傾向を辿っている 21。
分析によれば、夏の賞与(ボーナス)の増加により実質賃金は一時的にプラスに転じる可能性があるものの、その後再びマイナスに陥り、安定的にプラスに転じるのは2025年の秋から冬にかけてになると予測されている 13。しかし、2026年以降の見通しは極めて不透明である。特に、米国の関税引き上げなどの外部からの逆風が強まり、企業収益が圧迫されれば、持続的な賃上げの余力は失われかねない 13。
日本は、企業の「価格を上げられない」というデフレマインドの克服には成功した。しかし、それに対応する「賃金を上げ渋る」という企業の慣行、すなわち賃金停滞マインドを打破するには至っていない。このため、現在のインフレは、国内の旺盛な需要に支えられた自己増殖的なものではなく、依然として輸入物価の上昇などコストプッシュ要因に大きく依存している。企業の収益拡大が持続的なベースアップを通じて従業員の所得を増やし、それが消費を拡大させ、さらなる企業収益につながるという、経済の好循環が確立されていないのである。この構造的な欠陥は、現在のデフレ脱却が依然として脆弱な基盤の上にあることを示している。もし外部からのコストプッシュ圧力が弱まった場合、国内に力強い賃金と物価のスパイラルが存在しなければ、インフレ率が再びゼロ近傍に逆戻りするリスクは否定できない。日銀が金融政策の正常化を極めて慎重に進めているのは、このリスクを深く認識しているからに他ならない 19。
表2:名目賃金と実質賃金の推移(前年同期比、%)
| 四半期/年 | 名目現金給与総額 | 消費者物価指数(生鮮除く) | 実質賃金(計算値) |
|---|---|---|---|
| 2023年 Q3 | 1.1 | 3.0 | -1.9 |
| 2023年 Q4 | 1.3 | 2.5 | -1.2 |
| 2024年 Q1 | 2.0 | 2.7 | -0.7 |
| 2024年 Q2 | 2.2 | 2.5 | -0.3 |
| 2024年 Q3 | 2.5 | 3.0 | -0.5 |
| 2024年 Q4 | 2.1 | 2.8 | -0.7 |
| 2025年 Q1 | 2.0 | 3.1 | -1.1 |
| 2025年5月 | 2.3 | 4.0 (総合指数ベース) | -1.7 |
注:計算値は単純な引き算による参考値。出典データを基に分析者が作成。
出典:7
IV. 需給ギャップの解剖:推計値の乖離と根底にある現実
A. 測定の難問:ギャップ推計における「ギャップ」
需給ギャップ(GDPギャップ)は、一国の経済における総需要と潜在的な供給力(潜在GDP)の差を示す指標であり、物価の方向性を判断する上で極めて重要である。しかし、その推計値を巡っては、推計主体によって大きく見解が分かれるという深刻な問題が存在する。内閣府や日銀といった公的機関の推計では、需給ギャップは一貫して小幅なマイナス(需要不足=デフレギャップ)とされている。例えば、2025年第1四半期の推計値は、内閣府が-0.2%、日銀が-0.34%であった 23。
これに対し、複数の民間調査機関は、需給ギャップは既にプラス(需要超過=インフレギャップ)に転じていると主張している 23。この乖離の根源は、潜在GDPの推計手法にある。公的機関の推計方法は、労働力不足の影響を過小評価し、資本ストックなどの供給能力を過大に評価している可能性がある 24。需給ギャップがマイナスであるという公式見解は、財政出動による需要喚起策を正当化する根拠となりうるため、経済が既に供給能力の限界に達していると考える人々にとっては、政策判断を誤らせるリスクがあると批判されている 26。
B. 労働投入ギャップ:過熱の明確なシグナル
需給ギャップを構成する要素に分解すると、問題の所在がより明確になる。労働投入の側面を見ると、全ての推計でギャップがプラスになっている点で意見が一致している 27。これは、広く報道されている人手不足の状況を統計的に裏付けるものである。経済は、その持続可能かつインフレを加速させない労働力の水準を超えて稼働している状態にある。労働投入ギャップは、労働力率、就業率(失業率)、労働時間という3つの要素のギャップから構成される 28。
C. 資本投入ギャップ:非効率性がもたらす持続的な足枷
労働投入ギャップがプラスであるにもかかわらず、全体の需給ギャップがマイナスと推計されるのは、資本投入ギャップがそれを上回る大きなマイナスとなっているためである 27。これは、国内に存在する工場や設備、機械といった資本ストックが十分に活用されていないか、あるいはその成長が需要に追いついていないことを意味する。この問題は、単なる投資量の不足ではなく、資本の効率性や生産性の低さに根差している。日本の労働生産性は、G7諸国の中で依然として低い水準にあり 29、技術革新や経営効率を反映する全要素生産性(TFP)の伸びも低迷している 30。
需給ギャップを巡るこの論争は、日本経済が直面する根源的な問いを浮き彫りにする。すなわち、「現在の日本経済の最大の問題は需要の不足なのか、それとも供給能力の制約なのか」という問いである。この問いに対する答えが、財政・金融政策の方向性を決定づける。もし内閣府や日銀の公式推計が正しく、経済にまだ余力がある(需要不足)ならば、景気刺激策の継続が正当化される 23。しかし、もし民間機関の推計が正しく、経済が既に供給の限界に達しているならば、さらなる需要刺激策は実質的な成長をもたらさず、インフレを悪化させるだけである。その場合の適切な処方箋は、規制緩和や労働移動の円滑化といった供給サイドの構造改革と、金融引き締めとなる。政府が自らの推計に依拠し続ける姿勢は 26、供給サイドの深刻な制約から目を背け、需要喚起策に偏重する政策バイアスを生んでいる可能性がある。
さらに、プラスの労働投入ギャップとマイナスの資本投入ギャップの組み合わせは、日本経済の深刻な構造的アンバランスを示唆している。端的に言えば、**「非効率な資本を使い切る前に、人がいなくなる」**という状況である。企業は人手不足に喘いでいる一方で 27、既存の設備は十分に活用されていない 27。これは、労働力が低生産性部門に滞留し、希少な労働力を補うべき資本が効果的に投下されていないという、資源配分の歪みを示している。この問題の解決策は、単に投資の総量を増やすことではなく、省人化技術やデジタル化への「賢い投資」を進め、労働者のスキルを再教育して生産性を向上させることにある。これを怠れば、労働力不足がインフレを伴わない経済成長の揺るぎない上限として機能し続けるだろう。
表3:需給ギャップ推計の比較(対潜在GDP、%)
| 推計主体 | 全体需給ギャップ | 労働投入ギャップ | 資本投入ギャップ |
|---|---|---|---|
| 内閣府(2025年Q1) | -0.2 | 正(プラス) | 負(マイナス) |
| 日本銀行(2025年Q1) | -0.34 | 正(プラス) | 負(マイナス) |
| 民間機関(例) | 正(プラス) | 正(プラス) | 負(マイナス) |
注:労働・資本投入ギャップの正負は定性的な情報27に基づく。
出典:23
V. 労働市場のパラドックス:慢性的不足と完全雇用の探求
A. 疑いのない逼迫市場
日本の労働市場が極めて逼迫していることは、各種データが明確に示している。完全失業率は、2023年から2024年にかけて2.6%前後という歴史的な低水準で安定的に推移している 12。求職者1人に対して何件の求人があるかを示す有効求人倍率は、2023年平均で1.31倍、2024年4月時点で1.26倍となっており、求職者数を大幅に上回る求人が存在することを示している 12。この逼迫は正社員市場にも及んでおり、正社員の有効求人倍率は2023年に1.02倍と、1倍を上回る水準に達した 31。
B. 「完全雇用」の定義:ヘッドラインの数字を超えて
「完全雇用」が達成されたか否かを判断するためには、実際の失業率を、インフレを加速させない失業率(NAIRU: Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment)または構造的失業率と比較する必要がある。直近の公式な推計値は提供された資料にはないものの、過去の日銀などの分析によれば、日本の構造的失業率は低下傾向にあり、2018年時点で2%台と推計されていた 32。構造的失業率の推計には、失業者数と欠員数の関係に着目するUV分析などの手法が用いられる 33。現在の失業率2.6% 12が、これらの過去の推計値に極めて近いことを考慮すると、日本経済はNAIRUの水準、あるいはそれを若干下回る水準で運営されている可能性が非常に高い。
C. 完全雇用に関する結論:達成されたが、望ましい形ではない
入手可能な証拠に基づけば、統計的な観点から日本は完全雇用を達成した、あるいはそれに極めて近い状態にあると結論付けるのが妥当である。実際の失業率は、NAIRUと同等か、それを下回っている可能性が高い。
しかし、この結論には重大な留保がつく。これは、いわば「質の低い」完全雇用である。広範な人手不足にもかかわらず、健全な経済に必要な、生産性向上に裏打ちされた力強い実質賃金の伸びを生み出せていない。この事実は、失業率と賃金・物価上昇率の間に存在するトレードオフの関係(フィリップス曲線)が、日本では極めてフラット化しているか、あるいは構造的要因によってその関係性自体が変質してしまったことを示唆している。
日本の「完全雇用」は、ダイナミックな経済活動の結果として達成されたというよりも、人口減少という人口動態上の不可避な帰結としての側面が強い。その主な原動力は、爆発的な雇用創出ではなく、高齢化と人口減少に伴う労働供給の縮小である。この人口動態上の圧力が人手不足を生み出す一方で、それが自動的に生産性の向上につながるわけではない。むしろ、労働力の囲い込みや非効率な業務プロセスの温存を助長しかねない。
さらに、正規雇用の「終身雇用」と非正規雇用の不安定な待遇という、日本の労働市場の硬直的な二重構造が、労働力のより生産性の高い企業や産業への円滑な移動を妨げ、経済全体の賃金上昇を抑制している。したがって、このような文脈で「完全雇用」に到達することは、他の経済圏におけるそれとは意味合いが異なる。それは経済的な成功の証というより、むしろ経済が人口動態という名の天井にぶつかっているという警告サインである。今後の日本の経済成長は、これまで実現が困難であった生産性の向上にほぼ全面的に依存せざるを得ない状況にあることを、この労働市場のパラドックスは示している 29。
VI. 今後の経済見通しと主要リスク
A. コンセンサス予測:低位安定成長への道筋
今後の日本経済に関する大方の見方は、その低い潜在成長率に沿った緩やかな成長が続くというものである。IMFは、日本の潜在成長率である0.5%程度の成長が続くと予測している 10。国内の予測はやや楽観的で、2025年の実質成長率を+1.6%とするものもあるが、これには前年の反動といった統計的な押し上げ効果も含まれている 35。インフレ率については、現在の高水準からは鈍化するものの、2026年から2027年にかけて日銀の目標である2%近傍で推移すると見られている 19。日銀は緩やかなペースでの利上げを継続する見込みであり 19、長期的なGDP成長率は2026年に0.4%程度で安定すると予測されている 1。
表4:主要機関による経済見通し(実質GDPとコアCPI、%)
| 予測機関 | 2025年度 実質GDP | 2026年度 実質GDP | 2025年度 コアCPI | 2026年度 コアCPI |
|---|---|---|---|---|
| 日本政府 | 1.2 | – | – | – |
| 日本銀行 | – | – | 2%台後半 | 1%台後半 |
| IMF | 0.5 (潜在成長率) | – | 2%近傍で維持 | – |
| OECD | 3.1 (世界経済) | 3.0 (世界経済) | – | – |
| 民間(大和総研) | 1.6 | – | – | – |
注:各機関で予測の対象年度や定義が異なるため、直接比較には注意が必要。
出典:2
B. 国内の逆風:実質所得停滞の影
国内における最大のリスクは、実質賃金のマイナス成長に起因する個人消費の弱さが続くことである 13。2025年後半に期待されている実質賃金のプラス転換が実現しない、あるいは市場の期待を下回る小幅なものにとどまった場合、消費者のマインドは冷え込み、日本経済の最大の構成要素である個人消費が失速し、経済全体を押し下げることになる。このリスクは、政府自身の月例経済報告でも重要な留意点として挙げられている 20。
C. 外部の脅威:保護主義の亡霊
より深刻かつ差し迫ったリスクは、国外からもたらされる。政府および民間のアナリストは、米国の追加関税やより広範な保護主義的な通商政策が日本経済に与える影響を強く警戒している 1。特に、いわゆる「トランプ2.0」シナリオは、日本の輸出依存度の高い製造業、特に自動車産業にとって、深刻な不確実性をもたらす 35。政府がすでに対米関税措置に関する「緊急対応パッケージ」の策定に言及していることは、この脅威がいかに現実的で重大なものであるかを物語っている 20。
日本経済の先行きは、国内の構造問題と外部環境の変動という二つの要因によって、ますます複雑な様相を呈している。国内政策は賃金と物価の好循環を生み出すことに注力しているが、その成否は緩やかで時間のかかるプロセスである。一方で、米国の15%一律関税のような突発的な外部ショックは 1、大手輸出企業の収益を瞬時に悪化させる力を持つ。そうなれば、国内政策の成功に不可欠な賃上げの原資そのものが失われ、芽生え始めたばかりの好循環の芽を摘み取ってしまう可能性がある 13。すなわち、国内政策がいかに適切に運営されたとしても、国際的な通商問題という日本自身のコントロールが及ばない要因によって、経済戦略全体が頓挫しかねないという大きな脆弱性を、現在の日本経済は抱えているのである。
VII. 総括的分析
日本は、一世代にわたって経済を規定してきたデフレという長いトンネルから、技術的には脱出を果たした。これは歴史的な転換点である。しかし、その先に待っていたのは、安定的で持続可能な繁栄への確固たる道筋ではなかった。日本は今、新たな岐路に立たされている。
現在の経済モデルは、深刻なアンバランスを抱えている。好調な企業部門と旺盛な外需に依存する一方で、国内の家計部門は、労働市場の逼迫が実質的な購買力に結びつかないという構造的問題のために、依然として力強さを欠いている。今後の日本経済にとっての中心的課題は、もはや単にインフレを創出することではない。生産性の向上と、労働市場の流動化を含む構造改革を通じて、いかにして「質の高い成長」を実現するかに移行している。
「完全雇用下の停滞」とも言うべきこのパラドックスを解消し、同時に、ますます不安定化する世界の貿易環境を乗り切ること。これが、今後数年間の日本の政策担当者に課せられた、極めて困難かつ重要な責務となるであろう。その舵取りの成否が、日本の将来の経済的軌道を決定づけることになる。
引用文献
- 日本のGDP成長率 | 1980-2025 データ | 2026-2027 予測 – 経済指標, 8月 18, 2025にアクセス、 https://jp.tradingeconomics.com/japan/gdp-growth
- マクロ経済基礎資料 – 内閣府, 8月 18, 2025にアクセス、 https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2025/0310/shiryo_02.pdf
- 国民経済計算(GDP統計) – 経済社会総合研究所 – 内閣府, 8月 18, 2025にアクセス、 https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/menu.html
- 2025~2026年度日本経済見通し(2025年3月)(2024年10-12月期GDP2次速報後改定), 8月 18, 2025にアクセス、 https://www.dlri.co.jp/report/macro/423538.html
- 2025~2026年度日本経済見通し(2025年5月)(2025年1-3月期GDP1次速報後改定), 8月 18, 2025にアクセス、 https://www.dlri.co.jp/report/macro/448868.html
- 日本:2025年対日4条協議終了にあたっての声明, 8月 18, 2025にアクセス、 https://www.imf.org/ja/News/Articles/2025/02/07/mcs-020725-japan-staff-concluding-statement-of-the-2025-article-iv-mission
- 統計局ホームページ/消費者物価指数(CPI) 全国(最新の月次結果の概要), 8月 18, 2025にアクセス、 https://www.stat.go.jp/data/cpi/sokuhou/tsuki/index-z.html
- 日本のCPI(消費者物価指数)|インフレ(物価高)とデフレ(物価安)率の推移 – 新電力ネット, 8月 18, 2025にアクセス、 https://pps-net.org/cpi
- 日本消費者物価指数(CPI) | 1957-2025 データ | 2026-2027 予測 – 経済指標, 8月 18, 2025にアクセス、 https://jp.tradingeconomics.com/japan/consumer-price-index-cpi
- IMF理事会、2025年の対日4条協議を終了, 8月 18, 2025にアクセス、 https://www.imf.org/ja/News/Articles/2025/04/01/pr25084-japan-imf-executive-board-concludes-2025-article-iv-consultation-with-japan
- 第2節 デフレ脱却に向けた展望 – 内閣府, 8月 18, 2025にアクセス、 https://www5.cao.go.jp/keizai3/2023/0213nk/n23_1_2.html
- June,2024 – 一般社団法人日本人材派遣協会, 8月 18, 2025にアクセス、 https://www.jassa.or.jp/wp-content/uploads/2024/06/information_market_06.pdf
- 大幅減少が続く実質賃金 (25年5月毎月勤労統計) – 第一生命経済研究所, 8月 18, 2025にアクセス、 https://www.dlri.co.jp/report/macro/477160.html
- 第1章 第3節 デフレ脱却に向けた動き – 内閣府, 8月 18, 2025にアクセス、 https://www5.cao.go.jp/keizai3/2014/0113nk/nk14/n14_1_3.html
- デフレ脱却の目指すもの – 日本銀行, 8月 18, 2025にアクセス、 https://www.boj.or.jp/about/press/koen_2013/data/ko131225a1.pdf
- デフレ脱却と持続的な経済成長の実現のための 政府・日本銀行の政策連携について (共同声明, 8月 18, 2025にアクセス、 https://www.mof.go.jp/public_relations/statement/other/20130122.pdf
- 日銀金融政策決定会合とは?株価への影響や速報を解説【2025年の日程・発表時間も紹介】, 8月 18, 2025にアクセス、 https://kabukiso.com/column/idiom/nichigin_kinyuseisakuketteikaigo.html
- 日銀の金融政策決定会合とは?基礎知識と株価・為替への影響をわかりやすく解説 | 知る-コラム, 8月 18, 2025にアクセス、 https://moneycanvas.bk.mufg.jp/know/column/QwBsHwDR9pjXsVH/
- 経済・物価情勢の展望 – 日本銀行, 8月 18, 2025にアクセス、 https://www.boj.or.jp/mopo/outlook/gor2507b.pdf
- 内 閣 府, 8月 18, 2025にアクセス、 https://www5.cao.go.jp/keizai3/getsurei/2025/0729getsurei/main.pdf
- 連合・賃金レポート, 8月 18, 2025にアクセス、 https://www.jtuc-rengo.or.jp/activity/roudou/shuntou/2024/wage_report/wage_report_summary.pdf?40
- 再び減少に転じた実質賃金(25年1月毎月勤労統計) ~物価上振れにより – 第一生命経済研究所, 8月 18, 2025にアクセス、 https://www.dlri.co.jp/report/macro/423449.html
- 需給ギャップって、意味ある指標なの?|飯塚 信夫(神奈川大学経済学部教授) – note, 8月 18, 2025にアクセス、 https://note.com/todobuono/n/ne443c8b50692
- 需要不足ではなく供給制約下の日本経済*1, 8月 18, 2025にアクセス、 https://www.jst.go.jp/fund/dl/researchnote30.pdf
- 物価安定に必要なGDPギャップ水準 ~政府見通し通りに行っても、2025年度の達成は困難な可能性~ | 永濱 利廣 | 第一生命経済研究所, 8月 18, 2025にアクセス、 https://www.dlri.co.jp/report/macro/403769.html
- 需給ギャップはあくまで「参考指標」 – 経済深読み, 8月 18, 2025にアクセス、 https://www.mizuho-rt.co.jp/publication/executive/pdf/km_c230613.pdf
- 「需給ギャップ」は利上げしない理由になるか? – みずほ銀行, 8月 18, 2025にアクセス、 https://www.mizuhobank.co.jp/forex/pdf/market_analysis/econ250204.pdf
- 31 (BOX1)需給ギャップと潜在成長率の見直しについて 日本銀行調査統計局では, 8月 18, 2025にアクセス、 https://www.boj.or.jp/mopo/outlook/box/data/1704BOX1a.pdf
- 再考:日本の生産性 – 資本市場研究会, 8月 18, 2025にアクセス、 https://www.camri.or.jp/files/libs/2114/202410111226098831.pdf
- 日本の潜在成長率向上に何が必要か: JIPデータベース2023を使った分析, 8月 18, 2025にアクセス、 https://www.rieti.go.jp/jp/publications/pdp/23p028.pdf
- 第2章 雇用情勢の動向 – 厚生労働省, 8月 18, 2025にアクセス、 https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/roudou/24/1-2.html
- 低下する構造的失業率 2018年09月13日 | 大和総研 | 小林 卓典, 8月 18, 2025にアクセス、 https://www.dir.co.jp/report/column/20180913_010113.html
- 構造的失業率の推移からみた 雇用の現状について, 8月 18, 2025にアクセス、 https://www.dl.ndl.go.jp/view/prepareDownload?itemId=info%3Andljp%2Fpid%2F8793943&contentNo=1
- GDPギャップと潜在成長率の新推計 – 日本銀行, 8月 18, 2025にアクセス、 https://www.boj.or.jp/research/wps_rev/rev_2006/data/rev06j08.pdf
- 2025 年の日本経済見通し – 大和総研, 8月 18, 2025にアクセス、 https://www.dir.co.jp/report/research/economics/outlook/20241220_024815.pdf
- 関税障壁の高まり受け、2025年成長率を下方修正、OECD予測(世界) | ビジネス短信 – ジェトロ, 8月 18, 2025にアクセス、 https://www.jetro.go.jp/biznews/2025/03/3e7028db2cb28867.html