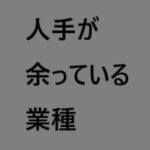私が、なぜ需給ギャップに拘るのか、説明したいと思います。 (この記事は生成AIを使わずに全て自分で書いています)
需給ギャップは日本経済全体の総需要と潜在供給能力(生産能力)の差である事は、以前の Claude の解説で分かったと思います。
Claudeはラーメン屋と客の数の差で、簡単に説明しました。
需要:そのラーメンを食べたい人の数
供給:そのお店が実際に作れるラーメンの数
お客さんが100人来たいのに、お店が1日50杯しか作れなければ、50杯分の「需要超過」、 逆に、お客さんが30人しか来ないのに50杯作れるなら、20杯分の「供給超過」、 となります。
昨年(2024年)前半までの「失われた30年」のデフレ時代は日本全体が「供給超過」の状態にありました。 今はインフレなので「需要超過」状態にあります。 この需要超過状態が人手不足の原因である事は、先の Claude の解説にある通りです。
ここで言う、国全体の「需要」が、日本経済の「GDP」に相当します。
GDPの日本語訳は「国内総生産」になるので、供給能力と誤解されるかも知れませんが、実際は「総需要」を意味します。
GDP = 総需要
日本全体の潜在供給能力(生産能力)は「潜在GDP」という別の統計で表します。
需給ギャップは、需要と供給能力の差ですから、GDPと潜在GDPの差でもあるわけです。
需給ギャップがプラス転換するという事は、GDPが伸びた事を意味します。
つまり、需要が伸びるということは、日本経済が成長している事を意味します。
実際に日本の名目GDPは600兆円を既に超えて成長を続けています。 これは需要が600兆円を超えて成長を続けているという事です。
GDP三面等価の原則
「GDPは総需要と同じ」と説明しましたが、他にもGDPと同じ値になるモノがあります。 それは、消費と所得と付加価値です。
ラーメン一杯1000円をお客さんが買って食べたとすると、この時点で1000円の消費が生じたことになります。
そして、この1000円の消費は、そのままラーメン屋の所得になります。
同時に、このラーメン屋は1000円の付加価値を生み出したことになります。
つまり、経済全体で見ると、このラーメン一杯の購入により、1000円の消費が生じ、1000円の所得が生じ、1000円の付加価値(利益)が生じたことになります。
ラーメンの麺や具材の仕入れの取引でも同様です。
ラーメン屋が製麺業者から麺を10万円で仕入れた時点で、製麺業者と経済全体で10万円の消費が生じ、10万円の所得が生じ、10万円の付加価値(利益)が生じたことになります。
経済全体で見ると、総消費と総所得と総付加価値は、同時発生するので同じ値になるのです。
そして、この需給ギャップの総需要とは、この総消費と総所得と総付加価値と同じものです。
全てまとめると、
GDP = 総需要 = 総消費 = 総所得 = 総付加価値
となります。
GDPと総消費と総所得と総付加価値が同じになる性質を「GDP三面等価の原則」と呼びます。
GDPのショートサイド原則
総需要と供給能力とGDPの関係には、「ショートサイド原則」という性質があります。
ショートサイド原則とは「総需要と供給能力を比較したとき、小さい方がGDPと同じになる」という性質です。
つまり、需給ギャップがマイナスの場合は、需要の方が供給能力より小さいので、需要の大きさがGDPになります。(供給超過の状態)
需給ギャップがプラスの場合は、供給能力の方が需要より小さいので、供給能力の方がGDPになります。(需要超過の状態)
ラーメン屋の例
これをラーメン屋の例で説明してみます。
お客さんが100人来たいのに、お店が1日50杯しか作れなければ、一日のGDPは「ラーメン50杯分」になります。(需要超過の状態)
お客さんが30人しか来ないのに50杯作れても、一日のGDPは「ラーメン30杯分」になります。残りの20杯はGDPに反映されません。(供給超過の状態)
供給超過の状態で、GDPを増やそうとするなら、ラーメンを70杯作れるようにしても売れ残りが増えるだけなので、無駄な努力になります。
供給超過の状態では、お客さんを50人に増やす努力をしなければ、GDPは増えません。
逆に、需要超過の状態では、お客さんが100人から120人に増やしても、作れるラーメンの数は50杯なので、GDPは増えません。
一日に作れるラーメンの数を増やさなければ、GDPは増えません。
これが、GDPにおいてショートサイド原則が成立する理由です。
有効需要の原理
1990年代から2010年代前半までの「失われた30年(20年)」とも呼ばれるデフレ経済の時代は、長期的な「供給超過の需要不足」の状態が続きました。
供給能力が総需要を上回っていたわけです。(需給ギャップがマイナスの状態)
このデフレ期には、需要不足なのでいくら頑張って生産能力を伸ばしてもGDPは増えません。
ショートサイド原則により、GDPを決めるのは総需要なので、デフレ期には消費を増やして総需要の方を伸ばさなければ、GDPが増え無いのです。
このデフレ期に一生懸命長時間労働して生産量を増やしても、沢山働くほど市場メカニズムにより労働単価が下がるので、さらに貧しくなります。 デフレ期の「働いたら負け」という考え方は、一理あるのです。
先のラーメン屋の例で言えば、客が30人しか来ないのに、懸命にラーメンを60杯作っている状態です。
就職氷河期の生きたデフレ時代はこんな時代だったのです。
デフレ期には、先のラーメン屋の例のように、お客さんを増やさなければGDPは伸びません。
国家の場合は、総消費を増やす必要があります。
2013年から始まったアベノミクスでは、金融緩和と財政出動により、政府支出を増やす形で総消費を増やす政策を実施しました。
このように経済には、需要不足のデフレ期には、総需要(総消費)を増やすとGDPが伸びる性質があります。
この性質を「有効需要の原理」と呼びます。
「有効需要の原理」は需給ギャップがマイナスの時にしか通用しません。
では、需給ギャップがプラスの時にはどうやってGDPを伸ばすのか。
セイの法則
現在の日本経済は需給ギャップがプラスの「需要超過の供給不足」の状況にあります。
この状況でGDPを増やしたいのなら、供給能力を方を増やす必要があります。
ラーメン屋の例で言うと、「お客さんが100人来るのにラーメンは50杯しか作れないので売上が50杯分しか稼げない」状況にあります。
売上(GDP)を増やすなら、ラーメンをもっと作れるようにする必要があります。
ショートサイド原則により、供給能力を増やすと、GDPもそれに応じて増えます。
この需要超過状態で、生産能力を増やすとGDP(総需要)も増える現象を「セイの法則」と呼びます。
今の日本経済は、今年(2025年)から既に需給ギャップがプラスの需要超過状態にあるので、生産を増やせばその分GDPが伸びる状態にあります。 むろん、これは労働人口など日本の生産能力の枠内での生産拡大に限られます。
デフレ経済下の日本は「働いたら負け」の経済状況でしたが、 今の日本経済は「働けば働くほど儲かる」時代に突入したということです。
(但し、例外として一般事務職は技術的失業の対象になっているので転職をお勧めします)
日本のIT産業の中で、生成AIが進歩しても失業が増えない理由として、この「セイの法則」が働いているから、という事も考えられます。
日本において、生成AIにより生産性が向上しても、その生産増加分だけGDP(総需要)が増えるので、失業が増えないわけです。 「少子化で労働者が減っている」、「人手不足で自動化省力化需要が増えている」など、他の理由もありますが、「セイの法則」も働いていると思います。
市場メカニズムには「価格が下がると需要が増える」性質もあるので、生成AIでソフトウェア開発生産性が上がりソフトウェア開発価格が下がる事により、ソフトウェア開発需要が増えるという作用も働いているかも知れません。
何れにせよ、今の日本経済は、GDPと総需要の成長路線に入っており、失業が増える状況にはほど遠い状況にあります。
経済成長のボトルネック
今のままでも日本経済は既に成長路線に入っていますが、成長速度が鈍いのも事実です。
なぜ成長が鈍いのか、以前 Gemini Deep Research にまとめてもらった記事が以下の記事です。
Deep Research に聞く「日本経済のボトルネックは何?」
この記事の「需給ギャップとGDPの関係」を踏まえていないと、Deep Research の説明の意味もよく分からないと思います。
要するに「今の日本経済のボトルネックは供給制約にある」という事です。 「GDP成長率を伸ばすには、生産性を引き上げなければならない」という事です。
ラーメン屋に例えると「もっとラーメンを沢山作れるようにして、売上を伸ばして、従業員にたくさん給料を支払えるようにしなければならない」という事です。
Gemini Deep Research 生成の記事の内容を、少し整理すると、日本経済は長い「失われた30年」と称するデフレ経済の期間に、産業界がデフレ経済に最適化してしまっているわけです。
デフレに最適化した産業構造によって非常に生産性の低い生産活動が行われる事業環境が固定化してしまっています。
このデフレ最適の産業構造により、今年からインフレ経済になり需要が増加していても、その需要を充分に満たす生産ができなくなっているのです。
ラーメン屋に例えると、昔のデフレ時代にお客が来なくて経営が苦しいので、経費節約の為に座席数や従業員数や調理設備を少なくして、デフレ不況に最適化して営業してきたラーメン屋があるとします。
今インフレになりお客さんが増えても、急には座席数は増やせないし調理設備も少なく従業員不足で、たくさん来るお客さん全てにラーメンを作ることができない状態にある、という状況に例えることができます。
ちょうど、今のタイミングで少子化の影響が加速しており、従業員を必要なだけ雇うことは絶望的な状況です。
一部、局所的に「一般事務職と管理職」などホワイトカラーの職務で技術的失業が加速していますが、日本経済全体では圧倒的に人手不足の状況です。
労働者にリスキリングが必要な理由として、この技術的失業の対象になっている人々を、人手不足の業種に転職させて、人手不足の供給制約を緩和する必要があるからです。 「一般事務職と管理職」以外は全て人手不足ですから、どの業種に転職しても構わないはずです。ホワイトカラー失業者を全て吸収してもまだ人手不足が解消しないぐらいの人手不足が進行中なので、これでホワイトカラー失業問題は解消します。
しかし、これだけでは人手不足は解消しません。
もう一つの人手不足対策として外国人労働者の受け入れがありますが、これも入管法改正により特定技能労働者制度が作られ「5年で82万人」という入国制限枠が定義されています。一年あたり16万人強という計算になります。
技能実習制度は2030年までに段階的に縮小して廃止することが決定しています。
この制度により多少は人手不足が緩和しますが、パーソル総合研究所の推計では日本全体の人手不足の規模が189万人という事なので、これと比べると「焼け石に水」といったところでしょう。 全く足りません。
外国人労働者の過剰な受け入れは、日本国民の労働賃金の低下を招くので、日本政府は「5年で82万人」という制限を設けているわけです。人手不足だからと言ってこれが覆ることは考えにくいです。
「ホワイトカラーの転職でも不十分」「外国人労働者を入れても不十分」となると、残りはAI・ITやロボット・機械設備など自動化・省力化の設備投資をするしかありません。
少なくとも、現行の仕組みの中でできる人手不足対策は、これだけです。
しかし、これだけでは人手不足問題は解消しないので、デフレに最適化した非効率な産業構造自体を構造改革して産業全体の生産性を上げる必要があるわけです。
その流れにある一つの要素がDXです。
デフレ最適の産業構造はいろいろありますが、派遣会社や非正規雇用への過度の依存や、多重請負構造による過剰な仲介マージンなどは、非効率の代表格でしょう。
日本のホワイトカラーが国際的に見て非常に生産性が低いという話は、20年30年前から言われていたことで、これまでホワイトカラーの構造改革に大企業が取り組んで来なかった事の方が、逆に不思議なぐらいです。
今、急速にホワイトカラーのリストラに多数の企業が着手するのは、生産性を向上させる手段として当然の事でしょう。
余剰ホワイトカラーを、他の人手不足業界に転職させた方が、日本経済全体にとっては有益です。
もう一つ、生産性が低く従業員の給料を充分に引き上げる事ができない企業から、生産性の高い企業に、労働者を転職させる必要があります。
これは国家視点に立てば、限られた日本の労働者を、より生産性の高い企業に移籍させた方が、国全体の労働者の生産性は向上することになります。
過去最高の企業倒産件数を記録しているのに、政府が何の対策もしないのは、「給料を上げられない会社は潰れてくれ」という政府の考えがあるからだと思います。
現在の日本にはデフレ経済に最適化した企業が多数存在し、これらの多くはインフレ人手不足経済には適応できない可能性が高いです。
インフレ人手不足経済に適応できない(従業員の給料を上げることができない)会社は、日本経済には必要の無い会社なのです。その会社の従業員を、他の高い給料を支払える会社に転職させた方が、国民経済にとっては良いのです。
パナソニックや三菱電機など大企業が黒字リストラを実施するのは、日本経済にとって生産性向上が必須である事が分かっているからです。不景気だからリストラしているわけではないのです。むしろ需要超過・供給制約の好景気だからリストラが必要なのです。
日本経済の成長には、産業界の生産性向上による国内労働者の賃上げが必要です。 賃上げにより労働者の所得が増えると、GDP三面等価の原則により、総消費と総付加価値も増えることになります。
今のボトルネックは生産性が低い産業構造なので、生産性を向上させる構造改革が必要なのです。
Gemini Deep Research の「Deep Research に聞く『日本経済のボトルネックは何?』」の記事に書かれていることは、簡単に要約すると、そういう事です。
私が最近、需給ギャップに拘る記事を書くのは、こういうマクロ経済状況の大きな変化が起こっているからです。
個人と企業はどうすれば良いのか
この需給ギャップのプラス転換を迎えた時期に個人と企業はどうすれば良いのか考えてみます。
まず個人ですが、なにより自分の年収を引き上げる行動をすべきです。
長年給料が上がらない会社に勤めているのなら、より年収の高い会社や他の職種へ転職する行動を起こすのが良いことになります。 国民全体の年収が上がれば、GDPが増えるからです。GDPは国民の所得の合計でもあります。(GDP三面等価の原則)
デフレ時代と異なり、今は雇用情勢が非常に良く転職先は見つけやすいはずです。
企業の場合は、受託仕事ならば利益率の低い顧客を切り、より請負単価の高い利益率の高い顧客を開拓すべきでしょう。
自社の商品・サービスなどの販売業(店舗商売)ならば「値上げ」をすべきです。 「値上げ」が難しいのなら値上げできるような商品やサービスを生み出す努力をすべきでしょう。インフレにより競合他社も値上げをしますし、供給不足なので消費者は高くても購入せざるを得ません。
雇用面では、需要超過なのでデフレ時代のように仕事が無くなるリスクよりも、人手不足で顧客に財やサービスを提供できない(機会損失)リスクの方が、高くなります。 そのため、派遣会社や外注に依存して、「いつでも発注を切れる」対価として高い中間マージンを支払い続けるより、直接生産能力を雇用して「人手不足でサービスを提供できない(機会損失)リスク」に備える方が、合理的な経営になります。
人手不足で賃上げをしないと新規採用ができないどころか、既存の従業員まで離職してしまいます。自社の商品・サービスを値上げして得た利益を、従業員の賃上げの原資にする必要があります。そのためにも「値上げ」が必要です。 派遣や外注に支払っているマージンは無駄でしかないと思います。需要超過の現在の市場で「いつでも発注を切れる」メリットに価値があるとは思えません。
極力、外注や派遣・非正規雇用に過度に依存する体制を改めて、必須の生産能力は直接雇用により、社内に保有した方が良いでしょう。 そして、コスト削減のために、中核(必須)業務で無い部門は、汎用品や汎用サービスを、汎用規格に従って利用するようにすべきだと、私は思います。
(補足)経産省はなぜ
ちなみに、経済産業省が「DX」を推奨するのも「デジタル経済レポート」で、労働集約的なSIer業界に事実上の「ダメ出し」をするのも、日本経済のボトルネックが「生産性の低い産業構造」にあるからだと認識しているからでしょう。
経産省の下位組織の日本生産性本部に「日本の情報通信業だけが生産性を低下させている」事を公に報告させたのも、本来日本全体の生産性向上に貢献しなければならないIT業界が、いつまでも労働集約的な業態を続けて、IT業界自身が生産性を低下させている事に対する強い不満があるからだ、と思います。
SIer業界は、いまのままではダメだという事は、素人考えでも充分に理解できる話だと思います。
2025年から需給ギャップはプラス転換して、いよいよ生産性のボトルネックが問題になってきました。 最近、経産省がSIer業界に厳しい態度を取るのも、マクロ経済状況の都合もあるのだと思います。
以下の資料を見ると経産省がどのような危機感を持っているのか分かると思います。
参考までに紹介しておきます。
日銀の広報(2025年9月30日追記)
日銀では、定期的に日銀審議委員による地方支部での講演が行われており、今回(2025年9月29日)は、経済学者の野口旭審議委員の札幌商工会議所での講演が、日銀のサイトから文書で公開されています。
その内容は、現在の日本と世界のマクロ経済状況の報告と、これまでの日本のマクロ経済状況の変移と歴史についての解説です。
大変、参考になるので、以下にご紹介しておきます。
PDF文書なのでスマホだと見にくいかも知れません。