IT(SIer)業界だけではなく、日本の他の産業界の多重請負構造について、Gemini 2.5 Pro に解説してもらいました。いつものように共有します。
産業別の多重請負構造
日本の産業界全体の中で、多重請負構造を形成している業界を教えてください。
不健全な多重請負構造
これら多重請負業界の中で、欧米先進国と比べて、あまり生産性の高くない不健全な構造を形成している業界を、抽出してください。
多重請負構造を持つ業界の中でも、特にIT業界(特にSIer業界)と建設業界は、欧米先進国と比較して生産性が低く、不健全な構造を形成していると指摘されることが多いです。
これらの業界は、単に下請けに出すというだけでなく、付加価値を生まない中間業者が介在し、労働者のスキル向上を妨げ、業界全体の競争力を削いでいる点で共通の問題を抱えています。
💻 IT業界(特にシステムインテグレーター業界)
日本のIT業界は、OECD主要7カ国の中で労働生産性が最下位というデータもあり、その大きな原因が多重請負構造にあるとされています。
不健全な構造:「人月商売」と中間搾取
- 日本の多くのSIer(システムインテグレーター)は、「技術者を何人・何か月提供するか」という人月(にんげつ)単位でビジネスを行っています。これは顧客の問題を解決するという価値提供ではなく、単なる労働力の提供になりがちです。
- 元請けのSIerは管理業務のみを行い、実際の開発は二次、三次請けの企業に丸投げされます。その過程で各社が中間マージン(手数料)を抜くため、末端で働くエンジニアに適正な報酬が支払われません。
- これにより、モチベーションの低下だけでなく、下層のエンジニアは単純作業ばかりを任され、スキルアップの機会を奪われるという問題も生じます。これが業界全体の技術力停滞を招いています。
欧米との違い
- 欧米では、企業が自社でエンジニアを雇用するか、特定のスキルを持つ専門家やフリーランスと直接契約を結ぶのが一般的です。
- プロジェクトの成果物や、解決されるべきビジネス課題に対して報酬が支払われるため、不要な中間業者が介在する余地が少なくなります。
- エンジニアは自らの専門性を高めることが直接評価につながり、生産性の高い働き方が促進されます。
🏗️ 建設業界
建設業界は古くから多重請負構造が根付いていますが、これが生産性の向上を妨げ、労働者不足を深刻化させる一因となっています。
不健全な構造:責任の曖昧化と労働条件の悪化
- 大手ゼネコンを頂点とするピラミッド構造では、下層に行くほど企業の規模は小さくなり、安全管理や品質管理の徹底が難しくなります。事故や欠陥が発生した際の責任の所在が曖昧になりがちです。
- IT業界と同様に、中間マージンによって下層の専門工事業者や職人の手取りが減り、厳しい労働条件(低賃金、長時間労働)につながっています。
- これが若者の建設業離れを招き、深刻な後継者不足と高齢化を引き起こしています。結果として、業界全体の生産性が上がらない悪循環に陥っています。
欧米との違い
- 欧米では、発注者が設計事務所やコンサルタントと契約し、施工は専門分野ごとに分離して直接発注する形態(分離発注方式)や、プロジェクト全体をマネジメントする専門企業(コンストラクション・マネージャー)を雇う方式が主流です。
- 各専門業者の役割と責任範囲が契約で明確に定められており、日本のゼネコンのように「丸投げ」する構造にはなりにくいです。
- 労働組合の力が強く、労働者の賃金や労働時間が保護される傾向にあることも、日本の構造との大きな違いです。
なぜ欧米と差が生まれるのか?
この差の根底には、日本の雇用慣行と取引文化があります。
- 雇用の流動性の低さ:正社員を解雇しにくい日本では、企業は需要の変動に対応するため、自社の社員を最小限に抑え、業務を外部に委託する傾向が強いです。
- 専門性への評価:欧米では専門性の高いスキルを持つ人材は高く評価され、直接契約で高報酬を得やすいですが、日本では多重構造の中でその価値が埋もれがちです。
結論として、IT業界と建設業界における日本の多重請負構造は、単なる分業システムではなく、中間搾取や人材育成の阻害といった問題を内包しており、これが欧米に比べて生産性を著しく低くしている不健全な構造と言えます。
物流・運送、製造業、広告・マーケティング業界の多重請負構造は、生産性が高く健全な形体を取っているのですか。
いいえ、これらの業界の多重請負構造は、多くの問題を抱えており、生産性が高く健全な形態とは言えません。
業界ごとに濃淡はありますが、共通して「中間搾取による下層の利益圧迫」と「責任の所在の曖-昧化」という根深い問題を抱えており、業界全体の生産性向上を阻害し、労働環境を悪化させる大きな要因となっています。
🚚 物流・運送業界
この業界の多重請負構造は、特に不健全さが際立っています。
- 生産性の低下: 階層が深くなるほど、情報伝達に時間がかかり、迅速な意思決定が困難になります。また、下層の事業者は利益率が極端に低いため、燃費の良い新車両への投資やIT化・自動化への投資ができず、業界全体の効率化が遅れています。
- 労働条件の悪化: 各階層で中間マージンが抜かれるため、末端で実際に荷物を運ぶドライバーの賃金は低く抑えられ、長時間労働が常態化しています。これが深刻な人手不足と高齢化を招き、日本の物流網を揺るがす「2024年問題」の根本的な原因にもなっています。
- 品質管理の困難さ: 元請けが下層の事業者の安全管理や品質を直接コントロールすることが難しく、事故のリスクが高まります。
🏭 製造業
製造業の重層下請け構造は、日本の経済成長を支えてきた側面もあり、一概に非効率的と断じることはできません。専門性の高い技術を持つ中小企業が分業することで、高品質な製品を効率的に生み出す「強み」とされてきました。
しかし、その健全性には疑問符がつきます。
メリット(建前): 大手メーカーは、専門技術を持つ下請け企業を活用することで、開発・生産のスピードを上げ、コストを削減できます。また、需要の変動に合わせて生産量を調整するバッファーとしても機能します。
デメリット(実態):
- 利益の圧迫: 親会社からの厳しいコストダウン要求により、下請け企業は十分な利益を確保できず、賃金が上がりにくく、設備投資もままならない状況に陥ることが少なくありません。
- 従属的な関係: 親会社への依存度が高いため、不利な取引条件を飲まざるを得ない弱い立場に置かれがちです。
- 技術継承の危機: 利益が少ないため、若手人材の確保や育成が難しく、世界に誇る日本の「匠の技」が失われるリスクに直面しています。
かつては機能していたこのモデルも、グローバル化の進展や産業構造の変化の中で、その歪みが顕在化してきています。
📈 広告・マーケティング業界
IT業界と類似した問題を抱えており、生産性が低く不透明な構造と言えます。
- 中間搾取(中抜き): 大手広告代理店がクライアントから高額な予算で案件を受注し、実際の制作業務は二次、三次請けの制作会社やフリーランスに低予算で丸投げされることが横行しています。中間に介在する業者が管理費やマージンを抜くだけで、付加価値をほとんど生まないケースも少なくありません。
- 品質の低下と責任の曖昧さ: クライアントの意図が末端の制作者まで正確に伝わらず、品質の低下を招きます。また、制作物が炎上するなど問題が発生した際に、責任の所在が曖昧になりがちです。
- クリエイターの疲弊: 低予算と短納期を強いられる末端の制作者は、十分な報酬を得られず、疲弊しています。これにより、業界全体から才能ある人材が流出する懸念も指摘されています。
これらの業界の多重請負構造は、一部の元請け企業に利益が集中し、現場で実際に価値を生み出している下層の事業者や労働者に適正な対価が支払われないという共通の課題を抱えています。これが結果的に、業界全体の生産性向上と健全な発展を妨げているのです
そもそも「健全な多重請負構造」というものが、有り得るのでしょうか。 欧米先進国に、そのような実例があるのでしょうか。
はい、有り得ます。しかし、それには厳格な条件が伴い、日本の多くの業界で見られる構造とは根本的に性質が異なります。
「健全な多重請負構造」とは、単に仕事を丸投げして中間マージンを抜くための構造ではなく、各階層の企業が、それぞれ異なる専門性と付加価値を提供する「専門家集団による分業体制」として機能している状態を指します。
そもそも「健全な多重請負構造」とは?
健全であるための条件は、以下の通りです。
- 🤝 明確な付加価値の提供: 各階層の企業が、プロジェクト管理、高度な設計、特定の専門技術、特殊な製造能力など、その企業でなければ提供できない独自の価値を生み出していること。単なる「人集め」や「仕事の再委託」だけを行う中間業者は存在しません。
- ** TRANSPARENT 公正で透明な契約関係**: 各社の役割、責任範囲、品質基準、そして報酬が契約によって明確に定められています。親会社が下請けに対して一方的にコスト削減を強いるような、不公正な力関係は存在しません。
- ** PARTNERSHIP 対等なパートナーシップ**: 元請けと下請けは、支配・従属の関係ではなく、プロジェクトを成功させるための対等なビジネスパートナーとして互いを尊重します。
- ✔️ 明確な責任分担: プロジェクトに問題が発生した場合、どの部分がどの企業の責任であるかが契約上明確になっています。
日本の不健全な構造が「減点方式のピラミッド(下にいくほど価値が削られる)」だとすれば、健全な構造は「加点方式のネットワーク(専門家が集まることで全体の価値が高まる)」と言えます。
欧米先進国における実例
欧米、特に米国などでは、このような「健全な分業体制」が大規模プロジェクトで機能しています。
✈️ 航空宇宙・防衛産業
ボーイング社やエアバス社が旅客機を製造する際、彼らは「プライム・コントラクター(主契約者)」として、プロジェクト全体の設計と最終組み立てに責任を持ちます。
しかし、エンジンはロールス・ロイス社やGE社、電子機器はハネウェル社、機体の一部は三菱重工など、世界中の専門メーカーが「Tier1(一次下請け)」として開発・製造を請け負います。さらにそのTier1メーカーも、部品や素材を専門の「Tier2(二次下請け)」から調達します。
これは、各社が自らの専門分野で最高の技術と品質を提供し、それを組み合わせることで巨大で複雑な製品を作り上げる、極めて高度で健全な多重請負構造です。そこには日本の「丸投げ」や「中間搾取」といった概念はほとんどありません。
🏗️ 大規模建設・エンジニアリング
巨大なプラントや超高層ビルを建設する際、元請けとなる建設会社(General Contractor)は施工管理全体を統括しますが、基礎工事、鉄骨、電気設備、空調設備といった各分野は、その道のトップクラスの専門業者(Specialty Contractor)に発注します。
元請けはオーケストラの指揮者のような役割を果たし、各専門業者は一流の演奏者として自らのパートを完璧にこなします。それぞれの専門性がプロジェクト全体の品質を高めており、これも健全な分業体制の一例です。
日本の構造との決定的な違い
欧米の健全な例と、日本の多くの業界で見られる不健全な構造との決定的な違いは、「専門性」に対する価値観と「契約文化」にあります。
欧米では、特定の分野で高い専門性を持つ企業や個人は高く評価され、それに見合った報酬を直接得ることができます。一方、日本では、多重請負構造の中でその価値が正当に評価されず、中間業者に搾取されやすい傾向があります。
したがって、「健全な多重請負構造」は存在しますが、それは日本の多くの人々がイメージするものとは大きく異なる、専門家同士の戦略的パートナーシップと呼ぶべきものなのです。
多重請負構造の歴史
日本で現在の多重請負構造が形成されたのは、いつ頃からですか。
高度成長期の昔から、多重請負構造で運営されてきたのでしょうか。
業界別に説明してください。
はい、日本の多重請負構造の起源は古く、多くの業界で高度経済成長期か、それ以前から存在していました。ただし、その形態や背景は業界によって大きく異なります。
建設業界 🏗️
建設業界の多重請負構造は、江戸時代の「組」制度にまで遡ると言われており、非常に長い歴史を持ちます。
- 江戸時代〜戦前: 大工の「棟梁」が仕事を取りまとめ、専門の職人集団(組)に仕事を割り振るという、徒弟制度に基づいた分業体制が原型です。
- 高度経済成長期: 戦後の復興やインフラ整備、都市開発が急ピッチで進む中で、この構造が爆発的に拡大・定着しました。大規模で複雑な工事を効率的に進めるため、大手ゼネコンが元請けとして全体を管理し、専門分野ごとに下請けに出すという分業モデルが最も合理的だったのです。この時期に、現在のピラミッド型の重層構造が確立されました。
したがって、建設業界は昔から多重請負構造で運営されており、高度成長期にその構造が巨大化・固定化されたと言えます。
製造業 🏭
製造業の重層下請け構造は、戦前の財閥系企業の仕組みに源流が見られます。
- 戦前〜戦中: 三菱や住友などの財閥が、自社の事業部門に必要な部品や加工を、系列の中小企業に発注するという垂直的な分業体制を築いていました。
- 高度経済成長期: 自動車や家電産業の急成長と共に、このモデルがさらに発展しました。大手メーカーを頂点に、部品を供給する一次下請け(ティア1)、さらにその部品を作る二次下請け(ティア2)という、現在につながる系列(けいれつ)を基本としたサプライチェーンが形成されました。これは、品質管理や安定供給の面で非常に効率的に機能し、日本の「モノづくり」の国際競争力を支える強みとなりました。
製造業もまた、昔から存在する構造が、高度成長期に大規模かつ精緻なシステムへと進化・定着したケースです。
IT業界 💻
IT業界の多重請負構造は、他の業界と比べて歴史が浅く、1980年代以降に形成され、特に2000年代に深刻化しました。
- 黎明期(〜1980年代): この頃のシステム開発は、まだ企業が自社の情報システム部門でエンジニアを抱え、内製するのが一般的でした。
- 形成期(1990年代〜): バブル崩壊後、企業はコスト削減のため、正社員のIT人材を抱えるリスクを嫌い、システム開発を外部の専門企業に委託する「アウトソーシング」が主流になりました。この流れの中で、大規模な案件を受注した大手SIer(システムインテグレーター)が、実際の開発作業を中小のソフトウェアハウスに再委託するという構造が生まれました。
- 深刻化(2000年代〜): 人材派遣法の改正なども影響し、技術者を「モノ」のように扱う「人月商売」が加速。何重にもわたる中抜きが常態化し、現在のような不健全な多重請負構造が定着しました。
IT業界は、高度成長期には存在しなかった新しい産業であり、その多重請負構造は、主にコスト削減と雇用の流動化という、比較的最近の経済的背景から形成されたものです。
IT業界以外の各産業界で、バブル崩壊以降の30年あまりのデフレ経済期に、多重請負構造に何か変化は見られましたか。
はい、見られました。バブル崩壊以降のデフレ経済は、各業界の多重請負構造をより深化・複雑化させ、問題点を深刻化させる方向に作用しました。
コスト削減への強い圧力が、既存の構造をさらに歪めてしまったのです。
建設業界 🏗️
建設業界では、多重請負構造が「延命」と「コスト削減」のための手段として、さらに複雑化しました。
- 構造のさらなる重層化: バブル崩壊で公共事業が減少し、仕事が激減。価格競争を生き残るため、元請けはコストカットを徹底する必要がありました。その手段として、職人や作業員を直接雇用せず、外注化(下請けに出すこと)を加速させました。
- 元請けの「商社化」: 大手ゼネコンは、自社で職人を抱えずに施工管理とマネジメントに特化するようになりました。これにより、現場作業は完全に下請け任せとなり、元請けが利益を確保した上で下層に仕事が流れる構造がより一層固定化しました。
- 「法律逃れ」のための小規模事業者増加: 社会保険や労働基準法の適用を逃れるため、一人親方や小規模な会社として独立するケースが増えました。これも末端の階層を増やし、構造を複雑にする一因となりました。
結論として、デフレ期はコスト削減圧力から下請けへの依存度をさらに高め、構造をより深く、複雑にする変化をもたらしました。
製造業 🏭
製造業では、日本の強みであった「系列」という安定的な下請け構造が、デフレ経済の中で大きく揺らぎました。
- 「系列」の崩壊と取引のドライ化: かつては親会社が系列の子会社・下請け企業を手厚く保護する関係性がありました。しかし、デフレとグローバル競争の激化により、親会社はコスト削減を最優先。より安く部品を調達できるなら、系列外の企業や海外企業とも取引するようになりました。
- 選別と淘汰: 親会社からの厳しいコストダウン要求に応えられない下請け企業は、取引を打ち切られ、淘汰されていきました。これにより、下請け企業は常に価格競争の圧力にさらされることになりました。
- 技術の空洞化: 厳しいコスト要求は、下請け企業が研究開発や設備投資に資金を回す余裕を奪いました。結果として、日本のモノづくりを支えてきた現場の技術力が少しずつ失われていく「産業の空洞化」の一因ともなりました。
デフレ期は、安定していたはずの製造業の下請け構造を流動的で厳しい競争関係へと変質させました。
物流・運送業界 🚚
物流業界の多重請負構造は、デフレ期に本格的に形成され、深刻化したと言えます。
- 規制緩和による事業者数の激増: 1990年の「物流二法」の制定や2003年の法改正により、運送業への参入が容易になりました。これにより事業者が急増し、過当競争が始まりました。
- 荷主優位と運賃の低下: 供給(運送会社)が増えたことで、荷主(仕事を依頼する側)の立場が圧倒的に強くなりました。荷主からの厳しい値引き要求に応えるため、元請けの運送会社は、より安い運賃で運んでくれる下請けを探すようになります。
- 「水屋」の介在: 自社ではトラックを一台も持たず、仕事の仲介(中抜き)だけで利益を得る「水屋」と呼ばれる利用運送事業者が増えました。これが中間搾取を助長し、多重下請け構造を複雑化させる大きな要因となりました。
このように、物流業界ではデフレ期の規制緩和と価格競争が、ゼロから多重請負構造を生み出し、一気に深刻化させたのです。
デフレ脱却の影響
現在の日本はデフレをほぼ脱却していますが、2024年から2025年の期間に各業界の多重請負構造に何か変化や不具合は見られますか。
はい、デフレを脱却し、インフレと深刻な人手不足が同時に進行する中で、各業界の多重請負構造はこれまでにない大きな圧力にさらされ、構造そのものの限界や不具合が顕在化しています。
コスト削減を前提としていたこの古いモデルが、現在の経済状況と全く適合しなくなっているのです。
共通する変化:下層からの悲鳴と構造の崩壊リスク
全業界で共通しているのは、物価上昇と賃上げの圧力が、ピラミッドの末端で働く下請け企業や労働者を直撃していることです。
- コスト増を価格転嫁できない: 下層の企業は立場が弱く、原材料費や光熱費の上昇分を元請けへの請求額に上乗せすることが非常に困難です。
- 賃上げの原資がない: 社会全体で賃上げの機運が高まっても、利益を削られている下層企業にはその原資がありません。これにより、人材の流出がさらに加速しています。
これまで何とか機能してきた多重請負構造が、末端から崩壊しかねないという危機的な状況に直面しています。
各業界の変化と不具合
物流・運送業界 🚚:2024年問題が構造の限界を直撃
多重請負構造の不具合が最も深刻な形で噴出しているのが物流業界です。
- 2024年問題の直撃: 2024年4月から施行されたドライバーの時間外労働の上限規制(2024年問題)により、これまでのような長時間労働で低運賃をカバーすることが不可能になりました。
- 下層の事業者の倒産・廃業: 規制に対応できず、燃料費の高騰と低運賃の板挟みになった中小・零細事業者の倒産や廃業が急増しています。
- 荷主・元請けの意識改革: 仕事を依頼する荷主や元請け企業も、運賃を適正化し、多重請負構造を見直さなければ、自社の荷物が運ばれなくなるという現実に直面し、ようやく取引慣行の是正に動き始めています。構造改革が待ったなしの状況です。
建設業界 🏗️:人手不足が限界点を突破
建設業界でも、物流業界と同様に労働規制と人手不足が構造を揺るがしています。
- 担い手不足の深刻化: 賃金が上がらず、労働環境も厳しい下層の専門工事業者では、職人の高齢化と若者の入職者減が極限に達しています。もはや「下請けに出せば何とかなる」という状況ではなくなりました。
- 労務単価上昇と価格転嫁問題: 国が定める公共工事の労務単価は上昇していますが、その上昇分が末端の職人にまで行き渡らないという問題が続いています。元請けや上位の下請けが上昇分を吸収してしまい、構造的な問題が改善を妨げています。
- 偽装請負から偽装一人親方へ: 社会保険への加入逃れなどを目的とした「偽装一人親方」の問題がクローズアップされており、労働者の権利保護が大きな課題となっています。
製造業 🏭:「系列」モデルの完全な転換期
安定していた製造業のサプライチェーンも、歴史的な転換点を迎えています。
- 円安と原材料高のダブルパンチ: 円安で輸入品の価格が高騰し、下請け企業の収益を強く圧迫しています。親会社もコスト増に苦しんでおり、かつてのように下請けを守る体力がなくなっています。
- サプライチェーンの再編: 公正取引委員会が下請けいじめに対する監視を強化するなど、国も価格転嫁を後押ししています。これにより、親会社と下請けの関係はより対等なパートナーシップへと変化せざるを得なくなっています。古い「系列」の力関係は、もはや通用しなくなりつつあります。
- 事業承継問題: 経営者の高齢化が進む中小の下請け企業では、後継者が見つからずに廃業するケースが増えており、日本のモノづくりを支えてきた技術の継承が危ぶまれています。
IT業界 💻:多重請負からの脱却の動き
IT業界では、慢性的なエンジニア不足とDX(デジタルトランスフォーメーション)の需要の高まりから、構造変化の兆しが見られます。
- ユーザー企業の内製化: SIerに丸投げするのではなく、自社でエンジニアを採用・育成し、システムを内製化しようとするユーザー企業が増えています。これは中抜きを前提とした多重請負構造のビジネスモデルを根本から揺るがします。
- エンジニアの価値向上: 人材不足を背景に、優秀なエンジニアはより待遇の良い企業へ転職したり、フリーランスとして独立したりする動きが活発です。これにより、スキルが正当に評価されない下層に留まる理由がなくなり、人材の流動化が構造を内側から変えつつあります。
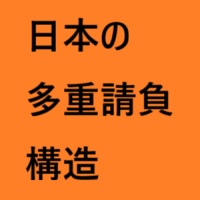

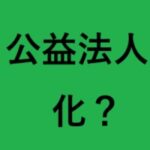
日本の産業界では、特定の業界において「多重請負構造(重層下請構造)」が定着しています。これは、発注者から仕事を受けた元請企業が、その業務の全部または一部を一次下請企業に発注し、さらにその一次下請が二次下請に、二次下請が三次下請に…と、ピラミッドのように仕事が再委託されていく構造を指します。
この構造が特に顕著に見られるのは、以下の業界です。
建設業界
建設業界は、多重請負構造の典型例として最もよく知られています。大手ゼネコン(総合建設業者)が施主から大規模な建設プロジェクトを元請として受注し、設計や施工管理などの上流工程を担当します。そして、実際の現場作業は、専門分野ごとに細分化され、専門工事業者である下請企業に発注されます。
このような構造は、大規模プロジェクトを効率的に進める上で合理的な面もありますが、下層の業者ほど報酬が低くなり、労働条件が悪化しやすいという問題を抱えています。
IT業界
IT業界、特にシステム開発の分野では、建設業界と同様の多重請負構造が見られます。「ITゼネコン」と揶揄されることもある大手SIer(システムインテグレーター)が顧客から大規模なシステム開発案件を受注し、要件定義や設計といった「上流工程」を担当します。そして、プログラミングやテストといった「下流工程」は、下請けの中小ソフトウェア開発会社や、さらにはフリーランスのエンジニアに再委託されます。
この構造は、必要な時に必要なスキルを持つ人材を確保できるというメリットがある一方で、以下のような問題点が指摘されています。
物流・運送業界
荷主から輸送業務を請け負った元請の運送会社が、実際の配送を他の中小運送会社や個人のドライバーに委託するケースが多く見られます。特に長距離輸送や繁忙期には、自社で対応しきれない貨物を下請けに依頼することで、柔軟な配送ネットワークを維持しています。
しかし、この業界でも、下請けになるほど運賃が安くなる「中抜き」が問題視されており、燃料費の高騰なども相まって、末端のドライバーの経営を圧迫する要因となっています。
その他の業界
上記以外にも、以下のような業界で多重請負構造が見られることがあります。
多重請負構造が生まれる背景
日本でこのような構造が定着した背景には、以下のような要因が挙げられます。
この構造は、日本経済の柔軟性を支えてきた側面がある一方で、労働者の待遇悪化や責任の所在の曖昧化といった深刻な問題も引き起こしており、各業界で是正に向けた取り組みが求められています。