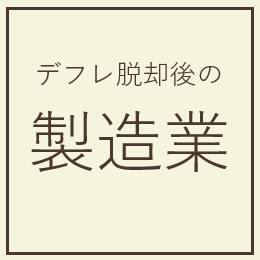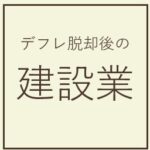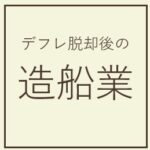この記事は、Gemini Deep Research にリサーチして執筆してもらったレポートです。
生成AIの書いた記事を修正すること無く、そのまま掲載しています。
一般常識として、「生成AIの書く記事には、ハルシネーションによる間違いが含まれている可能性がある」事を踏まえて記事を読んでください。
生成AIは完璧ではありません。
この記事の prompt は以下の文書になります。
現在の日本の製造業における、デフレ脱却と人手不足による経営状況をリサーチしてください。
特に、収益率の変化、商流変更や事業再編・経営統合や、人材確保の方法の変更、倒産状況などの動向も知りたいです。
また、人手不足を受けての設備投資・IT活用などの動向もリサーチしてください。
わからない事は、わからないと回答してください。
ハルシネーションは避けてください。
以降は、全て Gemini Deep Research の書いたレポートです。
日本製造業の新たな現実:デフレ脱却後の圧力と未曾有の人手不足という二重の課題への対応
第I部 マクロ経済のるつぼとその財務的影響
日本の製造業は、数十年にわたるデフレからの脱却と、深刻化する構造的な人手不足という、二つの強力なマクロ経済的変化が交差する歴史的な転換点に立たされている。この新しい経済環境は、企業の経営戦略、収益構造、そして存続そのものに根本的な変革を迫っている。本章では、このマクロ経済的背景を定義し、それが製造業企業の景況感、収益性、そして喫緊の課題である価格転嫁に与える直接的な財務的影響を分析する。
1.1 変動する経済情勢:二極化する景況感
現在の製造業における景況感は、企業規模によって明確に二極化する様相を呈している。グローバル市場に事業を展開する大企業がある程度の強靭性を示す一方で、国内経済の動向に大きく左右される中小企業は、コスト上昇と将来への不確実性という、より厳しい現実に直面している。この乖離は、現在の経済環境を象徴する中心的なテーマである。
日本銀行が発表した2025年6月の企業短期経済観測調査(短観)によれば、大企業製造業の業況判断DI(最近)は、前回調査から1ポイント改善し+13となった 1。この回復の背景には、素材業種における燃料価格を中心とした投入コストの減少や、自動車をはじめとする最終製品への底堅い需要が存在する 1。しかし、この改善は盤石とは言えない。加工業種では、金属製品や個別に関税が課せられている自動車などを中心に景況感は悪化しており、米国の関税政策や海外景気の減速といった下振れリスクへの懸念も根強い 1。
対照的に、中小企業製造業の状況は著しく厳しい。同調査における業況判断DIは1ポイント悪化して+1となり、先行きについてはさらに3ポイント悪化の-2が見込まれている 1。これは、中小企業が原材料価格の上昇という直接的なコスト圧力に晒され、将来的な収益への不安を強く感じていることの表れである 4。中小企業の景況感は持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい状況が続いていることが複数の調査で示されている 5。
表1:業況判断DI(日銀短観サマリー)
| 区分 | 最近のDI(2025年6月) | 前回調査からの変化幅 | 先行きDI(2025年9月) |
|---|---|---|---|
| 大企業・製造業 | +13 | +1 | +12 |
| 中小企業・製造業 | +1 | -1 | -2 |
| 大企業・非製造業 | +34 | -1 | +27 |
| 中小企業・非製造業 | +15 | -1 | +9 |
| 出典:1を基に作成 |
この景況感の乖離は、単なる企業規模の違いに起因するものではなく、事業モデルと市場における交渉力の構造的な差異を反映している。大企業はグローバルなサプライチェーン、多様な販売市場、そして強力なブランド力を活用してコストを吸収、あるいは転嫁する余力を持つ。一方で、多くの中小企業は国内市場の状況や、価格決定権を持つ大口取引先に依存する構造にあり、デフレ脱却過程で生じるコストプッシュ型インフレの圧力を直接的に受けることになる。つまり、大企業と中小企業のDIの差は、デフレ後の新しい経済環境に適応する能力の構造的な格差が顕在化したものと分析できる。
1.2 収益性の圧迫:上昇するコストと停滞する生産性の狭間で
一部の企業が価格改定によって利益を確保しているものの、製造業全体、特に中小企業の収益性は深刻な圧力に晒されている。この問題の根源には、原材料、エネルギー、人件費といった投入コストの急騰と、長年にわたって横ばいが続く労働生産性という二つの構造的課題の衝突がある。
経済産業省の調査によると、製造業の平均売上高営業利益率は大企業・中小企業ともに4.0%であり、一般的に標準とされる5%前後と比較してやや低い水準にある 6。大企業は、円高が輸入原材料コストを抑制する効果もあり、利益計画を上方修正する動きも見られるが、これは中小企業が直面する困難な状況を覆い隠している 2。
より深刻な根本問題は、労働生産性の停滞である。製造業の一人当たり名目労働生産性は、2021年時点で1,077万円と全産業平均(815万円)の約1.3倍に達するものの、2015年に1,000万円を突破して以降、1,000万~1,100万円の範囲でほぼ横ばいが続いている 7。これは、生産性を向上させる抜本的なイノベーションがなければ、人件費の上昇が直接的に利益率を侵食することを意味する。現在の収益圧迫は、原材料価格の高騰、エネルギーコストの上昇、そして深刻な人手不足に対応するために不可欠な賃上げ圧力という、三重のコスト増によって引き起こされている 4。
この生産性の停滞こそが、日本製造業のアキレス腱と言える。現在のインフレ環境は、収益性問題の「原因」ではなく、この既存の構造的脆弱性を白日の下に晒した「触媒」である。デフレ期には、投入コストや賃金も安定していたため、生産性の停滞は問題として顕在化しにくかった。しかし、あらゆるコストが上昇する現在、生産性(労働者一人当たりの産出量)が変わらなければ、コスト上昇分を価格に転嫁できない限り、利益率の低下は避けられない。企業はコストを吸収して利益を犠牲にするか、価格転嫁を試みるかという困難な選択を迫られている。したがって、現在の「収益性圧迫」は、生産性のダイナミズムを失った経済システムがインフレショックに見舞われた必然的な結果なのである。
1.3 価格転嫁という至上命題:生き残りを左右する最重要因子
上昇するコストを販売価格に転嫁できるかどうか(価格転嫁)は、今や企業の財務健全性を測り、経営危機に陥る企業とそうでない企業とを分ける、最も重要な単一の要因となっている。価格転嫁は進展を見せているものの、依然として不完全であり、多くの中小企業がコスト負担の大部分を自社で吸収せざるを得ない状況に置かれている。
帝国データバンクの2024年7月の調査によると、コスト上昇分に対する価格転嫁率は過去最高の44.9%に達した 10。これは、コストが100円上昇した場合、企業は価格を44.9円しか引き上げられず、残りの55.1円は自社の利益を削って負担していることを意味する。コスト上昇分の「多少なりとも価格転嫁できている」企業の割合は75.1%に上る一方で、「全く価格転嫁できない」企業も10.9%存在し、これらの企業は極めて高いリスクに晒されている 10。実際に、直近3年間で企業が実施した行動として、約9割が「価格転嫁」を挙げており、これが普遍的な経営課題であることがわかる 12。
重要なのは、価格転嫁の成否が賃上げの実現可能性と強く相関している点である。価格転嫁率が高い企業ほど、賃上げ率も高い傾向にあることが調査で明らかになっており、価格転嫁に成功した企業は、人材確保・定着のための原資を生み出す好循環を創出できる 13。反対に、価格転嫁に失敗した企業は、収益悪化から倒産に至るリスクが高まる。特に、原材料費や人件費などのコスト上昇分を価格に転嫁できずに倒産に追い込まれる「物価高倒産」が急増している 15。
価格転嫁は、もはや単なる価格設定戦術ではなく、企業の総合的な競争力と提供価値を測る代理指標へと進化している。コストを転嫁できないという事実は、単なる財務上の問題ではない。それは、自社の製品やサービスが市場において十分な差別化や価格決定力を持たないという、戦略的な危険信号なのである。価格転嫁率の業種間格差が大きいことは、市場構造や製品特性が重要であることを示唆している 11。競争が激しくコモディティ化した分野の企業は、独自の技術や強固な顧客関係を持つ企業よりも苦戦を強いられる。そして、賃上げとの連動性はフィードバックループを生み出す。強い価値提案を持つ企業は、コストを転嫁し、賃金を上げ、より良い人材を惹きつけ、さらなるイノベーションを起こし、価値提案を一層強化する。逆に、価値提案の弱い企業は、コストを転嫁できず、賃金を上げられず、人材を競合に奪われ、競争力がさらに低下し、倒産へと向かう。したがって、価格転嫁率は、インフレと人手不足が常態化した新経済環境における、企業の長期的な戦略的健全性を示す先行指標と言える。
第II部 新時代への戦略的・運営的対応
本章では、課題の分析から解決策の検討へと焦点を移す。製造業企業が、人的資本、テクノロジー、企業構造(M&A)、サプライチェーンという4つの主要分野において、いかに積極的に戦略を適応させているかを詳述する。
2.1 人的資本の危機と進化する職場環境
人手不足はもはや周期的な問題ではなく、人口動態に根差した深刻な構造的危機となっている。この状況に対応するため、先進的な企業は単なる採用活動を超え、定着、人材育成、そしてより魅力的で柔軟な労働環境の創出に重点を置いた、人的資本戦略の根本的な再構築を進めている。
中小企業における人手不足感は、新型コロナウイルス感染症の拡大以前よりも強い水準に達している 17。特に深刻なのは、6割以上の事業所が「指導する人材が不足している」と回答しているように、社内で従業員を育成する能力そのものが枯渇している点である 17。
このような状況下で、企業は人材獲得のアプローチを多様化させている。特定の経験よりも「人柄」を重視した採用 19、女性の技術分野への積極的な登用 20、そしてテレワークのような柔軟な勤務形態を導入することで、育児や介護といった制約を持つ人材を含め、より広範な地域から優秀な人材を惹きつけようとしている 19。
同時に、離職コストの高さを認識し、人材定着への投資を強化している。これには、独自の「育児教育手当制度」の導入 21、一人の従業員が複数の業務をこなせるようにする「多能工化」の推進による柔軟で強靭なチーム作り 19、そして金銭的援助や情報提供を通じた従業員のスキルアップ・リスキリング(リカレント教育)支援が含まれる 18。さらに、一部の企業では、自社の枠を超え、地域内の他企業と連携して合同研修会や技術者の相互出向を実施し、地域エコシステム全体で人材を育成・定着させようという先進的な取り組みも見られる 22。
これらの動きは、「労働力」という概念が「戦略的人的資本」へと再定義されていることを示している。デフレ時代の特徴であった人件費の最小化という考え方から、希少な資源である人材の価値と生産性を最大化するという考え方への転換である。これは、単なる経営戦術の変更ではなく、根深い企業文化とマネジメントの変革を意味する。多能工化やリスキリング支援は、短期的な欠員補充ではなく、従業員の長期的価値を高めるための投資である。地域連携の取り組みは、人材プールが競争の場であるだけでなく、共有すべきコミュニティ資源であるとの認識が広まっていることを示している。現在の危機は、従業員の幸福と成長が企業の存続と発展の前提条件であるという、ステークホルダーモデルへの移行を企業に強いているのである。
2.2 技術的対応:戦略的レバーとしてのアウトメーションとデジタル化
テクノロジー、特にソフトウェア、自動化、そしてより広範なデジタルトランスフォーメーション(DX)への投資は、人手不足に対する主要かつ不可欠な対応策となっている。これらの投資は、もはや効率改善のための任意選択ではなく、事業継続と競争力維持のための必須戦略と化している。
経済的な不透明感が一部で存在するにもかかわらず、設備投資意欲は依然として旺盛であり、特に製造業でその傾向が強い 23。中でも顕著なのは、中小企業におけるソフトウェア投資の劇的な伸びであり、2025年度計画では前年比42.8%増という驚異的な数字が示されている 3。これは、企業戦略の軸足が明確にデジタルソリューションへと移行していることを物語っている。世界的に見ても、自動化・省人化ニーズの高まりを背景に、製造業向けロボット市場は大幅な成長が見込まれている 24。
DXの導入は急速に拡大しており、デジタル技術を活用している製造業企業の割合は、2019年の5割弱から2023年には8割超へと急増した 17。そして最も重要な点は、DXの導入が具体的な成果に結びついていることである。デジタル技術の活用が進んだ中小企業は、営業利益を伸ばし、賃上げを実施している割合が高いことが確認されており、投資の正当性が財務的に裏付けられている 17。
DXの成功事例は多岐にわたる。
- プロセスイノベーション: ㈱木村鋳造所は、従来の木型に代わり3Dプリンタで砂型を製造する新技術を導入し、リードタイムを劇的に短縮した 25。
- リアルタイム監視: ある企業では、IoT技術を導入した「MCM System」により製造ラインの稼働状況を可視化し、ボトルネックの特定と業務効率化に成功した 25。
- 自動化: シンフォニアテクノロジー㈱は、RFIDソリューションを導入して部品在庫管理を自動化し、部品捜索時間を90%削減、部品不足による生産遅延をゼロにした 26。
- 遠隔サービス: 秀和工業㈱は、遠隔監視・予知保全を可能にするIoTシステムを組み込んだ装置を開発し、技術者の緊急出動回数を7割近く削減する見込みを立てた 27。
DX戦略には二つの潮流が生まれつつある。第一の波は、人手不足の解消や業務効率化といった、喫緊の社内課題を解決するための「防衛的DX」である。自動化による在庫管理や生産プロセスの可視化などがこれにあたる。しかし、より先進的な第二の波は「攻撃的DX」と呼ぶべきものであり、企業がデジタル能力を活用して全く新しいビジネスモデルや価値提案を創造する段階である。秀和工業の事例は、単に自社の業務を効率化しただけでなく、IoTシステムを製品に組み込むことで、機械そのものではなく「遠隔メンテナンス」という新たなサービスを顧客に販売するモデルへと転換した。これは、テクノロジーを旧来の業務をより良く行うための手段として使うのではなく、新しいビジネスを行うための基盤として活用する動きである。DXの成熟度が高まるにつれて、企業は単なる労働力の代替から、ビジネスモデルの根幹を革新する方向へと舵を切っていくだろう。
2.3 戦略的再編:M&Aと事業再構築
製造業では、M&A(企業の合併・買収)が活発化している。この背景には、経営者の高齢化と後継者不在という慢性的な問題、新しい技術や熟練人材を迅速に獲得する必要性、そして事業規模を拡大しサプライチェーンを強化するという戦略的要請という、複数の圧力が複合的に作用している。
表2:製造業におけるM&Aの主要な動機
| M&Aの動機 | 内容 | 戦略的目標 | 関連資料 |
|---|---|---|---|
| 事業承継 | 後継者のいない高齢経営者が事業の売却を目指す。 | 事業の継続、従業員の雇用維持。 | 9 |
| 技術獲得 | DX、自動化、ロボティクス、IoT等の専門技術を持つ企業を買収。 | 技術導入の加速、競争優位性の確保。 | 28 |
| 人的資本の確保 | 熟練した技術者やエンジニアチームを擁する企業を買収。 | 採用難の克服、重要な人材の確保。 | 9 |
| サプライチェーン強化 | 部品メーカーや物流関連企業を買収し、垂直統合を進める。 | 供給の安定化、外部リスクの低減。 | 28 |
| 規模・市場拡大 | 競合他社との水平統合や、新市場への参入。 | 市場シェアの拡大、規模の経済の実現。 | |
| 出典: |
M&Aの主な動機は多岐にわたる。依然として「事業承継」は強力な推進力であり、後継者不在に悩む経営者が会社の存続と従業員の雇用を守るための最も現実的な手段としてM&Aを選択している 9。同時に、企業はM&Aを、自社で育成するには時間がかかりすぎる能力を獲得するための近道として活用している。これには、自動化やIoTといった特定の技術を持つ企業の買収 28 や、個別に採用することが困難な熟練技術者チームを丸ごと獲得する目的も含まれる 9。さらに、重要な部品へのアクセスを確保し、供給網の脆弱性を低減するための垂直統合も活発化している 28。
近年の新たなトレンドとして、M&Aの「民主化」が挙げられる。オンラインM&Aマッチングプラットフォームの台頭や、地域金融機関による支援の強化により、中小企業にとってもM&Aが身近な戦略的選択肢となりつつある 29。また、同業の中小企業同士が統合し、顧客基盤の拡大や仕入れにおけるスケールメリットを追求する「水平統合」も増加している 29。国内市場の縮小を見据え、東南アジアなどの成長市場に進出するために海外企業を買収するクロスボーダーM&Aも活発化している 28。
M&Aは、市場原理に基づいた産業再編と能力移転のメカニズムとして機能している。これは、生産性の低い企業から高い企業へと資本と人材の再配分を加速させ、DXのような現代的な技術が中小企業のエコシステム全体に普及するための重要な経路となっている。例えば、伝統的な家族経営の企業は、大規模なDX導入に必要な資本や専門知識を欠いているかもしれない 9。そこへ、より技術的に進んだ企業が、その企業の特定の製造ノウハウや顧客基盤を求めて買収を行う 28。買収後、買い手企業は資本とデジタルシステムを注入して事業を近代化する。同時に、買い手は模倣困難な「現場の知」と熟練労働者を獲得する。このように、M&Aは単に所有権を移転させるだけでなく、本来であれば自然には起こりにくい近代化のサイクルを促進する触媒として作用し、業界全体の新たな経済環境への適応を加速させている。
2.4 バリューチェーンの再設計:サプライチェーンの多様化と国内回帰
地政学的リスク、パンデミックによる供給網の混乱、そして海外におけるコスト上昇を受け、日本の製造業はグローバル・サプライチェーン戦略の根本的な見直しを迫られている。長年信奉されてきた「ジャスト・イン・タイム」の思想は、「ジャスト・イン・ケース」というリスク対応型の考え方によって補完されつつあり、調達先の多様化、近隣国への生産移管(ニアショアリング)、そして戦略的な国内回帰という顕著なトレンドを生み出している。
特に注目されるのが、生産拠点を日本国内に戻す「リショアリング」の動きである。これはリスク軽減と安定供給の確保を目的としている。
- 具体例: パナソニックは洗濯乾燥機の国内生産を強化し、TSMCとソニーは熊本に巨大な半導体新工場を建設、日清食品は茨城県に国内最大級の研究開発・製造拠点を建設するなど、幅広い業界で国内投資が活発化している 32。
- 動機: これらの動きの背景には、物流リスクの低減、品質管理の向上、そして国内需要の変動に対するより柔軟な対応といった狙いがある 33。
同時に、特定国への一極集中リスクを回避するため、調達先を多様化する「マルチソーシング」も進んでいる。
- 戦略: これには、同じ部品を複数のサプライヤーから調達することで冗長性を確保し、価格競争を促す「デュアルソーシング」 35 や、異なる製品ラインで部品を標準化・共通化することで調達を簡素化し、交渉力を高める取り組みが含まれる 36。
これらの動きは、単なる経営判断としてだけでなく、事業継続計画(BCP)を含む「経済安全保障」の観点からも推進されており、企業は意識的に強靭で安定した調達体制の構築を進めている 12。
この国内回帰のトレンドは、日本国内に新たな競争力学を生み出している。これは、かつての国内製造業への単純な回帰ではない。新たに建設される国内工場は、人手不足を前提として設計されており、その結果として高度に自動化され、データ駆動型の「スマートファクトリー」となる。TSMCやソニーのような企業は、日本の労働力不足と、かつての海外拠点と比較して高い人件費を十分に認識している。そのため、過去の労働集約的なモデルを日本で再現することは非論理的である。これらの新工場への巨額の設備投資は、それらがロボティクス、AI、IoTを駆使し、最小限の人的介入で高い生産性を達成する最先端の施設であることを示唆している 12。このことは、国内回帰のトレンドが日本における先進製造技術の導入を加速させ、他の国内企業が競争しなければならない生産性と自動化の新たな、より高い基準を設定することを意味する。
第III部 広がる格差:市場の帰結と将来展望
最終章では、これまで述べてきた様々な圧力と戦略的対応がもたらす究極的な結末を分析する。企業倒産の厳しい現実を検証し、本レポートの分析結果を統合して、日本製造業の将来像に関する戦略的展望を提示する。
3.1 淘汰の実態:「物価高倒産」と「人手不足倒産」の増加
近年の企業倒産の急増は、単なる景気後退の兆候ではなく、構造的な淘汰が進んでいることの証左である。売上不振ではなく、新たな高コスト・人手不足の環境下でビジネスモデルが立ち行かなくなったために倒産する企業が増加している。「物価高」と「人手不足」を直接の原因とする倒産の増加は、このパラダイムシフトを最も明確に示している。
2024年度の企業倒産件数は11年ぶりに1万件を超え、高水準で推移している 16。2025年度上半期もこの傾向は続いている 38。倒産の原因を詳しく見ると、構造変化が明らかになる。
- 「物価高倒産」: 2024年度には925件に達し、過去最多を更新した 15。これは、企業が原材料費やエネルギーコストの上昇を吸収も転嫁もできなくなった直接的な結果であり、製造業や建設業で特に顕著である 15。
- 「人手不足倒産」: こちらも2024年度に350件と過去最多を記録し、2025年度も記録的なペースで増加している 15。主な内訳は、「人件費高騰」「従業員退職」「求人難」であり、人材を確保・維持できなくなったことが事業継続を不可能にしている 38。
- 中小企業の脆弱性: これらの倒産の大部分は、中小・零細企業で発生している。2024年度上半期の人手不足倒産のうち、82.2%は従業員10人未満の企業であった 40。
表3:近年の企業倒産の原因分析(2024年度、製造業)
| 倒産の主因 | 件数(製造業) | 主な背景・要因 |
|---|---|---|
| 物価高 | 180件 | 原材料・エネルギーコストの上昇分を価格転嫁できず、採算が悪化。 |
| 人手不足 | (データより算出) | 人件費の高騰、従業員の退職、採用難により事業継続が困難に。 |
| 販売不振 | (データより算出) | 伝統的な倒産要因。比較対象として記載。 |
| 後継者難 | (データより算出) | 経営者の高齢化に伴う構造的な問題。 |
| 出典: |
「物価高倒産」と「人手不足倒産」という二つの現象は、深く相互に関連し、互いを増幅させる関係にある。これらは、脆弱な中小企業を罠にかける悪循環を形成している。まず、企業は原材料コストの上昇に直面するが、価格転嫁ができない(「物価高」の問題)15。これにより利益率が圧迫され、競争力のある賃金を提示することが不可能になる。賃上げができないため、従業員はより待遇の良い職場へと流出し、新たな人材の採用も困難になる(「人手不足」の問題)40。人手不足は生産能力とサービスの質をさらに低下させ、顧客に対する価格引き上げの交渉を一層難しくする。この負のフィードバックループは、企業の資金が尽きるまで続き、最終的に「物価高」と「人手不足」が複合した倒産へと至る。この二つは別々の問題ではなく、新たな経済のファンダメンタルズに適応できなかったという、同じコインの裏表なのである。
3.2 戦略的展望と提言
日本の製造業は、極めて重要な変曲点にある。インフレと人手不足という圧力は、痛みを伴うものではあるが、構造変革を促す強力な触媒として機能している。将来は、積極的に変化に適応する企業が飛躍し、旧来のやり方に固執する企業が衰退していく「K字型」の格差拡大によって特徴づけられるだろう。
本レポートの分析から導き出される結論は以下の通りである。
- 受動的なコスト削減によって生き残れた時代は終わった。能動的な価値創造が不可欠である。
- 競争力の主戦場は、人材マネジメント、技術導入(DX)、戦略的機敏性(M&A)、そしてサプライチェーンの強靭性へと移行した。
- 人材と技術に投資する能力は、企業の価格決定力(価格転嫁)と直接的に結びついており、「持つ者」と「持たざる者」の間に明確な格差を生み出している。
この新しい時代を勝ち抜くための成功要因は、以下の4点に集約される。
- 人間中心モデルへの転換: 従業員を最小化すべきコストではなく、投資すべき戦略的資産として扱う。これには、競争力のある賃金、継続的な教育訓練、そして柔軟で魅力的な労働環境の提供が含まれる。
- 戦略的DXの追求: 防衛的なコスト削減目的のDXを超え、テクノロジーを活用して新たなサービス、製品、ビジネスモデルを創造する攻撃的な戦略へと移行する。
- 戦略的機敏性の涵養: M&Aや提携を一度限りのイベントとしてではなく、能力獲得、市場参入、変化への適応を続けるための継続的なツールとして位置づける。
- 強靭なバリューチェーンの構築: 調達先の多様化や戦略的な国内投資を通じて、サプライチェーンリスクを積極的に管理し、その強靭性を競争優位性へと転化させる。
今後数年間は厳しい道のりが続くであろうが、それは同時に日本製造業のルネサンス(再生)に向けたまたとない機会でもある。この移行を成功裏に乗り越えた企業は、よりスリムで、技術的に進み、強靭で、そして最終的にはよりグローバルな競争力を持つ存在となるだろう。現在の危機は、製造業に対して、次の100年を築くための礎を築くことを強いているのである 12。
引用文献
- 日銀短観(2025 年 6 月調査)結果 – 三菱UFJリサーチ …, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2025/07/tankan_res_2507_01.pdf
- 業況判断DIは台風の影響等で横ばい ~2024年9月日銀短観~ | 熊野 英生, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.dlri.co.jp/report/macro/381361.html
- 大企業・製造業の業況+1ポイント改善 ~2025年9月日銀短観:関税妥結は反応薄~ | 熊野 英生, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.dlri.co.jp/report/macro/517563.html
- 中小企業関連調査・レポート | J-Net21
, 11月 2, 2025にアクセス、 https://j-net21.smrj.go.jp/report/corona/index.html - 中小企業景況調査報告書 結果の概要, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/keikyo/index_gaiyo.html
- 製造業の利益率目安とは?低下する要因と改善ポイントを徹底解説 | お役立ち情報ナビ | DAIKO XTECH株式会社, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.daiko-xtech.co.jp/daiko-plus/production-control/manufacturing-industry-profit-marginntrol/
- 製造業の業績と投資動向[2023年版ものづくり白書より] – 株式会社エクサ, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.exa-corp.co.jp/blog/manufacturing_innovation_and_investment.html
- 【2024年版 ものづくり白書】要点まとめ!製造業の「稼ぐ力」の向上に必要なこと|coevo, 11月 2, 2025にアクセス、 https://aconnect.stockmark.co.jp/coevo/monodzukuri2024/
- 【2025年最新】製造業のM&A動向 | M&A仲介・アドバイザリーのご相談はストライク, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.strike.co.jp/ma_trend/manufacture/
- 価格転嫁に関する東京都企業の実態調査(2024年7月) – 帝国データバンク, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tdb.co.jp/report/economic/r4z_6s10wc/
- 価格転嫁に関する実態調査(2024年7月) – 帝国データバンク, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tdb.co.jp/report/economic/20240828_pricepass-on/
- 2025年版 ものづくり白書 – 独立行政法人経済産業研究所, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.rieti.go.jp/jp/events/bbl/25061901_kawamura.pdf
- 価格転嫁と賃上げの相関、中小企業ほど鮮明に | TSRデータインサイト | 東京商工リサーチ, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1197359_1527.html
- 中小企業で賃上げは定着するか?カギは価格転嫁と生産性向上 – 三菱総合研究所, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mri.co.jp/knowledge/insight/20230420.html
- 倒産集計 2024年度報(2024年4月~2025年3月) – 帝国データバンク, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tdb.co.jp/report/bankruptcy/aggregation/g2-5yfk9w/
- 2024年度の企業倒産1万70件 負債総額3年連続で2兆円超 物価高や人手不足など背景 帝国データバンク|TBS NEWS DIG – YouTube, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=5jfshuGwmmc
- 2024年版 ものづくり白書 概 要 – 厚生労働省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mhlw.go.jp/content/001258804.pdf
- 2025年版 ものづくり白書 概 要 – 厚生労働省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mhlw.go.jp/content/001496473.pdf
- 事例から学ぶ!「どうすればいいの?人手不足」 – ミラサポPlus, 11月 2, 2025にアクセス、 https://mirasapo-plus.go.jp/hint/16928/
- 2024年版 ものづくり白書 概 要 – 経済産業省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.meti.go.jp/report/whitepaper/mono/2024/pdf/gaiyo.pdf
- 中小企業で深刻な人手不足!今すぐ取り組める施策3選と企業成功事例, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.nice2meet.us/how-smb-should-tackle-shortfall-in-human-resources
- 2024年版「中小企業白書」 第1節 人材の確保, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2024/chusho/b2_1_1.html
- 法人企業統計季報(2024 年 7-9 月期), 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.dlri.co.jp/files/macro/396186.pdf
- 製造業向けロボットの世界市場を調査 | プレスリリース | 富士経済グループ, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.fuji-keizai.co.jp/press/detail.html?cid=25039
- 中小企業のDX推進の成功事例14選!課題や進め方、成功のコツを解説 – MENTER, 11月 2, 2025にアクセス、 https://menter.jp/blog/dx-examples-smes
- 事例10選に学ぶ製造業DX – リコー, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.ricoh.co.jp/service/digital-manufacturing/media/article/detail16
- 成功事例から紐解く製造業のDX : 後編「中小企業編」 日本が誇る“中小企業のものづくり” その現場を支えるIoT活用事例 | IoT設計構築支援 TED REAL IoT – 東京エレクトロン デバイス, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.teldevice.co.jp/ted_real_iot/column/dx-smes/
- 【2025年】M&A業界の動向を解説!業界別の動向や今後の展望について解説 – CINC Capital, 11月 2, 2025にアクセス、 https://cinc-capital.co.jp/column/ma/comparison/ma-industry
- 2025年における中小企業のM&Aトレンドと今後の展望, 11月 2, 2025にアクセス、 https://tsunagari-syoukei.com/column/816
- 【2025年版】製造業(メーカー)のM&A動向!事例や成功の秘訣と売却価格の相場を解説, 11月 2, 2025にアクセス、 https://ma-navigator.com/columns/seizougyou_ma
- 製造業界のM&Aと事業承継の動向・2025年最新, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.nihon-ma.co.jp/sector/c_manufacturing.php
- サプライチェーンにおけるセキュリティとは?製造業の国内回帰で高まる重要性, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.ntt.com/bizon/return_supplychains.html
- リショアリングとは?製造業の国内回帰が進む理由と成功事例解説 – QMS学習支援サイト, 11月 2, 2025にアクセス、 https://iatf-iso.net/blog/iot/reshoring.html
- 成功した製造委託の国内回帰事例:地政学リスクへの対策とビジネス改革 – 半導体事業 – マクニカ, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.macnica.co.jp/business/semiconductor/articles/basic/147504/
- 購買部門が進める製造業における複数調達の実践例 – 受発注AIエージェント | newji, 11月 2, 2025にアクセス、 https://newji.ai/procurement-purchasing/best-practice-examples-of-dual-sourcing-in-manufacturing/
- 購買部門が推進する部品共通化によるコスト削減の実例 – newji, 11月 2, 2025にアクセス、 https://newji.ai/procurement-purchasing/cost-reduction-through-parts-standardization-promoted-by-the-purchasing-department-a-successful-case-study/
- 中小企業のデジタル活用・DX事例集 – 東京商工会議所, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tokyo-cci.or.jp/digital-support/jirei/
- 【4~9月倒産】12年ぶりの高水準 「人手不足」理由が過去最多 | nippon.com, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.nippon.com/ja/japan-data/h02562/
- 全国企業倒産状況 | 倒産・注目企業情報 – 東京商工リサーチ, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tsr-net.co.jp/news/status/
- 人手不足倒産が急増⁉業種ごとの傾向や中小企業の割合をチェック, 11月 2, 2025にアクセス、 https://edenred.jp/article/hr-recruiting/204/