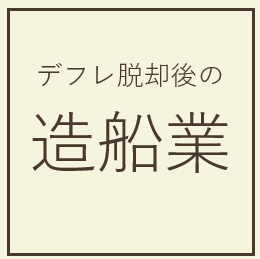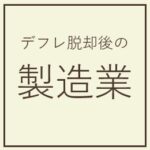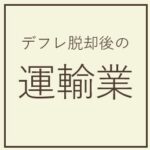この記事は、Gemini Deep Research にリサーチして執筆してもらったレポートです。
生成AIの書いた記事を修正すること無く、そのまま掲載しています。
一般常識として、「生成AIの書く記事には、ハルシネーションによる間違いが含まれている可能性がある」事を踏まえて記事を読んでください。
生成AIは完璧ではありません。
この記事の prompt は以下の文書になります。
現在の日本の造船業界における、デフレ脱却と人手不足による経営状況をリサーチしてください。
特に、収益率の変化、商流変更や事業再編・経営統合や、人材確保の方法の変更、倒産状況などの動向も知りたいです。
また、人手不足を受けての設備投資・IT活用などの動向もリサーチしてください。
わからない事は、わからないと回答してください。
ハルシネーションは避けてください。
以降は、全て Gemini Deep Research の書いたレポートです。
転換期を迎える日本の造船業:生き残りをかけた戦略と変革
エグゼクティブサマリー
日本の造船業界は、重大な岐路に立たされている。円安という追い風が一時的に収益性を押し上げているものの、その裏では世界的な競争力の低下と、深刻化する構造的な人手不足という根深い危機が進行している。本レポートは、日本の主要造船企業がこの二重の圧力に対し、大規模な戦略的再編、積極的な技術導入、そして人材戦略の根本的な見直しを通じていかに対応しているかを分析するものである。
本レポートの中心的な論点は、業界の長期的な存続は、好都合な為替動向に依存するのではなく、自動化され、より専門特化し、デジタルに統合されたセクターへと、痛みを伴いながらも必要不可欠な変革を断行できるかどうかにかかっているという点である。大手企業間の連携による「ナショナルチャンピオン」の形成、防衛分野や高付加価値船への事業の集中、そして労働集約型から知識集約型への転換を目指すAIやロボット技術への投資は、もはや選択肢ではなく、生き残りのための必須条件となっている。この一時的な収益改善という好機を活かし、未来への投資を断行できるか否かが、日本の造船業の将来を決定づけるであろう。
第1章 グローバル市場の荒波:日本の競争力が直面する逆風
本章では、日本の造船業界が置かれている厳しい外部環境を分析し、後の章で詳述する各社の経営判断の背景を明らかにする。かつて世界を席巻した日本の競争優位性は失われ、業界は守りの姿勢を強いられている。
1.1. 一時代の終焉:世界首位から縮小するプレゼンスへ
日本の造船業は、かつてその高い技術力で世界市場をリードしてきた。しかし、その栄光は過去のものとなり、現在では市場における存在感が著しく低下している。この変化は単なる景気の循環的な落ち込みではなく、構造的な地位の喪失を示唆している。
具体的なデータとして、世界の船舶受注量に占める日本のシェアは、かつて15-16%で推移していたが、2024年にはわずか8%にまで急落した 1。これは、業界の競争力が根本的に揺らいでいることの明確な証左である。同時に、日本の造船所における建造量自体も2019年以降、減少傾向にある。対照的に、中国は建造量を維持し、市場シェアを拡大しており、生産能力と勢いの差が鮮明になっている 1。
このシェア低下が特に顕著なのは、近年の発注ブームを牽引したコンテナ船やLNG(液化天然ガス)運搬船といった、需要が旺盛で付加価値の高い分野である。これらの大型案件の受注は、その大半を中国と韓国が獲得しており、日本の造船業界は市場で最も収益性の高いセグメントでの競争から脱落しつつあることを示している 1。
1.2. 中韓の挑戦:競争劣位の構造分析
市場シェア喪失の背景には、中国および韓国の造船業界との熾烈な競争がある。両国の造船所は、国家的な強力な支援を背景に、日本よりも低い船価と短い納期を提示することが可能であり、これが日本の価格競争力を著しく削いでいる 2。
この競争劣位を象徴する、極めて憂慮すべき事態が、国内の海運会社による発注動向の変化である。伝統的に日本の造船所の安定的な顧客であった国内船主が、近年、中国の造船所への発注を急増させている。2022年以降、日本船主による新規発注の3割から4割が中国の造船所に向けられており、これは2010年代後半の約1割から2割という水準から劇的な増加である 1。
国内顧客の離反は、日本の造船業が輸出市場だけでなく、国内市場においてさえも競争力を失っているという厳しい現実を突きつけている。これは、長年にわたり日本の海事産業の中核を成してきた「海事クラスター」と呼ばれる、船主、造船所、舶用機器メーカー間の強固な連携関係が崩壊し始めていることを意味する。価格、納期、あるいは技術といった総合的な価値提案において、国内造船所が顧客の要求に応えきれていないことの表れであり、業界にとって最大の警鐘と言える。
1.3. デフレ脱却後の逆風:高騰するコストの管理
国際競争力の低下に加え、国内経済のデフレ脱却に向けた動きが、造船業界の経営に新たな圧力を加えている。特に2021年以降、主要な原材料である鋼材価格の高騰は、建造コストを直接的に押し上げ、造船所の採算を著しく悪化させている 2。これに加えて、他の資機材費や外注加工費も上昇を続けており、コスト管理は喫緊の課題となっている。
国家的な支援を受ける競合相手に対して、すでに価格面で不利な立場にある日本の造船所にとって、このコストインフレは致命的である。コスト上昇分を船価に転嫁すれば、さらなる受注競争力の低下を招き、自社で吸収すれば利益を圧迫するというジレンマに陥っている。この厳しいコスト環境こそが、後の章で詳述するM&Aによる規模の追求や、生産性向上を目指した自動化投資を加速させる直接的な要因となっている。
表1:世界の造船市場シェア(国別、契約年ベース)
| 年 | 中国 (%) | 韓国 (%) | 日本 (%) | その他 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35 | 32 | 17 | 16 |
| 2020 | 49 | 32 | 11 | 8 |
| 2021 | 50 | 33 | 12 | 5 |
| 2022 | 49 | 31 | 16 | 4 |
| 2023 | 59 | 24 | 13 | 4 |
| 2024 | 54 | 28 | 8 | 10 |
注:データは各年の受注量シェアを示す。出典に基づき構成 1。
日本の造船業界は、高付加価値船の市場では韓国に、物量とコスト競争力では中国に後れを取るという「挟み撃ち」の状態にある。かつての得意分野であったバルカーやタンカーの建造数も減少しており 1、ハイエンド市場とマスマーケットの両方で足場を失いつつある。この戦略的な地盤沈下こそが、業界全体を事業再編や専門特化といった抜本的な変革へと駆り立てる根本的な動因なのである。
第2章 人材危機:生産能力を脅かす構造的課題
日本の造船業が直面するもう一つの深刻な課題は、人手不足である。これは単なる景気変動に伴う一時的な問題ではなく、少子高齢化という人口動態に根差した構造的な危機であり、受注の有無にかかわらず、船舶を建造する能力そのものを根底から揺るがしている。
2.1. 人手不足の構造:人口動態、技能承継、そして「3K」イメージ
造船業界の現場は、熟練技能者の高齢化が進行する一方で、若年層の業界離れが深刻化しており、長年培われてきた高度な技術の承継が危ぶまれている 2。地方に拠点を置く企業が多いことから、若者の都市部への流出も相まって、人材確保は極めて困難な状況にある 3。
この問題の深刻さは、具体的な数値にも表れている。2019年時点での有効求人倍率は、溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立てといった主要な職種のすべてで2.5倍を超えている。特に、塗装、鉄工、仕上げといった中核的な技能職においては4倍を超えており、企業が求人を出しても、応募者が全く集まらないという異常事態が常態化している 4。
国土交通省の推計によれば、業界全体の人材不足は2019年10月時点で約6,400人に達し、2023年には約2万人にまで拡大すると予測されていた 4。これは、生産計画を直接的に制約する要因であり、受注機会の損失にもつながりかねない。
こうした人材離れの背景には、「きつい、汚い、危険」を意味する「3K」という長年のイメージが根強く残っていることがある。特に、工業系の学校卒業者が大半を占めるという業界の特性から、女性の就労者が極端に少なく、人材の多様性が乏しい点も課題となっている 4。さらに、多くの企業で離職率が10%を超えるとの報告もあり、新規採用だけでなく、人材の定着も大きな問題となっている 3。
表2:主要な造船技能職における有効求人倍率(2019年度)
| 職種 | 有効求人倍率 |
|---|---|
| 塗装 | 4.0倍以上 |
| 鉄工 | 4.0倍以上 |
| 仕上げ | 4.0倍以上 |
| 溶接 | 2.5倍以上 |
| 機械加工 | 2.5倍以上 |
| 電気機器組立て | 2.5倍以上 |
出典に基づき構成 4。
2.2. 新たな労働力:特定技能制度への高まる依存
深刻な国内の人材不足を補うため、2019年に導入された在留資格「特定技能」制度は、造船業界にとって不可欠な生命線となっている 2。この制度は、一定の専門性・技能を持つ外国人材の受け入れを目的としており、造船・舶用工業分野では「特定技能1号」および、より高度な技能を持ち在留期間に上限のない「特定技能2号」の両方が対象となっている 4。
この制度は、技能試験に合格した即戦力となる人材を確保できるため、人手不足の解消に直結する仕組みとして大きな期待が寄せられている 3。しかし、その活用は計画通りには進んでいない。制度開始から5年間で1万3,000人の受け入れが目標とされているのに対し、2022年3月時点での受け入れ人数は1,971人にとどまっている 4。この遅れは、制度の複雑さや、受け入れ態勢の整備、他国や他産業との人材獲得競争など、多くの課題が残されていることを示唆している。
外国人労働者への依存は、単なる労働力の補充にとどまらず、新たな経営課題も生み出す。言語や文化の違いを乗り越え、円滑なコミュニケーションを図るためのサポート体制の構築や、日本人従業員との相互理解を促進する取り組みが不可欠となる 3。
2.3. 採用を超えて:定着、職場改善、多様性確保への戦略
人材危機に対応するため、業界は単に新たな人材を確保するだけでなく、既存の従業員が長く働き続けられる環境を整備し、これまで十分に活用されてこなかった層にアプローチする必要性を認識し始めている。
具体的な取り組みとして、各企業や地方自治体は、職場環境の改善に力を入れている。例えば、ロッカールームやトイレの洋式化、休憩室の整備といった基本的なインフラを近代化し、女性や若者にとってより魅力的な職場作りを進めるための補助金制度などが設けられている 5。
また、業界のイメージ刷新に向けた広報活動も活発化している。親子参加型の工場見学会や、学生向けの仕事体験プログラム、SNS(YouTubeなど)を活用した情報発信などを通じて、造船業が持つ「ものづくり」の魅力や、社会貢献度の高さをアピールする動きが広がっている 5。常石造船は、「徹底的にひと重視」を掲げ、従業員の処遇改善や子育て支援の強化を打ち出すなど、人材を最優先する経営姿勢を明確に示している 8。
これらの動きは、造船業界が、もはや他の造船所だけを競争相手とするのではなく、あらゆる産業と人材を奪い合う時代に入ったことを示している。従業員のウェルビーイングやキャリア形成、多様な働き方を重視する現代的な人事戦略へと、経営哲学そのものを転換せざるを得ない状況に直面しているのである。この人材不足こそが、不可逆的な変化を業界に強いる最大の圧力であり、結果として、次章以降で述べる技術投資や事業再編を加速させる最も強力な触媒となっている。
第3章 高コスト・円安環境下における財務パフォーマンス
日本の造船業界は、前述の厳しい競争環境と深刻な人手不足にもかかわらず、近年、収益性が改善するという一見矛盾した状況にある。本章では、この財務状況を分析し、その改善が脆弱な基盤の上に成り立っていることを明らかにする。
3.1. 収益性のパラドックス:円安が覆い隠す構造的課題
2024年度において、日本の主要造船会社9社の平均売上高営業利益率は8.3%に達し、世界全体の平均である5.5%を大きく上回った 9。この好調な収益性の最大の要因は、「円安効果」である 9。船舶の取引は主に米ドル建てで行われるため、円安が進行すると、ドル建ての売上を円換算した際に金額が膨らみ、会計上の利益が押し上げられる。
この収益改善には、世界的な新造船価格の高水準も寄与している 10。旺盛な需要を背景に、各社は潤沢な受注残を抱えており、これが短期的な財務の安定につながっている 10。
しかし、この円安に依存した収益構造は極めて脆弱である。これは、生産性やコスト競争力といった事業の本源的な強さに裏打ちされたものではなく、外部要因である為替レートの変動に大きく左右されるためだ。ひとたび円高に振れれば、この利益は瞬時に失われ、国際競争力の欠如という根本的な問題が再び露呈するリスクをはらんでいる。現在の好業績は、業界が抱える構造的な課題を一時的に覆い隠す「見せかけの好景気」である可能性を否定できない。
3.2. 主要企業における収益率と売上動向の分析
業界全体の収益性が改善する中でも、その内容は企業によって一様ではない。企業の戦略や事業ポートフォリオの違いが、収益構造に明確な差を生み出している。
例えば、名村造船所の2025年3月期の業績予想では、事業セグメントによって利益率に大きなばらつきが見られ、事業ごとの収益性の違いが浮き彫りになっている 11。
一方、川崎重工業の船舶海洋事業は、複数回にわたる業績の上方修正を発表している。その主な要因は、コスト競争力のある中国の合弁造船所からの持分法投資利益が大幅に改善したこと、そして、同社本体が手掛けるガス運搬船や潜水艦といった高付加価値船の採算が好転したことである 12。
これらの事例は、業界内での財務的な二極化が進んでいることを示唆している。川崎重工業のように、海外の低コスト生産拠点を活用できる企業や、防衛関連や特殊船など、技術的な優位性を持つ高収益ニッチ市場に特化している企業は、安定した収益を確保しやすい。対照的に、価格競争が激しい汎用的なバルクキャリア市場などで競争を続ける企業は、より厳しい収益環境に置かれていると考えられる。
3.3. 船価上昇と生産コスト高騰の相克
現在の造船業界の収益を理解する上で重要なのは、船価の上昇と生産コストの高騰という二つの相反する力のバランスである。世界的な需要増により新造船価格は高水準で推移しており、これは造船所の収益にとって追い風となっている 10。
しかし、その一方で、鋼材をはじめとする資機材価格の高騰が、生産コストを著しく押し上げている 2。造船業の収益は、契約時に船価が固定される一方で、実際の建造は数年後に行われるため、その間に発生するコスト変動のリスクを負うという特徴がある。
したがって、現在の高い利益は、コストが高騰する前に受注した案件の成果が反映されている可能性がある。今後、高騰したコスト環境下で建造が進む案件が増えるにつれて、利益率は圧迫されるリスクがある。各社が抱える潤沢な受注残 10 は、収益の安定性を保証する一方で、将来のコスト上昇リスクを内包した「両刃の剣」とも言える。
この状況は、現在の好業績が持続可能ではない可能性を示唆している。むしろ、この円安によってもたらされた一時的な利益は、業界が構造改革を断行するための、またとない「時間と資金」を提供していると捉えるべきである。この好機を活かし、自動化や研究開発といった未来への投資に資金を振り向けられるかどうかが、企業の長期的な存続を左右する重要な分岐点となる。
第4章 業界地図の再編:M&Aと戦略的再編
第1章から第3章で概説した厳しい外部環境と内部課題に対応するため、日本の造船業界では、生き残りをかけた大規模な事業再編と経営統合が加速している。その動きは、規模の追求を目指す「水平統合」と、特定の分野に経営資源を集中させる「専門特化」という二つの大きな潮流に集約される。
4.1. ナショナルチャンピオンの誕生:今治造船とJMUの提携
近年の業界再編において最も象徴的な動きは、国内最大手の今治造船と、大手の一角であるジャパンマリンユナイテッド(JMU)との間の資本業務提携である 2。
両社は2021年、LNG船を除く一般商船の設計・販売を共同で行う新会社「日本シップヤード(NSY)」を設立した。この提携により、国内シェア約5割、世界シェアでも約12%を占める巨大な企業グループが誕生した 2。さらに最近では、今治造船がJMUを子会社化する動きを見せており、統合を一層加速させている 15。
この提携の明確な狙いは、設計・営業部門の統合によるスケールメリットを最大限に引き出し、巨大な中国・韓国の造船大手に対抗できる競争力を確保することにある 2。個々の中規模な企業が単独で戦うのではなく、国内の資源を結集して一つの強力な「ナショナルチャンピオン」を形成するという戦略である。これは、もはや日本の造船業が、かつてのような多数の企業が乱立する状態ではグローバル競争に勝ち残れないという厳しい現実認識の表れである。
4.2. 戦略的転換:三菱重工業の防衛・高付加価値船への集中
三菱重工業(MHI)は、今治・JMU連合とは異なるアプローチを選択した。それは、不得意な分野から戦略的に撤退し、自社の強みが活かせる分野に経営資源を集中させる「選択と集中」である。
MHIは、大型船を建造していた長崎造船所の香焼工場を大島造船所に売却し、価格競争の激しい大型商船の建造事業から事実上撤退した 16。その一方で、三井E&S造船から艦艇事業を買収し、防衛分野を大幅に強化している 2。
この戦略の背景には、中国勢との価格競争では勝ち目がないと判断し、代わりに防衛省向けの艦艇や特殊船、海洋エンジニアリングといった、高い技術力と長期的な顧客関係が求められる高収益分野で確固たる地位を築くという明確な意図がある 2。これは、価値連鎖(バリューチェーン)を駆け上がり、技術力という「堀」で守られた、収益性の高い事業領域に特化する戦略と言える。
4.3. 中堅企業の統合:常石造船と三井E&Sの連携に見る論理
中堅造船所の間でも、競争力強化を目的とした再編が進んでいる。その代表例が、常石造船による三井E&S造船の連結子会社化である 2。
この統合は、両社の強みを補完し合うことを目的としている。常石造船が持つコスト管理能力と高い生産効率に、三井E&S造船が持つ先進的な設計技術や研究開発力を組み合わせることで、より競争力のある企業体を目指している 2。拠点の再配置や生産工程の標準化を進めることで、コスト削減と効率化を実現し、受注競争で優位に立つことが狙いである。
これは、異なる能力を持つ企業が連携することで、単独では成し得なかった「1+1=3」の効果を生み出そうとする、相補的な統合戦略の典型例である。
表3:日本の造船業界における主要なM&A・提携(2020年以降)
| 時期 | 主導/買収企業 | 対象/提携企業 | 取引の概要 | 戦略的意図 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年1月 | 今治造船 | ジャパンマリンユナイテッド (JMU) | 共同出資会社「日本シップヤード(NSY)」設立。その後、JMUを子会社化。 | 設計・営業部門の統合による規模の経済を追求し、中韓大手に対抗。 |
| 2021年3月 | 三菱重工業 | 三井E&S造船 | 三井E&Sの艦艇事業を買収。 | 防衛事業を強化し、高付加価値分野へ経営資源を集中。 |
| 2022年10月 | 常石造船 | 三井E&S造船 | 三井E&Sの株式を追加取得し、連結子会社化。 | 常石のコスト競争力と三井の技術力を融合し、総合的な競争力を強化。 |
| 2022年 | 三菱重工業 | 大島造船所 | 長崎造船所香焼工場を大島造船所へ売却。 | 価格競争の激しい大型商船事業から事実上撤退。 |
出典に基づき構成 2。
4.4. 再編の主題分析:規模か、専門特化か
これらの事例を総合すると、日本の造船業界の再編は、「規模の追求」と「専門特化」という二つの軸に沿って進んでいることがわかる。
- 規模の追求:今治・JMU連合は、国内のリソースを統合して巨大化し、コスト競争力と交渉力を高める純粋なスケール戦略である 2。
- 専門特化:三菱重工業は、規模よりも技術的優位性が重要な高収益ニッチ市場での支配を目指す、純粋な専門特化戦略である 2。
- ハイブリッド:常石・三井E&Sの統合は、規模に裏打ちされたコスト効率と、専門的な技術力の両方を追求するハイブリッド戦略と位置づけられる 2。
これらの再編は、単に生産能力を統合するだけでなく、業界全体で減少しつつある貴重な設計者やエンジニアといった人的資本を集約するという側面も持つ。特に、LNGやアンモニア燃料船といった次世代環境対応船の開発には、莫大な研究開発費と高度な専門知識が必要となる 2。個々の企業が単独でこの負担に耐えることは困難であり、M&Aは、未来の船舶を開発するために必要な技術者と研究開発予算の「クリティカルマス」を確保するための、極めて合理的な手段なのである。かつてのように、全ての企業があらゆる船種を建造しようとした時代は終わり、各社がそれぞれの強みを活かせる分野に特化し、必要に応じて連携する、より効率的な協業ネットワークへと業界構造そのものが変容しつつある。
第5章 生存をかけた技術革新:自動化とデジタル化の推進
深刻な人手不足と熾烈な国際競争という二重の圧力に直面する日本の造船業界にとって、技術革新はもはや単なる効率化の手段ではなく、企業の存続そのものを左右する生命線となっている。本章では、労働集約的な建造プロセスからの脱却を目指す、自動化とデジタル化への取り組みを詳述する。
5.1. ロボットの台頭:溶接、塗装、搬送工程の自動化
伝統的に、造船は規格化が難しい巨大な構造物を扱うため、自動化の導入が遅れてきた分野である 18。しかし、人手不足が限界に達した今、ロボット技術の導入が不可避となっている。
- 溶接工程:川崎重工業は、自社がロボットメーカーでもある強みを活かし、船殻ブロックの溶接などに大型のアーク溶接システムを導入してきた実績がある 18。大島造船所では、モバイル溶接ロボットを導入し、生産性の向上と品質の安定化を実現している 19。これらのロボットは、複雑な形状であってもAIが継手をリアルタイムで解析し、高品質な溶接を自動で行うことができる 19。
- 3K作業の代替:特に人手不足が深刻で、労働環境が過酷な「3K」作業の自動化が重点的に進められている。溶接後のバリを除去する研磨・バリ取り作業や 18、狭隘な区画での溶接作業 20 などに特化したロボットが導入され始めている。
- マテリアルハンドリング:ジャパンマリンユナイテッド(JMU)では、LNG船の建造において、防熱パネルの搬送工程にロボットを導入し、重量物の取り扱いを自動化している 21。
これらの取り組みは、不足する労働力を直接的に補うだけでなく、危険で過酷な作業から人間を解放することで職場環境を改善し、若手人材の採用や定着にも貢献するという二重の効果をもたらす。
5.2. デジタルシップヤード:設計AI、生産IoT、デジタルツインの活用
物理的なロボットの導入と並行して、ソフトウェアとデータを活用した建造プロセス全体のデジタル変革も進行している。
設計のAI活用:船舶設計において、AIは燃費性能や環境性能を最適化するために活用されている。AIは、人間では不可能な数千もの設計パターンをシミュレーションし、流体力学的に最も効率的な船体形状を提案することができる 19。これは、環境規制の強化に対応した、より複雑な次世代エコシップを開発する上で不可欠な技術である。
生産のデジタル化:
- デジタルツイン:造船所全体の仮想モデル(デジタルツイン)をコンピュータ上に構築し、実際の建造に着手する前に、生産計画や物流、作業工程の全てをシミュレーションする取り組みが進められている。これにより、事前にボトルネックを特定し、手戻りや遅延を最小限に抑えることが可能になる 23。
- IoTの活用:工場内の機械や部材に設置されたセンサーからリアルタイムでデータを収集(IoT)し、AIが分析することで、生産の進捗状況を正確に把握し、サプライチェーン全体を最適化する。数万点にも及ぶ部品の管理をデジタル化することで、建造プロセス全体の効率が飛躍的に向上する 24。
技能承継への応用:AIは、退職していく熟練技能者の「暗黙知」を形式知化し、デジタルデータとして継承する手段としても期待されている。過去の設計図書や作業ノウハウをAIに学習させ、若手技術者が対話形式で質問できる知識ベースを構築することで、技能承継の危機を乗り越えようという試みも始まっている 25。
5.3. 技術革新のケーススタディ:「i-Factory」と「J-Smart Ship」
業界をリードする企業は、個別の技術導入にとどまらず、経営戦略の中核にデジタル化を据えた包括的な取り組みを進めている。
- 今治造船の「i-Factory」構想:AIとデータを活用して生産管理や品質検査を高度化し、工場全体を連携させたインテリジェントな生産システムを構築することを目指している 19。
- JMUの「J-Smart Ship」:AIを搭載した「スマートシップ」の開発に注力している。航行中の最適航路の選定、機関の故障予知保全、燃費効率の最大化などをAIが支援することで、船舶の運航そのものを高度化する 19。
- 常石造船の業務自動化:設計・建造だけでなく、間接業務の効率化にも着目している。RPA(Robotic Process Automation)ツールを導入し、「デジタルワーカー」と呼ばれるソフトウェアロボットが定型的な事務作業を自動化することで、年間7,000時間もの労働時間を削減し、その分の人的リソースをより付加価値の高い業務へ再配置することを目指している 27。
これらの事例が示すのは、日本の造船業が目指す未来像である。それは、単に人手を機械に置き換えるだけでなく、設計から生産、運航、保守に至るまでの全てのプロセスをデータで繋ぎ、ビジネスモデルそのものを変革しようとする野心的な挑戦である。このデジタル変革を主導できるかどうかが、企業間に新たな競争力格差、すなわち「デジタル・デバイド」を生み出し、業界の将来の勢力図を塗り替えることになるだろう。その最終的な目標は、労働集約型産業から、少数の高度なスキルを持つ人材が技術を駆使して高い付加価値を生み出す「知識集約型産業」への転換に他ならない。
第6章 財務的苦境との闘い:業界における倒産動向の分析
業界全体が変革を迫られる中、すべての企業がその変化に対応できるわけではない。本章では、ユーザーの関心事である倒産動向に焦点を当て、業界が直面する財務的なストレスと、特に適応力に欠ける企業が直面する淘汰の現実を分析する。
6.1. マクロトレンド:「人手不足倒産」の増加
造船業界固有の動向を分析する前に、日本経済全体に広がる傾向を理解することが重要である。近年、全国的に「人手不足」を直接的な原因とする企業の倒産が急増しており、2025年度上半期には214件と過去最多を記録した 28。2024年通年の倒産件数も、過去10年で最多となるペースで推移している 29。
このマクロトレンドは、極めて深刻な人手不足に悩む造船業界にとって、対岸の火事ではない。むしろ、業界がこの種の倒産に対して特に脆弱であることを示唆している。企業が経営破綻に至る原因が、もはや受注の不足ではなく、受注した仕事を採算の取れる形で遂行するための人材を確保できないという「実行能力の欠如」へとシフトしているのである。
6.2. ケーススタディ:神田造船所の経営破綻が示すもの
近年の造船業界における最も重大な経営破綻事例は、中堅の神田造船所(事業再編後は株式会社クレサービス)のケースである。同社は2024年8月、負債総額109億円超を抱え、特別清算の開始決定を受けた 30。
世界的に海運市況が活況を呈し、新造船需要が旺盛な中での、歴史ある中堅造船所の倒産は、業界に大きな衝撃を与えた。この事例は、たとえ市場に需要があっても、コスト競争力や生産効率といった根本的な経営体力がなければ生き残れないという厳しい現実を浮き彫りにしている。神田造船所の破綻は、同様の課題を抱える他の中堅企業にとって、自社の経営モデルを見直すことを迫る警鐘となった。
このほかにも、旧南日本造船が清算に至ったケース(事業そのものは今治造船グループ企業が継承)など、経営体力の弱い企業が淘汰されたり、より強力なグループに吸収されたりするパターンが散見される 33。
6.3. 企業規模別に見た財務的耐性の評価
業界内の財務状況は一様ではなく、特に中堅・中小企業は厳しい状況に置かれている。2020年度の調査データによれば、造船業関連企業の27.9%が赤字経営であり、そのうちの約半数は2期連続の赤字であった 28。
近年の円安による収益改善は、これらの企業の一部に一時的な猶予を与えたかもしれないが、その根本的な脆弱性が解消されたわけではない。最もリスクが高いのは、大規模な技術投資を行う資本力も、ニッチ市場で柔軟に立ち回る機動力も持たない「中途半半端な規模」の企業群であると考えられる。
これらの倒産事例は、市場の失敗(需要の欠如)ではなく、経営の失敗(高コスト・人手不足環境下で利益を上げて建造する能力の欠如)を反映している。旺盛な需要があるにもかかわらず企業が倒産するという事実は、第2章で詳述した人手不足問題が、いかに深刻で直接的な経営リスクであるかを物語っている。そして、こうした弱い企業の淘汰は、結果として業界の再編をさらに加速させる。経営不振に陥った企業は、今治・JMU連合や常石グループのような体力のある大手にとって格好の買収対象となり、市場メカニズムを通じて、資源がより効率的な企業へと集中していくプロセスの一環と見なすことができる。
第7章 基盤の再構築:海事サプライチェーンの変革
造船所の競争力は、単独の企業の努力だけで決まるものではない。数万点に及ぶ部品や機器を供給するサプライヤー群、すなわちサプライチェーン全体の効率性と技術力が、最終的な建造コストと納期を大きく左右する。本章では、造船所を取り巻くエコシステム全体の変革の動きを分析する。
7.1. 「部品」から「システム」へ:統合ソリューションへのシフト
船舶の技術が高度化・複雑化するにつれて、サプライチェーンのあり方も大きく変化している。自動運航システムや、LNG・アンモニアといった新燃料に対応する推進システムなど、現代の船舶は多数のコンポーネントがソフトウェアで緊密に連携する「動くシステム」となっている。
これに伴い、舶用機器メーカーに求められる役割も、単にポンプやモーターといった個別の「部品」を供給することから、関連する機器群をあらかじめ統合し、機能全体をパッケージ化した「システム」として提供する形態へとシフトしつつある 34。例えば、燃料供給に関連するポンプ、バルブ、制御装置などを一つのモジュールとして納入する形である。
この変化は、造船所とサプライヤー間のより緊密な連携と、設計段階からのデータ共有を不可欠なものにする。一方で、高度なシステムインテグレーション能力を持たない中小のサプライヤーにとっては大きな挑戦となり、技術力を持つ大手サプライヤーへの寡占化が進む可能性がある。
7.2. 国家戦略:海事クラスター強化に向けた政府の取り組み
日本政府(国土交通省)も、個々の造船所の支援にとどまらず、海運、造船、舶用工業を一体とした「海事クラスター」全体の国際競争力を強化する方針を明確に打ち出している 14。これは、一国の造船業の強さが、それを支えるサプライチェーン全体の強さに依存するという認識に基づいている。
政府は2026年度予算の概算要求において、「造船の強靭なサプライチェーン構築」を重点項目として掲げた 14。具体的な施策としては、次世代燃料船などの環境対応技術や、舶用機器のデジタル化(DX)に関する研究開発への支援、サプライチェーン全体でのデータ連携や業務プロセスの標準化の推進などが挙げられる 14。
これらの政策の背景には、国家ぐるみで巨大なエコシステムを形成している中国や韓国に対抗するためには、日本も官民一体となって国内のサプライチェーンを高度化し、海事産業全体の生産性を向上させる必要があるという強い危機感がある。国土交通省は、サプライチェーンの最適化などを通じて、2025年までに日本の造船業の生産性を2割向上させるという具体的な目標を掲げている 34。
このデジタル化されたサプライチェーンの構築は、競争上の新たな優位性を生み出す。設計から建造までのデータを一貫して連携させ、部品表(BOM)を標準化・再利用することで、リードタイムの短縮、在庫コストの削減、建造工程の精度向上といった多大な効果が期待できる 24。逆に、こうしたデジタルサプライチェーンの構築に乗り遅れた造船所は、非効率な旧来型のプロセスに縛られ、コストとスピードの両面で大きなハンディキャップを背負うことになるだろう。
第8章 戦略的展望と提言
本レポートで分析してきたように、日本の造船業界は、円安による一時的な収益改善という好機と、構造的な競争力低下および深刻な人手不足という存亡の危機が交差する、重大な転換点に立っている。成功は決して約束されておらず、業界の未来は今後の戦略的な意思決定にかかっている。
8.1. 総括:収益性、市場シェア、人的資本の相互作用
日本の造船業が直面している課題は、複雑に絡み合っている。円安がもたらした現在の利益は、 declining market share と a critical lack of human capital という根深い構造的問題を解決するための、貴重な「軍資金」と「時間」を提供している。この好機を活かして、事業再編、技術投資、人材改革を断行し、高コスト・人手不足時代に適応した新たな事業モデルを構築できるかどうかが、今後の業界の趨勢を決定づける。
8.2. 将来シナリオ:持続可能な競争力への道筋
考えられる将来像は、以下の三つのシナリオに大別される。
- シナリオ1:変革の成功
業界は現在の好機を最大限に活用する。M&Aによる再編が効率的なスケールメリットや専門性を生み出し、自動化・デジタル化への投資が人手不足のギャップを埋めることに成功する。そして、環境対応船や防衛分野など、高付加価値なニッチ市場での地位を確立する。この結果、日本の造船業は、規模では中韓に及ばないものの、高い技術力と収益性を誇る、筋肉質で競争力のあるプレーヤーとして生き残る。 - シナリオ2:漸進的な対応(Muddling Through)
業界は部分的な改善は進めるものの、痛みを伴う抜本的な変革を先送りする。収益性を円安に依存する体質から抜け出せず、技術力や生産性における中韓との差は埋まらない。業界は存続するものの、そのプレゼンスはさらに低下し、国際市場での影響力を失った、脆弱な存在となる。 - シナリオ3:構造的衰退
変革が完了する前に円高が再来し、収益基盤が崩壊する。人手不足はさらに深刻化し、生産能力の維持が困難となり、倒産や事業撤退が相次ぐ。日本の造船業は、国内の防衛需要などに細々と応えるだけのマイナーな存在へと縮小し、国際市場からは事実上姿を消す。
8.3. ステークホルダーへの提言
最良のシナリオである「変革の成功」を実現するため、各ステークホルダーは以下の行動を迅速に実行することが求められる。
企業経営者に対して:
- 積極的な再投資:現在の利益を短期的な株主還元に用いるのではなく、工場の自動化、設計・生産プロセスのデジタル化、そして次世代燃料技術の研究開発といった、未来の競争力を生み出す分野へ大胆に再投資すべきである。
- M&Aの加速:規模の経済を追求するか、あるいは特定の高付加価値分野に特化するかの戦略を明確にし、その実現に向けたM&Aや事業再編をためらわずに実行すべきである。中途半端な立ち位置が最も危険である。
- 人事戦略の抜本的改革:賃金や休暇といった労働条件の改善はもちろんのこと、多様な人材が働きやすい職場環境の整備、明確なキャリアパスの提示、そして業界のイメージ刷新に全力を挙げるべきである。人材はもはや「コスト」ではなく、競争力の源泉となる最も重要な「資本」である。
政策立案者に対して:
- 外国人材受け入れの円滑化:当面の人手不足を緩和するため、現場のニーズに即した形で「特定技能」ビザ制度の運用を改善し、手続きの迅速化・簡素化を図るべきである。
- 海事クラスター全体への支援強化:造船所だけでなく、舶用機器メーカーも含めたサプライチェーン全体のデジタル化と、環境対応技術に関する共同研究開発(R&D)への支援を拡充すべきである。
- 公的需要の戦略的活用:防衛省や海上保安庁が発注する艦船などを通じて、国内造船所が次世代技術を開発・実装する機会を創出し、その技術が民間船舶へ波及することを後押しすべきである。
引用文献
- 船舶産業を取り巻く現状 – 国土交通省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001895997.pdf
- 造船のM&A動向は?事例や成功のポイントを解説【2025年】 | M&A …, 11月 2, 2025にアクセス、 https://cinc-capital.co.jp/column/industry/shipbuilding-ma
- 造船業の未来を支える特定技能外国人雇用とは?人手不足を乗り越えるための採用ガイド, 11月 2, 2025にアクセス、 https://tokuty.jp/blog/shipbuilding_labor_shortage/
- 造船・舶用工業における人手不足の現状と外国人雇用の概要 | 特定 …, 11月 2, 2025にアクセス、 https://samurai-law.com/tokutei/sub01-06/
- 人材の確保・育成に向けた取組 – 国土交通省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001734700.pdf
- 【人手不足 陸・海・空 荒波の先】 (4)造船の協力会社も危機。構造改革に翻弄 – 高甲實業有限公司, 11月 2, 2025にアクセス、 https://hotservice.com.tw/ja/%E3%80%90%E4%BA%BA%E6%89%8B%E4%B8%8D%E8%B6%B3-%E9%99%B8%E3%83%BB%E6%B5%B7%E3%83%BB%E7%A9%BA-%E8%8D%92%E6%B3%A2%E3%81%AE%E5%85%88%E3%80%91-%EF%BC%884%EF%BC%89%E9%80%A0%E8%88%B9%E3%81%AE%E5%8D%94/
- 造船業・海洋産業における人材確保・育成のための具体的施策(例), 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mlit.go.jp/common/001097536.pdf
- 常石造船、グループ会社再編のお知らせ | ツネイシホールディングス株式会社のプレスリリース, 11月 2, 2025にアクセス、 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000063.000115319.html
- 世界造船業の利益率5.5%に改善24年実績を本紙試算、日本は8%で …, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.kaijipress.com/news/shipbuilding/2025/08/195146/
- 欧州造船業概況調査JSCアニュアル調査シリーズ2024年度 – 日本船舶技術研究協会, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.jstra.jp/PDF/report2_2024.pdf
- 2025年3月期 – 決算説明資料, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.namura.co.jp/ja/ir/materials/main/00/teaserItems1/02/linkList/0/link/202506.01.pdf
- 中期経営計画「中計2019」 (2019〜2021年度) 船舶海洋カンパニー, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.khi.co.jp/ir/pdf/etc_191001-5j.pdf
- 通期事業益260億円に上方修正川崎重工のエネ・船舶部門、造船の業績改善で, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.kaijipress.com/news/shipbuilding/2024/02/181866/
- 国土交通省、造船サプライチェーン強化で海事産業支援へ – HPS Trade Co.,Ltd(日本語サイト), 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.hps-trade.co.th/ja/column/logistics-radio/p5940/
- 「造船ニッポン」復活へ!今治造船のジャパンマリンユナイテッド子会社化で中韓へ反撃態勢、26年から需要沸騰、米から協力要請と好条件整う | Diamond Premium News | ダイヤモンド・オンライン, 11月 2, 2025にアクセス、 https://diamond.jp/articles/-/368081
- 【有名企業5選】造船業界は日本の貿易を支える存在! 展望と課題 – キャリアパークエージェント, 11月 2, 2025にアクセス、 https://careerpark-agent.jp/column/81501
- 造船のM&A動向とは?業界課題を解決する再編戦略と最新事例まとめ – アーク・パートナーズ, 11月 2, 2025にアクセス、 https://archpartners-manda.com/%E9%80%A0%E8%88%B9%E3%81%AEma%E5%8B%95%E5%90%91%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%E6%A5%AD%E7%95%8C%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E3%82%92%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E3%81%99%E3%82%8B%E5%86%8D%E7%B7%A8%E6%88%A6%E7%95%A5/
- 船舶 | 川崎重工の産業用ロボット – Kawasaki Robotics, 11月 2, 2025にアクセス、 https://kawasakirobotics.com/jp/industries/shipbuilding/
- AI×造船で業務効率化!活用事例や未来展望を詳しく解説 | AI Front …, 11月 2, 2025にアクセス、 https://ai-front-trend.jp/shipbuilding-ai/
- FAIRINO溶接導入事例 鋼構造・車体・船体の自動化成功例 – iCOM技研株式会社, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.icom-giken.com/blog/frweldpr/
- ロボット導入実証事業, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.robo-navi.com/document/hb26new.pdf
- 造船業の未来を拓くDX・AI活用とは?映像制作会社が提案する採用・ブランディング戦略, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.synapps.co.jp/post/shipbuilding
- 次世代の造船設計システム構想 – 日本船舶海洋工学会, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.jasnaoe.or.jp/lecture/symp/e.200909/resume06.pdf
- デジタル技術の活用の方向性 – 国土交通省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001708012.pdf
- 成AI時代の船舶設計 – 変わらないもの、変わるもの – – 大阪大学 船舶海洋工学コース, 11月 2, 2025にアクセス、 http://www.naoe.eng.osaka-u.ac.jp/naoe/naoe10/doc/4_%E8%A8%AD%E8%A8%88_%E4%B8%80%E3%83%8E%E7%80%AC%E5%85%88%E7%94%9F.pdf
- 《シリーズ》海事産業とAI設計や計画など工数削減に期待造船所、着手小局でもコスト減に直結, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.kaijipress.com/news/shipbuilding/2025/09/195653/
- 企業動向 | プレスリリース | ニュース – 常石グループ, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tsuneishi-g.jp/news/press/corporate-trends/
- 国内造船、2020年度は約6割が減収 4割強が減益に 売上高合計は前年度比3%減で2兆円を割り込む | 株式会社帝国データバンクのプレスリリース – PR TIMES, 11月 2, 2025にアクセス、 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000387.000043465.html
- 2024 年報 – 帝国データバンク, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tdb.co.jp/resource/files/assets/d4b8e8ee91d1489c9a2abd23a4bb5219/787079408f28464f8eeef6f74c8bccd5/%E5%85%A8%E5%9B%BD%E4%BC%81%E6%A5%AD%E5%80%92%E7%94%A3%E9%9B%86%E8%A8%882024%E5%B9%B4%E5%A0%B1%E3%83%BB12%E6%9C%88%E5%A0%B1.pdf
- 8月度 | 2024年(令和6年) | こうして倒産した | 倒産・注目企業情報 | 東京商工リサーチ, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tsr-net.co.jp/news/process/2024/8/
- 株式会社クレサービス|倒産速報 – 帝国データバンク, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tdb.co.jp/report/bankruptcy/flash/5065/
- TSR速報 | 倒産・注目企業情報 – 東京商工リサーチ, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tsr-net.co.jp/news/tsr/index.html?area=chugoku
- マーレ株式会社(旧:南日本造船株式会社)|倒産速報 – 帝国データバンク, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tdb.co.jp/report/bankruptcy/flash/4484/
- 海事:造船業の国際競争力の強化 – 国土交通省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_tk5_000014.html
- ⑥サプライチェーン全体の最適化等の実現に向けた戦略の検討等 〜欧州・韓国造船所の取組みとその背景 – 日本船舶技術研究協会, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.jstra.jp/seminar/PDF/%E8%B3%87%E6%96%991-6_%E5%9B%BD%E4%BA%A4%E7%9C%81SC%E8%AA%BF%E6%9F%BB_%E6%88%90%E6%9E%9C%E5%A0%B1%E5%91%8A%E2%91%A5%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E5%85%A8%E4%BD%93%E3%81%AE%E6%9C%80%E9%81%A9%E5%8C%96%E7%AD%89%E3%81%AE%E5%AE%9F%E7%8F%BE%E3%81%AB%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%9F%E6%88%A6%E7%95%A5%E3%81%AE%E6%A4%9C%E8%A8%8E%E7%AD%89.pdf