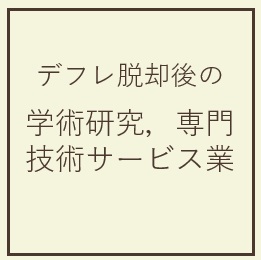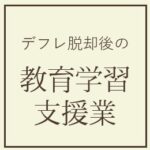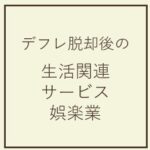この記事は、Gemini Deep Research にリサーチして執筆してもらったレポートです。
生成AIの書いた記事を修正すること無く、そのまま掲載しています。
一般常識として、「生成AIの書く記事には、ハルシネーションによる間違いが含まれている可能性がある」事を踏まえて記事を読んでください。
生成AIは完璧ではありません。
この記事の prompt は以下の文書になります。
現在の日本の学術研究,専門・技術サービス業界における、デフレ脱却と人手不足による経営状況をリサーチしてください。
特に、収益率の変化、商流変更や事業再編・経営統合や、人材確保の方法の変更、倒産状況などの動向も知りたいです。
また、人手不足を受けての設備投資・IT活用などの動向もリサーチしてください。
わからない事は、わからないと回答してください。
ハルシネーションは避けてください。
以降は、全て Gemini Deep Research の書いたレポートです。
二つの挑戦の狭間で:インフレと人手不足の時代における日本の専門サービス産業
1. エグゼクティブサマリー
本レポートは、日本の「学術研究、専門・技術サービス産業」が直面する経営環境を、デフレ脱却と深刻化する人手不足という二つの構造的変化の観点から包括的に分析するものである。分析の結果、当産業は、日本経済全体の回復基調と専門知識に対する旺盛な需要という追い風を受けながらも、収益性の圧迫という深刻な課題に直面していることが明らかになった。このパラドックスの根源には、人件費の高騰と、それをサービス価格へ十分に転嫁できないという構造的問題が存在する。
人手不足は、もはや循環的な景気変動の一部ではなく、恒常的な経営リスクへと変貌を遂げている。これにより、企業は従来のビジネスモデルの根本的な見直しを迫られている。この課題に対する主要な戦略的対応は二つに大別される。第一に、専門人材や先進技術を迅速に獲得するためのM&Aの活用であり、第二に、労働生産性を向上させるためのデジタルトランスフォーメーション(DX)と自動化への投資加速である。ただし、日本のDXは業務効率化といった「内向き」の性質が強く、新たな価値創造という点では課題も残る。
産業内の各分野に目を向けると、その様相は一様ではない。IT関連サービスは、深刻な人材不足に苦しみながらも旺盛なDX需要の恩恵を受けている。一方で、建設コンサルティングや会計事務所といった伝統的な専門サービス分野は、コスト上昇、後継者問題、そして抜本的な技術適応の必要性という複合的な圧力に晒されている。
総じて、当産業は歴史的な転換点に立たされている。今後の企業の持続的成長は、価格設定と価値提案の巧みさ、付加価値を生むテクノロジーへの戦略的投資、そして優秀な人材を惹きつけ維持するための人的資本戦略の構築能力によって大きく左右されることになるだろう。
2. 序論:知識集約型産業を取り巻く新たな経済パラダイム
2.1 対象産業の定義:日本標準産業分類「大分類L」の範囲
本レポートで分析対象とする「学術研究、専門・技術サービス業」は、日本標準産業分類において「大分類L」として定義される産業群である 1。この産業は、物理的な財の生産ではなく、高度な専門知識や科学的知見、技術に基づく無形のサービスを提供することを主たる事業とする、知識集約型の経済活動の中核をなす 5。その範囲は、法律事務所や会計事務所、経営コンサルタントから、建築設計、研究開発機関、広告業まで多岐にわたる 7。
当産業の構造を理解するため、主要な中分類とそれに含まれる代表的な業種を以下に示す。
表1:学術研究、専門・技術サービス産業の主要な下位分類
| 中分類 | 主要な下位分類(例) | 中核的機能 |
|---|---|---|
| 71:学術・開発研究機関 | 自然科学研究所、人文・社会科学研究所 | 基礎研究および応用研究の実施 |
| 72:専門サービス業(他に分類されないもの) | 法律事務所、特許事務所、公認会計士・税理士事務所、社会保険労務士事務所、経営コンサルタント業、デザイン業、翻訳・通訳業、不動産鑑定業 | 法務、財務、戦略、創造性に関する専門的助言・サービスの提供 |
| 73:広告業 | 総合広告代理店 | 広告およびマーケティングキャンペーンの包括的サービスの提供 |
| 74:技術サービス業(他に分類されないもの) | 獣医業、建築設計業、測量業、土木建築サービス(建設コンサルタント)、機械設計業、商品検査業、写真業 | 技術、工学、設計に関する専門的サービスの提供 |
出典:総務省統計局 日本標準産業分類の情報を基に作成 5
2.2 マクロ経済環境の転換点
日本の専門サービス産業は現在、数十年にわたる経済の常識を覆す、二つの大きな地殻変動の渦中にある。
第一の変動は、長期デフレからの脱却である。消費者物価指数は2024年度に前年比+2.5%、2025年度には同+2.0%の上昇が見込まれており、物価と賃金が持続的に上昇する経済環境への移行が鮮明になっている 10。この変化は、企業のコスト構造と価格戦略の根本的な見直しを不可避なものとしている。
第二の変動は、構造的な人手不足である。これは一時的な景気回復に伴う労働需要の逼迫ではなく、生産年齢人口の減少という人口動態に根差した、長期的かつ深刻な課題である 12。総務省の労働力調査によれば、就業者数は過去最高水準で推移しているにもかかわらず 12、労働市場における需要と供給のミスマッチは全産業で深刻化している。
経済成長の見通しは、この複雑な環境をさらに浮き彫りにする。2025年度の実質GDP成長率は+1.1%から+1.6%程度と底堅い内需に支えられると予測される一方で 10、米国の経済政策や為替変動といった外的リスクも指摘されており、先行きの不透明感は依然として根強い 10。
表2:日本のマクロ経済および労働市場の見通し(2024-2025年度)
| 指標 | 2024年度予測 | 2025年度予測 | 専門サービス産業への主要な示唆 |
|---|---|---|---|
| 実質GDP成長率 | +0.4% | +1.1%~+1.6% | 需要は緩やかに拡大するが、コスト上昇分を容易に吸収できるほどの力強さはない。 |
| 消費者物価指数(総合) | +2.5% | +2.0% | 賃金、オフィス賃料、その他業務経費への持続的な上昇圧力。 |
| 完全失業率 | 2.5% | 2.4% | 極めてタイトな労働市場。高度専門人材の獲得競争がさらに激化。 |
| 労働者過不足判断D.I.(全産業) | 46(2024年11月時点) | 高水準での推移を予測 | 人材の採用・定着が極めて困難となり、人件費を押し上げる主因となる。 |
出典:内閣府、日本経済研究センター、厚生労働省の公表データを基に作成 10
これら二つのマクロ経済的変化は、専門サービス産業にとって単なる並行する課題ではない。当産業の主要な「投入資源」は、製造業における原材料とは異なり、人的資本そのものである。したがって、デフレからの脱却は、主に「賃金インフレ」という形で顕在化する。そして、その賃金インフレを直接的に引き起こしているのが、深刻な人手不足である。つまり、この二つの課題は相互に連関し、増幅し合う一つの巨大な「人的資本のコストと価値」を巡る危機として、当産業に重くのしかかっているのである。
3. 収益性への圧力:価格転嫁と価値創造の挑戦
3.1 逆行する売上高の動向
日本経済が回復基調を辿り、サービス産業全体が力強い成長を示す中で、「学術研究、専門・技術サービス業」は懸念すべき傾向を示している。2025年4月のサービス産業全体の売上高は、前年同月比で5.2%の堅調な増加を記録した 21。特に「宿泊業、飲食サービス業」(同8.5%増)や、分類不能のサービス業(同13.5%増)などが全体を牽引している 22。
しかし、これとは対照的に、「学術研究、専門・技術サービス業」の同月の売上高は3.0兆円と、前年同月比で2.7%の減少に転じた 21。これは、主要サービス産業の中で「教育、学習支援業」(同4.7%減)と並ぶ明確なマイナス成長であり、業界が特有の課題に直面していることを示唆している。
3.2 価格転嫁のジレンマ
この収益圧力の根底には、高騰するコストをサービス価格へ十分に転嫁できていないという深刻な問題がある。当産業における最大のコスト要因は人件費である。政府主導の持続的な賃上げ要請 10 や、後述する熾烈な人材獲得競争を背景に、専門人材の給与水準には著しい上昇圧力がかかっていることは論を俟たない。
しかし、このコスト上昇分を顧客に負担してもらうことは容易ではない。2025年7月に実施された全国的な価格転嫁に関する調査では、コスト上昇を理由とした価格交渉が実施された企業の割合は89.2%に達したものの、実際にコスト上昇分のうち価格に転嫁できた割合(価格転嫁率)は平均で**39.4%**にとどまり、調査開始以来の最低値を記録した 23。これは、交渉の場についても、企業がコスト上昇分を十分に価格に反映させられていない厳しい現実を物語っている。
この問題は、サプライチェーンの下層に位置する企業ほど深刻化する。元請け企業では価格転嫁率が5割を超える一方、4次請け以下の下請け企業では4割程度まで低下する傾向が見られる 25。専門サービスを提供する企業、特に中小規模の事務所やコンサルティング会社は、大企業からの下請けや業務委託という形で事業を行うケースが多く、価格交渉において弱い立場に置かれがちである。
この売上高の減少は、必ずしも当産業への需要が減退していることを意味するものではない。むしろ、これは企業レベルでの「供給能力の制約」に起因する現象と解釈できる。人手不足により、請求可能な業務時間を担う専門家の数を増やすことができず、企業の売上成長には自ずと上限が生まれる。同時に、既存の優秀な人材を維持するために支払う人件費は高騰し続けている。この状況下で、高騰したコストをサービス価格に十分に転嫁できなければ、利益率は圧迫される。結果として、企業は利益率の低い案件の受注を抑制したり、既存スタッフの燃え尽きを防ぐために業務量を調整したりせざるを得なくなる。これが、専門サービスへの潜在的な需要が依然として強いにもかかわらず、産業全体の売上高が伸び悩み、あるいは減少するという逆説的な状況を生み出しているのである。当産業は、人的資本の希少性によって課せられた「売上の天井」に突き当たっていると言えよう。
4. 人的資本の危機:売り手市場における人材戦略の再定義
4.1 不足の定量化
「学術研究、専門・技術サービス業」における人手不足は、他産業と比較しても際立って深刻である。厚生労働省が2024年11月に公表した労働経済動向調査によると、当産業の労働者過不足判断D.I.(「不足」と回答した企業の割合から「過剰」と回答した企業の割合を引いた値)は**+56ポイント**に達している 20。
この数値は、全産業平均の+46ポイントを大幅に上回り、社会問題化している「医療、福祉」(+63ポイント)、「建設業」(+57ポイント)、「運輸業、郵便業」(+57ポイント)に匹敵する、極めて高い水準である。このデータは、当産業が日本の人手不足問題の震源地の一つであることを明確に示している。
表3:主要産業における労働者過不足判断D.I.の比較(2024年11月)
| 産業 | 労働者過不足判断D.I.(ポイント) |
|---|---|
| 医療、福祉 | 63 |
| 建設業 | 57 |
| 運輸業、郵便業 | 57 |
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 56 |
| 全産業平均 | 46 |
出典:厚生労働省「労働経済動向調査(令和6年11月)の概況」20
特に、産業の中核をなす「情報サービス業」では、ITエンジニアの不足が慢性化しており、企業の**70.2%**が正社員の不足を訴えている 26。これは、あらゆる業界でDX(デジタルトランスフォーメーション)への需要が絶え間なく続いていることに起因する 27。
4.2 変化する採用・定着戦略
この未曾有の人材獲得競争に対応するため、企業は採用と定着に関する戦略の抜本的な見直しを迫られている。
- 多様な人材プールの活用:従来の正社員採用だけでは人材を確保できないため、副業・フリーランス人材の活用に関心が集まっている。しかし、その活用はまだ限定的である。2025年のある調査では、活用経験のある企業は3割未満にとどまった。一方で、活用した企業の約8割が満足していると回答しており、活用のポテンシャルは高い 29。導入が進まない背景には、コストへの懸念や、業務への効果的な組み込み方に関するノウハウ不足がある 29。
- 労働環境の魅力向上:特に若手世代の人材を惹きつけるため、労働環境の質的向上が不可欠となっている。例えば、デザイナーの職場では、単なる機能性だけでなく、心理的安全性が高く、円滑なコミュニケーションを促すオフィス環境が求められている 30。知識労働者全般においては、柔軟な働き方やワークライフバランスの実現が、フリーランスという選択肢と比較される上で重要な要素となっている 31。
- 専門人材市場の二極化:弁護士や公認会計士といった高度専門職の市場では、新たな傾向が見られる。弁護士全体としては就職難ではないものの 32、企業や法律事務所は経験豊富な特定分野のスペシャリストを求めており、採用基準はむしろ厳格化している 33。公認会計士市場も同様に、監査法人と事業会社の双方から高い需要があるが、単なる監査経験だけでなく、M&Aや経営企画といった特定のスキルを持つ人材の価値が高まっており、経験者間の競争は激化している 34。
この深刻な人手不足は、単なる採用問題ではなく、専門職の伝統的なキャリアパスそのものを変容させる強力な触媒として機能している。かつて主流であった一つの組織での終身雇用というモデルは、企業のニーズと個人の価値観の両面から挑戦を受けている。企業は特定のプロジェクトのために高度な専門スキルを必要とし(フリーランス活用の動機)、専門家、特に若手層はより大きな自律性と柔軟性を求めている 31。この状況は、企業に二つの戦略的選択を突きつけている。一つは、卓越した企業文化と報酬制度を構築し、正社員の獲得競争を勝ち抜く「選ばれる雇用主」となる道。もう一つは、中核となる正社員と外部の専門家を効果的に統合する、洗練された「ブレンデッド・ワークフォース(混合型労働力)」モデルを構築する道である。このいずれかの道を明確に選択せず、中途半半端な状態に留まる企業は、あらゆる人材獲得戦線で競争力を失い、その人的資本基盤を徐々に蝕まれていくことになるだろう。
5. 戦略的再編:生き残りと成長のための事業再構築とM&A
5.1 戦略的必須要件としてのM&A
現在の不確実な経済環境は、2025年を「変革的なM&Aの年」にすると予測されている 37。もはやM&Aは成長のための選択肢の一つではなく、変化に適応し、生き残るための必須の戦略ツールとなりつつある。サービス産業全体でM&Aを加速させている主な要因は以下の通りである。
- 人手不足への対応:個別の採用活動よりも、高度なスキルを持つ専門家チームをまとめて獲得する方が迅速かつ効果的である 38。
- DXの加速:確立されたデジタル技術やプラットフォームを持つ企業を買収することで、自社のDXを飛躍的に推進する 38。
- 規模の経済の追求:事業統合によりスケールメリットを確保し、顧客に対する価格交渉力を強化する 38。
- 事業承継問題の解決:特に創業者が高齢化した中小規模の専門事務所にとって、M&Aは事業存続のための有力な選択肢となる 38。
5.2 各分野におけるM&Aの動向
**「学術研究、専門・技術サービス業」全体を網羅するM&Aの統計データは、本調査で利用可能な資料の中には存在しない。**しかし、主要な下位分類の動向から、業界全体の潮流を推察することは可能である。
- 広告業:当分野では、デジタル化への対応がM&Aの最大の駆動力となっている。データ分析会社 40、AIカメラを搭載したデジタルサイネージ事業者 41、Web広告運用専門会社 43 などの買収事例が相次いでいる。これは、広告ビジネスの主戦場が、従来のマスメディアからデータ駆動型のデジタル領域へ完全に移行したことを象徴している。
- コンサルティング業:市場では、ITおよびデジタルトランスフォーメーションに関する専門知識への需要が極めて高い 28。大手ファームがニッチな専門性を持つブティックファームを買収する動きが活発化している。世界的に見ても、AIの台頭が既存事業の価値を再評価させ、「戦略・実行・テクノロジー」を一体で提供できる「フルスタック型」への転換を促している 45。
- 会計・専門事務所:具体的なM&A案件は明示されていないものの、専門家の高齢化やテクノロジー投資の必要性といった背景を考慮すると、特に中小規模の事務所間での合従連衡が進む可能性が高い 38。
5.3 異業種からの参入の活発化
全く異なる業種の企業が、自社の中核事業を強化するために専門サービス企業を買収したり、サービス事業に新規参入したりする動きも目立つ。例えば、日本生命保険が介護サービス大手に、家具小売のニトリが外食産業に参入した事例がある 47。こうした動きは、従来の業界の垣根を曖昧にし、競争環境を一層複雑化させている。
当産業におけるM&Aは、単なる財務戦略から、人的資本と技術を獲得するための主要な戦略へとその性質を変化させている。買収対象となる「資産」は、もはや顧客リストや収益源だけではない。採用困難な専門家チームと、彼らが持つ組織的なノウハウや業務プロセスそのものが、買収の核心となっている。この変化は、買収後の統合プロセス(PMI: Post Merger Integration)、特に企業文化や業務システムの統合を、これまで以上に重要かつ困難なものにしている。統合に失敗すれば、買収の目的であったはずの優秀な人材が流出し、ディールの価値そのものが失われかねない。これは、M&Aのリスク構造が根本的に変化したことを意味する。財務諸表の精査と同等、あるいはそれ以上に、組織文化の適合性やキーパーソンの定着リスクに対するデューデリジェンスが、M&Aの成否を分ける決定的な要因となっているのである。
6. レジリエンスへの投資:加速する自動化とデジタルトランスフォーメーション(DX)
6.1 設備投資の動向
経済の先行き不透明感にもかかわらず、企業の設備投資意欲は比較的堅調に推移している。2025年度の調査では、57.4%の企業が設備投資を計画しているが、この割合は過去数年と比較するとやや低下している 48。
投資の実行を妨げる要因として、「工事費の高騰」や、人手不足に起因する「工期の遅れ」が挙げられており、計画が下方修正されたり、遅延したりするケースが少なくない 49。
6.2 日本のサービス産業におけるDXの特性
DXへの取り組みは業界全体で加速しているが、その内容は日本特有の性質を持っている。日本のDXは、**「内向き」かつ「部分最適」**な性格が強い 50。主な目的は、既存業務の効率化、コスト削減、生産性向上であり、新たなサービスやビジネスモデルの創出といった変革には必ずしも繋がっていない。
これに対し、米国やドイツの企業は、売上や市場シェアの拡大、顧客価値の向上を目的とした**「外向き」で「全体最適」**なDXを志向している 50。この目的意識の違いは、成果にも表れている。自社のDXが目標を達成していると回答した企業の割合は、米国・ドイツでは8割を超えるのに対し、日本では6割弱にとどまる 50。
DXの導入率にも差が見られる。情報通信業では8割以上の企業がDXに取り組んでいる一方、より広範な「サービス業」では6~7割程度となっている 50。
表4:DXの目的と導入状況に関する国際比較(日本 vs. 米国・ドイツ)
| 比較項目 | 日本 | 米国・ドイツ |
|---|---|---|
| DXの志向 | 内向き・部分最適(既存業務の効率化) | 外向き・全体最適(新規価値創造) |
| 主な目的 | コスト削減、生産性向上 | 売上・利益増加、市場シェア向上 |
| 成果達成率 | 約6割 | 約8割以上 |
| 連携 | 経営層・IT・事業部門間の連携が弱い | 連携が強く、全体最適を志向 |
出典:IPA「DX白書2025」の情報を基に作成 50
6.3 実践におけるDX:活用事例と課題
専門事務所(士業):弁護士、公認会計士、税理士などの士業事務所では、定型業務を自動化し、専門家をより付加価値の高い業務に集中させるためのDXが進んでいる。
- 法律分野では、契約書のドラフト作成、判例リサーチ、内容分析などにAIが活用されている 52。
- 会計分野では、AI-OCR技術を用いて領収書や請求書からのデータ入力を自動化し、記帳業務を効率化している 54。
- クラウドベースの文書管理システムやコミュニケーションツール(Slack、Google Calendarなど)の導入により、リモートワークの推進と情報共有の円滑化が図られている 56。
中小企業における共通の失敗要因:多くのDXプロジェクト、特に中小企業においては、期待された成果を上げられずに失敗に終わるケースも多い。共通する原因は以下の通りである。
- 目的の欠如:明確な経営戦略上の目的がないまま、「流行だから」という理由でツール導入自体が目的化してしまう 58。
- 業務プロセスの不変:新しいツールを導入したにもかかわらず、旧来の業務フローを見直さないため、効果が限定的になる 55。
- 現場の抵抗と教育不足:従業員への十分なトレーニングが行われず、現場の理解や協力が得られない 55。
- 拙速な全面導入:段階的な導入(スモールスタート)ではなく、一気に全社展開しようとして現場の混乱を招く 55。
日本のDXが「内向き」であることは、人手不足という喫緊の課題への直接的な対応(より少ない人数でより多くの業務をこなす)としては合理的である。しかし、このアプローチは長期的な戦略的リスクを内包している。既存プロセスの効率化にのみ注力するあまり、AIやデータ分析がもたらす全く新しい高付加価値サービスを創出する機会を逸する可能性があるからだ。将来的には、日本の専門サービス企業は既存業務の効率化には長けているものの、それは既にコモディティ化したサービスの提供に過ぎず、一方で「外向き」のDXを推進したグローバルな競合企業が、より収益性の高い新たな市場を席巻している、という事態に陥る危険性をはらんでいる。
7. 企業の新陳代謝:倒産の動向分析
7.1 サービス業における倒産件数の増加
企業倒産は明確な増加基調にある。2025年度上半期(4月~9月)の全国企業倒産件数は5,146件に達し、上半期としては12年ぶりに5,000件を超えた 39。
この増加傾向において、サービス業は主要な牽引役の一つとなっている。同期間のサービス業の倒産件数は1,348件に上り、2000年度以降で最多を記録した 39。月次データを見ても、2025年9月のサービス業倒産件数は、2000年以降の同月として最多となっており、厳しい経営環境が続いていることを示している 60。
分析上の重要な留意点:帝国データバンクや東京商工リサーチが公表するデータは、「サービス業」を一つの大きな括りとして集計している。本レポートの主題である**「学術研究、専門・技術サービス業」に限定した倒産件数の詳細な統計データは、利用可能な資料の中には含まれていない** 39。したがって、ここでの分析は、同様の経営圧力に晒されていると想定されるサービス業全体の動向を基に行う。
7.2 倒産要因の新たな潮流
倒産の内訳を分析すると、現在の経済環境を反映した新たな要因が顕著になっている。
- 「人手不足倒産」:2025年度上半期に過去最多の214件を記録 39。これは、事業継続に必要な人員を確保できず、受注した業務を遂行できなくなったり、事業規模の縮小を余儀なくされたりした結果、経営破綻に至るケースである。
- 「物価高倒産」:こちらも同期間に過去最多の488件が発生 39。人件費を含む各種コストの上昇分を価格に転嫁できず、採算が悪化し、事業継続が困難になる企業が増加している。
- 「後継者難倒産」:長年の課題であるが、依然として深刻であり、同期間に264件発生している 39。特に、創業者である専門家個人の能力に依存する中小規模の事務所にとって、事業承継は大きな経営課題である。
「人手不足倒産」や「物価高倒産」といった新しいカテゴリーの倒産が増加している事実は、企業経営における競争の力学が根本的に変化したことを示している。デフレ時代には、競争の主軸は「顧客の獲得」にあった。しかし、現在のインフレと人手不足の環境下では、競争の主軸は「経営資源(人材と資本)の確保」へと移行している。かつて、企業の破綻は主に売上不振、すなわち需要の欠如によって引き起こされていた。しかし今や、旺盛な需要があるにもかかわらず、業務を担う人材を確保できない、あるいは採算の合う価格でサービスを提供できない、という供給側の制約によって破綻に至る企業が出現している。これは、専門サービス企業にとって、リスク管理のパラダイムが需要サイドから供給サイドへ根本的にシフトしたことを意味する。
8. 分野別詳細分析:好対照な市場の様相
「学術研究、専門・技術サービス業」は一枚岩ではなく、その内部は多様な分野で構成されており、それぞれが異なる課題と機会に直面している。
8.1 高成長と高ストレス:ITサービス・ソフトウェア開発
- 課題:当分野は、全産業の中でも最も深刻な人手不足に直面しており、7割以上の企業がITエンジニアの不足を訴えている 26。この背景には、あらゆる業界で進むDX化に伴う爆発的な需要がある 27。
- 対応:熾烈な人材獲得競争が賃金高騰を招いている。M&Aは、専門家チームや特定技術を獲得するための重要な手段となっている。DXの導入は事業の根幹であるが、その多くは顧客のプロジェクト管理に向けられており、自社の内部変革が追いついていないケースも見られる。需要に応えきれないことによる機会損失や、既存従業員の燃え尽きが経営上の大きなリスクとなっている。
8.2 安定需要と収益圧迫:建設コンサルタント・土木設計
- 課題:国土強靭化計画などに伴う安定した公共投資に支えられているものの 61、労務費や資材価格の高騰に直接的に晒されており 63、収益性の確保が大きな課題となっている 64。また、就業者の高齢化も深刻である 65。
- 対応:生産性向上を目的としたDXが官民一体で強力に推進されており、特にBIM/CIM(Building/Construction Information Modeling)の導入が加速している 62。ドローンやIoTといった技術を活用し、人手不足を補う取り組みも進んでいる 65。大手企業の中には、厳格なプロジェクト管理によって高い利益成長を実現している例もあるが 66、業界全体としては厳しい経営環境が続いている。
8.3 人材中心の変革:法律・会計などの専門事務所(士業)
- 課題:限られた有資格者をいかに有効活用するかが経営の核心である。定型的な事務作業を自動化し、専門家を高度なコンサルティング業務に集中させる必要に迫られている。また、中小規模の事務所では事業承継が大きな課題となっている。
- 対応:文書作成、リサーチ、データ入力といった業務にAIや自動化ツールを導入する動きが活発化している 52。クラウドベースの業務管理システムも標準となりつつある 56。ビジネスモデルは、時間単価に基づく定型業務から、戦略的助言に対する価値ベースの価格設定へと移行しつつある。人材市場では専門性が高く評価され、特定分野に強みを持つ人材への需要が集中している 33。
8.4 抜本的な再創造:広告・マーケティング
- 課題:当分野は、マスメディア中心の時代から、細分化されデータが複雑に絡み合うデジタル中心の時代へと移行する中で、最も根本的な構造変革を経験している。
- 対応:M&Aが事業再編の主要な手段となっている。広告代理店は、データ分析、AI、SNSマーケティング、デジタル広告技術といった専門性を持つ企業を積極的に買収し、顧客の購買プロセス全体を支援できる「フルファネル」対応への転換を急いでいる 40。ビジネスの核心は、もはや広告キャンペーンを制作することではなく、データに基づいた複雑な顧客体験を設計・管理することへとシフトしている。
9. 結論と将来展望:レジリエントな未来への航路
本レポートで分析したように、日本の専門サービス産業は、デフレ時代のビジネスモデルがもはや通用しない歴史的な転換点に立っている。人件費を主因とするコスト上昇と、構造的な人的資本の希少性という二重の圧力が、避けることのできない進化を企業に強いている。
この新たなパラダイムの中で持続的な成功を収める企業は、以下に挙げる新たな三つの中核的能力を獲得した企業であろう。
- 高度な価値伝達と価格設定能力:従来のコストプラス方式の価格設定から脱却し、自社が創造する価値を顧客に明確に伝え、それに見合った対価を要求する能力。これにより、コスト上昇分を適切に価格転嫁し、人材や技術への再投資原資を確保することが可能になる。
- 戦略的なテクノロジー活用:人手不足に対応するための社内業務効率化と、バリューチェーンの上流を目指すためのテクノロジーを活用した新サービス開発を同時に進める「デュアルDX」戦略の実践。守りの効率化と攻めの価値創造の両立が求められる。
- ダイナミックな人的資本マネジメント:優秀な正社員の獲得競争を勝ち抜くための魅力的な組織を構築すると同時に、増加するフリーランスや外部の専門家を柔軟に活用・統合できる、レジリエントな組織能力の構築。
今後の当産業は、M&Aによる業界再編の継続、テクノロジーへの適応能力による企業間格差の拡大、そして企業と専門家、顧客との関係性の根本的な再定義といった潮流によって特徴づけられるだろう。変化に適応し、これらの中核的能力を磨き上げた企業のみが、不確実性の高い未来においても、その専門性を社会と経済の発展に貢献させ続けることができるのである。
引用文献
- clip-corporation.com, 11月 2, 2025にアクセス、 https://clip-corporation.com/column/researchanddevelopment/#:~:text=%E5%AD%A6%E8%A1%93%E7%A0%94%E7%A9%B6%EF%BC%8C%E5%B0%82%E9%96%80%E3%83%BB%E6%8A%80%E8%A1%93%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E6%A5%AD%E3%81%AF%E3%80%81%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A8%99%E6%BA%96,%E6%A5%B5%E3%82%81%E3%81%A6%E9%AB%98%E3%81%84%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%88%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
- 日本標準産業分類(令和5年
7月改定) 学術研究、専門・技術サービス業 | 詳細情報, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10/04/L - 産業分類コード一覧(大分類) – ハローワークインターネットサービス – 厚生労働省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/info/industry_list01.html
- 日本標準産業分類(令和5年
7月改定) – e-Stat 政府統計の総合窓口, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10 - 大分類L−学術研究,専門・技術サービス業 総 説, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.soumu.go.jp/main_content/000290731.pdf
- 学術研究,専門・技術サービス業の特色や代表する企業, 11月 2, 2025にアクセス、 https://clip-corporation.com/column/researchanddevelopment/
- 大分類 L-学術研究,専門・技術サービス業, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.stat.go.jp/data/e-census/2014/pdf/26bunruil.pdf
- 大分類 L-学術研究,専門・技術サービス業, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.stat.go.jp/data/e-census/2009/kakuho/pdf/21s_l.pdf
- 日本標準産業分類 – Wikipedia, 11月 2, 2025にアクセス、 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%A8%99%E6%BA%96%E7%94%A3%E6%A5%AD%E5%88%86%E9%A1%9E
- 2025年度政府経済見通しと経済政策の課題 – Nomura Research Institute (NRI), 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.nri.com/jp/media/column/kiuchi/20241226_2.html
- 令和7年度(2025年度)政府経済見通しの概要, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www5.cao.go.jp/keizai1/mitoshi/r061225mitoshi-gaiyo.pdf
- 【2025年最新】人手不足の日本の現状と中小企業の生き残り戦略, 11月 2, 2025にアクセス、 https://edenred.jp/article/hr-recruiting/247/
- 【2025年】日本の人手不足は深刻|将来にむけた企業の人手不足解消方法について紹介, 11月 2, 2025にアクセス、 https://hito-colle.com/blog/labor-shortage
- 2025年問題とは?日本の企業が直面する人材不足の課題と対策解説, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.takumi-base.com/hr-branding039/
- 労働力調査(2025(令和7)年6月分) – YouTube, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=yF5q68OTwkc
- 産業別にみた就業者の状況 ―労働力調査(基本集計)の結果から, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2025/05/c_01.html
- 2025 年の日本経済見通し – 大和総研, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.dir.co.jp/report/research/economics/outlook/20241220_024815.pdf
- 7-9月期GDPは大幅マイナス成長の可能性大 ~外需と住宅投資の不振が足を引っ張る, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.dlri.co.jp/report/macro/533976.html
- 統計局ホームページ/労働力調査(基本集計)月次結果, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/tsuki/
- 【2025年最新】企業を蝕む人材不足!データで見る現状と解消に向けた対策, 11月 2, 2025にアクセス、 https://edenred.jp/article/hr-recruiting/229/
- サービス業の売上高が35.6兆円に到達、前年同月比5.2%増の詳細分析と人材需要の行方(令和7年4月分 速報) – 【公式】福岡の求人広告は株式会社パコラ, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.pacola.co.jp/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E6%A5%AD%E3%81%AE%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E9%AB%98%E3%81%8C35-6%E5%85%86%E5%86%86%E3%81%AB%E5%88%B0%E9%81%94%E3%80%81%E5%89%8D%E5%B9%B4%E5%90%8C%E6%9C%88%E6%AF%945-2/
- 「サービス産業動態統計調査」 2025年(令和7年)4月分(速報), 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.stat.go.jp/data/mbss/kekka/pdf/m202504.pdf
- 価格転嫁に関する実態調査(2025年7月)|株式会社 帝国データ …, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tdb.co.jp/report/economic/20250828-pricepass-on202507/
- 価格交渉促進月間(2025年3月) フォローアップ調査 … – 経済産業省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.meti.go.jp/press/2025/06/20250620003/20250620003-1.pdf
- 価格交渉促進月間(2025年3月)フォローアップ調査結果の概要及び「令和7年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」について, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/wgkaisai/roumuhitenka_dai5/siryou2.pdf
- 人手不足に対する企業の動向調査(2024年10月)|株式会社 帝国 …, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tdb.co.jp/report/economic/20241113-laborshortage202410/
- 【業界別】深刻な人手不足の現状・原因・影響。6つの対策も解説 – NTT東日本サービス, 11月 2, 2025にアクセス、 https://biz.service.ntt-east.co.jp/columns/labor-shortage/
- 【2025】コンサルティング業界のM&A動向と最新事例を紹介!現状と今後の課題は?, 11月 2, 2025にアクセス、 https://masouken.com/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E6%A5%AD%E7%95%8C%E3%81%AEM&A%E5%8B%95%E5%90%91
- 「副業・フリーランス人材白書2025」を公開 活用経験のある企業は …, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.persol-career.co.jp/newsroom/news/service/2025/20250522_1845/
- <ヴィス>2025年、オフィスは個性を発揮した「リクルーティング強化」につながるデザインへ|オフィストレンド予想 | 株式会社ヴィスのプレスリリース – PR TIMES, 11月 2, 2025にアクセス、 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000214.000058162.html
- 2025年新卒の41.2%が「フリーランス志向」、うち45.5%が「入社3年以内」の転身を希望, 11月 2, 2025にアクセス、 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000182.000039136.html
- 「弁護士は就職難」は嘘である理由や実態|就職できないケースも解説 – リーガルジョブボード, 11月 2, 2025にアクセス、 https://legal-job-board.com/media/lawyer/difficulty/
- 弁護士の転職トレンド2025:キャリア構築の新たな選択肢とは – KOTORA JOURNAL, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.kotora.jp/c/87986-2/
- 公認会計士の転職先と最新求人動向|キャリアの選び方と市場トレンド – レックスアドバイザーズ, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.career-adv.jp/cpa/cpa2/
- 【2025年更新】公認会計士の転職まとめ(年齢別評価、キャリアプラン、求人例, 11月 2, 2025にアクセス、 https://yamatohc.co.jp/dd/certified-accountant/
- 【2025年版】公認会計士の就活完全ガイド!|超短期決戦を …, 11月 2, 2025にアクセス、 https://career.jusnet.co.jp/cpa/cpa_124_01.php
- 2025年のグローバルM&Aの見通し – Mercer, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mercer.com/ja-jp/insights/people-strategy/mergers-and-acquisitions/delivering-the-deal-the-keys-to-successful-transactions-in-2025/
- サービス業界のM&Aと事業承継の動向・2025年最新 – 日本M&Aセンター, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.nihon-ma.co.jp/sector/c_services.php
- 倒産集計 2025年度上半期(4月~9月)|株式会社 帝国データ …, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tdb.co.jp/report/bankruptcy/aggregation/20251008-bankruptcyh1fy2025/
- 広告業界のM&A事例12選 | fundbook(ファンドブック)事業承継・M&A仲介サービス, 11月 2, 2025にアクセス、 https://fundbook.co.jp/column/industries-ma/advertisement/
- 広告代理店のM&A動向|市場規模から主な事例・成功ポイントまで, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.recof.co.jp/column/useful/detail/61.html
- 広告代理店のM&A動向と事例13選, 11月 2, 2025にアクセス、 https://ma-succeed.jp/content/knowledge/post-7496
- 広告業界のM&A動向 昨今の事業買収・売却の事情やM&A事例を紹介 …, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.ma-cp.com/about-ma/industry/printing-advertising/3/
- 2025年上期コンサルティング業界の採用動向を徹底分析!経験者・未経験者問わず幅広い領域で多様な人材が求められる | 株式会社コトラのプレスリリース – PR TIMES, 11月 2, 2025にアクセス、 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000094.000009015.html
- コンサルティング業界の地殻変動が始まった:野石龍平の人事/ITコンサル徒然日記, 11月 2, 2025にアクセス、 https://blogs.itmedia.co.jp/taps/2025/11/post_1532.html
- 2025年上半期最新情報 世界のM&A業界別動向 | PwC Japanグループ, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/dealsinsights/deals-trends2025-mid-year.html
- 異業種参入とは? メリットやデメリット、実行の流れ、成功させる …, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.ma-cp.com/about-ma/entry-into-other-industries/
- 2025年度の設備投資に関する企業の意識調査 – 帝国データバンク, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tdb.co.jp/report/economic/20250528-2025capinvest/
- 2025年度設備投資計画調査, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.dbj.jp/pdf/investigate/equip/national/2025_summary.pdf
- DX 動向 2025 について – IPA, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.ipa.go.jp/digital/chousa/dx-trend/tbl5kb0000001mn2-att/dx-trend-2025.pdf
- DX動向2025(データ集) – IPA, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.ipa.go.jp/digital/chousa/dx-trend/tbl5kb0000001mn2-att/dx-trend-data-collection-2025.pdf
- 生成AIで士業の業務効率化を実現する7つの方法 – note, 11月 2, 2025にアクセス、 https://note.com/ai_komon/n/n3afaf2c9489b
- 士業における生成AIの活用方法とは?業務効率化と課題、今後の展望を解説 | WEEL, 11月 2, 2025にアクセス、 https://weel.co.jp/media/generative-ai-professionals/
- AIで税理士事務所はどう変わる?現場が語る“AI導入・業務効率化”の成功事例集 | 株式会社LOG, 11月 2, 2025にアクセス、 https://log-port.com/case/taxfirm-ai-case/
- AI導入で失敗する会計事務所の特徴とは?|株式会社PLEASURE, 11月 2, 2025にアクセス、 https://note.com/pleasure_7190/n/nf55d99e9b232
- 生成AIを活用した士業ビジネスのDX化って何から始めればいい?効率化をすすめるための6つのポイント – リーガルエステート, 11月 2, 2025にアクセス、 https://s-legalestate.com/sigyoudx
- 【事例あり】士業DXとは?必要性や取り組み方、手順を解説 – ブレインズテクノロジー, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.brains-tech.co.jp/neuron/blog/dx-certified-professions/
- DX支援サービスの活用事例、よくある失敗例、効果的な活用ポイント, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.ksw.co.jp/media/column/a36
- STEP6-2 中小企業におけるDX導入の失敗事例と成功の秘訣 | 経営と …, 11月 2, 2025にアクセス、 https://cfio.jp/step6-2/
- 倒産集計 2025年 9月報 – 帝国データバンク, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tdb.co.jp/report/bankruptcy/aggregation/20251008-bankruptcy202509/
- 【ゼネコンランキング】業界最新決算:2025年3月期 売上トップ25社一覧 | 土木・建築「施工管理技士派遣ならおまかせ」プロバイドグループ株式会社、未経験でも仕事多数 – PRVD constructionとは, 11月 2, 2025にアクセス、 https://prvd-construction.jp/column/%E3%80%90%E3%82%BC%E3%83%8D%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%80%91%E6%A5%AD%E7%95%8C%E6%9C%80%E6%96%B0%E6%B1%BA%E7%AE%97%EF%BC%9A2025%E5%B9%B43%E6%9C%88%E6%9C%9F-%E5%A3%B2%E4%B8%8A%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%9725/
- 2025年【建設業の将来性と未来展望】市場予測と成長戦略 – syokunin.work, 11月 2, 2025にアクセス、 https://syokunin.work/column/construction-future-prospects/
- 建設業界の最新動向2025 ~市場概況、制度改正、建設コストの値動きまで~ – 建設 IT NAVI, 11月 2, 2025にアクセス、 https://process.uchida-it.co.jp/itnavi/info/c20250317/
- 2025年最新【建設業経営指標分析ガイド】評価精度200%向上を実現 – syokunin.work, 11月 2, 2025にアクセス、 https://syokunin.work/column/management-construction-business-indicators-guide/
- 【2025年最新】土木作業員が知っておくべき建設業界の動向と将来性, 11月 2, 2025にアクセス、 https://hatanakakensetsu.com/archives/2991
- 2025年度版!! 大手ゼネコン5社、決算概況と展望 徹底解説【業界研究】 | 新着記事一覧, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.arc-navi.shikaku.co.jp/column/details.php?column_id=4098