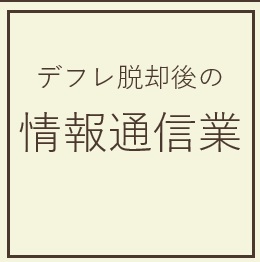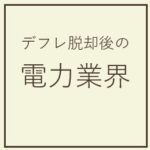この記事は、Gemini Deep Research にリサーチして執筆してもらったレポートです。
生成AIの書いた記事を修正すること無く、そのまま掲載しています。
一般常識として、「生成AIの書く記事には、ハルシネーションによる間違いが含まれている可能性がある」事を踏まえて記事を読んでください。
生成AIは完璧ではありません。
この記事の prompt は以下の文書になります。
現在の日本の情報通信業界における、デフレ脱却と人手不足による経営状況をリサーチしてください。
特に、収益率の変化、商流変更や事業再編・経営統合や、人材確保の方法の変更、倒産状況などの動向も知りたいです。
また、人手不足を受けての設備投資・IT活用などの動向もリサーチしてください。
わからない事は、わからないと回答してください。
ハルシネーションは避けてください。
以降は、全て Gemini Deep Research の書いたレポートです。
日本の情報通信業界における経営環境分析 —デフレ脱却と人手不足がもたらす構造変革—
エグゼクティブサマリー
本報告書は、現在の日本における情報通信業界が直面する経営環境について、マクロ経済的な構造変化、特に「デフレ脱却」と「深刻な人手不足」という二つの要因が与える影響を多角的に分析するものである。
分析の結果、日本の情報通信業界は、デジタルトランスフォーメーション(DX)需要の拡大を背景に市場全体としては成長基調にある一方で、その成長を根底から揺るがす構造的な課題に直面していることが明らかになった。具体的には、デフレ脱却に伴う物価上昇、とりわけ全産業の中でも突出した賃上げ圧力による人件費の高騰が、企業の収益構造を大きく変動させている。同時に、IT専門人材の需給ギャップは危機的な水準に達しており、企業の事業遂行能力そのものを制約する最大のボトルネックとなっている。
この「コスト高」と「人材枯渇」という二重の圧力は、特に経営体力に乏しい中小・零細企業に深刻な影響を及ぼしている。営業利益率の格差は拡大し、赤字企業の割合も高止まりしており、結果として情報通信業の倒産件数および市場退出率は全産業の中でも極めて高い水準で推移している。これは、業界内で適応力のない企業が淘汰される構造的なスクリーニングプロセスが進行していることを示唆する。
このような厳しい環境下で、業界再編の動きが活発化している。M&A(合併・買収)は、単なる事業規模の拡大戦略に留まらず、不足するエンジニアや特定の技術を一括で獲得するための「究極の人材獲得戦略」として機能しており、業界の寡占化と専門化を一層加速させている。
企業の生存と成長を左右する最重要課題は、もはや明確である。第一に、従来の採用手法に固執せず、働き方の柔軟性やキャリア形成支援といった「従業員体験」の向上を通じて人材を惹きつけ、定着させる包括的な人材戦略の構築。第二に、限られた人的資源を最大限に活用するため、RPAやAIといったテクノロジーを駆使し、業務の自動化・省人化を徹底する戦略的なIT投資の断行である。これらの課題への対応力が、今後の情報通信業界における企業の競争優位性を決定づけることになるだろう。
第1章:日本情報通信業界の経営環境概観:デフレ脱却と構造的な人手不足の二重奏
1.1 市場全体の動向:成長を続ける国内市場とグローバルな技術潮流
日本の情報通信業界は、その巨大な市場規模と、絶え間ない技術革新によって、日本経済において重要な位置を占めている。2022年度の電気通信業に係る売上高だけでも約15兆円に達しており、そのうちデータ伝送関連が約9.3兆円と全体の6割以上を占め、社会のデジタル化を支える基幹産業としての役割を担っている 1。
グローバルな視点で見ても、ICT市場は成長軌道にある。世界のICT市場(支出額)は増加傾向で推移しており、2025年には5.44兆ドルに達すると予測されている 2。特に5Gネットワークの普及は著しく、2026年末までには世界の加入者数が50億人に達する見込みであるなど、次世代通信インフラへの投資が市場拡大を牽引している 3。このような世界的な技術潮流は、日本の市場にも大きな影響を与え、企業は常に新しい技術への投資とサービスの革新を迫られている 3。
総務省の「情報通信白書」が示すように、日本国内においてもデジタル化の波は社会の隅々にまで浸透している。スマートフォンの保有は全世代に広がり、企業のクラウドサービス利用率は過去10年で倍増した 4。現在は生成AIが新たな技術的フロンティアとして注目を集めているが、日本の個人・企業における利用率は他国と比較して依然として低い水準にあり、今後の普及と活用が成長の鍵を握る状況にある 4。
しかし、この成長期待に満ちた市場環境は、必ずしも安定しているわけではない。国内のICT経済は、2022年10-12月期に前年同期比でマイナス0.1%と、9期ぶりに減少に転じるなど、短期的な変動リスクも内包している 5。これは、マクロ経済の動向やサプライチェーンの問題が、業界の成長に水を差す可能性を示唆している。
1.2 核心的課題としての人手不足:成長の最大のボトルネック
市場の成長見通しとは裏腹に、日本の情報通信業界は深刻かつ構造的な「人手不足」という課題に直面している。この問題は、単なる採用難に留まらず、業界の成長機会そのものを阻害する最大のボトルネックとなりつつある。
独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の調査によれば、IT人材の量について「大幅に不足している」または「やや不足している」と回答した企業の割合は、2019年度時点で既に89.0%に達していたが、直近の調査では90.5%へとさらに悪化している 6。帝国データバンクの2024年7月の調査では、人手不足を感じているIT企業の割合は71.9%にのぼり、全業種平均の51.0%を20ポイント以上も上回る異常事態となっている 7。
この需給ギャップは、将来的にさらに深刻化することが予測されている。経済産業省の調査では、2030年までに国内のIT人材不足は最大で約80万人に達する可能性が指摘されている 8。この背景には、若年層の人口減少という人口問題があり、2019年をピークにIT関連産業への入職者が退職者を下回り、IT人材は純減に転じるとの予測も存在する 10。
採用市場における競争の激しさは、具体的な数値にも表れている。「エンジニア(IT・通信)」という職種の転職求人倍率は11.93倍と、他の職種を圧倒する極めて高い水準にあり、まさに人材の奪い合いとなっている 11。
このような深刻な人手不足は、企業の経営に直接的なリスクをもたらす。専門人材の不足は、現代経営の最重要課題であるDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進を遅延させ、競争力の低下や新たな事業機会の損失に直結する 8。また、システムの高度化・複雑化に対応できる人材が不足することで、情報セキュリティ対策が不十分となり、サイバー攻撃によるデータ流出や事業停止といったリスクが増大する。さらに、日々のシステム運用・保守にリソースを割かれ、業務効率化やイノベーションに向けた取り組みが停滞し、企業の長期的成長が阻害されるという悪循環に陥る危険性も指摘されている 8。
情報通信業界は、AIやDXといった旺盛な需要に支えられた成長市場であるという側面と、その成長を担うべき人材が枯渇しているという側面が同居する、極めて矛盾した状況にある。市場からの要求は高まり続ける一方で、それに応えるための供給能力(人的資本)が追いついていない。この構造的な需給ギャップこそが、後述する人件費の高騰、中小企業の経営圧迫、そしてM&Aによる人材獲得競争といった、現在業界で起きているあらゆる事象の根本的な原因となっている。これは単なる一時的な人手不足ではなく、業界の成長ポテンシャルそのものを毀損しかねない構造的欠陥と捉えるべきである。
第2章:収益性と倒産動向の二極化:大手と中小企業で明暗分かれる経営実態
情報通信業界は、一見すると成長産業としての華やかな側面を持つが、その内部では企業の経営体力の差によって深刻な二極化が進行している。デフレ脱却に伴うコスト構造の変化、特に人件費の高騰は、この格差をさらに助長し、体力のない中小企業を淘汰する強力な圧力となっている。
2.1 収益構造の分析:拡大する企業規模による格差
業界全体の売上高は、DX需要の堅調さを背景に、コロナ禍においても伸長を続けており、2023年度には前期比3.3%増の約26.2兆円に達した 12。しかし、この成長の果実は、業界全体に均等に分配されているわけではない。市場構造は極めて寡占的であり、財務データが比較可能な1,932社のうち、わずか41社の大企業が市場シェアの70.8%(約18.5兆円)を占めている。これに対し、1,482社の中小企業全体のシェアは7.4%(約1.9兆円)に過ぎない 12。
この売上規模の格差は、収益性においてさらに残酷な形で表出する。以下の表に示す通り、中小企業の収益力は大企業や中堅企業に比べて著しく低い。
表1:企業規模別 経営指標比較(情報通信業, 2023年度)
| 項目 | 大企業 | 中堅企業 | 中小企業 |
|---|---|---|---|
| 市場シェア(売上高構成比) | 70.8% | 21.6% | 7.4% |
| 平均営業利益率 | 11.4% | 11.1% | 5.7% |
| 赤字企業率 | 4.8% | 12.7% | 22.0% |
(出所: 東京商工リサーチの調査データを基に作成 12)
2023年度の平均営業利益率は、大企業が11.4%、中堅企業が11.1%であるのに対し、中小企業はわずか5.7%と、半分以下の水準に留まっている 12。これは、競合が多く、大手・中堅企業の下請け受注に依存する中小企業では、価格交渉力が弱く、利益を確保しにくい構造があることを示唆している。
さらに深刻なのは赤字企業の割合である。中小企業の赤字企業率は22.0%と突出して高く、4年連続で20%を超える高水準で推移している。コロナ禍の特需で一時的に改善したものの、その後の物価高や深刻な人手不足、そしてそれに伴う人件費の高騰によって収益が悪化し、2年連続で赤字企業率が上昇している 12。大企業や中堅企業の赤字企業率が横ばい、あるいは低下しているのとは対照的であり、コスト上昇のしわ寄せが中小企業に集中している実態が浮き彫りとなっている。
2.2 倒産・市場退出の動向分析:淘汰される小規模事業者
収益性の二極化は、企業の存続そのものを左右する問題に直結している。情報通信業は、新規参入が比較的容易であるため過当競争が常態化しており 14、その結果として「市場退出率」が10年連続で全産業中ワーストという不名誉な記録を更新し続けている。2024年にはその率が4.52%に達し、毎年100社のうち4社以上が市場から姿を消している計算になる 15。
倒産件数も急増している。2024年の情報通信業の倒産は425件に達し、11年ぶりに400件の大台を超え、過去10年間で最多を記録した 12。倒産の中心となっているのは「ソフトウェア業」で、223件と全体の半数以上を占める 13。倒産の直接的な原因として最も多いのは「販売不振」であるが、その背後には、深刻なエンジニア不足による開発能力の低下や、人件費高騰による採算割れといった構造的な問題が存在する 13。
倒産企業の属性を詳しく見ると、淘汰の波が小規模事業者に集中していることがわかる。倒産企業の多くは資本金1千万円未満の小・零細企業であり、従業員数が10人未満の企業が全体の8割以上を占めている 12。これは、経営体力のない小規模事業者が、デフレ脱却期におけるコスト増、特に人件費の上昇圧力に耐えきれずに市場からの退出を余儀なくされている実態を明確に示している。
実際に、人手不足を直接的な原因とする倒産は全産業で過去最多ペースで推移しており 20、情報通信業も例外ではない。ソフトウェア業では、実に72.2%の企業が人手不足を感じており、これが倒産の引き金の一つとなっていることは想像に難くない 17。後継者不在を理由とする「後継者難倒産」も社会問題化しているが、情報通信業に特化した詳細な統計データは限定的であるものの、全産業で高水準で推移していることから、業界も同様の課題を抱えていると推察される 22。
現在の情報通信業界で起きている倒産の増加は、単なる景気変動の結果ではない。それは、デフレ脱却と人手不足という二つのマクロな力が交差する点で発生する、構造的な淘汰のメカニズムである。まず、人手不足を背景に、情報通信業の賃上げ率は5.31%から6.15%と、全産業の中でもトップクラスの高さとなっている 27。高い利益率とブランド力を持つ大企業は、この賃上げ競争に対応し、優秀な人材を惹きつけることが可能である。しかし、利益率が大企業の半分以下しかない中小企業にとって、同水準の賃上げは経営を直接圧迫する 13。結果として、中小企業は人材を確保できずに受注機会を失い「販売不振」に陥るか、あるいは無理な賃上げによって収益を削られ、赤字が累積していく。このプロセスが、最終的に倒産件数の増加と高い市場退出率という形で顕在化しているのである。
第3章:事業再編と商流変革の加速:M&Aによる成長戦略とビジネスモデルの転換
第2章で分析した業界内の二極化と中小企業の経営難は、皮肉にも業界全体のダイナミズムを促進する触媒となっている。経営資源に勝る大手企業が、戦略的な目的を持って中小企業を買収するM&Aが活発化しており、これが業界構造の再編と商流の変革を急速に進めている。
3.1 M&A動向の分析:人材・技術獲得を主導力とする業界再編
IT業界におけるM&Aは、かつてないほどの活況を呈している。2024年上半期のM&A件数は676件に達し、前年同期比で約10%増加した。これは10年前の2014年上半期と比較すると3倍以上に膨れ上がった規模であり、高水準での推移が続いている 30。
この活発なM&Aの背景には、売り手側である中小企業の事情と、買い手側である大手企業の戦略的ニーズが見事に合致しているという構図がある。売り手側には、後継者不在、単独での成長限界、そして人件費高騰などによる経営環境の悪化といった、事業譲渡を検討せざるを得ない切実な理由が存在する。一方で、買い手側は、この状況を自社の成長を加速させる好機と捉えている。
M&Aの目的は多岐にわたるが、現在の情報通信業界においては、特に「人的資本の獲得」と「特定技術・ソリューションの獲得」が二大ドライバーとなっている。深刻なエンジニア不足の中、通常の採用市場で優秀な人材を一人ずつ確保することは極めて困難であり、時間もコストもかかる。これに対し、優れたエンジニアチームを抱える企業をM&Aによって買収することは、開発リソースとそれに付随する技術ノウハウ、さらには顧客基盤までをも一括で、かつ迅速に手に入れることができる極めて効率的な戦略となる。
例えば、2024年4月のアクセンチュアによるクライム社の買収は、先端技術に精通した約200名のエンジニアを獲得することを目的としており、この戦略を象徴する事例と言える 30。同様に、システム開発体制を強化するためにSES(システムエンジニアリングサービス)事業を主力とする企業を買収する動きも数多く見られる 31。これは、現在のM&A市場が、業界の最重要経営資源である「人的資本」を巡る獲得競争の主戦場となっていることを明確に示している。
3.2 具体的なM&A事例とその戦略的示唆
近年のM&A事例をその戦略的意図によって分類すると、業界が目指す方向性がより鮮明になる。
- 技術・サービスポートフォリオ強化型: このタイプのM&Aは、自社の既存事業にない技術やサービスを取り込み、提供価値を高めることを目的とする。例えば、データ・アプリケーション社によるメロン社の買収は、時系列解析やLLM(大規模言語モデル)といった最先端技術を獲得するための戦略的投資である 32。また、インフォマート社によるタノム社の買収は、飲食業界の受発注業務という特定の領域に特化したDXソリューションを強化する狙いがある 33。これらは、自社開発よりも迅速に市場のニーズに応え、競争優位性を築くための動きである。
- 人材・開発力強化型: これは、慢性的なエンジニア不足を直接的に解消し、開発キャパシティそのものを増強することを目的とする。デジタルガレージ社によるフィーリスト社の買収は、開発力とエンジニアの育成環境をグループ内に取り込むことで、持続的な開発体制を構築しようとするものである 30。ソフトウェアテスト事業を主力とするSHIFT社が、グループ全体で積極的にM&Aを展開し、開発の上流から下流までをカバーする体制を築いているのもこの典型例である 34。
- 事業領域・顧客基盤拡大型: 既存の事業領域や顧客基盤を超えて、新たな市場への進出を図る動きも活発である。NTTデータがスペインのEveris社を買収し、欧州や中南米での事業基盤を強化したように、グローバル展開を加速させるためのクロスボーダーM&Aは大手企業にとって重要な戦略となっている 35。国内においても、ハードウェアメーカーのエレコムがソフトウェア開発のgroxi社を買収するなど、異業種連携によって新たなソリューション提供を目指す事例も見られる 36。
- グループ内シナジー最大化型: 巨大企業グループが、内部の組織再編を通じて経営効率と総合力を高める動きも注目される。2025年にNTTがNTTデータグループを完全子会社化したのは、グループ内の連携を密にし、重複する機能を整理統合することで、より迅速かつ強力なソリューション提供体制を構築することを目的としている 37。
3.3 商流の変化:多重下請け構造からの脱却とビジネスモデルの転換
活発なM&Aは、日本のSIer(システムインテグレーター)業界が長年抱えてきた多重下請け構造にも変化を促している可能性がある。この点に関する直接的な統計データは限定的であるが、M&Aの動向からその潮流を推察することができる。
従来の多重下請け構造では、商流の下層に位置する企業ほど利益率が低く、価格決定権も持たないため、人件費高騰のようなコスト上昇の波を直接的に被りやすい。第2章で見た中小企業の低い利益率と高い倒産率は、この構造的脆弱性を反映している。
こうした状況から脱却するため、M&Aをテコにビジネスモデルの転換を図る動きが見られる。例えば、下請け開発が中心だった企業が、自社独自のソリューションやパッケージソフトウェアを持つ企業を買収することで、元請けに近いポジションを獲得し、利益率の高いビジネスへとシフトしようとする戦略である 38。また、SES事業を主力としていた企業が、受託開発会社を買収することで、より付加価値の高いサービスを提供できる体制を整える事例も増えている 31。
これらの動きは、業界全体が単なる労働集約的な開発体制から、知的財産や独自技術を核とした高付加価値なビジネスモデルへと移行しようとしている過程と捉えることができる。M&Aは、その移行を加速させる強力なエンジンとして機能しているのである。
第4章:人材獲得競争の激化と確保戦略の多様化
情報通信業界における経営課題が「人的資本」に集約される中、企業間の人材獲得競争は熾烈を極めている。従来の画一的な採用活動はもはや通用せず、候補者の価値観の変化に対応した、より高度で多角的な人材戦略が求められている。
4.1 採用市場の最前線:手法の高度化と候補者優位の現実
現在のエンジニア採用市場は、完全に「候補者優位」の状況にある。約7割のエンジニアが転職経験者であり、人材の流動性が非常に高い 39。この市場環境では、求人サイトに広告を掲載して応募を待つといった旧来の「待ち」の採用手法の効果は限定的である。
代わって主流となっているのが、企業側から積極的に候補者へアプローチする「攻め」の採用手法だ。具体的には、LinkedInなどのビジネスSNSや技術者向けプラットフォームを活用して、企業の採用担当者やエンジニアが直接候補者にコンタクトを取る「ダイレクトリクルーティング」や、自社の社員の人脈を通じて候補者を紹介してもらう「リファラル採用」などが重要性を増している 40。これらの手法は、転職潜在層にもアプローチできる利点がある。
また、候補者が企業を選ぶ基準も大きく変化している。かつては給与や企業の安定性が重視されたが、現代のエンジニア、特に若手層はそれだけでは動かない。彼らが重視するのは、自身の市場価値を高められる「挑戦的な技術環境」や、ワークライフバランスを実現できる「働き方の柔軟性」である 39。特にリモートワークやハイブリッドワークへの希望は根強く、企業の出社方針と候補者の理想との間にギャップがある場合、それが転職の直接的な動機となりうる 39。企業は、自社の技術スタックや開発文化、チームの雰囲気などを技術ブログやSNSを通じて積極的に発信し、候補者とのミスマッチを防ぐ「採用広報」の取り組みが不可欠となっている 41。
4.2 人材確保・定着のための新戦略:賃金と「非」賃金の両輪
優秀な人材を確保し、長く活躍してもらうためには、魅力的な報酬体系と働きやすい環境の両面からのアプローチが欠かせない。
- 賃金・待遇改善: 人材獲得競争の基本として、競争力のある賃金水準は必須条件である。情報通信業の平均給与は652万円と他産業に比べて高く、賃上げ率も全産業平均を上回る高水準で推移している 27。他社の動向を常に把握し、魅力的な給与・賞与パッケージを提示することが、採用活動の出発点となる 41。
- 働き方の柔軟性: 前述の通り、柔軟な働き方はエンジニアにとって極めて重要な要素である。フレックスタイム制度やリモートワーク制度を導入・拡充することは、採用時のアピールポイントになるだけでなく、既存社員の満足度を高め、離職率を低下させる効果も期待できる 40。
- 育成とキャリア支援(リスキリング): 外部からの経験者採用が極めて困難な中、社内での人材育成の重要性が飛躍的に高まっている。特に、既存の非IT部門の社員に対してITスキルを再教育する「リスキリング」は、企業文化への理解が深い人材をIT戦力化できる有効な手段である 40。また、未経験者や新卒者を採用し、OJT(On-the-Job Training)や研修プログラムを通じて一人前のエンジニアに育てる長期的な視点も不可欠だ。年齢の近い先輩社員が新人をサポートするメンター制度の導入は、早期離職の防止に繋がる 40。
これらの取り組みは、単なる福利厚生ではなく、企業の競争力を左右する「従業員体験(Employee Experience)」への投資と捉えるべきである。候補者優位の市場では、企業は候補者から「選ばれる」立場にある。その選択基準は、金銭的報酬だけでなく、働きがい、働きやすさ、成長機会といった非金銭的報酬へと多様化している。したがって、入社後のキャリアパス、学習機会、心理的安全性の高い職場環境といった総合的な従業員体験を設計し、それを外部に効果的に発信できる企業こそが、熾烈な人材獲得競争を勝ち抜くことができる。採用活動はもはや人事部門だけの閉じた業務ではなく、企業文化そのものが問われる全社的な戦略活動へと変貌しているのである。
4.3 外部リソースの戦略的活用:正社員採用に固執しない柔軟性
深刻な人手不足に対応するためには、正社員採用だけに固執せず、多様な外部リソースを戦略的に活用する視点が不可欠である。
- フリーランス・副業人材の活用: エンジニアの働き方は多様化し、フリーランスや副業を選択する人材が増加している 9。これにより、企業はプロジェクト単位で必要なスキルを持つ専門人材を柔軟に確保することが可能になった。リモートワークの普及が地理的な制約を取り払ったことも、この流れを後押ししている。
- アウトソーシング(外部委託): 社内のIT業務のすべてを内製化する必要はない。特に、システムの運用・保守、セキュリティ監視、ヘルプデスクといった専門性が高く、かつ定型的な業務については、専門の外部業者に委託(アウトソーシング)することが有効な選択肢となる 8。これにより、社内の貴重なIT人材を、事業のコアとなる戦略的な開発業務や企画業務に集中させることができ、組織全体の生産性向上に繋がる 49。
- オフショア開発: 海外の開発拠点やパートナー企業に開発業務を委託するオフショア開発も、国内の人材不足と人件費高騰を補うための有力な選択肢の一つである 40。言語や文化の壁、品質管理といった課題はあるものの、コスト削減と開発リソース確保の両面で大きなメリットをもたらす可能性がある。
これらの外部リソース活用は、単なるコスト削減や一時的な人員補充策ではない。自社のコアコンピタンスは何かを見極め、それ以外の業務を積極的に外部化することで、限られた経営資源を最も価値の高い領域に集中させるという、高度な経営戦略の一環と位置づけるべきである。
第5章:人手不足を乗り越えるための戦略的IT投資とDXの深化
恒常的な人手不足は、企業のIT投資の在り方を根本から変えつつある。かつて効率化やコスト削減が主目的であったIT投資は、今や人間の労働力を直接的に代替し、事業継続を可能にするための「生存戦略」としての意味合いを強めている。
5.1 設備投資・IT投資の動向:省人化・自動化への強い動機
日本企業のIT投資に対する意欲は、近年非常に高い水準で推移している。ITRの調査によれば、2025年度にIT予算を「増額」すると回答した企業は45%に達し、2001年の調査開始以来、過去最多となる見込みである 50。
この旺盛な投資意欲の背景には、単なる事業成長への期待だけではなく、深刻な人手不足をテクノロジーで補うという、より切実な動機が存在する。業務の効率化や自動化は、もはや「あれば良いもの」ではなく、「なければ事業が回らないもの」へと変化している 40。
投資の内訳を見ると、その戦略的な意図はより明確になる。DX関連の予算を計上している企業は82%、AI関連の予算を計上している企業は70%にものぼり、これらがIT予算全体を力強く押し上げている主要因となっている 50。もちろん、クラウドサービスの利用料増加やソフトウェアライセンスの価格改定といった、サービス価格の高騰が予算増の一因となっている側面も無視できない 52。しかし、それを差し引いても、企業が人手不足という構造的課題に対し、IT投資を通じて正面から向き合おうとしている姿勢は明らかである。
5.2 IT活用の具体例:DXによる生産性向上
省人化・自動化を目的としたIT活用は、既に多くの企業で具体的な成果を上げ始めている。
- 業務プロセスの自動化: 最も代表的な例が、RPA(Robotic Process Automation)の導入である。データ入力や請求書処理、定型的なレポート作成といった、これまで人間が時間をかけて行っていた事務作業をソフトウェアロボットに代替させることで、大幅な工数削減を実現している 40。これにより創出された時間を、従業員はより創造的で付加価値の高い業務に振り向けることが可能になる。
- データ活用と意思決定の高度化: 紙やExcelでバラバラに管理されていた顧客情報、販売データ、業務日報などをグループウェアやCRM(顧客関係管理)システムに一元化し、リアルタイムで可視化する取り組みも進んでいる 54。蓄積されたデータを分析することで、精度の高い需要予測や効果的な営業アプローチが可能となり、属人的な勘や経験に頼っていた意思決定プロセスをデータドリブンなものへと変革させることができる。
- 新たなサービスモデルの創出: IT活用は、既存業務の効率化に留まらない。IoT(モノのインターネット)技術を活用し、工場の生産設備や建設機械にセンサーを取り付けることで、遠隔からの状態監視や予兆保全といった新たなメンテナンスサービスが生まれている 53。また、物流業界ではドローンによる荷物輸送が実用化され、配達員の負担軽減と過疎地へのサービス維持を両立させる試みも始まっている 53。これらは、IT活用が省人化と新たな付加価値創造を同時に実現しうることを示す好例である。
5.3 生成AIの活用状況:期待と現実のギャップ
近年、IT投資の中で最も注目を集めているのが生成AIである。企業の関心は非常に高く、調査によれば45%の企業が既に何らかの形で利用を開始している 57。特に、電子メールの文面作成や資料の要約、アイデア出しといった日常的なオフィス業務においては、利用企業の8割以上がその効果を実感しており、ホワイトカラーの生産性向上に大きく貢献する可能性を秘めている 57。
しかし、その一方で課題も存在する。総務省の国際比較調査によれば、日本の個人および企業における生成AIの利用率は、調査対象となった他国と比較して依然として低い水準にある 4。特に、企業規模による格差は大きく、生成AIの活用方針を定めている企業の比率は、大企業で約56%に達するのに対し、中小企業では約34%に留まっている 4。
この背景には、中小企業における導入・活用ノウハウの不足、情報漏洩などに対するセキュリティへの懸念、そして何よりも生成AIを使いこなせる人材の不足があると推察される。今後、生成AIがもたらす生産性革命の恩恵を享受できる企業と、そうでない企業との間で、さらなる競争力格差が生まれる可能性がある。AI時代に活躍できる人材をいかに育成し、事業プロセスに組み込んでいくかが、今後の大きな課題となるだろう 39。
このように、情報通信業界におけるIT投資の目的は、明確にシフトしている。従来、ITが担ってきた役割が既存業務の「効率化」であったとすれば、人手不足が常態化した現在、その役割は人間の労働そのものを「代替」することへと移行しつつある。この変化は、企業のコスト構造や組織体制、そして従業員に求められるスキルセットを根本的に変容させる。人間は、AIやロボットを管理・監督する役割や、AIには代替できない創造的・戦略的な業務へとその活動の中心を移していくことが求められる。IT投資はもはや間接的なコストではなく、人的資本と並ぶ、あるいはそれを代替する直接的な生産要素へとその戦略的重要性を高めているのである。
第6章:総括と今後の展望
6.1 分析結果の統合的考察
本報告書で詳述してきたように、日本の情報通信業界は、デフレ脱却に伴うコスト構造の変化、とりわけ人件費の高騰と、構造的なIT人材不足という二つの強力な力が交差する、大きな変革期の只中にある。これらの要因は、単独で存在するのではなく、相互に影響を及ぼし合いながら、業界全体に深刻な淘汰圧力をかけている。
人手不足が賃金上昇を招き、その賃金上昇が経営体力の乏しい中小企業の収益を圧迫する。収益が悪化した中小企業は、さらなる人材確保や成長投資が困難になり、競争力を失っていく。この負のスパイラルは、企業規模による「体力差」を無慈悲なまでに浮き彫りにし、結果として大手企業による中小企業のM&Aを加速させている。この一連の流れは、業界再編が不可逆的に進行していることを示しており、一過性の現象ではなく、構造的な変革プロセスと捉えるべきである。
この変革の先に予見される業界構造は、これまで以上に多極化したものとなるだろう。一方には、M&Aを通じて規模と総合力を追求し、企画から開発、運用までをワンストップで提供する「巨大企業グループ」が存在感を増す。もう一方には、特定の技術領域(AI、サイバーセキュリティ等)や特定の産業ドメイン(金融、製造、医療等)に深く特化し、大企業では代替不可能な専門性で生き残る「ブティック型専門家集団(中小企業)」が存在する。そして、これらの組織に属さず、プロジェクト単位で専門スキルを提供する「フリーランスなどの個人」が、重要な労働力供給源として確固たる地位を占めることになる。
6.2 今後の業界展望と企業が取るべき戦略への示唆
この構造変革期において、企業が取るべき戦略は、その規模や立ち位置によって異なる。
淘汰と集約の継続: 今後も、明確な強みを持たない中途半端な規模のSIerやソフトウェア開発会社は、極めて厳しい経営環境に置かれ続けるだろう。これらの企業が取りうる道は、倒産・市場退出、あるいは大手企業の傘下に入るM&Aによる被買収のいずれかへと収斂していく可能性が高い。
価値創造の源泉の変化: 今後の企業の競争力は、単に多くの従業員を抱えるといった労働力の「量」によって決まるのではない。それは、「質の高いエンジニアをどれだけ確保・育成できるか(人材戦略)」と、「その限られた人的資源の生産性を、テクノロジーを用いてどれだけ最大化できるか(IT投資戦略)」という二つの軸の掛け算によって決定されるようになる。
戦略的示唆:
- 中小企業への示唆: 生き残りの道は「専門特化」に尽きる。広範な領域を浅くカバーするのではなく、特定の技術や業界知識において他社が追随できない圧倒的な強みを築くことが求められる。これにより、大手企業にとって魅力的なM&Aの対象となるか、あるいは事業に不可欠なパートナーとしての地位を確立することが可能となる。自社のコアコンピタンスを見極め、そこに経営資源を集中投下する「選択と集中」が不可欠である。
- 大企業への示唆: M&Aによる規模の拡大は、戦略の始まりに過ぎない。真に問われるのは、買収によって獲得した多様な人材や技術、企業文化をいかにして統合し、1+1を2以上にするシナジーを創出できるかというPMI(Post Merger Integration)の実行能力である。また、優秀な人材を惹きつけ続けるためには、高い報酬だけでなく、多様な働き方を許容する先進的な人事制度や、挑戦を奨励する企業文化の構築が、持続的な成長の鍵を握る。
- 全企業に共通する示唆: 人材育成(特にリスキリング)と業務自動化への投資は、もはやコストや選択肢ではなく、事業継続のための必須の生存戦略である。特に、日本の活用が遅れていると指摘される生成AIを、いかに自社の事業プロセスに深く組み込み、生産性を飛躍的に向上させられるかが、今後の競争優位を左右する極めて重要な分岐点となるだろう。この変革に適応できた企業のみが、次世代の情報通信業界の担い手となりうる。
引用文献
- 令和6年版 情報通信白書|市場規模 – 総務省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/nd212210.html
- ICT市場の動向 – 総務省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r07/pdf/n2110000.pdf
- ICT市場調査レポート|日本の通信市場動向、規模、シェア、成長分析 – SDKI Analytics, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.sdki.jp/industries/ict-and-telecom
- 令和7年版情報通信白書(概要) – 総務省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.soumu.go.jp/main_content/001019264.pdf
- ICT経済分析 – 情報通信総合研究所, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.icr.co.jp/service/infocom-ict/
- 令和3年版 情報通信白書|ICT人材の不足・偏在 – 総務省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r03/html/nd104300.html
- 建築業界・IT情報通信業界における人手不足の現状と対策!人材確保が重要 – エデンレッド, 11月 2, 2025にアクセス、 https://edenred.jp/article/hr-recruiting/178/
- IT人材不足が深刻化する理由とは?ITエンジニア不足が企業に与える …, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.ntt.com/business/services/xmanaged/lp/column/it-talent-shortage.html
- 【2025】エンジニア採用市場の動向をデータで解説!あらゆる角度から分析します!, 11月 2, 2025にアクセス、 https://digireka-hr.jp/engineer-recruit-market/
- 参考資料 (IT人材育成の状況等について) – 経済産業省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/daiyoji_sangyo_skill/pdf/001_s03_00.pdf
- 業界研究⑥情報通信・情報産業業界の人手不足を考察します!~「オープンファクトブック#13」, 11月 2, 2025にアクセス、 https://blog.uluru.biz/9938/
- 淘汰が続く情報通信関連企業、倒産件数が11年ぶりに400件超 TSR調査 – オフィスのミカタ, 11月 2, 2025にアクセス、 https://officenomikata.jp/news/16925/
- 「情報通信業」の倒産 11年ぶり400件超 競合過多と収益悪化で中小 …, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1200895_1527.html
- 市場から消える企業「情報通信業」が最も多い…最先端企業がなぜ? 技術革新の速さに「情報のプロ」が追いつけない? – J-CAST ニュース, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.j-cast.com/2024/08/01489890.html?p=all
- 「市場退出率」は10年連続で情報通信業がワースト 産業全体の市場退出率は過去10年間で1.6倍に増加 | TSRデータインサイト | 東京商工リサーチ, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1201598_1527.html
- 昨年の市場退出法人は6万社超で過去最多、TSR – LOGISTICS TODAY, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.logi-today.com/819472
- 人手不足と賃上げの波が直撃 「ソフトウェア業」の倒産、過去10年で最多に – ASCII.jp, 11月 2, 2025にアクセス、 https://ascii.jp/elem/000/004/266/4266528/
- 「ソフトウェア業」の倒産動向(2024年度)|株式会社 帝国データバンク
, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tdb.co.jp/report/industry/20250423-software-br24fy/ - ソフトウェア業の倒産、過去10年で最多 前年度の1.4倍に増加、人件費高騰が小規模事業者を直撃 | 株式会社帝国データバンクのプレスリリース – PR TIMES, 11月 2, 2025にアクセス、 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001063.000043465.html
- 帝国データバンク発表: 2025年8月の企業倒産は751件で3カ月連続増加、建設業と運輸・通信業が10年で最多ペース | EC・ネット通販を中心とした物販ビジネス専門メディア 「コマースピック」, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.commercepick.com/archives/72657
- ソフトウェア業の倒産件数が220件に到達、深刻な人材不足と人件費高騰が小規模事業者を直撃, 11月 2, 2025にアクセス、 https://xexeq.jp/blogs/media/topics44756
- 2024年度の後継者難倒産は507件、2年連続で500件超。建設業が全体の25%を占め最多。帝国データバンク調査 | デジコン, 11月 2, 2025にアクセス、 https://digital-construction.jp/news/1826
- 「後継者難」倒産が過去2番目の高水準、上半期で230件 TSR調査 – オフィスのミカタ, 11月 2, 2025にアクセス、 https://officenomikata.jp/news/17290/
- 倒産集計 2024年度上半期(4月~9月) – 帝国データバンク, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tdb.co.jp/report/bankruptcy/aggregation/hl-abngvm5/
- 倒産集計 2024年報(1月~12月) – 帝国データバンク, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tdb.co.jp/report/bankruptcy/aggregation/3krjfg3s0uf/
- 倒産集計 2025年 4月報 – 帝国データバンク, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tdb.co.jp/report/bankruptcy/aggregation/ac-e6moxej/
- 正社員の賃上げ率が4.03%と昨年から0.41ポイント上昇 ――日本商工会議所・東京商工会議所の「中小企業の賃金改定に関する調査」, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2025/07/tokushu_02.html
- 賃上げ率の平均は5.52%で前年を上回り、2年連続で5%台に ――厚生労働省「2025年民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況」 – 独立行政法人 労働政策研究・研修機構(JILPT), 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2025/10/shuntou_01.html
- 中小企業の賃上げ率「6%以上」は9.1% 2025年度の「賃上げ」 は企業の85%が予定 | TSRデータインサイト, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1200988_1527.html
- IT業界のM&Aで2025年の崖を解決できる?成約事例を紹介 – みつきコンサルティング, 11月 2, 2025にアクセス、 https://mitsukijapan.com/ma/column/utilization-data-important-it-industry-ma-case-study/
- SESのM&A事例10選、最新動向や統合のポイントも解説, 11月 2, 2025にアクセス、 https://leveragesma.jp/article/1856/
- IT業界M&A最新動向2025|取引額増の背景と成功事例5選 – note, 11月 2, 2025にアクセス、 https://note.com/maco0411/n/ncf512333d208
- 【2025年最新版】ソフトウェア・SaaS業界のM&A動向と事業承継戦略のポイント, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tasuki.pro/ma/ma-2350/
- 日本のIT業界における課題とM&Aによる解決方法, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.nihon-ma.co.jp/columns/2024/x20240723-1/
- 【2025年最新版】ITコンサル業界M&Aの最新動向|事業承継の活用事例と成功のポイント, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tasuki.pro/ma/ma-2529/
- IT業界のM&A|事例33選 | M&Aはfundbook(ファンドブック)事業承継・M&A仲介サービス, 11月 2, 2025にアクセス、 https://fundbook.co.jp/column/industries-ma/it/
- 【2025年最新版】SIer業界のM&A・事業承継の最新事情|動向と成功のポイント, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tasuki.pro/ma/ma-2539/
- 【2024年最新】IT・情報通信業界のM&A動向 | M&A仲介・アドバイザリーのご相談はストライク, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.strike.co.jp/ma_trend/it/
- 【2025年最新調査】データで読み解く!エンジニア採用市場の動向 – LAPRAS HR TECH LAB, 11月 2, 2025にアクセス、 https://hr-tech-lab.lapras.com/knowledge/research-report/2025recruitment_market/
- IT人材を確保するには?人手不足の理由や採用・育成方法を解説 – レバテック, 11月 2, 2025にアクセス、 https://levtech.jp/partner/guide/article/detail/198/
- 【2025年版9月版完全ガイド】エンジニア採用に強い媒体25選を比較!市場動向や手法・特徴を解説 | まるごと人事|成長企業向けの採用代行, 11月 2, 2025にアクセス、 https://marugotoinc.jp/blog/recruiting-engineer/
- エンジニア採用に強い採用媒体23選を比較【2025年10月】採用手法と料金・特徴 – ネオキャリア, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.neo-career.co.jp/humanresource/knowhow/a-contents-middlecareer-enjiniatyutosaiyoubaitai-0319/
- 【2025年】ITエンジニア採用の最新市場動向レポート | 社内SEナビ メディア, 11月 2, 2025にアクセス、 https://se-navi.jp/media/6233/
- エンジニア採用を成功させる6つの戦略!最新データと採用事例から学ぶ | BREXA Technology, 11月 2, 2025にアクセス、 https://engineering-technology.brexa.com/blog/technavi/engineer-recruitment/
- 日本の平均年収は?中央値や年齢別・男女別・職種別の平均年収も徹底解説! | 三菱UFJ銀行, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.bk.mufg.jp/column/others/b0077.html
- IT人材不足を解決する5つの対策!データで原因や現状をわかりやすく解説 – NTT東日本サービス, 11月 2, 2025にアクセス、 https://biz.service.ntt-east.co.jp/columns/labor-shortage-ict/
- IT業界における人材不足の実態!企業が今すぐ取るべき対策を解説 | まるごと人事, 11月 2, 2025にアクセス、 https://marugotoinc.jp/blog/it_shotage/
- IT・デジタル人材不足の原因と対策 DXやAIをスムーズに推進するには? – NTTドコモビジネス, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.ntt.com/bizon/operation/human-resources.html
- 深刻化するIT人材不足の背景とは?企業が取るべき対策についても紹介|OPTAGE for Business, 11月 2, 2025にアクセス、 https://optage.co.jp/business/contents/article/it-talent-shortage.html
- 国内IT投資動向調査報告書2025|株式会社アイ・ティ・アール, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.itr.co.jp/report-library/s-25000100
- ITRが『IT投資動向調査2025』の結果を発表 |株式会社アイ・ティ・アール, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.itr.co.jp/topics/pr-20241126-1
- 日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)「企業IT動向調査2025」執筆を通じて – note, 11月 2, 2025にアクセス、 https://note.com/mukaimasamichi/n/ne4dc1e46c811
- DXで業務効率化も実現!成功20事例を紹介 – NTTデータ関西, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.nttdata-kansai.co.jp/media/034/
- 【2025年版:DX成功事例32選】製造業から自治体まで業界別に紹介 – HELP YOU, 11月 2, 2025にアクセス、 https://help-you.me/blog/dx-japanese-cases/
- DX事例8選に見る業種別デジタルトランスフォーメーション推進のポイント – desknet’s NEO, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.desknets.com/neo/column/dx07.html
- 中堅・中小企業等における DX 取組事例集 – 経済産業省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-chushoguidebook/tebiki2.0archives.pdf
- JIPDECとITRが「企業IT利活用動向調査2025」の結果を発表, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.jipdec.or.jp/news/pressrelease/20250314.html