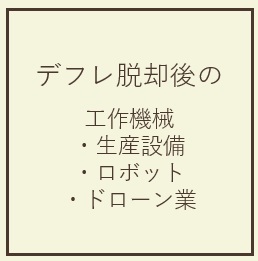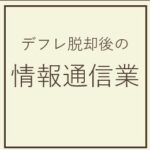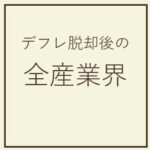この記事は、Gemini Deep Research にリサーチして執筆してもらったレポートです。
生成AIの書いた記事を修正すること無く、そのまま掲載しています。
一般常識として、「生成AIの書く記事には、ハルシネーションによる間違いが含まれている可能性がある」事を踏まえて記事を読んでください。
生成AIは完璧ではありません。
この記事の prompt は以下の文書になります。
現在の日本の工作機械や生産設備・ロボットやドローンなどの製造販売関連業界における、デフレ脱却と人手不足による経営状況をリサーチしてください。
特に、収益率の変化、商流変更や事業再編・経営統合や、人材確保の方法の変更、倒産状況などの動向も知りたいです。
また、人手不足を受けての設備投資・IT活用などの動向もリサーチしてください。
わからない事は、わからないと回答してください。
ハルシネーションは避けてください。
以降は、全て Gemini Deep Research の書いたレポートです。
パラダイムシフトを乗り越える:人手不足と脱デフレ下における日本の先端製造業の戦略的分析
Executive Summary
日本の工作機械、生産設備、ロボット、ドローンなどの先端製造業は、歴史的な転換点に直面している。数十年にわたるデフレ経済の終焉と、構造的かつ深刻化する人手不足という二つの巨大な圧力が、業界の根幹を揺るぶる強力な触媒として作用している。本レポートは、この二重の課題がもたらす経営環境の変化を多角的に分析し、企業の戦略的対応と今後の展望を詳述するものである。
分析の結果、主要な動向として以下の点が明らかになった。第一に、伝統的な工作機械分野では原材料費や人件費の高騰を価格に転嫁できず収益性が悪化する一方、自動化ソリューションを提供するロボット・ドローン分野は急成長しており、業界内で収益機会の二極化が鮮明になっている。第二に、この厳しい環境を乗り越えるための戦略として、事業再編やM&A(合併・買収)が記録的な水準で活発化している。これは、技術ポートフォリオの拡充、事業規模の拡大、そして深刻な後継者問題の解決策として、企業の生存と成長に不可欠な手段となっている。第三に、人材確保は単なる採用活動から、企業の魅力を高めるブランディング、従業員のスキルを再開発するリスキリング、そして外国人材や女性、シニア層といった多様な人材の戦略的活用を含む、包括的な人的資本戦略へと進化している。
これらの変化の根底にあるのは、デジタルトランスフォーメーション(DX)と自動化への不可逆的なシフトである。設備投資やIT活用は、もはや生産性向上のための一手段ではなく、人手不足を補い、熟練技能を継承し、新たな付加価値を創出するための最重要の経営課題となっている。
結論として、日本の先端製造業は、二つのグループへと明確に分かれつつある。一つは、テクノロジーと戦略的統合を積極的に活用し、この変革の波に乗って成長を遂げる「能動的適応者」。もう一つは、コスト上昇、人材枯渇、そして革新の遅れによって存亡の危機に瀕する「受動的対応者」である。本レポートは、この構造変化の実態をデータに基づき解き明かし、企業が未来を切り拓くための戦略的示唆を提供することを目的とする。
第1章 二重の挑戦:日本の製造業を再構築するマクロ経済の逆風
1.1 一時代の終焉:デフレ脱却とコスト上昇の衝撃
日本の製造業は、長らく続いたデフレという特異な経済環境下で事業モデルを最適化してきた。この時代において、収益性を確保するための主要な手段は、徹底したコスト削減と効率化の追求であった。しかし、近年のマクロ経済環境の変化は、この前提を根底から覆している。原材料価格やエネルギーコストの高騰は、企業の利益構造に直接的な打撃を与えている 1。
このコスト構造の変化は、単なる一時的な市況変動ではなく、企業戦略の根本的な転換を強いる構造的な変化である。デフレ下で形成された「価格は上がらないもの」という社会通念は根強く、コスト上昇分を製品やサービスの価格に転嫁することは容易ではない。これにより、企業は単なる効率化の追求から、技術革新や高付加価値化によって価格決定力を持ち、顧客に適正な価格を提示できるような、真の価値創造へと舵を切ることを余儀なくされている。この転換に成功するか否かが、今後の企業の収益性を大きく左右する決定的な要因となる。
1.2 人口動態という不可避な現実:深刻化する労働力・スキル不足の分析
デフレ脱却と並行して、日本の製造業はより深刻かつ構造的な課題に直面している。それは、少子高齢化に起因する労働力不足と、長年業界を支えてきた熟練技能者の高齢化・引退である。経済産業省の統計によれば、製造業の労働人口は2002年から2021年の約20年間で157万人も減少し、約11万人の需給ギャップが生じている 4。特に34歳以下の若年就業者は過去20年間で121万人減少する一方、65歳以上の高齢就業者は33万人増加しており、現場の高齢化が急速に進行している 5。
この問題の根源は、単なる人口動態だけではない。製造業が持つ「3K(きつい・汚い・危険)」というネガティブなイメージや、IT・サービス業といった他産業と比較して低い賃金水準が、若年層の製造業離れを加速させている 4。厚生労働省の調査では、製造業の平均賃金は情報通信業や金融・保険業に比べて月額7万円以上の差があり、これが人材の流出を招く一因となっている 4。
この労働力とスキルの不足がもたらす影響は甚大である。第一に、生産能力の低下による競争力の喪失が挙げられる。人手不足は、新規受注への対応を困難にし、最悪の場合、受注があっても生産ラインを維持できず黒字倒産に至るリスクさえ生じさせる 7。第二に、そしてより深刻なのが「技術継承」の危機である。日本のものづくりの強みは、加工条件の設定や品質管理など、文書化が難しい「暗黙知」として熟練工の中に蓄積されてきた 8。しかし、世代交代が急速に進む中で、この貴重なノウハウが次世代に受け継がれることなく失われつつある。これは単なるスキル不足ではなく、日本の製造業が世界に誇る競争力の源泉そのものが空洞化していくことを意味している 4。
1.3 価格転嫁のジレンマ:新たな経済環境における収益性の決定要因
前述のコスト上昇と人件費高騰という二つの圧力は、「価格転嫁(コスト上昇分を販売価格に反映させること)」という課題に集約される。この価格転嫁の成否が、現在の製造業、特に中小企業にとって死活問題となっている。
中小企業庁の調査によると、中小企業の価格転嫁の状況は改善傾向にはあるものの、依然として道半ばである 9。コストを全て価格転嫁できた、またはコスト上昇がなかった企業の割合は、2022年3月時点の28.6%から2024年9月には47.2%まで上昇した 9。しかし、コスト全般の転嫁率で見ると49.7%にとどまり、上昇したコストの半分しか価格に反映できていないのが実情である 9。
この背景には、サプライチェーンにおける力関係の不均衡が存在する。特に、サプライチェーンの下流に位置する中小企業ほど、大手の発注元に対して価格交渉力が弱く、コスト上昇分を十分に転嫁できない傾向が強い 11。発注側からの「納得できる説明」なしに価格を据え置かれるケースも少なくなく、これが中小企業の収益を著しく圧迫し、経営体力を奪い、ひいては倒産の増加に直結している 10。
このように、デフレの終焉によるコスト構造の変化と、人口動態に起因する労働力不足は、独立した課題ではなく、相互に連関しながら製造業に襲いかかる「挟撃」となっている。一方は原材料費や人件費という形でコストを押し上げ、もう一方は生産能力そのものを制限する。この二重の圧力から生まれる収益性の悪化を食い止める唯一の手段が価格転嫁であるが、長年のデフレマインドとサプライチェーンの構造的問題がそれを阻んでいる。このジレンマを解決できない企業は、財務状況の悪化から事業縮小、そして倒産へと追い込まれていく。この構造こそが、現在の日本の製造業が直面する最も根源的な課題である。
第2章 圧力下の財務パフォーマンス:収益性と市場のダイナミクス
2.1 工作機械セクターの収益性トレンド分析
マクロ経済の逆風は、特に伝統的な工作機械セクターの財務状況に色濃く影を落としている。日本工作機械工業会(JMTBA)が公表した上場企業13社の連結決算データは、この厳しい現実を如実に示している。2023年度通期の業績は、売上高こそ前年度比1.6%減と微減にとどまったものの、営業利益は14.8%減、経常利益は15.5%減、そして当期純利益に至っては21.2%減と、軒並み二桁の大幅な減益となった 13。
表1:主要工作機械メーカーの財務パフォーマンス(2023年度実績および2024年度見通し)
| 項目 | 2023年度 通期 (百万円) | 2022年度 通期 (百万円) | 前年度比 増減率 (%) | 2024年度通期見通し (百万円) | 2023年度実績比 増減率 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 816,841 | 830,122 | △1.6 | 798,857 | △2.2 |
| 営業利益 | 65,421 | 76,764 | △14.8 | 60,371 | △7.7 |
| 経常利益 | 71,246 | 84,314 | △15.5 | 62,328 | △12.5 |
| 当期利益 | 49,146 | 62,346 | △21.2 | 45,006 | △8.4 |
出典:日本工作機械工業会(JMTBA)の公表データを基に作成 13
このデータが示す最も重要な点は、売上高の減少幅に比べて利益の減少幅が著しく大きいこと、すなわち深刻なマージン圧縮が起きているという事実である。これは、第1章で論じた原材料費や人件費の上昇を、製品価格へ十分に転嫁できていないことの直接的な証左と言える。さらに、2024年度の通期見通しにおいても、売上高・各利益ともに減少傾向が続くと予測されており、調査対象13社のうち6社が「減収減益」を見込んでいる 13。この状況は、業界が直面する課題が一時的なものではなく、構造的なものであることを示唆している。
一方で、悲観的な材料ばかりではない。工作機械市場全体としては、一時的な落ち込みの後、2025年にはコロナ禍以前の水準を超える2.7兆円規模まで回復することが予測されている 14。また、日本の工作機械メーカーは、欧州製に比べて「品質対比価格の良さ」や耐久性の高さで依然として競争優位性を保っている 14。特に、人手不足を背景に一台で多様な加工を行える「複合機」への需要は高まっており、これは日本の得意分野でもある 14。
2.2 ロボット・ドローン分野の成長軌道:対照的な市場見通し
伝統的な工作機械セクターが収益性の課題に直面する一方で、人手不足という逆風を直接的な追い風に変えているのが、ロボットおよびドローン分野である。これらの自動化ソリューション市場は、対照的に極めて明るい成長見通しを示している。
世界の産業用ロボット市場は、年平均成長率(CAGR)14.2%という高い成長率で拡大し、2032年までに市場規模は555億5,000万ドルに達すると予測されている 15。この成長を牽引しているのは、まさに日本の製造業が直面している人手不足と、生産性向上への強い要求である 17。日本国内においても、政府が推進する「Society 5.0」構想などを背景に、スマート製造への移行が加速しており、協働ロボット(コボット)などの導入が活発化している 17。
さらに劇的な成長が期待されるのが、製造業以外の分野で活用されるサービスロボット市場である。2020年時点で3,000億円弱であった国内市場は、物流、ホスピタリティ、医療・介護、建設といった人手不足が特に深刻な分野での活用が進むことで、2030年には約1.3兆円、2040年には約2.8兆円へと急拡大すると推計されている 18。
ドローン市場も同様に、人手不足を解決するソリューションとして大きな期待を集めている。特に、農業における農薬散布、建設現場での測量やインフラ点検、そして過疎地域における物流など、従来は多大な人的リソースを必要とした分野での活用が急速に進んでおり、今後の市場の伸びが確実視されている 19。
この工作機械とロボット・ドローン分野における財務パフォーマンスと市場見通しの著しい乖離は、単なる市場サイクルの違いでは説明できない。これは、製造業における価値創造の源泉が、個々の「機械(ツール)」の性能から、それらを統合し知能化させた「自動化システム(ソリューション)」へと根本的に移行しつつあることを示している。人手不足という課題に直面する顧客が求めているのは、もはや単に高性能な機械ではなく、生産プロセス全体を効率化し、労働力への依存を低減する包括的な解決策である。したがって、従来型の「ツール」提供者であり続ける企業は価格競争とマージン圧縮に苦しみ、一方で「ソリューション」提供者へと変貌を遂げる企業は、旺盛な需要を背景に高い成長を享受するという二極化が、今後ますます進行していくと考えられる。
第3章 戦略的再編:M&A、事業再構築、サプライチェーン変革
3.1 合従連衡の加速:M&Aの動機とトレンド
日本の製造業は現在、記録的なM&Aの波に洗われている。2023年には製造業を対象としたM&A件数が240件に達し、過去10年間で最多を記録した 22。この背景には、第1章で詳述したマクロ経済環境の激変と、それに伴う企業の生存戦略の転換がある。M&Aはもはや単なる成長戦略の一環ではなく、変化に適応し、生き残るための必須の手段となっている。
M&Aを駆動する主要な動機は、以下の5つに大別できる。
- 技術獲得(Technology Acquisition):自社に不足しているIoT、AI、自動化といった先進技術を持つ企業を買収し、スマートファクトリー化への対応を急ぐ動きが活発化している。特に日本の工作機械業界は、高い技術力を持ちながらもIT活用で海外競合に後れを取っており、M&Aによってこの弱点を補完しようとしている 23。
- 製品ポートフォリオの拡充(Product Portfolio Expansion):顧客に対してより包括的なソリューションを提供するため、自社の製品ラインナップにない製品群を持つ企業を買収する。これにより、ワンストップでの提案力を高め、顧客の囲い込みを図る 26。
- 市場アクセスと規模の経済(Market Access & Scale):特に海外市場への進出や販路強化を目的としたクロスボーダーM&Aが増加している。また、国内での再編により事業規模を拡大し、購買力や価格交渉力を高め、コスト競争力を強化する 23。
- 事業承継(Business Succession):中小企業において最も深刻な課題の一つである後継者不在問題の解決策として、M&Aが積極的に活用されている。これにより、経営者は事業の継続と従業員の雇用を守り、長年培ってきた技術の散逸を防ぐことができる 23。
- 垂直統合(Vertical Integration):世界的なサプライチェーンの混乱を受け、部品メーカーや物流関連企業を買収することで、供給網の安定化と強靭化を図る動きも見られる 25。
3.2 ケーススタディ分析:大型買収の戦略的合理性
近年の大型M&A案件は、これらのトレンドを象徴している。ここでは、特に注目すべき2つの事例を深掘りする。
ケース1:DMG森精機による倉敷機械の買収
この案件は、典型的な「製品ポートフォリオの拡充」を目的とした戦略的買収である。業界最大手のDMG森精機は、業界最大級の品揃えを誇る一方で、航空・宇宙やエネルギー分野で需要が拡大しているCNC横中ぐりフライス盤を製造していなかった 26。一方、倉敷機械はこの分野で約40%の国内シェアを持つ有力企業である 26。この買収により、DMG森精機は瞬時に戦略的な製品ラインの空白を埋めることができた。今後は、DMG森精機が持つ強力なグローバル販売網、特に欧州での販路を活用し、倉敷機械の製品を世界市場で拡販していくことが期待される 27。
ケース2:ニデックによるTAKISAWAの買収
この案件はより複雑で、異業種からの積極的な市場参入とシナジー創出を目指す野心的な買収である。モーターで世界的な地位を築いたニデックは、近年、工作機械事業を新たな成長の柱とすべく、2021年の三菱重工工作機械の買収を皮切りに積極的なM&Aを展開している 30。旋盤(NC旋盤)大手のTAKISAWAを買収することで、ニデックは自社に欠けていた中核製品群を獲得した 30。
期待されるシナジーは多岐にわたる。まず、TAKISAWAが手薄だった欧米市場において、ニデックグループの広範な販売網を活用し、売上を拡大する 30。次に、ニデックが得意とするモーターなどの基幹部品をTAKISAWA製品に内製供給することで、コスト競争力を高める 30。そして、両社の事業を統合することで売上規模1,000億円超の事業体となり、規模の経済を追求する 31。この案件は、当初敵対的買収の様相を呈したことでも注目され、日本のコーポレートガバナンスの変化を象徴する事例ともなった 27。
3.3 国内生産への回帰:サプライチェーンの再構築と「リショアリング」
M&Aによる業界再編と並行して、企業の生産拠点戦略にも大きな変化が見られる。長らくコスト削減を目的とした海外移転が主流であったが、近年は生産拠点を日本国内へ回帰させる「リショアリング」の動きが顕著になっている。
経済産業省の「2023年版ものづくり白書」によれば、2022年度において、中国・香港から日本国内へ生産拠点を移転した企業は100社に上り、これは日本から同地域へ移転した65社を大きく上回っている 33。この潮流を後押ししている要因は複合的である。
- 地政学的リスクの増大:米中間の対立激化や半導体規制の強化などを受け、特定の国、特に中国への過度な依存が経営上の重大なリスクとして認識されるようになった 34。
- サプライチェーンの脆弱性の露呈:新型コロナウイルスのパンデミックは、長く複雑なグローバルサプライチェーンがいかに脆弱であるかを白日の下に晒した。安定供給の確保が、コスト削減以上に重要な経営課題として浮上した 33。
- 海外生産コストの上昇:中国をはじめとするアジア諸国での人件費高騰により、海外生産のコストメリットが相対的に低下している 33。
- 政府による国内投資の促進:日本政府は、経済安全保障の観点から、サプライチェーンの国内回帰を支援する補助金制度などを積極的に展開しており、これが企業の国内投資を後押ししている 33。
この国内回帰の動きは、日本の製造業の基盤強化に繋がる一方で、国内の労働力不足をさらに深刻化させるというジレンマも抱えている 33。結果として、国内に新設・増強される工場では、省人化・自動化が当初から前提となり、DXやロボット導入への投資を一層加速させるというフィードバックループを生み出している。
これらのM&Aやサプライチェーン再編の動きは、単発の経営判断ではなく、日本の製造業エコシステム全体が構造変化に適応しようとするダイナミックなプロセスである。特に中小企業にとっては、後継者不在、技術投資の資金不足、コスト圧力という三重苦から逃れるためのM&Aが、事業を未来に繋ぐための現実的かつ重要な選択肢となっている。技術承継を専門に行うファンドの登場 22 や、小規模案件を扱うM&Aプラットフォームの普及 25 は、M&Aがもはや大企業だけのものではなく、産業構造を再配線するための不可欠なインフラとなったことを示している。
第4章 人材獲得競争:進化する人事・労働力戦略
4.1 採用活動の再定義:受け身から攻めのタレントアクイジションへ
深刻な人手不足は、製造業の採用活動に根本的な変革を迫っている。従来のような求人サイトに情報を掲載し応募を待つ「受け身」の姿勢では、もはや必要な人材を確保することはできない。企業は、自社の魅力を積極的に発信し、多様なチャネルを通じて潜在的な候補者にアプローチする「攻め」のタレントアクイジションへと転換を図っている。
その戦略は多岐にわたる。
- エンプロイヤーブランディングの強化:3Kというネガティブなイメージを払拭するため、自社の高い技術力、製品が社会に与える価値、そして最新の設備や働きやすい職場環境を積極的にアピールする。実際の社員が登場する動画コンテンツの制作や、工場見学会、インターンシップの実施などを通じて、仕事のやりがいや成長の機会を具体的に伝え、企業のブランドイメージを向上させる 37。
- 採用チャネルの多様化:従来のハローワークや求人サイトに加え、LinkedInなどのビジネスSNSを活用したダイレクトリクルーティング、技術者コミュニティへの参加、インセンティブを充実させた社員紹介制度の強化、そして地域の工業高校や大学との連携を深めるなど、あらゆる接点を通じて人材にリーチしようと試みている 38。
- 候補者体験(Candidate Experience)の向上:競争が激しい売り手市場においては、選考プロセスそのものが候補者から評価される。応募から内定までの期間を短縮し、オンライン面接を積極的に活用することで、迅速なコミュニケーションを図る。これにより、優秀な人材が他社に流出するのを防ぐ 38。
4.2 人への投資:リスキリング、アップスキリング、生涯学習の隆盛
新たな人材の獲得が困難である以上、既存の従業員の能力を最大限に引き出し、新たなスキルを習得させる「リスキリング(学び直し)」の重要性が飛躍的に高まっている。これは単なる研修制度の拡充ではなく、事業環境の変化に対応できる人材を社内で育成するための戦略的投資と位置づけられている。
具体的な取り組みとしては、以下のようなものが挙げられる。
- DXリテラシーの向上:全社員を対象に、データ分析やデジタルツールの活用に関する基礎的な教育を実施する。これにより、組織全体のデジタル対応能力の底上げを図る 39。大手企業では、日立製作所が国内グループ全社員16万人を対象にDX研修を実施し、富士通も全社的なDX人材育成に取り組むなど、大規模な投資が行われている 40。
- 多能工化の推進:一人の従業員が複数の工程や業務を担当できるよう訓練する。これにより、特定の従業員の欠勤や退職に強い、柔軟で強靭な生産体制を構築できる。少人数でも生産ラインの変動に柔軟に対応できるようになり、生産性向上に直結する 42。
- 専門技術の育成:今後需要が高まる半導体や電池、あるいはIoTやAIといった先端分野において、社内大学の設立や外部専門機関との連携を通じて、高度な専門知識を持つ人材を育成する 44。ダイキン工業では、AI人材を育成する社内大学を設立し、ベテラン社員と若手AI技術者の協業を促進している 40。
4.3 新たな人材プールの開拓:外国人材、女性、シニア層の戦略的活用
労働力人口そのものが減少する中で、企業は従来の「日本人男性中心」という労働力モデルからの脱却を迫られている。これまで十分に活用されてこなかった多様な人材プールに積極的にアクセスすることが、人材獲得競争を勝ち抜く鍵となっている。
- 外国人材の戦略的活用:かつての技能実習制度が人手不足の「穴埋め」として問題視されることもあったが 46、現在はより戦略的な活用へとシフトしている。単なる労働力としてではなく、専門技術を持つエンジニアや将来の幹部候補として採用し、日本語教育やキャリアパスの提供、異文化理解を促進する社内環境の整備などを通じて、長期的な定着と活躍を支援する動きが広がっている 47。
- 女性とシニア層の活躍推進:製造現場の自動化や補助機器の導入により、従来は体力的負担が大きいとされてきた作業の負荷を軽減し、女性が働きやすい環境を整備している 38。また、豊富な知識と経験を持つシニア人材を、定年後も技術指導役やメンターとして再雇用し、その貴重なスキルを若手への技術継承に活かす取り組みも重要となっている 4。
この人材を巡る一連の動きは、製造業における人事部門の役割が根本的に変化していることを示唆している。かつて、潤沢な労働力を前提としていた時代には、人事の役割は採用や労務管理といった管理的業務が中心であった。しかし、人材が希少な戦略的資産となった今、人事部門は単なるコストセンターではなく、企業の持続的成長を支える人的資本開発を担う戦略的機能へと変貌を遂げなければならない。従業員のエンゲージメントを高め、キャリア開発を支援し、多様な人材が活躍できる企業文化を醸成すること。これらが、未来の工場を動かすスキルと知識を確保するための最前線の戦いとなっている。
第5章 経営危機のバロメーター:企業倒産動向の分析
5.1 製造業における近年の倒産統計の概観
デフレ脱却に伴うコスト増と深刻な人手不足という二重の圧力は、経営体力の弱い企業を淘汰し、倒産件数の増加という形で顕在化している。帝国データバンクの調査によれば、企業倒産は全体として33カ月連続で前年同月を上回るなど増加傾向が続いており、2024年度は11年ぶりに1万件を超える可能性があると指摘されている 54。
この傾向は製造業も例外ではない。2022年の製造業の倒産件数は722件と、前年の664件から8.7%増加しており、非製造業の増加率(6.3%)を上回っている 2。倒産に至る直接的な要因は、コロナ禍で導入された実質無利子・無担保(ゼロゼロ)融資の返済本格化や、原材料・エネルギー価格の高騰、そして人件費の上昇などが複合的に絡み合っている 29。
表2:日本の主要な倒産トレンド(2023年-2025年)
| 指標 | 期間 | 件数/状況 | 前年同期比増減率 (%) | 主要因/コメント |
|---|---|---|---|---|
| 企業倒産(全体) | 2024年度見込み | 1万件超 | 13.4% (vs 2023年度) | 11年ぶりの1万件台へ。33カ月連続で前年を上回る 54。 |
| 製造業倒産 | 2024年1-11月累計 | 501件(後継者難) | – | 後継者難倒産のうち製造業が最多業種の一つ 29。 |
| 人手不足倒産 | 2025年度上半期 | 214件 | – | 過去最多を更新。特に労働集約型業種で増加が目立つ 29。 |
| 後継者難倒産 | 2024年1-11月累計 | 501件 | – | 2年連続で500件超。経営者の高齢化が背景 29。 |
| 経営者の病気・死亡による倒産 | 2025年1-9月 | 249件 | – | 2024年を上回るペースで推移。高齢化問題を反映 |
出典:帝国データバンクの各調査レポートを基に作成 2
5.2 「人手不足倒産」と「後継者難倒産」の増加
近年の倒産動向で特に注目すべきは、倒産の主因として「人手不足」と「後継者難」が明確に識別され、その件数が著しく増加している点である。
「人手不足倒産」は過去最多ペースで推移しており、2025年度上半期には214件に達した 29。これは、企業が事業を継続したくても、必要な従業員を確保できないために操業停止に追い込まれるという、極めて深刻な事態が常態化しつつあることを示している。特に、従業員の退職が直接的な引き金となる「従業員退職型」の倒産も増加しており、人材の定着がいかに重要であるかを物語っている 29。
同時に、「後継者難倒産」も年間500件を超える高水準で推移している 29。これは特に中小製造業において深刻な問題であり、優れた技術やノウハウを持ちながらも、経営者の高齢化や親族内に後継者が見つからないために事業継続を断念せざるを得ないケースが後を絶たない。これらの倒産のうち、約4割が「経営者の病気・死亡」を直接的な契機としており、事業承継の準備が間に合わないまま廃業に至る現実を浮き彫りにしている 55。
5.3 ケーススタディ:企業破綻の根本原因を探る
統計データだけでなく、個別の倒産事例は、これらのマクロな圧力が企業経営にどのように作用するかを具体的に示している。
- 外部環境の変化への対応の遅れ:ある自動車部品メーカーは、大手取引先がより安価な海外製部品に切り替えたことや、EVシフトによって自社製品の需要が消滅したことにより、受注が激減し経営破綻した 59。また、造船不況や円高といった外部環境の激変に対応できず、事業構造の転換に失敗した機械メーカーの事例もある 60。
- コスト転嫁の失敗:食材費や配送コストの高騰を販売価格に転嫁できず、収益性が悪化し続けた食品加工会社は、最終的に事業継続を断念した 3。これは、サプライチェーンにおける価格交渉力の弱さが、いかに企業の存続を脅かすかを示す典型例である。
- 技術開発の遅延と資金ショート:大きな注目を集めた全自動洗濯物折りたたみ機「ランドロイド」の開発企業は、製品の発売予定が度重なる延期の末、開発資金が枯渇し経営破綻に至った 61。これは、革新的な技術開発に伴うリスク管理の難しさを示唆している。
これらの事例から浮かび上がるのは、現代の企業倒産が、かつてのような景気循環に伴う販売不振だけを原因とするものではなくなっているという事実である。むしろ、倒産の性質そのものが、景気変動に左右される「循環的」なものから、人口動態、技術変革、サプライチェーンの構造変化といった、より根源的で不可逆的な要因によって引き起こされる「構造的」なものへとシフトしている。この構造的な脆弱性こそが、一部の企業を淘汰し、第3章で述べたM&Aによる業界再編、すなわち一種の「創造的破壊」を促進する原動力となっているのである。
第6章 最重要の対抗策としての投資:自動化、DX、そしてスマートファクトリー
6.1 自動化という至上命題:ロボットと先端設備への資本投下
人手不足という構造的な課題に対する最も直接的かつ効果的な対抗策は、自動化への設備投資である。企業は、産業用ロボットや人との協働が可能な協働ロボット(コボット)、工場内の搬送を自動化する無人搬送車(AGV)などを導入し、これまで人手に頼ってきた反復作業、過酷な肉体労働、危険な作業からの脱却を加速させている 8。
この動きの目的は、単に労働者を機械に置き換えることによるコスト削減に留まらない。より本質的な狙いは、限られた人的資源を、機械にはできない付加価値の高い「知的労働」へとシフトさせることにある 1。単純作業や定型業務を自動化することで、従業員は品質改善、工程改良、新たな製品開発といった、より創造的な業務に集中できるようになる。これにより、企業全体の生産性と競争力を向上させることが可能となる。
6.2 生存と成長の核となるDX戦略
デジタルトランスフォーメーション(DX)は、自動化を包含する、より広範で根源的な経営戦略である。DXは、単にデジタルツールを導入することではなく、デジタル技術を活用してビジネスプロセス、企業文化、そしてビジネスモデルそのものを変革することを意味する。製造業において、DXは生存と成長のための核心的な戦略として位置づけられている。
製造業DXの主要な取り組みは以下の通りである。
- 暗黙知のデジタル化による技能継承:熟練技能者が持つ勘やコツといった「暗黙知」を、センサーデータや作業動画、デジタルマニュアルといった形式でデータ化・可視化する。これにより、退職とともに失われかねない貴重なノウハウを組織の資産として蓄積し、若手従業員への効率的な技能継承を可能にする 64。
- オペレーションの可視化による生産性向上:工場内の設備にIoTセンサーを取り付け、稼働状況や生産データをリアルタイムで収集・分析する。これにより、生産ラインのボトルネックや非効率な部分を特定し、改善につなげることができる。また、設備の故障予兆を検知する予知保全も可能となり、ダウンタイムを最小限に抑えることができる 1。
- バックオフィス業務の効率化:手書きの日報、紙ベースの在庫管理、口頭での引き継ぎといった非効率な間接業務をデジタル化・自動化する。在庫管理システムや生産管理システム、RPA(Robotic Process Automation)ツールの導入により、事務作業にかかる工数を大幅に削減し、従業員をより付加価値の高い業務に再配置する 64。
6.3 実践段階のスマートファクトリー:中小企業が直面する導入障壁と克服
スマートファクトリーは、これらのDXの取り組みを統合し、工場全体をデータで連携させ最適化する構想である。しかし、その実現、特に中小企業にとっては、いくつかの大きな障壁が存在する。
- 導入障壁:最大の課題は、高額な初期投資である 62。ロボットやIoTセンサー、ソフトウェアの導入には多額の費用がかかり、投資対効果が不透明な中で決断を下すことは容易ではない。さらに、DXを推進できる専門的なスキルを持つ人材が社内に不足していること 69、そして既存の業務プロセスや組織文化が変化への抵抗勢力となること 69 も、導入を妨げる大きな要因となっている。
- 成功事例:一方で、これらの障壁を乗り越え、DXを成功させている中小企業(町工場)も増えている。成功の鍵は、大規模で包括的なシステム導入を目指すのではなく、自社の課題に直結する領域からスモールスタートすることである。例えば、ある町工場では、QRコードを活用した簡単な工程管理システムを導入するだけで、年間840時間の工数削減を達成した 68。また、愛知県の金属加工工場では、AIを活用した外観検査システムを導入し、不良品率を劇的に低下させ、年間数千万円のコスト削減に成功している 71。これらの事例は、高額な投資や高度な専門人材がいなくても、身の丈に合った実践的なDXが可能であることを示している 69。
6.4 投資対効果の定量化:DXと自動化がもたらす便益
スマートファクトリー化への投資は、明確で定量的なリターンをもたらす。その効果は多岐にわたる。
- 生産性の向上:設備の稼働率向上や段取り時間の短縮により、生産量が20%向上した事例や、一人当たりの売上が1.4倍になった事例がある 68。
- 品質の安定化:リアルタイムのデータ監視やAIによる画像認識検査により、ヒューマンエラーを排除し、不良品率を50%以上削減することが可能となる 71。
- コスト削減:省人化による人件費の削減はもちろん、エネルギー監視システムによる電力消費の最適化(10-20%削減)や、需要予測に基づく在庫の適正化なども、大きなコスト削減効果を生む 68。
- 労働力への貢献:自動化により、24時間無人での稼働(いわゆる「灯りを消した工場」)も可能となり、労働力不足を直接的に補うことができる 1。
しかし、こうしたDXの恩恵を享受できる企業と、そうでない企業との間には、深刻な「デジタルデバイド(格差)」が生まれつつある。資本力と人材を持つ大企業がDXを加速させ競争力を高める一方で、資本とスキルが不足する中小企業は、DXに着手できずに取り残されていく。この構造は、中小企業が「DXを推進するために利益が必要だが、利益を出すためにDXが必要」というジレンマに陥っていることを示している。この格差を埋めるためには、政府による補助金制度の活用 4 や、第3章で述べたM&Aによる大企業グループへの参画が、中小企業にとってますます重要な選択肢となってくるだろう。
第7章 特定セクターへの深掘り:ロボットとドローンの二重の役割
7.1 産業用・サービスロボット:生産ツールから社会課題解決ソリューションへ
ロボット技術は、その役割を大きく進化させている。従来の工場内で特定の作業を繰り返す産業用ロボットに加え、人手不足というより広範な社会課題を直接解決するサービスロボットの社会実装が急速に進んでいる。
その活用範囲は、もはや製造業に限定されない。
- 物流・倉庫:EC市場の拡大に伴う労働力不足に対応するため、商品のピッキングや仕分け、搬送を自動で行うロボットシステムの導入が不可欠となっている 18。
- 医療・介護:高齢化が深刻なこの分野では、患者の移乗介助や施設内の清掃、配膳などを担うロボットが、職員の身体的負担を軽減し、人手不足を補っている 18。
- 接客・飲食:レストランやホテルでは、配膳・下膳ロボットや清掃ロボットが導入され、従業員はより付加価値の高い接客業務に集中できるようになっている 17。
このロボット活用の拡大を後押ししているのが、政府による規制緩和と国家戦略である。従来、安全上の理由から厳しく制限されていた「人とロボットの協働作業」に関する規制が緩和され、安全柵なしで人と並んで作業できる協働ロボットの導入が容易になった 79。さらに経済産業省は、AIを搭載したロボットの開発・活用を推進する国家戦略を策定し、特に製造や物流、介護など多様な現場で活用できるヒューマノイド型ロボットの開発を重点的に支援する方針を示している 80。また、ユーザー側の業務フローや施設環境をロボットが導入しやすいように変革する「ロボットフレンドリーな環境」の実現に向けた取り組みも進められている 81。
7.2 ドローン:物流、農業、点検における新たな効率性の解放
ドローン(無人航空機)は、特に地理的・物理的な制約が大きい環境下での人手不足を解消する強力なツールとして、その価値を証明しつつある。
主要な活用事例は以下の通りである。
- 農業:高齢化と後継者不足が深刻な農業分野において、ドローンによる農薬や肥料の自動散布は、従来数時間かかっていた作業をわずか数分に短縮するなど、劇的な省力化を実現している 19。
- インフラ点検:橋梁、ダム、送電線、ビル外壁といった高所や危険な場所の点検作業を、ドローンが代替する。これにより、作業員の安全を確保しつつ、足場の設置などが不要になるため、コストと時間を大幅に削減できる 19。
- 物流:山間部や離島などの過疎地域では、トラックによる配送が非効率で、いわゆる「買い物弱者」問題が深刻化している。ドローンは、こうした地域へ医薬品や食料品を届ける「ラストワンマイル配送」の新たな担い手として期待されている 21。
ドローン市場の成長を支えているのも、規制緩和である。2022年12月の改正航空法の施行により、操縦者の国家資格制度が創設されるとともに、一定の条件下で「レベル4飛行(有人地帯での目視外飛行)」が可能となった 85。これにより、都市部での物流など、ドローンの活用範囲が飛躍的に拡大した。さらに、補助者の配置や立看板の設置が不要となる「レベル3.5飛行」制度も導入され、事業化のハードルが引き下げられている 86。
7.3 人と技術の新たなフロンティア:AI・ロボット操作における人材ギャップ
しかし、ここには重大なパラドックスが存在する。人手不足を解決するために導入されるロボットやドローンといった先端技術が、今度はその技術を開発・導入・運用・保守できる高度なスキルを持つ人材の、新たな不足を生み出しているのである。
経済産業省の試算によれば、2040年にはAI・ロボット関連人材が326万人も不足すると予測されている 87。特に、従来の機械工学の知識と、AIやソフトウェアのプログラミング能力を併せ持つような「ハイブリッド人材」の不足は深刻であり、現在の産業界と教育システムにとって大きな課題となっている 21。
このロボットやドローンの導入は、単なる技術的な更新に留まらない。それは、企業のビジネスモデルそのものを変革する可能性を秘めている。例えば、ドローンを導入して自社のインフラ点検を行っていた建設会社が、その過程で蓄積したノウハウとデータを活用し、他社に対して「点検サービス」を提供するようになる 82。これは、一回限りの「製品」販売から、継続的な収益を生む「サービス(X as a Service)」提供へとビジネスモデルを転換することを意味する。この転換こそが、先端技術を真にマスターした企業が手にする最大の果実であり、新たな競争優位の源泉となるのである。
第8章 結論と戦略的提言
8.1 主要な分析結果の統合:新たな競争環境
本レポートの分析を通じて、日本の先端製造業が、不可避な人口動態と経済構造の変化によって、強制的かつ急速な進化の過程にあることが明らかになった。この変革は、業界の競争環境を根本的に再定義している。
数十年にわたり日本企業の強みとされてきた、終身雇用を前提とした人材育成、現場主導の漸進的な改善(カイゼン)、そしてデフレ下でのコスト削減といった従来の成功モデルは、もはや有効性を失いつつある。代わりに求められるのは、市場の変化に迅速に対応する俊敏性(アジリティ)、データとAIを駆使する技術力、そして業界の垣根を越えた戦略的な合従連衡である。
その結果、業界内には明確な分断線が引かれつつある。一方には、M&AやDXを駆使してこの構造変化に能動的に適応し、新たな成長機会を掴む企業群が存在する。他方には、旧来のビジネスモデルに固執し、コスト増と人材枯渇の波に飲まれ、衰退あるいは淘汰されていく企業群が存在する。この二極化は、今後ますます鮮明になっていくだろう。
8.2 企業経営層への戦略的必須事項
この新たな競争環境を勝ち抜くため、企業経営層は以下の戦略的行動を喫緊の課題として実行する必要がある。
- M&Aを戦略的ツールとして活用する:技術、人材、市場アクセスを迅速に獲得するための手段として、M&Aを積極的に検討すべきである。また、中小企業にとっては、大手企業の傘下に入ることで事業の継続と成長を確保することも、重要な戦略的選択肢となる。
- 人事部門を戦略機能へと昇格させる:人材を単なる「資源」ではなく、最も重要な「資本」と位置づけ、その獲得・育成・定着に経営資源を重点的に投下する。企業の魅力を高める採用ブランディング、全社的なリスキリング・プログラムの構築、そして多様な人材が最大限の能力を発揮できるインクルーシブな職場環境の整備は、もはや人事部門だけの仕事ではなく、経営トップが主導すべき最重要課題である。
- 実践的なDXを優先する:特に中小企業においては、壮大な構想よりも、現場の具体的な課題を解決するDXプロジェクトを優先すべきである。例えば、人手のかかる検査工程の自動化や、紙ベースの管理業務のデジタル化など、明確な投資対効果(ROI)が見込める領域からスモールスタートし、成功体験を積み重ねながら全社へと展開していくアプローチが有効である。
- ビジネスモデルを再評価する:単に優れた「モノ(製品)」を売るだけでなく、保守、運用、データ解析といった「コト(サービス)」を組み合わせ、顧客に包括的なソリューションを提供するビジネスモデルへの転換を図る。テクノロジーを活用して、継続的な収益を生む新たなストリームを構築することが、収益性の向上に不可欠である。
- 強靭なサプライチェーンを構築する:地政学的リスクや自然災害など、予期せぬ混乱に対する耐性を高めるため、サプライチェーン全体を再評価する。特定の国や地域への過度な依存を見直し、国内生産と海外生産のバランスを取るなど、より安定的で多角的な供給網を構築することが事業継続の鍵となる。
8.3 将来展望:産業変革の次なるフェーズを見据えて
本レポートで分析した現在の変革は、まだ序章に過ぎない。産業変革の次なるフェーズは、設計・開発から生産、保守に至るまで、製品ライフサイクル全体に生成AIが深く浸透し、人間とロボットがよりシームレスに協働し、そしてサプライチェーンが完全にデジタルで統合される時代となるだろう。
現在の困難な課題を乗り越え、変革を成功させた企業こそが、この次なる、より高度な技術が支配する製造業の時代をリードする資格を得る。その根底にある挑戦は、今も未来も変わらない。それは、絶えず変化する世界の中で、テクノロジー、人材、そして戦略をいかにして最適に組み合わせ、持続的な価値を創造していくかという、普遍的な経営の問いなのである。
引用文献
- 【2025年最新版】製造業の人手不足の原因や対策、取り組み事例 | お役立ち情報ナビ | DAIKO XTECH株式会社, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.daiko-xtech.co.jp/daiko-plus/production-control/manufacturing-industry-labor-shortage/
- 金属加工会社を資源高とインフレが直撃、生き残り策は? – 機械買取センター, 11月 2, 2025にアクセス、 https://kikaikaitori-center.com/2023/11/15/%E9%87%91%E5%B1%9E%E5%8A%A0%E5%B7%A5%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%92%E8%B3%87%E6%BA%90%E9%AB%98%E3%81%A8%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E3%81%8C%E7%9B%B4%E6%92%83%E3%80%81%E7%94%9F%E3%81%8D%E6%AE%8B/
- 相次ぐ弁当製造業の倒産… 破産の前にM&Aと事業再生で工場売却の検討を, 11月 2, 2025にアクセス、 https://ma-all.net/column/food-manufacturers_lunch-box_ma/
- 製造業における人手不足とは?現状・原因から対策・事例まで徹底解説 – Digital Library, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.nomura-system.co.jp/contents/%E8%A3%BD%E9%80%A0%E6%A5%AD%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E4%BA%BA%E6%89%8B%E4%B8%8D%E8%B6%B3%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%E7%8F%BE%E7%8A%B6%E3%83%BB%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E3%81%8B%E3%82%89%E5%AF%BE/
- 製造業(工場)の人手不足の原因と解決策, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.fiweek.jp/hub/ja-jp/blog/article02-iob.html
- 日本の産業機械製造業で深刻化する機械エンジニアの人材不足の実態と外国人機械エンジニアの活用 – Timedoor, 11月 2, 2025にアクセス、 https://jp.timedoor.net/blogs/%E7%94%A3%E6%A5%AD%E6%A9%9F%E6%A2%B0%E8%A3%BD%E9%80%A0%E6%A5%AD%E3%81%AE%E6%A9%9F%E6%A2%B0%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B8%E3%83%8B%E3%82%A2%E4%BA%BA%E6%9D%90%E4%B8%8D%E8%B6%B3/
- 製造業界の人手不足はどう解決できるのか?原因と共に解説 – ビジネストレンド – ブラザー, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.brother.co.jp/product/biz/business-navi/column/product-logistic/use36/index.aspx
- 工作機械業界の今後の見通しは?最新の動向や将来性を解説 – PEAKS MEDIA, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.peaks-media.com/9384/
- 価格転嫁・官公需等の取引適正化 – 内閣官房, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/kaigi/dai32/shiryou1.pdf
- 価格転嫁・取引適正化対策の 最近の動きと今後の方針, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/katsuryoku_kojyo/katsuryoku_kojyo_wg/dai7/siryou2.pdf
- 価格転嫁に関する実態調査(2025年2月) – 帝国データバンク, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tdb.co.jp/report/economic/20250317-pricepass-on/
- 「自動車業界」サプライチェーン動向調査(2025年7月) – 帝国データバンク, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tdb.co.jp/report/economic/20250714-automotive-sc/
- 工作機械工業 収益状況集計 (2023年度 通期), 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.jmtba.or.jp/wjmtbap/wp-content/uploads/2024/05/73f862ec16c9bf5b58f3c10c690937c7.pdf
- 我が国工作機械産業の競争力強化に 関するルール形成戦略に係る調査, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2023FY/000282.pdf
- 産業用ロボット市場規模・シェア|業界レポート、2032年 – Fortune Business Insights, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.fortunebusinessinsights.com/jp/%E6%A5%AD%E7%95%8C-%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88/%E7%94%A3%E6%A5%AD%E7%94%A8%E3%83%AD%E3%83%9C%E3%83%83%E3%83%88%E5%B8%82%E5%A0%B4-100360
- 産業用ロボット市場シェアの最新動向と主要メーカーの競合分析, 11月 2, 2025にアクセス、 https://kibo-robo.jp/industrial-robot-market-share-analysis/
- 日本の産業用ロボット市場規模は2033年に2710百万米ドルを突破|CAGR:9.8%の成長, 11月 2, 2025にアクセス、 https://newscast.jp/news/7867914
- 未来を担うサービスロボット市場のポテンシャルは? – 三菱総合研究所, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mri.co.jp/knowledge/column/20250909.html
- ドローンの活用事例を分野別に紹介!今後に期待が高まるその魅力とは – BUD International, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.bud-international.co.jp/column/drone-use-cases/
- ドローンによる業務革新と未来の展望|be CONNECTED. – KDDI法人サイト, 11月 2, 2025にアクセス、 https://biz.kddi.com/beconnected/feature/2025/250422/
- ドローンビジネスの急成長を支える複合要因と今後の展望|理系大学生の日常 – note, 11月 2, 2025にアクセス、 https://note.com/son_jon/n/n3e64686a9017
- 製造業・商社業界で進行する業界再編|船井総合研究所, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.funaisoken.co.jp/press/22734
- 【2025】工作機械業界のM&A動向と最新事例を紹介!現状と今後の課題は?, 11月 2, 2025にアクセス、 https://masouken.com/%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E6%A9%9F%E6%A2%B0%E6%A5%AD%E7%95%8C%E3%81%AEM&A%E5%8B%95%E5%90%91
- 精密部品製造業界のM&A・事業承継の動向!事例や案件例・注意点も解説, 11月 2, 2025にアクセス、 https://mastory.jp/%E7%B2%BE%E5%AF%86%E9%83%A8%E5%93%81%E8%A3%BD%E9%80%A0%E3%81%AEM&A
- 【2025年】M&A業界の動向を解説!業界別の動向や今後の展望について解説 – CINC Capital, 11月 2, 2025にアクセス、 https://cinc-capital.co.jp/column/ma/comparison/ma-industry
- 工作機械業界M&A活性化。再編の動きは? – 機械買取センター, 11月 2, 2025にアクセス、 https://kikaikaitori-center.com/2023/10/27/%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E6%A9%9F%E6%A2%B0%E6%A5%AD%E7%95%8Cma%E6%B4%BB%E6%80%A7%E5%8C%96%E3%80%82%E5%86%8D%E7%B7%A8%E3%81%AE%E5%8B%95%E3%81%8D%E3%81%AF%EF%BC%9F/
- 【工作機械】止まぬニデック旋風、盟主のDMG森精機は8年ぶり買収 …, 11月 2, 2025にアクセス、 https://maonline.jp/articles/nidek_takisawa_dmgmori_202309
- 工作機械業界におけるM&Aの動向と今後の展望, 11月 2, 2025にアクセス、 https://ma-shoukei.com/colmun/eGEPj41c
- 倒産件数は834件 31カ月連続で前年同月を上回る2024年累計は11月時点で2015年以降で最多に – PR TIMES, 11月 2, 2025にアクセス、 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000984.000043465.html
- ニデックが「同意なきTOB」も辞さないTAKISAWAとは何者か – 四季報オンライン, 11月 2, 2025にアクセス、 https://shikiho.toyokeizai.net/news/0/688517
- 企業価値の最大化に向けた経営統合に関する意向表明書, 11月 2, 2025にアクセス、 https://nidec.g.kuroco-img.app/v=1737507616/files/topics/8105_ext_2_0.pdf
- 「同意なき」TOBは増加するか――ニデックのTAKISAWA買収提案に考える – Globis学び放題, 11月 2, 2025にアクセス、 https://globis.jp/article/58190/
- 日本の製造業において加速する国内回帰 その背景にある変化と課題とは? – EMS, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.willtecgroup-ems.jp/column/reshoring/
- 供給網強化としてのフレンド・ショアリングの動向と 日本企業への影響 – 財務省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mof.go.jp/pri/research/seminar/fy2023/lm20230414.pdf
- 製造業の設備投資動向【最新版】日本のトレンドと今後の見通し | CANARIS(カナリス), 11月 2, 2025にアクセス、 https://canaris.jp/post-3510
- 【2025年最新】M&A業界の特徴と今後の動向!業界に将来性はあるのか | M&A・事業承継コラム, 11月 2, 2025にアクセス、 https://ma-navigator.com/columns/ma-industry
- 人材の確保・定着に成功した 企業の取組事例集 – 厚生労働省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mhlw.go.jp/content/001474492.pdf
- 製造業の採用課題を解決!6つの具体的アプローチと成功事例 – note, 11月 2, 2025にアクセス、 https://note.com/toru1960/n/n29152df66e05
- リスキリング事例14選!国内外の企業の取り組みまとめ | Reskilling.com(リスキリングドットコム), 11月 2, 2025にアクセス、 https://reskilling.com/article/9/
- リスキリングの導入事例6選|取り組みの効果や導入すべき企業とは, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.persol-group.co.jp/service/business/article/12215/
- 製造業のリスキリングとは? リカレント教育・生涯教育との違い、目的、メリット、導入ステップ、事例を紹介 – スキルノート, 11月 2, 2025にアクセス、 https://skillnote.jp/knowledge/reskilling-toha/
- 生産性を向上させる戦略とは?製造業の成功事例を紹介 – 株式会社タナカサトル技術支援, 11月 2, 2025にアクセス、 https://ts-techsup.co.jp/seisansei-seizou-jirei/
- 【製造業DXで人手不足対策】現場の自動化と人員配置の最適化とは? – フツパー, 11月 2, 2025にアクセス、 https://hutzper.com/genba-dx/manufacturing-dx-labor-shortage-automation/
- 令和6年度群馬県DX人材リスキリング推進事業 取組事例集, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.pref.gunma.jp/uploaded/attachment/664469.pdf
- 製造業で大注目のリスキリングとは?スキルの再開発で得られる効果, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.nikken-totalsourcing.jp/business/tsunagu/column/3550/
- ロボット産業ビジョン2050, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.jara.jp/publications/img/vision/visionver0_booklet.pdf
- 製造業界における外国人材の活用事例とそのメリット:人手不足解消と成功要因, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.vnservice.co.jp/%E8%A3%BD%E9%80%A0%E6%A5%AD%E7%95%8C%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E6%9D%90%E3%81%AE%E6%B4%BB%E7%94%A8%E4%BA%8B%E4%BE%8B%E3%81%A8%E3%81%9D%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%88%EF%BC%9A%E4%BA%BA%E6%89%8B%E4%B8%8D%E8%B6%B3%E8%A7%A3%E6%B6%88%E3%81%A8%E6%88%90%E5%8A%9F%E8%A6%81%E5%9B%A0
- 国内製造業に広がる高度外国人材の活用事例1 – 日本語オンラインスクール, 11月 2, 2025にアクセス、 https://nihongo-jinzai.com/column-page/column110/
- 製造業における 特定技能外国人材受入れ事例, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.sswm.go.jp/assets/img/top/ukeire_jirei.pdf
- 外国人労働者が働きやすい 工夫をしている企業事例集 – 宮崎県, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.pref.miyazaki.lg.jp/documents/70093/70093_20240726154119-1.pdf
- 外国人の活用好事例集, 11月 2, 2025にアクセス、 https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/3006251325-4.pdf
- 超人手不足時代における中小企業の自動化戦略、知っておきたい「補助金」活用法 – ビジネス+IT, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.sbbit.jp/article/st/146533
- アンケートと事例にみる 中小製造業のリスキリングの実態 – 日本政策金融公庫, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.jfc.go.jp/n/findings/pdf/soukenrepo_24_12_20.pdf
- 倒産集計 2025年 1月報 – 帝国データバンク, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tdb.co.jp/report/bankruptcy/aggregation/foi_6xmbg0q/
- 倒産集計 2024年度報(2024年4月~2025年3月) – 帝国データバンク, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tdb.co.jp/report/bankruptcy/aggregation/g2-5yfk9w/
- 製造業の倒産が120件超え!企業の倒産が増える背景・対策・将来予想を解説 | キャド研, 11月 2, 2025にアクセス、 https://cad-kenkyujo.com/seizougyou-tousan/
- 倒産集計 2025年度上半期(4月~9月) – 帝国データバンク, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tdb.co.jp/report/bankruptcy/aggregation/20251008-bankruptcyh1fy2025/
- 倒産集計 2025年 8月報 – 帝国データバンク, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tdb.co.jp/report/bankruptcy/aggregation/20250908-bankruptcy202508/
- 破綻リスクの高い製造業を見抜く!【令和7年 最新情報付き】 – 株式会社Gron, 11月 2, 2025にアクセス、 https://gron.co.jp/tosan-company/
- 変化への対応 工作機械の名門 株式会社池貝の変遷と富士フイルムを襲ったデジタル化, 11月 2, 2025にアクセス、 https://ilink-corp.co.jp/2271.html
- ロボットは人の仕事を奪う? ~産業ロボットの歴史と最新のロボット技術, 11月 2, 2025にアクセス、 https://ilink-corp.co.jp/6847.html
- 【2025】国内工作機械メーカーランキングを紹介!業界の現状や今後の動向も徹底分析!, 11月 2, 2025にアクセス、 https://smart-factory-kenkyujo.com/kousakukikai-ranking/
- 人手不足解消の切り札! 自動化とロボットの可能性を探る – バロ電機工業株式会社, 11月 2, 2025にアクセス、 https://valo-e.com/column/article516/
- 製造業のDX事例とは?製造業のDX事例の成功例・失敗例とポイント – ZAICO, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.zaico.co.jp/zaico_blog/dx-examples-in-the-manufacturing-industry/
- 製造業DXの事例を徹底解説|成功企業に学ぶ取り組みのポイントとは? – ものづくり研究所, 11月 2, 2025にアクセス、 https://monoken.yamazen.co.jp/blog/articles/smart-factorygiken/manufacturing-dx-cases
- 【中小企業DX】DXを進めやすい業務と具体的なステップ、成功事例について解説 – BizRobo!, 11月 2, 2025にアクセス、 https://rpa-technologies.com/insights/dx_smaller-companies/
- スマートファクトリーの成功事例を紹介!実現までのロードマップも解説 – リコージャパン, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.ricoh.co.jp/service/digital-manufacturing/media/article/detail42
- スマートファクトリーとは?工場はどう変わる?失敗しない導入方法を事例付きで解説, 11月 2, 2025にアクセス、 https://smartf-nexta.com/archives/12256
- 【事例あり】製造業DXが進まない理由とは?経済産業省のガイドラインについても解説!, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.fact-cam.co.jp/document/column/archives/000974.html
- 製造業DXとは?重要性や導入方法・よくある課題【事例あり】 | 記事一覧 | 法人のお客さま, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.persol-group.co.jp/service/business/article/11817/
- 愛知県の町工場がAIで世界へ!驚きの業務効率化事例 – 【公式】株式会社ライノテック, 11月 2, 2025にアクセス、 https://rhinotech.jp/ai/%E6%84%9B%E7%9F%A5%E7%9C%8C%E3%81%AE%E7%94%BA%E5%B7%A5%E5%A0%B4%E3%81%8Cai%E3%81%A7%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%B8%EF%BC%81%E9%A9%9A%E3%81%8D%E3%81%AE%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%8A%B9%E7%8E%87%E5%8C%96%E4%BA%8B/
- 多品種少量生産の効率化を実現する9つの方法|成功事例から学ぶIoT/AI活用術, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.sellbot.jp/column/tahinsyusyoryo/
- スマートファクトリーとは?DXとの違いや事例を簡単にわかりやすく説明 – リコージャパン, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.ricoh.co.jp/service/digital-manufacturing/media/article/detail29
- 製造業界のスマートファクトリー導入!現状の課題と導入事例、活用のポイントを紹介 – iot-mos, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.iot-mos.jp/column/2025/05/722/
- 持続可能な産業化を実現するスマートファクトリーとは?SDGs目標9達成に向けた取り組み事例を交えて解説, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.melsc.co.jp/business/column/details/sng16/
- スマートファクトリーとは?製造業で導入するメリットや課題、事例を紹介 – 関西電力, 11月 2, 2025にアクセス、 https://sol.kepco.jp/useful/aircontrol/w/smartfactory/
- 日本のロボット技術戦略とは?新たに求められている注目分野も紹介! – AGRIST, 11月 2, 2025にアクセス、 https://agrist.com/archives/1837
- ロボットで人手不足を解消|ロボットの種類、導入するメリット・デメリットも解説, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.usen-almex.jp/blog/all-20250128-alm.html
- 機能安全活用実践マニュアル-ロボットシステム編 – 厚生労働省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/0000197860.pdf
- 経済産業省、AIロボット国家戦略を公表 人手不足解消へ多用途化支援 | Plus Web3 media, 11月 2, 2025にアクセス、 https://plus-web3.com/media/latestnews_1000_5688/
- ロボット (METI/経済産業省), 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/robot/index.html
- 【2025年版】ドローン新規事業の基礎知識と成功のポイント | 株式会社koujitsu, 11月 2, 2025にアクセス、 https://koujitsu.co.jp/blogs/new-business-drone/
- ドローン社会実装に向けた日本の現状と課題 – GLAVIS(グラビス)グループ, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.glavis-hd.com/social_problem/000417/
- 自治体によるドローンの活用事例集 – 中部経済産業局, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.chubu.meti.go.jp/b21jisedai/info_2023/20240312/jirei_202403.pdf
- 【2025年】ドローンの法改正(航空法改正)と今後伸びる業界・職種, 11月 2, 2025にアクセス、 https://agekke-drone.co.jp/column/2874/
- ドローン規制緩和の全貌|レベル3.5飛行と国家資格で変わる未来 – テックジム, 11月 2, 2025にアクセス、 https://techgym.jp/column/draone/
- 2040年、日本でAI・ロボット関連人材が326万人不足へ 経産省が就業構造の将来試算を公表, 11月 2, 2025にアクセス、 https://ledge.ai/articles/ai_robot_workforce_gap_2040
- ロボット新戦略から10年 〜日本のロボット産業は次の10年をどう戦うのか〜 – RoboStep, 11月 2, 2025にアクセス、 https://robo.japanstep.jp/learn/2025/04/893/
- ドローンビジネスをする際の勝ち筋とは?市場動向、将来性など, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.accelainc.com/archives/10269