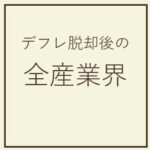岸田政権と高市政権により日本の防衛費は対GDP比で2%に増額されます。
防衛費の増額は確実に国内需要増大に結びつきます。
今回は、Gemini Deep Research に、防衛費増額の日本経済への影響をリサーチしてもらいました。
生成AIの回答をそのまま掲載します。
生成AIにはハルシネーションの問題があり、その解答には間違いが含まれている可能性があることは、常識として踏まえて、この記事を読んでください。
日本の防衛費は長らく対GDP比1%未満で抑制されてきましたが、岸田政権のときに5年で43兆円と実質対GDP比1.8%程度に押し上げられ、現在の高市政権でさらに対GDP比2%まで押し上げられることになりそうです。
既に防衛費は毎年段階的に増額されています。
この防衛費増額により日本のマクロな需要は増加するはずです。
実際のところ、どの産業でどのような需要の増加が起こっているのか、リサーチしてください。
また、防衛費増額により、日本の産業界と雇用にどのような影響が起きているのかも調べてください。
また、需要増加以外に防衛費増額による負の影響についても同時に調べて欲しいです。
最後に総合的に防衛費増額が日本の経済に与える影響を纏めてください。
構造的転換期にある日本の防衛経済:GDP比2%目標がもたらすマクロ経済と産業基盤へのインパクト分析
エグゼクティブ・サマリー:戦後最大の産業構造改革と「超過需要」の時代
日本経済は現在、戦後安全保障政策の根幹であった「防衛費対GDP比1%枠」の撤廃に伴い、歴史的な構造転換の只中にある。長らく「抑制」と「停滞」の代名詞であった防衛産業は、岸田政権による「安保3文書」の改定、そして後継となる高市政権によるGDP比2%目標の前倒し達成方針により、かつてない「需要の奔流」に直面している。2023年度から始まった5年間で総額43兆円という防衛力整備計画は、単なる政府支出の増加にとどまらず、重工業、航空宇宙、サイバーセキュリティ、そしてデュアルユース(民生軍事両用)技術を持つスタートアップ企業群をも巻き込んだ、巨大な産業政策としての側面を帯びている。
本レポートは、急速に拡大する防衛支出が日本のマクロ経済、産業構造、労働市場、そして財政に与える影響を包括的に分析したものである。リサーチの結果、浮き彫りになったのは以下の主要なトレンドである。
- 「超過需要」時代の到来と供給制約:
防衛省による発注額が国内産業の生産能力を上回る「超過需要(Excess Demand)」の状態が恒常化しつつある。これにより、三菱重工業(MHI)や川崎重工業(KHI)などのプライム企業(主契約企業)は過去最高水準の受注残高を抱え、設備投資(CAPEX)と研究開発(R&D)を加速させている。 - 利益構造の構造的改善:
従来、日本の防衛産業は「低収益・高リスク」なビジネスと見なされ、撤退が相次いでいた。しかし、防衛装備庁による利益率算定方式の見直しや、企業の予見可能性を高める長期契約の導入により、重工各社の防衛セグメントにおける利益率は構造的に改善し、株主価値に貢献する「成長ドライバー」へと変貌を遂げた。 - デジタル・トランスフォーメーション(DX)とサイバー領域の民需波及:
「能動的サイバー防御」の導入に伴い、防衛省は従来の閉域網主義から脱却し、AWSやMicrosoft等のパブリック・クラウド活用へと舵を切った。これは国内のシステムインテグレーター(NEC、富士通)やクラウド事業者(さくらインターネット)に新たな特需をもたらすと同時に、日本全体のセキュリティ水準を底上げする波及効果を生んでいる。 - 「人」という最大のボトルネック:
資金と設備への投資が加速する一方で、自衛隊の採用難と産業界のエンジニア不足は深刻な「壁」となっている。少子化による構造的な労働力不足は、無人機(ドローン)や省人化技術への投資を「選択」ではなく「必須」のものとしており、これがロボティクス産業への強制的なイノベーション圧となっている。
本稿では、高市政権下で加速する防衛費増額の行方と、それがもたらす「光」と「影」を、最新の財務データと政策動向に基づき詳らかにする。
第1章 戦略的マクロ環境:地政学リスクと「高市ドクトリン」
日本の防衛費増額は、単発的な景気対策ではなく、不可逆的な地政学的要請に基づく構造変化である。欧州におけるロシアのウクライナ侵攻と、インド太平洋における中国・北朝鮮の軍事的圧力の増大は、ユーロ・アトランティックとインド太平洋の安全保障が不可分であることを日本に認識させた1。
1.1 岸田路線から高市路線への加速
2022年末に策定された「国家安全保障戦略」等3文書は、2027年度までに防衛費をGDP比2%に引き上げることを定めた。しかし、新たに発足した高市政権はこのタイムラインをさらに前倒しする姿勢を鮮明にしている。高市首相は所信表明において「対GDP比2%水準を今年度中に前倒しして措置を講ずる」と断言し、国際社会に対しても日本の防衛力強化の意思を強く発信している2。
この「前倒し」政策は、産業界に対して以下の2つの強力なシグナルを送っている。
- 予見可能性の確立:予算の単年度主義による弊害を打破し、複数年度にわたる巨額投資が可能であることを企業に確約した。
- 即応性の要求:装備品の調達スケジュールが圧縮されることで、サプライチェーン全体に対し、急速な増産体制の構築を迫っている3。
1.2 43兆円の配分と重点投資分野
5年間で43兆円とされる防衛力整備計画の予算は、全方位的にばら撒かれるわけではない。防衛省は7つの重点分野を定義しており、産業界の需要はこの7分野に集中している4。
表1: 防衛力整備計画における7つの重点分野と産業的含意
| 重点分野 | 主要な装備・施策 | 恩恵を受ける主要産業 |
|---|---|---|
| スタンド・オフ防衛能力 | 12式地対艦誘導弾能力向上型、トマホーク | 誘導機器、航空宇宙、推進システム |
| 統合防空ミサイル防衛 | イージス・システム搭載艦、PAC-3 | 造船、レーダー、電子機器 |
| 無人アセット防衛能力 | 各種ドローン(空・海・水中) | ロボティクス、AI、通信 |
| 領域横断作戦能力 | 宇宙、サイバー、電磁波 | 衛星、ITサービス、クラウド |
| 指揮統制・情報関連機能 | クラウド基盤、AI分析 | ソフトウェア、データセンター |
| 機動展開能力 | 輸送機、輸送船舶 | 重機、自動車、造船 |
| 持続性・強靱性 | 弾薬備蓄、施設の地下化・強靱化 | 化学(火薬)、建設、素材(特殊鋼) |
特に注目すべきは、従来の「正面装備(戦闘機や戦車)」だけでなく、「持続性・強靱性(弾薬や部品の備蓄)」や「無人アセット」への配分が大幅に増加している点である。これは、有事における継戦能力(サステナビリティ)が重視され始めたことを意味し、消耗品や維持整備(MRO)市場の拡大を示唆している。
第2章 「超過需要」時代の到来と産業構造の転換
日本の防衛産業は長らく「冬の時代」にあった。防衛費の伸び悩みと輸出規制により、市場規模が限定的であったため、大手企業ですら防衛部門を縮小し、中小のサプライヤーは相次いで撤退した5。しかし、2024年から2025年にかけて、その状況は一変した。
2.1 「需要不足」から「供給不足」へ
現在の防衛産業における最大の課題は、発注がないことではなく、**「作れないこと」**である。急激な予算増額により、企業の生産キャパシティを超える発注が殺到する「超過需要(Excess Demand)」の状態が発生している。
シンクタンクの分析によれば、この需要急増は成長の機会であると同時に、余剰生産能力の欠如という新たな構造的課題を露呈させている5。企業は生産ラインの増設や人員の確保に奔走しているが、熟練工の不足や部材の納期遅延がボトルネックとなり、バックログ(受注残)が積み上がる事態となっている。
2.2 利益率の構造的改善メカニズム
特筆すべき変化は、防衛ビジネスの「収益性」である。かつて防衛省の契約は厳格な原価計算に基づいており、企業の営業利益率は数%程度に抑えられていた。開発リスクを企業が負うケースも多く、赤字プロジェクトも珍しくなかった。
しかし、政府は「防衛生産・技術基盤強化法」等の法的枠組みを通じ、企業の利益率(マージン)を最大15%程度まで許容する新たな算定方式を導入しつつある。
- インセンティブ契約:コスト削減努力や納期短縮に対し、インセンティブ報酬を支払う仕組みの導入。
- 長期契約の活用:一括調達によるコスト低減と、企業の予見可能性向上。
この政策転換により、防衛部門は「お荷物」から「稼ぎ頭」へと変貌しつつある。実際、MHIやIHIの決算において、防衛セグメントの増益要因として「マージンの改善」や「価格転嫁の進展」が明記されるようになったことは、この構造変化の証左である6。
2.3 市場規模の拡大予測
市場調査レポートによると、日本の防衛市場規模は2025年の433億ドルから、2030年には489億ドルへと成長し、年平均成長率(CAGR)は約2.5%で推移すると予測されている8。一見緩やかな成長に見えるが、これは既存の装備品の維持費等を含んだ全体数値であり、宇宙関連支出(CAGR 7.1%)やサイバーセキュリティ分野など、特定領域では爆発的な成長が見込まれている8。
第3章 セクター別詳細分析 I:重厚長大産業(プライム企業)の復活
防衛費増額の最大の受益者は、やはり「防衛プライム」と呼ばれる重工業グループである。三菱重工業(MHI)、川崎重工業(KHI)、IHIの「重工3社」は、防衛省からの受注の大部分を占め、そのサプライチェーンの頂点に君臨している。
3.1 三菱重工業(MHI):国家防衛の要石
三菱重工業は、陸・海・空・宇宙の全領域において主要装備品を手掛ける、まさに日本の防衛産業の盟主である。同社の2025年度上期(2025年4月-9月)の決算は、防衛事業の力強い拡大を如実に示している。
- 財務パフォーマンス:
航空・防衛・宇宙(ADS)セグメントの売上収益は、前年同期比で1,071億円増の5,388億円となった10。これは、豊富な受注残高の着実な消化によるものである。事業利益についても、前年同期比163億円増の603億円と大幅な増益を達成した10。 - 受注動向の質的変化:
受注高自体は前年同期比で減少している(▲2,570億円)が、これは前年度にスタンド・オフ・ミサイルなどの大型案件(数年分の一括契約)が計上された反動(High Base Effect)に過ぎない6。実質的な事業活動は拡大基調にあり、通期見通しでは全社で6兆1,000億円の受注を見込んでいる11。 - 戦略的プロジェクト:
MHIは、12式地対艦誘導弾能力向上型や極超音速誘導弾などの「反撃能力」の中核を担うほか、次期戦闘機(GCAP)の開発主体でもある。これらのプロジェクトは今後10年以上にわたり安定的な収益をもたらすことが確定している。
表2: 三菱重工業(MHI)航空・防衛・宇宙セグメント業績推移(単位:億円)
| 指標 | 2024年度上期 | 2025年度上期 | 前年同期比 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 受注高 | 8,021 | 5,450 | ▲2,570 | 前年度の大型一括受注の反動減 |
| 売上収益 | 4,317 | 5,388 | +1,071 | 受注残の順調な消化 |
| 事業利益 | 440 | 603 | +163 | 利益率改善と増収効果 |
(出典: 10)
3.2 川崎重工業(KHI):海洋と航空の覇者
川崎重工業もまた、防衛特需の恩恵を享受している。特に、海上自衛隊の潜水艦建造と、P-1哨戒機、C-2輸送機の製造が主力である。
- 在庫の積み増しと将来需要:
KHIの財務諸表において特徴的なのは、航空宇宙システムセグメントにおける「棚卸資産(在庫)」の増加傾向である13。一般製造業において在庫増はリスクとされる場合があるが、防衛産業においては、将来の売上計上が確約された「仕掛品(Work in Progress)」の増加を意味し、生産活動の活発化を示唆している。 - 上方修正:
同社は2025年度の受注見通しを、防衛省およびボーイング向けの需要増を理由に300億円上方修正した13。 - 新領域への進出:
KHIは、無人ヘリコプター「K-RACER」による物資輸送の実証実験を成功させており、将来的な無人補給機としての採用を狙っている14。また、2025年10月には最新鋭潜水艦「そうげい」が進水し、MHIとの複社体制による潜水艦隊増強(22隻体制)を支えている15。
3.3 IHI:推進システムと宇宙への飛躍
IHIは、航空エンジンとロケット推進系における圧倒的なシェアを持つ。
- 過去最高益の更新:
航空・宇宙・防衛事業領域は、民間航空エンジンのスペアパーツ需要の回復と、防衛案件の採算性向上により、売上・利益ともに過去最高水準で推移している7。 - 見通しの引き上げ:
2025年度第2四半期時点で、防衛システムおよび原子力関連の拡大を背景に、受注高見通しを600億円上方修正した16。 - 次期戦闘機エンジン:
日英伊共同開発の次期戦闘機(GCAP)において、エンジン開発の中核を担うことは、同社の技術基盤維持と長期的な収益確保にとって決定的に重要である。
第4章 セクター別詳細分析 II:火力、素材、サプライチェーンの強靱化
プライム企業だけでなく、その下支えとなる素材・部品メーカーや、弾薬・火器を製造する企業群にも「静かなるブーム」が訪れている。ウクライナ戦争の教訓は、「継戦能力(Sustainability)」の重要性を再認識させ、弾薬備蓄や稼働率向上への投資を急拡大させた。
4.1 日本製鋼所(JSW):火力の復権
日本製鋼所(JSW)は、戦車砲や艦艇用火砲の砲身を製造できる国内唯一の企業であり、世界的に見ても希少な技術力を持つ。
同社は2025年3月期の防衛関連機器の受注高が、前期比440億円増の1,145億円に達する見通しであると発表した17。これは前年比で約60%増という驚異的な伸びであり、155mm榴弾砲や艦載砲などの「火力」に対する需要が、備蓄積み増しのために爆発的に増えていることを示している。
4.2 弾薬と誘導弾のサプライチェーン
防衛力整備計画では、弾薬の取得費だけで5年間で約2兆円が計上されている。
- スタンド・オフ・ミサイル:12式地対艦誘導弾能力向上型や、島嶼防衛用高速滑空弾の開発・量産が進められており、これに関連する推進薬、誘導装置、複合材のメーカーへの波及効果は大きい4。
- サプライチェーン支援:防衛省は、防衛産業からの撤退を防ぐため、サプライチェーン強化やサイバーセキュリティ対策を行う企業に対して財政的支援を行う制度を整備している5。これにより、これまで採算が合わずに撤退を検討していた特殊鋼メーカーや精密加工業者が、事業継続へと舵を切るケースが出ている。
第5章 セクター別詳細分析 III:デジタル・サイバー領域のパラダイムシフト
ハードウェア(装備品)以上に劇的な変化が起きているのが、ソフトウェアとネットワークの領域である。防衛省は「クラウド・バイ・デフォルト」の方針を打ち出し、防衛ITインフラの抜本的な近代化を進めている。
5.1 ガバメント・クラウドと「メガクラウド」の導入
かつて自衛隊のシステムは、インターネットから物理的に遮断された「クローズド・ネットワーク」が原則であった。しかし、情報共有の遅れやコスト高を解消するため、防衛省はAWS(Amazon Web Services)、Microsoft、Googleといった米国の「メガクラウド」の導入を決定した18。
これは、米国のJEDI(現JWCC)プロジェクトに追随する動きであり、日米の相互運用性(インターオペラビリティ)を高める狙いがある。
5.2 国内ITベンダーの勝機と「ソブリン・クラウド」
メガクラウドの採用は、国内ITベンダーにとって脅威であると同時に、巨大なシステムインテグレーション(SI)の機会でもある。
- NEC・富士通の役割:航空自衛隊のクラウドシステム構築において、NECは「共通サービス(約30億円)」や「指揮統制サービス(約67億円)」を、富士通は「指揮管理通信サービス」を受注している19。彼らはメガクラウドと自衛隊の独自要件を接続する重要な役割を担う。
- さくらインターネットの躍進:特筆すべきは、国産クラウドベンダーであるさくらインターネットが、防衛装備庁からサプライチェーン調査にかかる役務契約(約7.5億円)を獲得したことである20。安全保障上の理由から、機微なデータの一部を国産の「ソブリン・クラウド」で管理しようとする動きの表れであり、経済安全保障の観点からも注目される。
5.3 サイバーセキュリティ産業の底上げ
防衛産業のサプライチェーン全体に対し、米国防総省のCMMC(サイバーセキュリティ成熟度モデル認証)と同等のセキュリティ基準(NIST SP800-171等)の遵守が求められるようになっている。
これに対応するため、政府は「IT導入補助金2025」においてセキュリティ対策推進枠を設け、中小企業のサイバー対策を支援している21。これは、国内のサイバーセキュリティ・ベンダーやコンサルティング企業にとって、かつてない特需を生み出している。
第6章 イノベーション・エコシステム:スタートアップとデュアルユース
従来の防衛産業は「閉鎖的クラブ」であり、新規参入は極めて困難であった。しかし、AIやドローン技術の進化により、民生技術(デュアルユース)の取り込みが不可欠となり、政府はスタートアップの活用に本腰を入れている。
6.1 防衛産業参入の障壁撤廃
経済産業省と防衛装備庁は連携し、「デュアルユース・スタートアップのエコシステム構築」を進めている。具体的には、先端技術を持つスタートアップの情報をリスト化し、防衛プライム企業や防衛省とのマッチングを行う施策である22。
6.2 資金の流れの変化
- 安全保障技術研究推進制度:防衛装備庁による競争的資金制度(ファンディング)は、かつて学術界からの忌避感が強かったが、潮目は変わりつつある。令和7年度(2025年度)の新規採択課題は、応募総数340件に対し49件が採択され、過去数年と比較しても活発な応募状況が続いている23。
- リスクマネーの供給:VC(ベンチャーキャピタル)に対し、防衛関連スタートアップへの投資を促すためのネットワーク構築が進められており、ドローン、宇宙、新素材分野での資金調達環境が改善している。
第7章 人的資本の制約:最大のボトルネック
カネとモノへの投資が加速する一方で、「ヒト」の不足がこの防衛力整備計画のアキレス腱となっている。
7.1 自衛官採用の危機的状況
装備品がいかに高性能化しても、それを運用する自衛官がいなければ防衛力は発揮できない。しかし、自衛隊の採用環境は「危機的」を通り越して「崩壊的」である。
- 採用目標の未達:2023年度の採用達成率は過去最低の51%を記録した。2024年度は目標数を約4,700人引き下げたにもかかわらず、達成率は65%にとどまっている24。
- 将来推計:モンテカルロ・シミュレーションを用いた分析によれば、悲観的シナリオでは応募者数は年々減少し続けると予測されており、既存の部隊編成の維持すら困難になる可能性が高い25。
7.2 産業界における「人材獲得競争」
防衛産業界でも同様に、エンジニア不足が深刻化している。特に、サイバーセキュリティやAI開発に不可欠なIT人材は、2025年時点で約79万人が不足すると予測されている26。
防衛産業は、給与水準の高い外資系IT企業やフィンテック業界と人材を奪い合わなければならない。このため、各社は賃上げを余儀なくされており、これが調達コストの上昇(コストプッシュ・インフレ)圧力となっている。
7.3 「自動化」への強制適応
この労働力不足は、産業界に対し「無人化・省人化」への投資を強制するドライバーとなっている。防衛省が「無人アセット防衛能力」を重点分野に掲げるのは、戦術的な理由だけでなく、人口動態上の要請でもある。
これにより、自律型無人潜水機(UUV)や無人航空機(UAV)、さらには艦艇の省人化システム(クルーの削減)に対する技術開発需要は、今後10年間で加速度的に高まると予測される。
第8章 財政・経済リスクと今後の展望
最後に、この急速な防衛費増額が内包するマクロ経済リスクについて触れる。
8.1 財源問題:増税か国債か
43兆円、そしてその先の恒久的なGDP比2%維持のための財源議論は、依然として流動的である。岸田政権時代には法人税、所得税、たばこ税の増税が検討されたが、政治的な反発は根強い。
高市政権は、積極財政的なスタンスから、当面は国債(建設国債や特例公債)の発行で賄う可能性が指摘されている27。しかし、金利のある世界に戻りつつある日本において、巨額の国債発行は利払い費の増加を招き、将来的な財政硬直化のリスクを高める。
8.2 クラウディング・アウトとインフレ
政府による強力な需要創出は、民間部門のリソースを奪う「クラウディング・アウト」を引き起こす懸念がある。特に希少なIT人材や特殊鋼などの戦略物資が防衛部門に集中することで、民生部門のイノベーションや生産活動が阻害される可能性がある。
また、円安基調が続く中での海外装備品(F-35、トマホーク等)の大量調達は、輸入インフレを助長し、防衛予算の実質的な購買力を低下させるリスク(為替リスク)を常に孕んでいる1。
結論:持続可能な防衛経済圏の構築に向けて
日本の防衛産業は、高市政権下のGDP比2%目標により、かつてない「特需」と「構造改革」の時を迎えている。MHIをはじめとする重工各社は収益性を回復し、宇宙・サイバー領域では新たなプレイヤーが台頭している。
しかし、その成否は「人口減少」という抗い難い現実といかに折り合いをつけるかにかかっている。単に予算を増やすだけでなく、省人化技術への徹底的な投資と、民生技術を取り込んだイノベーション・エコシステムの構築こそが、日本の防衛経済を持続可能なものにする唯一の道である。
2025年は、日本が「普通の国」の防衛産業基盤を持てるかどうかの、歴史的な分岐点となるだろう。
レポート作成者: 主席研究員(防衛経済・地政学担当)
日付: 2025年11月(2025年度中間決算データに基づく分析)
引用文献
- Japan’s Defence Budget Surge: A New Security Paradigm – RUSI, 11月 22, 2025にアクセス、 https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/japans-defence-budget-surge-new-security-paradigm
- 【深掘り】高市早苗首相の政策~「防衛費」~「対GDP比2%を今年度中に前倒し措置」の内容とは?【サン!シャインニュース】 – YouTube, 11月 22, 2025にアクセス、 https://www.youtube.com/watch?v=6oQGq2gtcAw
- 「高市首相、防衛費を年内にGDPの2%へ引き上げる方針」 | Joongang Ilbo | 中央日報, 11月 22, 2025にアクセス、 https://japanese.joins.com/JArticle/340156?sectcode=A00&servcode=A00
- 防衛力抜本的強化の 進捗と予算, 11月 22, 2025にアクセス、 https://www.ssri-j.com/MediaReport/DocumentJPN/FY25Budget.pdf
- From Decline to Surge: The Defense Industry in the Era of Excess …, 11月 22, 2025にアクセス、 https://instituteofgeoeconomics.org/en/research/2025102402/
- Mitsubishi Heavy Industries Announces Order Intake, Revenue, and Profit Growth in Strong 1H FY2025, Raises Full-Year Order Intake and Revenue Guidance | Nasdaq, 11月 22, 2025にアクセス、 https://www.nasdaq.com/press-release/mitsubishi-heavy-industries-announces-order-intake-revenue-and-profit-growth-strong
- State of Operations | Company Management | Investor Relations | IHI Corporation, 11月 22, 2025にアクセス、 https://www.ihi.co.jp/en/ir/management/business_summary/
- Japan Defense Market Size, Growth Drivers, Trends Report 2025-2030 – Mordor Intelligence, 11月 22, 2025にアクセス、 https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/japan-defense-market
- Japan Aerospace & Defense Industry 2025-2033 Analysis: Trends, Competitor Dynamics, and Growth Opportunities, 11月 22, 2025にアクセス、 https://www.datainsightsmarket.com/reports/japan-aerospace-defense-industry-17813
- Mitsubishi Heavy Industries Announces Order Intake, Revenue, and Profit Growth in Strong 1H FY2025, Raises Full-Year Order Intake and Revenue Guidance, 11月 22, 2025にアクセス、 https://www.mhi.com/news/25110701.html
- Financial Results | Mitsubishi Heavy Industries, 11月 22, 2025にアクセス、 https://www.mhi.com/finance/library/result
- Aircraft, Defense & Space: FY2024 Financial Results | Mitsubishi Heavy Industries, 11月 22, 2025にアクセス、 https://www.mhi.com/finance/finance/performance/fy20244q/segment/ads.html
- Earnings call transcript: Kawasaki Heavy Industries Q2 2025 sees stock surge, 11月 22, 2025にアクセス、 https://www.investing.com/news/transcripts/earnings-call-transcript-kawasaki-heavy-industries-q2-2025-sees-stock-surge-93CH-4361521
- News of Aerospace Company | Kawasaki Heavy Industries, Ltd., 11月 22, 2025にアクセス、 https://global.kawasaki.com/en/corp/profile/division/aero/news.html
- Press Releases | Kawasaki Heavy Industries, Ltd., 11月 22, 2025にアクセス、 https://global.kawasaki.com/en/corp/newsroom/category/pressrelease/index.html
- Financial Results for Second Quarter FY2025 (IFRS) (For the Year Ended March 31, 2026) – IHI, 11月 22, 2025にアクセス、 https://www.ihi.co.jp/en/ir/library/statements/_cms_conf01/__icsFiles/afieldfile/2025/11/06/Financial_Results_2Q_FY2025_1.pdf
- 日本製鋼所 25年3月期 防衛関連機器の受注高 440億円増予測 – 日刊産業新聞, 11月 22, 2025にアクセス、 https://www.japanmetal.com/news-t20241115138976.html
- 米国防総省がAWSなど“メガクラウド”4社と契約 90億ドル規模 – ITmedia NEWS, 11月 22, 2025にアクセス、 https://www.itmedia.co.jp/news/articles/2212/08/news176.html
- 空自クラウドシステムで3社と契約 – 航空新聞社, 11月 22, 2025にアクセス、 https://www.jwing.net/news/1409
- さくらインターネット、防衛装備庁と約7.5億円の役務請負契約を締結, 11月 22, 2025にアクセス、 https://www.sakura.ad.jp/corporate/information/newsreleases/2024/07/01/1968216202/
- セキュリティ対策推進枠 – IT導入補助金, 11月 22, 2025にアクセス、 https://it-shien.smrj.go.jp/applicant/subsidy/security/
- デュアルユース・スタートアップ のエコシステム構築 … – 経済産業省, 11月 22, 2025にアクセス、 https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/aerospace/5_startup.pdf
- 防衛装備庁 : 安全保障技術研究推進制度(防衛省ファンディング), 11月 22, 2025にアクセス、 https://www.mod.go.jp/atla/funding/kadai.html
- 自衛官応募 2000人減/政府の募集強化効果なし – 日本共産党, 11月 22, 2025にアクセス、 https://www.jcp.or.jp/akahata/aik25/2025-06-17/2025061701_03_0.html
- 自衛隊の採用状況に関する分析 および予測・シミュレーション – レジリエンス協会, 11月 22, 2025にアクセス、 https://resilience-japan.org/wp/wp-content/uploads/2025/03/20250225_doc3.pdf
- 【2025年2月】IT人材不足を経済産業省が指摘。企業が今後取るべき対策を解説, 11月 22, 2025にアクセス、 https://overflow.co.jp/hr/4475
- 高市政権は最初の難関「防衛費増額」をどう賄うか?「GDP比2%」を前倒しで実現するやり繰りは, 11月 22, 2025にアクセス、 https://toyokeizai.net/articles/-/915767?display=b