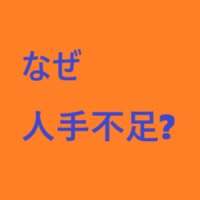この記事は、需給ギャップについて、Claude Sonnet4 に解説してもらったモノをそのまま掲載しています。 最初は自分で解説記事を書こうかと考えていましたが、Claudeの解説記事の方がずっと分かりやすいので、そのまま掲載しました。
この手の単純な知識の説明は、もう生成AIには敵わないですね。
そして、このように「AIに聞けば分かる」程度の事を知らない人は、恥を感じた方が良いと思います。
いまだに、日本は不景気だと思っている人は多く、闇バイトなどを「不景気のせいだ」と主張している人はまだ多いですよね。 日本の景気や人手不足の状況ぐらい、少しは自分でAIに質問して確認した方が良いと思います。
需給ギャップとは何か
まず、日常生活で考えてみましょう。人気のラーメン店があったとします。
需要:そのラーメンを食べたい人の数
供給:そのお店が実際に作れるラーメンの数
もしお客さんが100人来たいのに、お店が1日50杯しか作れなければ、50杯分の「需要超過」が生まれます。逆に、お客さんが30人しか来ないのに50杯作れるなら、20杯分の「供給超過」となります。
これと同じことが、国全体の経済でも起こります。それが「需給ギャップ」です。
経済全体での需給ギャップ
需要:国民全体がモノやサービスを買いたい総額
供給:国全体が実際に生産できるモノやサービスの総額
- 需要超過(インフレギャップ):欲しいものが生産量を上回る → 物価上昇
- 供給超過(デフレギャップ):生産量が需要を上回る → 物価下落、失業増加
なぜ生産能力に限界があるのか
ここで重要なのは「なぜ供給に限界があるのか」です。実は、生産には2つの重要な要素が必要なんです。
1. 労働投入ギャップ
働く人の数や能力の不足
例えば、IT企業がアプリを開発したくても:
- プログラマーが足りない
- 必要なスキルを持つ人がいない
- 働ける時間に限界がある
これが「労働投入ギャップ」です。人材不足で本来の生産能力を発揮できない状態を指します。
2. 資本投入ギャップ
設備や機械、インフラの不足
同じIT企業で:
- サーバーの処理能力が足りない
- 開発用のコンピューターが古い
- オフィススペースが狭い
これが「資本投入ギャップ」です。物理的な生産手段の不足で、思うように生産できない状態です。
実際の経済への影響
この2つのギャップは相互に関連しています:
- 優秀な人材がいても古い設備では生産性が低い
- 最新設備があっても操作できる人がいなければ意味がない
- 両方が揃って初めて、経済の潜在的な生産能力が発揮される
政府や企業は、教育投資(労働投入の改善)とインフラ投資(資本投入の改善)の両方に取り組むことで、これらのギャップを埋めようとしているのです。
この理解があると、なぜ「人材育成」と「設備投資」の両方が経済成長に重要なのかが見えてきますね。
今の需給ギャップの状況
現在の日本の需給ギャップの状況について、分かりやすく説明しますね。まず最新の情報を確認してから説明します。
現在の日本の需給ギャップの労働投入ギャップと資本投入ギャップの状況について、分かりやすく説明しますね。
全体の需給ギャップの現状
まず、日本経済全体の状況から見てみましょう。2025年度の実質成長率が1.2%となった場合、日本経済の需要と供給の差を表す需給ギャップは0.4%と7年ぶりにプラスとなり、需要増に転じると予測されています。これは「欲しいものが生産能力を少し上回る」状態を意味し、経済が回復しつつあることを示しています。
しかし、この背景には2つの大きな制約があります。
1. 労働投入ギャップ(人手不足)の深刻化
現在の状況:歴史的な人手不足
現状不足している189万人の働き手に関しては、1日あたり約960万時間の労働力が不足しているという深刻な状況です。
身近な例で言うと:
- コンビニの営業時間短縮
- レストランの定休日増加
- 工事現場の人員不足による工期遅れ
- 介護施設の新規受入れ停止
特に深刻な業界
業種別で正社員が「非常に不足」・「やや不足」していると答えた企業は、建設業が84.41%、運輸業が77.95%、情報通信業が76.34%、サービス業が69.74%となっています。
将来予測
2035年、日本の労働市場では1日当たり1,775万時間の労働力が不足し、2023年の労働力不足960万時間/日よりも1.85倍大きい数になると予測されています。今感じている人手不足の約2倍になるということです。
2. 資本投入ギャップ(設備・インフラの制約)
設備投資の現状
良いニュースもあります。2024年度は、前年比21.6%の大幅増の計画となり、1980年代以降では、2022年度(26.8%増)に次いで、2018年度に並ぶ高い伸びとなっており、企業の設備投資意欲は高まっています。
しかし「作りたくても作れない」問題
ここに大きな問題があります:
工事ができない状況 設備投資の計画と実績を見ると、コロナ禍以降、その乖離が大きくなっている。アンケート調査から乖離の理由をみると、「工期の遅れ」「工事費高騰に伴う見直し」が顕著に増加している
これは、例えるなら:
- 新しいお店を開きたいけど、建設会社に人がいない
- 最新の機械を導入したいけど、設置工事ができない
- データセンターを建てたいけど、建設が順番待ち
インフラの老朽化問題
さらに深刻なのは、今後20年間で、建設後50年以上経過する施設の割合は加速度に高くなる見込みという状況です。
これは家に例えると:
- 古い家の修理が必要なのに
- 新しい家も建てなければならないのに
- 大工さんが足りない
両方のギャップが連動する問題
建設関連の有効求人倍率は5倍超と、ひときわ人手不足が顕著である。その結果、建設業の手持ち工事高は積み上がり、順番待ちの注文が消化しきれない状況が続いている
つまり:
- 労働投入ギャップ:建設現場で働く人が足りない
- 資本投入ギャップ:そのせいで新しい設備や建物が作れない
- 悪循環:設備が古いままだと、さらに生産性が上がらない
対策の方向性
政府と企業は以下の取り組みを進めています:
労働面:人材の獲得のため、企業は賃上げにより積極的な姿勢に。人材獲得の代替策として、デジタル活用や自動化投資に前向きな姿勢が継続
資本面:2024年度は34.0%増を計画している。幅広い業種で業務効率化のためのシステム投資がみられた
結局、人手不足と設備不足が同時に起きているため、単純に「人を増やす」「設備を増やす」だけでは解決せず、両方を同時に、かつ効率的に改善していく必要があるのが現在の日本経済の課題なのです。
デフレ時代とインフレ時代の代表的な違い
需給ギャップがマイナスのデフレ時代とプラスのインフレ時代の違いについて、身近な例から説明していきますね。
デフレ時代(需給ギャップがマイナス)の特徴
基本的な状況
「作れるけど売れない」時代
町の商店街で例えると:
- パン屋さんは1日100個作れるのに、お客さんは50個しか買わない
- 50個分の「売れ残り」が毎日発生
- これが経済全体で起こっている状態
物価の動き
値下げ競争が続く
- 売れ残るので、店主は値段を下げて売ろうとする
- 隣の店も値下げするので、さらに値下げ
- 消費者は「来月はもっと安くなるかも」と買い控える
- 結果として物価がどんどん下がる
企業の行動
「守り」の経営
- 売れないので新しい設備投資はしない
- 従業員の給料は上げられない(むしろ下げることも)
- 新しい人は雇わない
- 借金は返済優先で、新しい事業はしない
家計の生活
「節約」が合理的
- 給料が上がらない(下がることもある)
- 物価は下がるので、買い物は先延ばしした方が得
- 貯金していれば相対的に価値が上がる
- でも将来不安で消費は控えめ
日本のデフレ時代の例(1990年代後半〜2010年代前半)
- 牛丼の値下げ競争(500円→280円→250円)
- 100円ショップの急拡大
- 「失われた20年」と呼ばれた経済低迷
- 就職氷河期の出現
インフレ時代(需給ギャップがプラス)の特徴
基本的な状況
「欲しいけど足りない」時代
同じ商店街で例えると:
- パン屋さんは1日100個しか作れないのに、お客さんは150個欲しがる
- 50個分の「品不足」が発生
- これが経済全体で起こっている状態
物価の動き
値上げが当たり前
- 品不足なので、店主は値段を上げても売れる
- お客さんは「今買わないと、もっと高くなる」と急いで買う
- 他の店も値上げするので、全体的に物価上昇
- 消費者も「今のうちに買っておこう」と考える
企業の行動
「攻め」の経営
- 需要があるので設備投資を積極的に行う
- 人手不足なので給料を上げて人材確保
- 新しい人をどんどん雇う
- 借金してでも事業拡大を目指す
家計の生活
「今使う」が合理的
- 給料が上がりやすい
- 物価も上がるので、貯金の価値は目減り
- 今買わないと高くなるので、消費が活発
- 将来の収入増加に期待
現在の日本(2022年〜)
- 食品・エネルギーの値上げラッシュ
- 人手不足による賃上げ圧力
- 名目賃金上昇率は24年度に前年度比2.8%と、物価上昇率の2.5%を上回る状況
両時代の決定的な違い
1. 時間に対する感覚
デフレ時代:「待てば得する」
- 物価が下がるので先延ばしが得
- 「いつか安くなる」という期待
インフレ時代:「今やらないと損する」
- 物価が上がるので今すぐ行動
- 「後で高くなる」という危機感
2. お金の価値
デフレ時代:現金が最強
- 何もしなくても貯金の価値が上がる
- 「現金で持っていれば安心」
インフレ時代:現金は目減り
- 物価上昇で貯金の実質価値が下がる
- 「投資や消費で資産を守る」必要
3. 企業と個人の心理
デフレ時代:「縮小均衡」
- 企業:コスト削減、リストラ優先
- 個人:節約、将来不安
インフレ時代:「拡大志向」
- 企業:投資拡大、人材獲得競争
- 個人:消費積極、収入増期待
4. 政策の効果
デフレ時代:金融緩和の効果が限定的
- お金を刷っても誰も借りたがらない
- 「流動性の罠」状態
インフレ時代:金融引き締めで調整可能
- 金利を上げれば消費や投資にブレーキ
- 政策の効果が見えやすい
まとめ:経済の「気分」の違い
デフレ時代は「みんなで我慢する時代」
- 企業も個人も守りに入る
- 経済全体が縮こまる
インフレ時代は「みんなで競争する時代」
- 企業も個人も積極的になる
- 経済全体が活気づく
ただし、インフレも行き過ぎると生活が苦しくなるので、適度なインフレ(年2%程度)が理想的とされています。現在の日本は、長いデフレから脱却して、適度なインフレ時代に移行しつつある転換点にあると言えるでしょう。
なぜ人手不足になるのか
これまでの説明を踏まえて、なぜ今の日本全体が人手不足になっているのか、その根本的な理由をまとめて説明しますね。
根本原因:日本経済の構造的転換
1. デフレからインフレへの大転換
20年以上続いたデフレ時代(1990年代後半〜2010年代前半)
- 「作れるけど売れない」状態が続いた
- 企業は人を雇わず、給料も上げなかった
- 人々は消費を控え、経済全体が縮小
現在:インフレ時代への転換
- 2025年度の需給ギャップは0.4%と7年ぶりにプラスとなり、需要増に転じる
- 「欲しいけど足りない」状態に変化
- 急に需要が戻ったのに、供給体制が追いつかない
2. 人口減少という避けられない現実
働く世代の減少 生産年齢人口が1995年をピークに減少に転じ、また総人口も2008年をピークに頭打ちの後、2011年以降一貫して減少する
家族に例えると:
- 昔:お父さん、お母さん、子供3人の5人家族
- 今:お父さん、お母さん、子供1人の3人家族
- でも家事の量は同じか、むしろ増えている
将来はさらに深刻 2035年、日本の労働市場では1日当たり1,775万時間の労働力が不足し、2023年の労働力不足960万時間/日よりも1.85倍大きい数
3. 長期間の「投資不足」のツケ
企業が人材育成を怠った20年
- デフレ時代に企業は人件費削減を優先
- 新卒採用の抑制(就職氷河期世代の大量発生)
- 技能継承が断絶
- 「即戦力」ばかり求めて、育てることをしなかった
設備投資も停滞
- 古い設備のまま働き続けた
- 自動化・効率化への投資を先送り
- これから人手はさらに減る。このままだと設備投資計画を立てても人がいなくて作れないといった状況になりかねない
4. 複数の構造変化が同時発生
働き方の多様化
- 終身雇用制度の変化
- 女性の社会進出(良い変化だが、労働市場の構造変化を伴う)
- 高齢者の定年延長(これも良い変化だが、適応が必要)
産業構造の変化 業種別で正社員が「非常に不足」・「やや不足」していると答えた企業は、建設業が84.41%、運輸業が77.95%、情報通信業が76.34%、サービス業が69.74%
- 製造業からサービス業へのシフト
- デジタル化の急速な進展
- 新しいスキルが必要なのに、教育が追いつかない
5. 「負のスパイラル」の連鎖
労働投入ギャップと資本投入ギャップの悪循環
人手不足 → 設備投資できない → 生産性上がらない →
賃金上がらない → 人材確保できない → さらに人手不足
具体例:
- 建設現場に人がいない
- だから新しい工場が建てられない
- 古い設備のままで生産性が低い
- 給料を上げられないので人が集まらない
- ますます人手不足に
6. コロナ禍が加速させた構造変化
一時的な緩和から急激な回復
- コロナ禍で一時的に人手不足が緩和
- 経済活動再開で急に需要が戻った
- でも労働供給体制は戻らない
- 新型コロナウイルス感染症が5類に移行し、行動制限が解除されたことにより、再び人手不足の割合が上昇しつつある
なぜ「全体」が人手不足なのか
従来の人手不足との違い
昔の人手不足:特定の業界だけ
- 高度成長期:建設業だけ人手不足
- バブル期:サービス業だけ人手不足
今の人手不足:ほぼ全業界で同時発生 2010年代以降は、広範な産業や職業で労働力需給ギャップが生じている
理由:基盤となる労働力そのものが減少
レストランに例えると:
- 昔:お客さんが和食レストランに集中(他の店は暇)
- 今:街全体の料理人が不足(どの店も人手不足)
結論:構造的・複合的な問題
今の日本の人手不足は、単純な「一時的な需要増加」ではありません。以下の要因が重なった構造的な問題です:
- 人口減少という根本的な変化
- 20年間の投資不足のツケ
- デフレからインフレへの急激な転換
- 産業構造の変化への対応遅れ
- 労働と資本の悪循環
つまり、これまで「縮小均衡」で何とかやってきた日本経済が、急に「拡大モード」に切り替わったものの、その準備ができていなかった、ということです。
解決には時間がかかりますが、逆に言えば、この構造変化に対応できれば、日本経済は新しい成長軌道に乗ることができる、ということでもあります。今はその大きな転換点にいるのです。
需給ギャップの補足説明
AIが網羅できなかった部分を、別記事で補足説明しています。
続けて以下の記事をご覧下さい。
以下の記事では、人手不足経済の中で例外的に人手が余っている業種について、生成AIに質問しています。参考までにどうぞ。
2025年9月25日追記> 以下の記事で、需給ギャップについて伝えたい事を、AIを使わないで説明してみました。AIで説明できなかった事をまとめています。
関連記事
これまでの説明で参照した外部リンクの一覧です:
需給ギャップ・経済全体の動向
- 日本経済新聞:25年度の需給ギャップ0.4%、7年ぶりプラス 内閣府試算 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA260750W4A221C2000000/
- 日本銀行:需給ギャップと潜在成長率 https://www.boj.or.jp/research/research_data/gap/index.htm
- 日本銀行:経済・物価情勢の展望 2025年4月 https://www.boj.or.jp/mopo/outlook/gor2504b.pdf
- 日本経済新聞:日銀推計の需給ギャップ、16四半期連続マイナス 1〜3月 https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB031YE0T00C24A7000000/
- 第一生命経済研究所:物価安定に必要なGDPギャップ水準 https://www.dlri.co.jp/report/macro/403769.html
- 内閣府:今週の指標 https://www5.cao.go.jp/keizai3/shihyo/index.html
労働投入ギャップ(人手不足)関連
- パーソル総合研究所:2035年の労働力不足は2023年の1.85倍―現状の労働力不足と未来の見通し https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/thinktank-column/202410250001/
- 労働政策研究・研修機構(JILPT):2010年代からの人手不足は過去に比べ「長期かつ粘着的」 https://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2024/11/top_01.html
- パーソル総合研究所:労働市場の未来推計 2030 https://rc.persol-group.co.jp/thinktank/spe/roudou2030/
- 内閣府:第2章 人手不足による成長制約を乗り越えるための課題 https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je24/h02-00.html
- Indeed Hiring Lab Japan:2024年日本の労働市場の展望:慢性的な人手不足の中でも市場の流動化が加速する可能性 https://www.hiringlab.org/jp/blog/2023/12/15/2024年日本の労働市場の展望:慢性的な人手不足の/
- smartmat.io:人手不足|日本の現状と深刻な業界。原因や影響、解消法と成功事例 https://www.smartmat.io/column/business_efficiency/8148
- 厚生労働省:第1章 我が国の労働力需給の展望と労働移動をめぐる課題 https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/roudou/21/2-1.html
資本投入ギャップ(設備投資)関連
- 日本政策投資銀行:製造業、非製造業ともに高い伸び 人手不足・物価高が課題も、デジタル化やEV等電動化が成長をけん引 https://www.dbj.jp/pdf/investigate/equip/national/2024_summary.pdf
- ニッセイ基礎研究所:供給制約をどう乗り切るか-設備投資の増勢を維持するために https://www.nli-research.co.jp/report/detail/id=81105?site=nli
- 経団連:日本産業の再飛躍へ https://www.keidanren.or.jp/policy/2024/031_honbun.html
- 中小企業庁:2024年版「中小企業白書」 第4節 設備投資 https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2024/chusho/b1_3_4.html
- 国土交通省:社会資本の老朽化の現状と将来 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/maintenance/02research/02_01.html
- 第一生命経済研究所:実はマイナスだった23年度の実質設備投資 https://www.dlri.co.jp/report/macro/400025.html
- SB Bit:壊滅的な「日本企業の設備投資」の大問題、なぜこのままだと「賃金上昇も遠のく」のか https://www.sbbit.jp/article/cont1/142206
以上、合計18の外部リンクを参照して説明を行いました。
以前書いた記事
続けて、以前書いた記事へのリンクです。
Deep Research に聞く「日本経済のボトルネックは何?」
これら二つの記事も生成AIに書いてもらった記事ですが、この手の単純な事実関係の記事執筆は、もう人間の仕事では無いですね。新聞記事や情報サイトなどの存在価値はどうなってしまうのでしょうか?
私自身、この種類の記事を自分で書く気にはなれなくなりました。
今でも自分で記事を書くことに拘る人が多いですが、何の意味があるのか良く分かりませんね。
この話は以前も、「最新情報もAI任せで良くなった」 という記事で書きました。人が記事を書く意味は、「個人的な意見や思想」と「身体的技能や知識」「経験・体験」にしかありません。
しかし、まだ「AIに質問すれば分かるのに、質問しない人」というのがたくさん存在するので、私はこの記事のように、AIに質問した結果をそのまま記事にしています。
「どうして人手不足になるのだろうね?」とか疑問を呟く人は、どうしてそれをAIに質問しないのでしようか。そっちの方が理解できません。
昔のググレカスと同じですが、検索しない人はなぜ検索しないのでしようか。本当に不思議です。
とりあえず、この世にググレカスが存在する限り、AIの回答をそのまま記事にする事を続けようと思っています。ご了承ください。