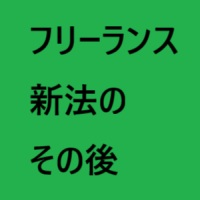フリーランス新法が施行されてから、もうすぐ一年近く経ちます。
Gemini Deep Research にフリーランス新法施行から、IT業界全般でどのような変化が起きたのか、聞いてみましたので、以下に共有したいと思います。
フリーランス新法施行から、しばらく時間が経ちました。
法施行からIT業界で起きた変化を調べてレポートにまとめてください。
もし可能なら変化の内容に「量や数」の報告も加えてください。
分からないことは、わからないと答えてください。
ハルシネーションは避けてください。
フリーランス新法の施行が日本のIT業界に与える影響:定量的・定性的分析
エグゼクティブサマリー
2024年11月1日に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、通称「フリーランス新法」は、日本のIT業界におけるフリーランス人材の活用と働き方に構造的な変化をもたらす重要な転換点となった。本レポートは、法施行後のIT業界における変化を、定量的データと定性的分析の両側面から包括的に解明することを目的とする。
分析の結果、本法は二つの主要な影響を及ぼしていることが明らかになった。第一に、フリーランスとして活動することへの心理的障壁を低減させ、ITフリーランス市場への人材供給を加速させる「触媒」として機能している。法施行後、ITフリーランス案件への希望者数は施行前比で約1.2倍に増加し、市場規模も2025年には1兆1,849億円に達すると予測されるなど、顕著な量的拡大が見られる。
第二に、IT企業に対して、フリーランスとの取引におけるコンプライアンス遵守と管理体制の高度化を強いる「新たなパラダイム」を提示している。取引条件の書面明示義務や報酬支払いの60日ルール、ハラスメント対策など、企業側には新たな運用コストと管理責任が発生しており、これに対応するための契約書の見直しやフリーランスマネジメントシステムの導入が進んでいる。
しかしながら、本法は万能薬ではない。契約上は独立事業者でありながら実態は労働者に近い「偽装フリーランス」の問題や、IT業界特有の多重下請け構造といった根深い課題は、法の射程外にあり、依然として解決されていない。特に「偽装フリーランス」問題については、本法がフリーランスとしての権利を強化することで、かえって労働者としての適切な処遇への転換を阻害し、問題を固定化させるリスクも内包している。
本レポートでは、これらの変化と課題を詳細に分析し、IT企業およびITフリーランスが新たな法規制環境下で持続的に成長するための戦略的示唆を提供する。
第1章 フリーランス新法の概要:ITビジネスの規制枠組みと主要義務
本章では、フリーランス新法の法的枠組みを詳細に解説し、IT企業が遵守すべき具体的な義務を明確にすることで、後続の分析における基礎的文脈を構築する。これは、企業にとっての実践的なコンプライアンスガイドとしての役割も果たす。
1.1 背景と核心的目的:取引の適正化と就業環境の整備
フリーランス新法の正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」である 1。この法律は、働き方の多様化が進展する中で、フリーランスという働き方を選択した個人が安定的に業務に従事できる環境を整備することを主眼に置いている 3。
法律の目的は、公式資料において明確に二つの柱で構成されている 2。
- 取引の適正化: 発注事業者とフリーランス間の業務委託取引における力関係の不均衡を是正し、報酬の未払いや一方的な契約変更といった不公正な取引慣行を排除すること。
- 就業環境の整備: ハラスメントからの保護や、育児・介護と業務の両立への配慮など、フリーランスが労働者に準じた形で安心して働ける環境を整えること。
この法律は、2023年4月28日に国会で可決・成立し 8、
2024年11月1日から施行された 1。
法の保護対象となる「フリーランス」(法文上は「特定受託事業者」)の定義は厳密に定められている。具体的には、従業員を使用しない個人事業主、または代表者1名のみで従業員を使用しない法人が該当する 3。したがって、従業員を雇用している個人事業主や法人は、この法律における「フリーランス」には含まれない。この定義により、保護の対象が、より事業者としての交渉力が弱い立場にある個人に絞られている点が特徴である。
1.2 ITフリーランスを活用する企業の主要義務:詳細な解説
フリーランス新法は、業務を委託する事業者(業務委託事業者)に対し、多岐にわたる義務を課している。IT業界においても、エンジニアやデザイナー、コンサルタントといったフリーランス人材の活用は不可欠であり、これらの義務を正確に理解し、遵守することが極めて重要となる。
義務1:取引条件の明示義務(法第3条)
すべての業務委託事業者は、フリーランスに業務を委託した後、直ちに、取引条件を**書面または電磁的方法(電子メール、SNSのメッセージ等)**により明示しなければならない 3。口頭での合意のみでは不十分であり、証拠が残る形での明示が必須とされた。これは、契約内容の曖昧さに起因するトラブルを未然に防ぐための基本的な措置である。
明示すべき事項は公正取引委員会規則で具体的に定められており、主に以下の項目が含まれる 1。
- 委託事業者および受託事業者の氏名または名称
- 業務委託をした日
- 給付の内容(IT開発であれば、要件、仕様、機能、担当範囲など)
- 報酬の額および支払期日
- 給付を受領する期日(納期)および場所
- 検査を行う場合は、その検査を完了する期日
義務2:報酬の適時支払い(法第4条)
報酬の支払いに関するルールは、フリーランスが直面する最も深刻な問題の一つであった支払い遅延に対処するため、厳格に定められた。
- 「60日ルール」: 成果物を受領した日(役務提供委託の場合は、役務の提供を受けた日)から起算して60日以内のできる限り短い期間内に報酬の支払期日を設定し、その期日までに支払わなければならない 1。このルールは、発注者側の検査期間の長短にかかわらず適用される。
- 「30日ルール」(再委託の場合): 発注元から業務を受託した事業者が、その業務の一部をフリーランスに再委託する場合、元委託者からの支払期日から30日以内にフリーランスへの支払期日を設定することが可能となる 9。これは、多重下請け構造における資金繰りの実態を考慮した例外規定である。
義務3:継続的契約(1ヶ月以上)における禁止行為(法第5条)
フリーランスとの間で1ヶ月以上の期間にわたる業務委託(継続的業務委託)を行う場合、発注事業者には以下の7つの行為が禁止される。これらは、優越的な地位の濫用を防ぐことを目的としている 3。
- 受領拒否: フリーランス側に責任がないにもかかわらず、成果物の受領を拒否すること。
- 報酬の減額: あらかじめ定めた報酬を、フリーランス側に責任がないにもかかわらず減額すること。
- 返品: フリーランス側に責任がないにもかかわらず、受領した成果物を返品すること。
- 買いたたき: 通常支払われる対価に比して著しく低い報酬額を不当に定めること。
- 購入・利用強制: 正当な理由なく、発注者が指定する物品の購入やサービスの利用を強制すること。
- 不当な経済上の利益の提供要請: 発注者のために金銭やサービスなどを不当に提供させること。
- 不当な給付内容の変更・やり直し: フリーランス側に責任がないにもかかわらず、一方的に発注内容を変更させたり、無償でやり直しをさせたりすること。
義務4:長期契約(6ヶ月以上)における追加義務
契約期間が6ヶ月以上となる継続的業務委託の場合、発注事業者にはさらに重い責任が課される。
- 育児・介護等への配慮(法第13条): フリーランスから妊娠、出産、育児、介護に関する申し出があった場合、業務との両立ができるよう、納期の調整やリモートワークの許可など、必要な配慮をしなければならない 3。
- 中途解除等の事前予告(法第16条): 契約を中途で解除する場合、または契約を更新しない場合には、少なくとも30日前までにその旨を予告することが義務付けられる。また、フリーランスから理由の開示を求められた場合は、遅滞なくその理由を開示しなければならない 1。
義務5:ハラスメント対策に関する体制整備(法第14条)
発注事業者は、フリーランスに対するパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント等が発生しないよう、必要な体制を整備する義務を負う 3。具体的には、相談窓口の設置、社内への方針の周知・啓発、ハラスメント発生時の迅速かつ適切な対応などが求められる。これは、フリーランスが従業員と同様に、尊厳を保ちながら働ける環境を確保するための重要な規定である。
義務6:募集情報の的確な表示(法第12条)
フリーランスを募集する際に広告等で情報を提供する場合は、その内容について虚偽の表示や誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保つ義務がある 3。これにより、フリーランスが応募段階で不利益を被ることを防ぐ。
表1:フリーランス新法に基づくIT企業の主要義務の概要
| 義務の分類 | 具体的な要件 | 適用条件 | 関連条文 |
|---|---|---|---|
| 取引条件 | 給付内容、報酬額、支払期日等の書面・電磁的方法による明示 | 全ての業務委託 | 第3条 |
| 報酬支払 | 成果物受領日から60日以内の支払期日設定・遵守 | 全ての業務委託 | 第4条 |
| 報酬支払 | 再委託の場合、元委託者の支払期日から30日以内の支払期日設定 | 再委託を行う業務委託 | 第4条 |
| 禁止行為 | 受領拒否、報酬減額、買いたたき等の7項目の禁止 | 1ヶ月以上の継続的業務委託 | 第5条 |
| 就業環境 | 募集情報の的確な表示(虚偽・誤解を招く表示の禁止) | フリーランスを募集する全ての事業者 | 第12条 |
| 就業環境 | 育児・介護等と業務の両立への配慮 | 6ヶ月以上の継続的業務委託 | 第13条 |
| 就業環境 | ハラスメント対策に関する体制整備(相談窓口設置等) | 全ての業務委託 | 第14条 |
| 契約終了 | 中途解除・不更新の場合の30日前予告および理由開示 | 6ヶ月以上の継続的業務委託 | 第16条 |
第2章 法施行後におけるITフリーランス市場の定量的変化
本章では、フリーランス新法の施行がIT市場に与えた具体的な量的影響を分析する。法律がフリーランスの参入意欲や企業の活用動向にどのように作用したかを、客観的な数値データに基づいて明らかにし、ユーザーの「量や数」に関する要求に直接的に応える。
2.1 ITフリーランス人材プールの拡大:法規制がもたらした信頼性向上
フリーランス新法の施行は、ITフリーランス市場への人材供給を加速させる強力な追い風となっている。ある調査によれば、2024年11月の法施行後、ITフリーランスの案件を希望する人の数は、施行前の水準と比較して約1.2倍に増加した 23。さらに、前年同月比で見ると、案件希望者数は**136%**という大幅な伸びを記録している 23。
この急激な増加は、単なる市場の自然成長だけでは説明が難しい。その背景には、新法がもたらした「信頼性の向上」と「リスクの低減」がある。これまでフリーランスという働き方には、報酬の支払遅延や不払い、契約内容の曖昧さといった取引上のリスクが常に付きまとっていた。これらは、高いスキルを持つITプロフェッショナルがフリーランスへの転身を躊躇する大きな要因であった。
フリーランス新法は、取引条件の書面明示義務や報酬支払いの60日ルールといった具体的な規定を設けることで、これらの根源的な不安を法的に解消しようと試みたものである 1。これにより、フリーランスという働き方の予見可能性と安定性が向上し、一種のセーフティネットが構築された。結果として、これまでリスクを懸念して会社員という立場に留まっていた潜在的なフリーランス層が、安心して市場に参入できる環境が整ったのである。つまり、この法律は、フリーランス市場の供給サイドにおける心理的な参入障壁を引き下げる「信頼醸成装置」として機能し、人材プールの拡大を直接的に促したと分析できる。
2.2 企業需要の堅調な推移と市場規模の予測
法規制による企業側のコンプライアンス負担が増加したにもかかわらず、ITフリーランス人材に対する企業の需要は依然として旺盛であり、むしろ拡大傾向にある。ITフリーランスを現在活用している企業の**約6割(59.8%)が、「今後、活用を増やしたい」と回答している 26。さらに、活用企業のうち
77.1%**が、フリーランス人材の活用に「満足している」と評価しており、企業とフリーランスの協力関係が良好に機能している実態がうかがえる 26。
この旺盛な需要を背景に、ITフリーランス市場の規模は今後も着実な成長が見込まれている。ある市場予測では、ITフリーランスの市場規模は2025年までに1兆1,849億円に達するとされており、これは2015年の7,199億円から比較して約1.6倍の成長である 27。また、ITフリーランスの人口も、2024年には約35.3万人に達し、2028年には45万人を突破すると推計されている 29。
このデータは、企業の人材戦略における重要な転換を示唆している。デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進や慢性的なIT人材不足という、より大きな経営課題に直面する企業にとって、高度な専門スキルを持つフリーランス人材の活用は、もはや単なるコスト削減策ではなく、事業成長に不可欠な戦略的選択肢となっている 31。フリーランス新法が課す新たなコンプライアンスコストは、この戦略的必要性の前では許容範囲内のものと捉えられている。むしろ、法律の施行は、これまで曖昧で属人的な管理に頼っていた企業に対し、フリーランスの活用方法をより体系的かつ専門的に見直すことを促した。結果として、場当たり的な活用から、戦略的な人材ポートフォリオの一環としてフリーランスを組み込むという、より成熟した活用モデルへの移行を加速させているのである。
2.3 報酬動向と専門分野別の需要変化
ITフリーランス市場の拡大は、報酬水準にも影響を与えている。2025年の調査によると、ITフリーランスエンジニアの平均月単価は82.2万円に達している 33。特に需要の高い専門分野では、年収換算で1,000万円近い高額な報酬が提示されるケースも珍しくない。例えば、Ruby on Railsエンジニアの平均年収は995万円、Flutterエンジニアは927万円といったデータも報告されている 29。
特に注目すべきは、特定の職種における需要の急増である。プロジェクトマネジメントを担うPM/PMOや、上流工程を担うITコンサルタントといった職種の案件発生数は、前年同月比で**184%**という驚異的な伸びを示している 23。これは、企業がフリーランスを単なる開発リソースとしてではなく、プロジェクト全体を牽引し、事業戦略に深く関与する高度専門人材として活用する傾向が強まっていることを示している。
また、生成AI技術の急速な普及に伴い、データ関連職種の需要も急拡大している。「プロンプト設計」や「LLM(大規模言語モデル)活用」といった最先端スキルを持つ人材への引き合いが強く、AI関連職種の単価も上昇傾向にある 23。
これらのデータは、ITフリーランス市場が「質の高い専門性」を求める方向にシフトしていることを明確に示している。企業は、単純なコーディング作業のアウトソース先としてではなく、社内では確保が難しい高度なスキルや経験を持つ戦略的パートナーとしてフリーランスを求めており、その対価として高額な報酬を支払うことを厭わない。この「専門性への集中」が、市場全体の報酬水準を押し上げている主要因と考えられる。
表2:フリーランス新法施行後におけるITフリーランス市場の主要な定量的変化
| 指標 | 数値・変化 | 出典 | 示唆する内容 |
|---|---|---|---|
| フリーランス希望者数の変化 | 2024年11月の法施行後、約1.2倍に増加 | 23 | 法規制による取引の安定化が、フリーランス転身への心理的障壁を低減させた可能性。 |
| 企業の活用意向 | 活用企業の**約60%**が「今後、活用を増やしたい」と回答 | 26 | コンプライアンス負担を上回る、柔軟な高度人材確保への戦略的ニーズが存在。 |
| 市場規模予測(2025年) | 1兆1,849億円(2015年比で約1.6倍) | 27 | 供給(希望者増)と需要(企業活用意向)の両面から市場の継続的な拡大が見込まれる。 |
| PM/PMO職の案件数 | 前年同月比**184%**に増加 | 23 | 企業がフリーランスを上流工程やマネジメント業務の戦略的パートナーとして活用する傾向が強まっている。 |
| フリーランスエンジニアの平均月単価 | 82.2万円 | 33 | 高度な専門性を持つ人材への需要が集中し、市場全体の報酬水準を押し上げている。 |
第3章 IT企業における実務的・運用的変化
フリーランス新法は、法規制や市場動向の変化に留まらず、IT企業の日常的な業務オペレーションにも具体的な変革を要求している。本章では、法律が企業の現場レベルでどのような実務的変更を促しているのかを、契約書の改訂、管理コストの増大、そしてエコシステム全体の役割分担の変化という三つの観点から分析する。
3.1 業務委託契約書の進化
フリーランス新法の施行に伴い、IT企業が最も直接的に対応を迫られたのが、業務委託契約書の見直しである。特に、法第3条で定められた取引条件の明示義務を遵守するためには、従来の曖昧な内容の契約書テンプレートを全面的に改訂する必要が生じた 19。
具体的には、以下の条項について、より詳細かつ法規制に準拠した内容への変更が不可欠となっている。
- 業務範囲と成果物の定義: 従来の契約書では「システム開発業務一式」といった包括的な記述も散見されたが、新法下ではトラブル回避の観点から、担当する機能、開発範囲、納品物の仕様などを具体的に明記することが求められる。これにより、スコープ外の追加作業や無償での修正要求といった、いわゆる「スコープクリープ」を巡る紛争を未然に防ぐ狙いがある 35。
- 報酬および支払条件: 報酬額を明確に記載することはもちろん、支払期日を「成果物受領日から60日以内」とする60日ルール、あるいは再委託の場合の30日ルールに準拠した形で設定する必要がある 17。検収期間が長期化する場合でも、支払期日の起算点はあくまで「受領日」であることを契約書上で明確化することが重要となる。
- 知的財産権の帰属: 開発したソースコードやデザイン、コンテンツなどの知的財産権が、発注者と受注者のどちらに帰属するのか、または譲渡されるのかを明確に規定する必要がある。譲渡する場合は、その対価が報酬に含まれていることを明記することも、後の紛争を防ぐ上で不可欠である 35。
- 契約解除および不更新: 契約期間が6ヶ月以上に及ぶ場合、中途解除や契約不更新の際には30日前の予告が必要となるため、契約書にもこの旨を反映した条項を盛り込む必要がある 22。自動更新条項を見直し、更新拒否の通知期間を法規制に合わせる改訂も求められる。
- ハラスメント防止: 発注者にはハラスメント対策の体制整備義務が課されているため、契約書に、企業のハラスメント防止方針や相談窓口について言及し、フリーランスが安心して相談できる環境があることを示す条項を追加する動きも見られる 17。
これらの改訂は、単なる形式的なものではなく、企業とフリーランス間の取引関係をより対等で透明性の高いものへと変革させるための実質的な一歩となっている。
3.2 コンプライアンスおよび管理コストの増大
フリーランス新法への対応は、企業に新たな管理コストをもたらしている。契約書の一件ごとの作成・管理、支払期日の厳格なトラッキング、ハラスメント相談窓口の設置と運用、担当者への法規制に関する教育など、バックオフィス部門の業務負担は確実に増加した 18。
特に、多数のフリーランスを同時に活用する企業にとっては、これらの管理業務を人手で行うことは非効率であり、コンプライアンス違反のリスクも高まる。こうした課題に対応するため、**「フリーランスマネジメントシステム(FMS)」**と呼ばれる新しいカテゴリーのITツール市場が急速に立ち上がりつつある 37。FMSは、フリーランスの募集から契約、業務進捗管理、発注、請求、支払いまでを一元的に管理し、新法の要件(取引条件の明示や支払期日の遵守など)をシステム上で担保する機能を提供する。
この動きは、フリーランス新法が企業にもたらした影響を象徴している。法律は、フリーランスの活用における運用基準を引き上げ、それに伴うコスト増を発生させた。しかし同時に、そのコストを効率的に管理するための新たなテクノロジー市場を生み出した。企業は、この追加コストを単なる負担と捉えるのではなく、フリーランスとの関係を専門的かつ体系的に管理し、長期的な協力関係を築くための「投資」と位置づけることが求められている。コンプライアンスを徹底することで、紛争リスクを低減し、優秀なフリーランス人材から選ばれる企業になるという、副次的な効果も期待できる。
3.3 「認知」と「実践」のギャップと仲介者の役割
フリーランス新法は、関係者の間で高い認知度を誇る一方で、その内容が実際の取引現場でどの程度実践されているかについては、大きな課題が残されている。
フリーランス協会が実施した「フリーランス白書2025」によれば、フリーランスにおける法の**認知度は98.7%と極めて高い水準にある 38。しかし、その法律の内容について「取引先と会話に出たことがある」と回答したフリーランスは、わずか
22.7%**に留まっている 38。企業側も同様に、経営層の多くは法律の概要を理解しているものの、具体的な運用方法や社内体制の見直しに不安を感じているという調査結果がある 41。
この「認知」と「実践」の間に存在するギャップは、フリーランスエージェントやクラウドソーシングプラットフォームといった仲介事業者が新たな役割を担う機会を生み出している。これらの仲介事業者は、単に案件と人材をマッチングさせるだけでなく、取引プロセス全体がフリーランス新法に準拠するよう、システムや運用フローを積極的に改訂している。
例えば、大手クラウドソーシングサイトのランサーズは、新法の施行を受け、プラットフォーム上で行われるすべての取引において自動的に発注確認書を発行する仕様に変更した。また、報酬の支払サイクルも、法の定める期日を遵守できるよう、報酬確定から15日経過後の締め日に自動で払い出される対象を拡大するなどのシステム改修を行っている 42。
このような動きは、仲介事業者が「コンプライアンス仲介者」としての機能を強化していることを示している。法律の複雑な要件をプラットフォーム側が吸収・自動化することで、個々の企業やフリーランスは、法規制を都度意識することなく、安心して取引に集中できる。これは、エコシステム全体の効率化に寄与する一方で、企業やフリーランスのプラットフォームへの依存度をさらに高め、市場における仲介事業者の中心的な地位をより強固にする結果をもたらす可能性がある。
第4章 根強い課題と法改正の限界
フリーランス新法は、取引の公正性向上という点で大きな前進であるが、IT業界に根強く存在する構造的な問題をすべて解決する万能薬ではない。本章では、法改正後も依然として残る「偽装フリーランス」問題や多重下請け構造といった課題を掘り下げ、法律の限界と今後の論点を浮き彫りにする。
4.1 「偽装フリーランス」というジレンマ
フリーランス新法が直面する最大の課題の一つが、「偽装フリーランス」問題である。偽装フリーランスとは、契約形式上は独立した事業者(業務委託)として扱われながら、その実態においては、企業の指揮命令下に置かれ、勤務時間や場所を拘束されるなど、労働者と何ら変わらない働き方を強いられている個人を指す 43。
この問題の根深さは、その広範な実態からもうかがえる。「フリーランス白書2025」の調査では、回答したフリーランスの約3割が、発注元から指揮監督を受けているなど、偽装フリーランスに該当する疑いのある状況で働いていることが示唆されている 38。
ここで、フリーランス新法が内包するパラドックスが浮上する。この法律は、あくまで「独立した事業者であるフリーランス」の権利を保護し、取引を適正化するために設計されている。法律の目的は、労働者か否かを判断することではなく、フリーランスとして扱われている個人の取引上の立場を強化することにある。
この構造が、意図せざる結果を生む可能性がある。偽装フリーランスを事実上雇用している企業にとって、その個人を労働者として正式に雇用し、社会保険料の負担や有給休暇の付与、労働基準法の遵守といった重い責任を負うよりも、フリーランス新法の規定(取引条件の明示や報酬の適時支払いなど)を遵守する方が、はるかにコストが低い。つまり、新法は、偽装フリーランスという不適切な状態を是正するインセンティブとして機能するのではなく、むしろその状態をより法的に整備された形で「固定化」させてしまうリスクをはらんでいる。企業は、労働者性の判断という根本問題から目をそらし、「法律を遵守した上でフリーランスとして活用している」という体裁を整えることが可能になる。これは、特にSES(システムエンジニアリングサービス)業界などで見られる、実質的な労働者派遣を業務委託契約で覆い隠す慣行を、結果的に助長しかねない。フリーランス新法が、労働者保護の根幹に関わるこの問題に対して、直接的な解決策を提示できていない点は、その最大の限界と言えるだろう。
4.2 既存の業界構造:SESと多重下請けへの影響
日本のIT業界、特に大規模なシステム開発においては、元請け企業から二次請け、三次請けへと業務が再委託されていく「多重下請け構造」が長年にわたり定着している 46。フリーランスのITエンジニアは、このピラミッド構造の末端で業務に従事することも少なくない。
フリーランス新法は、この構造自体を問題視するものではないが、その各階層における取引には適用される。例えば、二次請け企業が三次請けのフリーランスに業務を委託する場合、その両者間の取引において、取引条件の明示義務や報酬の60日ルールなどが適用される。これにより、下層のフリーランスが直接の契約相手から不当な扱いを受けるリスクは、ある程度軽減されることが期待できる。
しかし、法律が介入するのはあくまで個別の契約関係のみであり、多重下請け構造がもたらす根本的な問題、すなわち「中抜き」による報酬の目減りや、上位企業からの圧力による厳しい納期設定といった課題には対処できない。ピラミッドの最下層にいるフリーランスは、たとえ直接の委託元から契約通りに期日内に支払いを受けたとしても、エンドクライアントが支払った総予算のごく一部しか受け取れないという状況は変わらない。
したがって、フリーランス新法は、多重下請け構造の各接点における「取引の透明性」を高める効果はあっても、構造全体がもたらす「非効率性」や「報酬配分の不公平性」を是正する力は持たない。この問題の解決には、法律による取引ルールの整備だけでなく、商慣行の見直しや、発注者であるエンドクライアント側の意識改革といった、より広範なアプローチが必要となる。
4.3 トラブル相談の動向:法施行前のベースライン
フリーランス新法がどのような問題の解決を目指して制定されたのかを理解するためには、法施行前のトラブルの実態を把握することが不可欠である。そのための重要なデータソースが、厚生労働省などが連携して運営する弁護士による無料相談窓口「フリーランス・トラブル110番」の統計である。
2021年2月から2022年8月までの相談データを分析すると、IT業界のフリーランスが直面していた課題が明確に浮かび上がる 48。
- 業種別に見ると、「システム開発・ウェブ作成関係」からの相談は全体の**12.7%**を占め、「配送関係」に次いで2番目に多いカテゴリーとなっている。これは、IT業界がフリーランストブルの多発地帯であったことを示している。
- 相談内容で最も多かったのは、報酬の不払いや遅延、減額を含む「報酬の支払い」に関連するもので、全体の**32.1%を占めた。次いで、契約条件の不明確さや契約書不作成といった「契約内容」に関する相談が22.4%**であった。この二つで、相談内容全体の過半数を占めている。
これらのデータは、フリーランス新法が取引条件の明示や報酬支払いのルールを厳格に定めたことが、現場で実際に起きていた問題に直接対応するものであったことを裏付けている。
ただし、ここで極めて重要な注意点がある。現在公開されている「フリーランス・トラブル110番」の詳細な統計データは、すべて2024年11月の法施行以前のものである。したがって、現時点では、フリーランス新法の施行によってIT関連のトラブル相談件数が実際に減少したかどうかを、定量的に評価することは不可能である。 本レポートで提示するデータは、あくまで法施行前の「ベースライン」であり、今後の法改正効果を測定するための比較対象として位置づけられるべきものである。
表3:法施行前のフリーランストブルの状況(IT分野に焦点を当てた分析)
| 相談者の業種 | 全相談に占める割合 |
|---|---|
| 配送関係 | 15.6% |
| システム開発・ウェブ作成関係 | 12.7% |
| デザイン関係 | 8.1% |
| 建設関係 | 6.8% |
| その他 | 14.6% |
| トラブルの種類 | 全相談内容に占める割合 |
|---|---|
| 報酬の支払い(不払い、遅延、減額等) | 32.1% |
| 契約内容(条件不明確、契約書不作成等) | 22.4% |
| 受注者からの解除 | 8.0% |
| 発注者からの損害賠償 | 7.8% |
| 作業・成果物・納品 | 6.8% |
注:出典は「フリーランス・トラブル110番」の統計データ(2021年2月~2022年8月)
48
第5章 結論と戦略的提言
本章では、これまでの分析結果を総括し、フリーランス新法がIT業界にもたらした変化の本質を結論づける。その上で、IT企業およびITフリーランスが、この新たな規制環境に適応し、持続的な成長を遂げるための具体的な戦略的提言を行う。
5.1 分析結果の総括
フリーランス新法の施行は、日本のIT業界に対して二重のインパクトを与えた。
第一に、法律はITフリーランス市場の成長と人材供給を加速させる触媒として機能した。取引条件の明示や報酬支払いの適時性を法的に保証したことで、フリーランスという働き方のリスクが低減され、より多くの高度IT人材が市場に参入する道を開いた。これに応える形で企業の活用意欲も高く、市場規模は拡大の一途をたどっている。この量的拡大は、法律がもたらした最も明確でポジティブな成果である。
第二に、法律は企業に対し、フリーランスとの取引における行動規範の高度化を強制した。コンプライアンス遵守のための契約管理や社内体制の整備が不可欠となり、運用コストは増加した。しかしこれは、フリーランス活用を場当たり的なものから、体系的でプロフェッショナルな人材戦略へと昇華させる契機ともなっている。
一方で、法律の限界も明らかになった。特に、実質的な労働者を業務委託契約で縛る「偽装フリーランス」問題や、業界に深く根差した「多重下請け構造」といった、より根源的な構造問題に対しては、本法は直接的な解決策を提供していない。取引の公正性を個々の契約レベルで担保することはできても、労働者性の判断や業界構造そのものを変革するまでには至っていない。
結論として、フリーランス新法は、ITフリーランス市場の「取引インフラ」を整備し、市場の健全な量的拡大を促した点で画期的な法律である。しかし、その効果は主に取引の透明性と安定性の向上に限定されており、IT業界が抱えるより複雑な労働問題や産業構造の課題は、依然として今後の重要な政策的・経営的アタジェンダとして残されている。
5.2 IT企業への戦略的提言
フリーランス新法が定着する今後の市場環境において、IT企業が競争優位性を維持・向上させるためには、以下の戦略的対応が求められる。
コンプライアンスとリスク管理の徹底:
- 契約プロセスの標準化: 既存のフリーランス向け業務委託契約書および関連テンプレートを法務部門または外部専門家と共に全面的に見直す。取引条件の明示、支払期日、知的財産権、解除予告など、法の要件を網羅した標準テンプレートを策定し、全社的に利用を徹底する。
- ライフサイクル管理の導入: フリーランスの募集から契約、業務遂行、納品、支払い、契約終了までの一連のプロセスを管理する標準的な業務フローを構築する。特に、6ヶ月以上の継続契約に移行する際の追加義務(育児介護配慮、解除予告)をトリガーとしたアラート機能などを組み込むことが望ましい。
フリーランス活用モデルの専門化・高度化:
- FMS(フリーランスマネジメントシステム)の導入検討: 多数のフリーランスを活用する企業は、管理業務の効率化とコンプライアンス遵守を両立させるため、FMSの導入を積極的に検討すべきである。これにより、管理コストを抑制しつつ、人的ミスによる法規制違反のリスクを低減できる 37。
- 「戦略的人材ポートフォリオ」への転換: フリーランスを単なる外部リソースではなく、正社員や派遣社員と並ぶ、企業の「人材ポートフォリオ」の重要な一角と位置づける。どの業務領域に、どのようなスキルを持つフリーランスを、どのような契約形態で活用するのかを戦略的に設計し、フリーランス人材マネジメントを人事戦略のコア機能として扱うべきである。
社内教育と文化醸成:
- 管理職への徹底した教育: プロジェクトマネージャーやチームリーダーなど、フリーランスと直接関わる可能性のある全ての管理職に対し、フリーランス新法の具体的な内容、特に禁止行為やハラスメント防止義務、そして「偽装フリーランス」と見なされかねない指揮命令の境界線について、定期的な研修を実施する。
- パートナーシップ文化の醸成: フリーランスを「下請け」ではなく、対等なビジネスパートナーとして尊重する企業文化を醸成する。公正な取引、円滑なコミュニケーション、そして成果に対する正当な評価を通じて、優秀なフリーランスから「選ばれる企業」となることが、長期的には最大の競争力となる。
5.3 ITフリーランスへの指針
フリーランス新法は、ITフリーランスにとって自らの権利を守るための強力な武器となる。この新たな法的保護を最大限に活用するため、以下の行動指針が推奨される。
新たな法的保護の積極的活用:
- 契約前の条件確認の徹底: 業務を開始する前に、必ず書面または電子メール等で取引条件の明示を求める。口頭での依頼や曖昧な指示に対しては、書面化を要求する権利があることを認識し、毅然と対応する。
- 支払期日の監視: 報酬支払いの60日ルールを正確に理解し、請求書に支払期日を明記する。期日を過ぎた場合は、速やかに、かつ記録が残る形で督促を行う。
契約リテラシーの向上:
- 契約書の精読: 提示された業務委託契約書の内容を細部まで注意深く確認する。特に、業務範囲、報酬、知的財産権の帰属、そして契約解除・不更新に関する条項は、自らに不利益な内容になっていないかを入念にチェックする。
- 交渉力の行使: 契約内容に不明な点や不公正と感じる点があれば、契約締結前に修正を求めることを躊躇しない。新法は、フリーランスがより対等な立場で交渉するための法的根拠を提供するものである。
サポートシステムの活用:
- 相談窓口の認知と準備: 取引先との間でトラブルが発生した場合に備え、「フリーランス・トラブル110番」のような無料で弁護士に相談できる公的窓口の存在を常に念頭に置く 6。連絡先や相談方法を事前に確認しておくことで、有事の際に迅速に行動できる。
- 権利主張の意識: フリーランス新法は、これまで慣習として見過ごされてきた不公正な取引に対して、フリーランスが自らの権利を主張するための明確な法的基盤を与えた。この法律を「お守り」としてではなく、自らのビジネスとキャリアを守るための「ツール」として能動的に活用する意識を持つことが重要である。
引用文献
- フリーランス保護法とは?いつから?内容や対策方法を解説, 9月 30, 2025にアクセス、 https://kigyobengo.com/media/useful/3317.html
- 公正取引委員会からのお知らせ>フリーランス・事業者間取引適正化等法について, 9月 30, 2025にアクセス、 https://www.nichizeiren.or.jp/whats-new/241009a/
- 2024年公正取引委員会フリーランス法特設サイト, 9月 30, 2025にアクセス、 https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号), 9月 30, 2025にアクセス、 https://www.jftc.go.jp/fllaw.html
- 【分かりやすく解説】フリーランス保護新法(フリーランス新法)とは?対象・内容を理解しよう!, 9月 30, 2025にアクセス、 https://keiyaku-daijin.com/media/about-freelancelaw-2024
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)等に係る取組について – 内閣官房, 9月 30, 2025にアクセス、 https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/freelance/index.html
- フリーランスの取引に関する 新しい法律が11 にスタート︕ – 中小企業庁, 9月 30, 2025にアクセス、 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/freelance/law_03.pdf
- フリーランス保護新法とは?いつから適用?わかりやすく解説 | SATO PORTAL, 9月 30, 2025にアクセス、 https://www.sato-group-sr.jp/portal/archives/927
- フリーランス保護新法とは?対象や罰則をわかりやすく解説, 9月 30, 2025にアクセス、 https://www.komon-lawyer.jp/qa/huriran/
- フリーランス新法はいつから施行?対象企業や必要な対応・罰則をわかりやすく解説 – 起業・開業お役立ち情報 – 弥生株式会社【公式】, 9月 30, 2025にアクセス、 https://www.yayoi-kk.co.jp/kigyo/oyakudachi/freelance-law01/
- フリーランス新法とは?対象や義務となる対応をわかりやすく解説! – HQ, 9月 30, 2025にアクセス、 https://hq-hq.co.jp/articles/241211_135
- 第1号 フリーランス新法(2024年秋頃までに施行予定) – Westlaw Japan, 9月 30, 2025にアクセス、 https://www.thomsonreuters.co.jp/ja/westlaw-japan/law_guide/2024/0402.html
- フリーランスが安心して働ける環境づくりのための法律、2024年11月からスタート!, 9月 30, 2025にアクセス、 https://www.gov-online.go.jp/article/202408/entry-6301.html
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)【令和6年11月1日施行】説明資料 – 中小企業庁, 9月 30, 2025にアクセス、 https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/freelance/law_02.pdf
- 公正取引委員会関係特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律施行規則(公正取引委員会規則第三号), 9月 30, 2025にアクセス、 https://www.jftc.go.jp/fllawjftcrules.html
- 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律の考え方 – 厚生労働省, 9月 30, 2025にアクセス、 https://www.mhlw.go.jp/content/001259281.pdf
- フリーランスの業務委託契約書の作り方と注意点、テンプレートを紹介 – PE-BANK, 9月 30, 2025にアクセス、 https://pe-bank.jp/guide/freelance/03/
- フリーランス新法で何が変わった?報酬・契約の新ルール – エンジニアファクトリー, 9月 30, 2025にアクセス、 https://www.engineer-factory.com/media/working/4157/
- 2024年11月施行「フリーランス新法」企業が知っておくべき規制対応と契約実務のポイント, 9月 30, 2025にアクセス、 https://nao-lawoffice.jp/venture-startup/labor-management/freelance-newlaw.php
- フリーランス保護新法とは?発注事業者が押さえておくべき内容を解説 – VWSシリーズ, 9月 30, 2025にアクセス、 https://vws-biz.com/column/freelance-new-law
- フリーランス新法とは?知っておくべきメリットや懸念点を詳しく解説 – PE-BANK, 9月 30, 2025にアクセス、 https://pe-bank.jp/guide/freelance/1205-01/
- フリーランス新法のポイントと業務委託契約書の見直しについて解説 – リーガルブレス D法律事務所, 9月 30, 2025にアクセス、 https://www.ys-law.jp/IT/%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9%E6%96%B0%E6%B3%95%E3%81%AE%E3%83%9D%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%88%E3%81%A8%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%A7%94%E8%A8%97%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8%E3%81%AE/
- ITフリーランスの案件希望者数が前年比136%に、 2024年11月の …, 9月 30, 2025にアクセス、 https://leverages.jp/news/2025/0730/5044/
- ITフリーランスの案件希望者数が前年比136%に、2024年11月の「フリーランス新法」施行後、約1.2倍に増加 | レバレジーズ株式会社のプレスリリース – PR TIMES, 9月 30, 2025にアクセス、 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000784.000010591.html
- 調査レポート一覧 – レバテック株式会社, 9月 30, 2025にアクセス、 https://levtech.co.jp/research/?c=%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9
- エン・ジャパン、ITフリーランス市場調査レポートを公開。ITフリーランスの市場規模は10年で1.6倍に成長見込み。現在活用中の企業の6割が「今後、活用を増やしたい」と回答。 | エン・ジャパン(en Japan), 9月 30, 2025にアクセス、 https://corp.en-japan.com/newsrelease/2025/42859.html
- 2025年版 – ITフリーランス市場調査レポート – PR TIMES, 9月 30, 2025にアクセス、 https://prtimes.jp/a/?c=725&r=1057&f=d725-1057-a13f7e9010d8f954241bda60ea89c786.pdf
- エン・ジャパンが発表したITフリーランス市場調査、2025年には1兆円超えの予測 – VOIX, 9月 30, 2025にアクセス、 https://voix.jp/business-cards/solo-proprietorship/en-japan-it-freelance-report/
- ITフリーランス人口は2024年に35万人を突破 – PR TIMES, 9月 30, 2025にアクセス、 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000116595.html
- 【Web版で無料公開開始】ITフリーランス及びフリーランスエージェント市場白書 2025 業界関係者から高評価、より多くの方にアクセス可能に | INSTANTROOM株式会社のプレスリリース – PR TIMES, 9月 30, 2025にアクセス、 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000116595.html
- 今さら聞けない「2025年の崖」問題。現状と課題、そしてフリーランスITエンジニアの可能性は?【情報処理安全確保支援士が解説】 | FREENANCE MAG, 9月 30, 2025にアクセス、 https://freenance.net/media/column/38870/
- デジタル人材を対象とした人材サービス市場に関する調査を実施(2025年) – 矢野経済研究所, 9月 30, 2025にアクセス、 https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3736
- 【2025年最新調査】IT/Webフリーランスエンジニアの市場動向とAI活用状況。8割以上が生成AIを活用、平均月単価は82.2万円 | ニュース | ファインディ株式会社(Findy Inc), 9月 30, 2025にアクセス、 https://findy.co.jp/2820/
- AI関連職種の単価が上昇! IT案件市況動向レポート2025年8月版を公開 – PR TIMES, 9月 30, 2025にアクセス、 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000198.000031814.html
- エンジニアの業務委託契約書の作成と注意点!フリーランスも活用するなら新法(保護法)への対応も, 9月 30, 2025にアクセス、 https://arrow-gyosei.com/archives/8484
- フリーランス新法施行前にITベンダーが見直すべきポイント – 企業向けオンライン法律相談「Web Lawyers」, 9月 30, 2025にアクセス、 https://web-lawyers.net/freelance_law/
- フリーランス保護新法にも対応!おすすめフリーランスマネジメントシステム6選【2025年最新】, 9月 30, 2025にアクセス、 https://saas.imitsu.jp/cate-freelance-management/article/l-2444
- フリーランス白書2025年, 9月 30, 2025にアクセス、 https://blog.freelance-jp.org/wp-content/uploads/2025/04/FreelanceSurvey2025.pdf
- フリーランス白書2025について, 9月 30, 2025にアクセス、 https://humalance.com/archives/column/column112
- フリーランス新法施行による効果と今後の課題 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング, 9月 30, 2025にアクセス、 https://www.murc.jp/library/column/sn_250515/
- 11月施行の「フリーランス保護新法」、約7割が「自社に与える影響が大きい」 – ITmedia, 9月 30, 2025にアクセス、 https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2409/20/news141.html
- フリーランス新法への対応について(ランサー向け) | クラウドソーシング「ランサーズ」, 9月 30, 2025にアクセス、 https://info.lancers.jp/33581
- 偽装フリーランスとは?判断基準や注意点、改善策を企業向けに解説 – クロスデザイナー, 9月 30, 2025にアクセス、 https://www.xdesigner.jp/contents/disguised-contract-freelance
- 偽装フリーランスの実態:業務委託のはずが雇用と変わらない現状|Iro – note, 9月 30, 2025にアクセス、 https://note.com/chick_6633/n/n9caab85eb65d
- 偽装フリーランスの問題点とは?雇用との違い、リスクについて解説 – セラク, 9月 30, 2025にアクセス、 https://www.seraku.co.jp/tectec-note/recruit/recruit_fakefreelancer/
- SESの良し悪しについて見解をまとめる – Qiita, 9月 30, 2025にアクセス、 https://qiita.com/wakka0014/items/6832d4f4bd6bc69cb069
- 結局自社開発/SIer/SES/フリーランスどれが良い? – Qiita, 9月 30, 2025にアクセス、 https://qiita.com/Sicut_study/items/56b9933ca4a780f89fba
- 相談件数は8月だけで642件。相談内容は「報酬の支払い」や「契約内容」が全体の5割強を占める ――厚生労働省などの「フリーランス・トラブル110番」の相談実績から – 労働政策研究・研修機構, 9月 30, 2025にアクセス、 https://www.jil.go.jp/kokunai/blt/backnumber/2022/11/k_03.html
- フリーランス・トラブル110番【厚生労働省委託事業・第二東京弁護士会運営】, 9月 30, 2025にアクセス、 https://freelance110.mhlw.go.jp/
- 【2024年11月1日施行】フリーランス保護新法とは?内容や下請法との違いをわかりやすく解説, 9月 30, 2025にアクセス、 https://freelance.levtech.jp/guide/detail/1680/