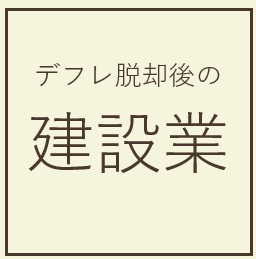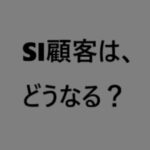この記事は、Gemini Deep Research にリサーチして執筆してもらったレポートです。
生成AIの書いた記事を修正すること無く、そのまま掲載しています。
一般常識として、「生成AIの書く記事には、ハルシネーションによる間違いが含まれている可能性がある」事を踏まえて記事を読んでください。
生成AIは完璧ではありません。
この記事のpromptは以下文書になります。
現在の日本の建設業界における、デフレ脱却と人手不足による経営状況をリサーチしてください。
特に、収益率の変化、商流変更や事業再編・経営統合や、人材確保の方法の変更、倒産状況などの動向も知りたいです。
また、人手不足を受けての設備投資・IT活用などの動向もリサーチしてください。
わからない事は、わからないと回答してください。
ハルシネーションは避けてください。
以降は、全て Gemini Deep Research の書いたレポートです。
岐路に立つ日本の建設業界:収益性、人手不足、そして戦略的適応に関する包括的分析
エグゼクティブサマリー
本レポートは、現在の日本の建設業界が直面する経営状況について、デフレ脱却に伴うコスト上昇と深刻化する人手不足という二つの構造的圧力の観点から詳細な分析を行う。旺盛な民間需要に支えられ、建設投資額は回復基調にある一方で、資材価格と労務費の急騰が企業の収益性を著しく圧迫している。特に、コスト上昇分を価格へ十分に転嫁できない中小企業は深刻な経営難に陥り、倒産件数は過去10年で最多を記録した。この状況は、業界内に明確な「二極化」を生み出している。
大規模・資本力のある企業は、M&Aによる人材・技術獲得や、i-Construction 2.0に代表される積極的なDX(デジタルトランスフォーメーション)投資を通じて生産性を向上させ、この難局に適応しつつある。対照的に、小規模事業者は人材確保難と利益圧縮の悪循環に陥り、市場からの退出を余儀なくされるケースが増加している。2024年4月から適用された時間外労働の上限規制、いわゆる「2024年問題」は、この構造変化を加速させる決定的な要因として機能している。
本レポートは、これらの動向を収益性、業界構造、人材戦略、倒産状況、設備投資の各側面から多角的に分析し、今後の建設業界が迎えるであろう変革の全体像と、各ステークホルダーが取るべき戦略的含意を提示する。
第1章 新たな経済的現実:高コスト・人手不足という事業環境
日本の建設業界は現在、コスト構造と労働市場の根本的な変化という、極めて困難な事業環境に直面している。旺盛な需要という追い風を受けながらも、資材と人件費のインフレ、そして構造的な労働力不足という二つの巨大な逆風が同時に吹き荒れており、すべての事業者にとって厳しい経営判断を迫る「るつぼ」のような状況を形成している。
1.1 市場需要の動向:二つのセクターが描く対照的な姿
建設市場全体としては回復基調にある。東日本大震災後の復興需要を契機に持ち直し、建設投資額は2024年度には74.2兆円に達する見込みであり、着実な成長を示している 1。建設工事の出来高も前年同月比で増加傾向にある 3。
しかし、その内実を見ると、成長の源泉は極めて偏っている。この成長は、旺盛な民間部門の需要によってほぼ全面的に牽引されている。大手建設会社50社の2024年度受注高は全体で前年度比5.3%増となったが、これは民間工事が8.9%増と力強く伸びた結果であり、今や民間工事が全体の72.0%を占めるに至っている 4。この需要は、サプライチェーンの見直しに伴う国内生産拠点の強化や、社会全体のデジタル化を背景としたデータセンター建設など、日本企業の戦略的設備投資によって支えられている 2。
一方で、公共工事と海外工事は対照的に縮小している。公共工事の受注高は4.1%減と3年ぶりのマイナスに転じ、海外工事も2.6%減と4年ぶりに減少した 4。特に公共工事の落ち込みは、財政的な制約からか地方自治体レベルで顕著であり、建設業界の民間需要への依存度を一層高め、景気循環リスクを増大させる構造となっている 4。
1.2 デフレの終焉:まん延するコストインフレーション
長期にわたったデフレ経済からの脱却は、建設業界に深刻なコスト上昇圧力をもたらしている。
第一に、資材価格の衝撃である。2021年後半から、世界的な原材料費やエネルギー価格の高騰を受け、主要な建設資材の価格が急騰し、高止まりしている 6。具体的なデータを見ると、生コンクリート(前年同月比+14.5%)やセメント(同+12.6%)といった基幹資材の価格が大幅に上昇しており、一部資材に価格の落ち着きが見られるものの、全体としては依然として高い水準にある 1。このコスト上昇は、顧客への価格転嫁が実現できなければ、プロジェクトの利益を直接的に侵食する 11。
第二に、労務費の急騰である。政府は経済界全体に賃上げを強力に推進しており、建設業界もその例外ではない。公共工事のコスト算定の基準となる公共工事設計労務単価は12年連続で引き上げられ、直近では前年度比5.9%増と、一般の消費者物価指数の伸びを上回る大幅な上昇となった 13。2025年度の改定においても平均5.9%の上昇が見込まれ、一部職種では6%を超える伸びが示されている 15。さらに、大手ゼネコン各社は初任給を6~9%引き上げるなど、業界全体の賃金水準を押し上げる動きを主導している 14。
1.3 人口動態の崖:深刻化する人的資本の危機
コスト上昇と並行して、建設業界は構造的かつ不可逆的な人的資本の危機に直面している。
業界の就業者数は、1997年のピーク時から約30%減少し、現在は477万人となっている 1。問題は単なる人数の減少だけでなく、年齢構成の極端な歪みにある。就業者のうち55歳以上が36.7%を占める一方、将来を担う29歳以下はわずか11.7%に過ぎない 1。全技能労働者の約4分の1が60歳以上であり、今後10年でその大半が引退すると見込まれている 1。これは一時的な景気循環の問題ではなく、日本の人口動態に根差した構造的な課題である。
この状況をさらに悪化させているのが、「2024年問題」である。2024年4月から建設業にも時間外労働の上限規制が適用された。これは労働者の健康を守るために不可欠な改革であるが、労働者一人当たりの投入可能な労働時間を直接的に減少させるため、ただでさえ不足している労働力をさらに制約する結果となっている 9。企業は、限られた時間内でこれまでと同等以上の成果を出すために、追加の人員を確保するか、あるいは生産性を飛躍的に向上させるかの選択を迫られている。
この「旺盛な需要」と「高騰するコスト」、「逼迫する労働力」という三つの要素が複雑に絡み合い、現在の建設業界の経営環境を極めて厳しいものにしている。トップラインの成長機会は豊富に存在するものの、それを利益に結びつけるためのコスト管理と人材確保がかつてなく困難になっている。この「高需要・高コストのパラドックス」こそが、現代の建設業界が直面する最も根源的な課題であり、企業の適応能力が厳しく問われる時代が到来したことを示唆している。
表1:日本の建設業界の主要指標(複数年トレンド)
| 指標 | ピーク時 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 (見通し) |
|---|---|---|---|---|
| 建設投資額 (兆円) | 84.0 (1992年度) | 67.0 | 70.3 | 74.2 |
| – うち政府投資 (兆円) | – | 23.3 | 23.1 | 22.9 |
| – うち民間投資 (兆円) | – | 43.7 | 47.2 | 51.3 |
| 許可業者数 (万業者) | 60.1 (1999年度末) | 47.5 | 47.9 | 48.0 |
| 就業者数 (万人) | 685 (1997年) | 479 | 479 | 477 |
| 就業者年齢構成 | – | – | – | – |
| – 29歳以下 (%) | – | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| – 55歳以上 (%) | – | 35.9 | 36.0 | 36.7 |
出典: 1 のデータを基に作成
第2章 収益性への圧力:利益率の動向と企業倒産の分析
第1章で概説した高コスト・人手不足という厳しい事業環境は、建設業界の財務パフォーマンスに直接的な影響を及ぼしている。本章では、企業の収益性がどのように変化し、それが企業倒産の増加にどう結びついているかを分析する。データが示すのは、業界内で企業の適応能力による格差が拡大し、「二極化」が進行しているという厳しい現実である。
2.1 マージンの圧迫:低下する収益性
建設業界の利益率は、建設投資の回復を背景に2012年度以降上昇傾向にあり、売上高営業利益率は数年間にわたり4%台という健全な水準を維持してきた 5。しかし、この安定期は終わりを告げつつある。
近年のデータは、収益性が明確な低下傾向にあることを示している。売上高営業利益率は2021年度に3%台に落ち込み、2023年度に再び同水準まで低下した 22。これは、コスト上昇の圧力が売上高の伸びを上回り始めていることを示す危険信号である。大手建設会社においては、2024年度に売上高総利益率が11.0%まで回復する動きも見られるが、これは業界全体の状況を代表しているとは考えにくい 5。特に、交渉力の弱い中小企業は、より深刻な利益圧縮に苦しんでいる可能性が高い。
この収益性悪化の根源にあるのが、価格転嫁の困難さである。調査によれば、74%以上の企業がコスト上昇分の一部を価格に転嫁できていると回答しているものの、上昇分を100%転嫁できている企業はわずか4.5%に過ぎない 6。平均価格転嫁率は43.6%にとどまっており、これは仕入価格が100円上昇しても、売価を43.6円しか引き上げられていないことを意味する 6。残りの56.4円は企業が吸収せざるを得ず、直接的に利益率を圧迫する構造となっている 11。建設業界特有の重層下請構造は、この問題をさらに深刻化させており、下位の下請企業になるほど価格転嫁が困難になる傾向がある 6。
2.2 増加の一途をたどる倒産
収益性の悪化は、企業の存続そのものを脅かし始めている。2024年の建設業の倒産件数は1,890件に達し、過去10年間で最多を更新、3年連続の増加となった 5。
この倒産急増の最も顕著な特徴は、その危機が中小・零細企業に極度に集中している点である。倒産した企業の実に92.2%が従業員数10人未満の事業者であり、大半が負債額5,000万円未満であった 24。これは、業界の末端を支える最も脆弱なプレーヤーが、現在の経済環境の変化に耐えきれずに淘汰されている実態を浮き彫りにしている。
倒産の主要因は、第1章で述べた圧力と完全に一致している。具体的には、資材価格の高騰に対応できない「物価高倒産」、人件費の上昇や職人不足による「人手不足倒産」が顕著である 24。これに加え、コロナ禍で導入された実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)の返済開始が、多くの中小企業の資金繰りをさらに圧迫していることも要因として挙げられる 24。
この状況は、業界内で深刻な「二極化」が進行していることを明確に示している。大手企業は、その規模と市場での交渉力を活かしてコストを管理し、技術投資を行い、人材を惹きつけることで収益性を維持、あるいは向上させている 5。一方で、中小企業は利益圧縮と資源不足の悪循環に陥り、倒産という形で市場からの退出を余儀なくされている 24。現在の市場は単に成長しているのではなく、弱者の淘汰を通じた再編・集約の過程にあると言える。
また、多数の「物価高倒産」は、業界の伝統的な見積・契約モデルが現代のボラティリティの高い経済環境に対応できていないという、より根深い問題を示唆している。特に中小企業は、契約後に発生した急激なコスト上昇を価格に反映させる交渉力や契約上の仕組みを持たず、致命的な打撃を受けている。倒産の急増は、この構造的欠陥がもたらした必然的な帰結なのである。
表2:主要な収益性指標の動向分析
| 会計年度 | 売上高総利益率 (%) | 売上高営業利益率 (%) | 自己資本比率 (%) |
|---|---|---|---|
| 平成28年度 | – | 4.0台 | – |
| 令和元年度 | – | 4.0台 | 低下 |
| 令和2年度 | 上昇傾向 | 4.0台 | 上昇 |
| 令和3年度 | 上昇傾向 | 3.0台に低下 | 上昇 |
| 令和4年度 | 上昇傾向 | 回復 | 上昇 |
| 令和5年度 | 上昇傾向 | 3.0台に再び低下 | 上昇 |
出典: 22 のデータを基に作成。売上高総利益率と自己資本比率の具体的な数値は非開示だが、傾向が示されている。
表3:建設業界の倒産分析(2024年)
| カテゴリー | 件数 | 前年比増減 (%) |
|---|---|---|
| 倒産総数 | 1,890 | 増加 |
| 従業員規模別 | ||
| – 10人未満 | 1,742 (全体の92.2%) | 増加 |
| – 10人以上50人未満 | 143 | 増加 |
| 業種別 | ||
| – 職別工事 | 879 | 増加 (過去10年で最多) |
| – 総合工事 | 600 | 増加 |
| – 設備工事 | 411 | 増加 (過去10年で最多) |
| 要因別 | ||
| – 物価高倒産 | 250 | 増加 |
| – 人手不足倒産 | 99 | 増加 |
| – ゼロゼロ融資後倒産 | 143 | 増加 |
出典: 24 のデータを基に作成。
第3章 人的資本の危機:労働力動態の変化と人材獲得戦略
建設業界が直面する課題の中で、最も構造的で解決が困難なのが人的資本の危機である。本章では、労働力不足の動態を深掘りし、近年の規制が与える影響を分析するとともに、企業が採用、定着、そして労働力の多様化においてどのような戦略的転換を図っているかを詳述する。
3.1 労働市場の動向:人材獲得競争の激化
建設業界の人手不足は、単に全体の人数が減少しているだけでなく、その内部で深刻な人材の偏在化が起きている。
特筆すべきは、労働力の「大移動」である。特に30~40代の働き盛りの層が、従業員29人以下の地方の中小企業から、100人以上の大都市圏の大企業へと流出する傾向が顕著に見られる 26。この業界内での人材流出は、中小企業セクターの空洞化を招き、競争力をさらに削いでいる。年間約17.7万人が業界内で転職しており、これは新規学卒者の流入や定年退職者の流出よりも大きなインパクトを持つ変動要因となっている 26。
従業員が企業を去る理由は、賃金だけではない。分析によると、離職の主な動機として、日給月給制などの不安定な雇用形態、現場移動に伴う負担の大きさ、そして休暇の取りにくさが挙げられており、賃金は4番目の理由に過ぎない 26。これは、安定した雇用と働きやすい環境の提供が、高い給与を提示することと同等、あるいはそれ以上に人材定着において重要であることを示唆している。
この人材獲得競争をさらに激化させているのが「2024年問題」である。ある調査では、建設会社の74%が2024年4月の規制適用開始に未対策であると回答しており、多くの企業が対応に苦慮している実態が明らかになった 27。長時間労働に依存できなくなった今、企業は生産性を向上させるか、さもなければ新たな人材を雇用するしかない 21。しかし、対策が進まない最大の理由として「工期を守ることが優先されるから」という現場の切実な事情が挙げられており、働き方改革と事業継続の狭間で多くの企業がジレンマに陥っている 9。
3.2 進化する人事戦略:新たな人材獲得・育成手法
深刻な人材不足は、保守的と言われる建設業界に人事戦略の根本的な見直しを強いている。
採用チャネルは、伝統的な手法からデジタルへと大きくシフトしている。ハローワーク経由の中途採用は全体の18%に過ぎず、その有効性は低下している 26。代わって、企業はWeb広告や、特にInstagram、TikTok、X(旧Twitter)といったSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を積極的に活用し、若年層へのリーチを図っている 28。その目的は、従来の「きつい・汚い・危険」という3Kのイメージを払拭し、現代的で魅力的な職場としてのブランディングを行うことにある 28。
同時に、労働力の多様性の確保が喫緊の課題となっている。
女性の活躍推進:国や企業は、女性が働きやすい環境を整備するための取り組みを強化している。現場に女性専用の更衣室や快適なトイレを設置したり、ロールモデルとなる女性技術者を積極的に広報したりする事例が見られる 32。大手ゼネコンの竹中工務店は、女性技術者の採用比率に具体的な目標を設定し、その比率を着実に高めることに成功している 35。
外国人材の活用:外国人労働者は、不足する労働力を補う重要な担い手として、その存在感を急速に増している。在留資格「特定技能」を持つ労働者数は2024年に倍増し、技能実習生と合わせると15万人を超える規模に達した 36。これはまだ全就業者数から見れば数パーセントに過ぎないが 26、建設分野では今後5年間で8万人の受け入れ目標が設定されており、極めて重要な労働力の供給源となっている 37。ただし、日本語能力の向上が円滑な就労に向けた課題として指摘されている 39。
人材を巡るこれらの動きは、建設業界が大きな文化的変革の入り口に立っていることを示している。SNSの活用、ワークライフバランスの重視、そして女性や外国人材の積極登用といった動きは、単なる小手先の対策ではない。これらは、人手不足という外部からの強烈な圧力によって、業界が長年抱えてきた古い体質や労働慣行を根本から見直さざるを得なくなった結果であり、生き残りをかけた必死の適応戦略なのである。
表4:公共工事設計労務単価の推移(全国・全職種単純平均)
| 適用年月 | 1日当たり単価 (円) | 前年度比上昇率 (%) |
|---|---|---|
| 2023年3月 | 22,227 | 5.2 |
| 2024年3月 | 23,600 | 5.9 |
| 2025年3月 | 24,852 | 5.3 |
出典: 13 のデータを基に作成。
第4章 構造変革:M&A、サプライチェーン再編、そしてビジネスモデルの転換
第1章から第3章で詳述した深刻な経営環境は、企業戦略および業界構造そのものに大きな変革を促している。本章では、企業や政策当局がこの新たな環境に対応するために進めている、M&A、サプライチェーンの改革、そして事業モデルの転換といった構造的な変化について分析する。
4.1 集約と能力獲得:M&Aの活発化
建設業界では近年、M&Aが明確な増加傾向にあり、年間約34件の取引が成立している 40。これは単なる事業規模の拡大を目的としたものではなく、業界が直面する根源的な課題を解決するための戦略的手段として位置づけられている。
M&Aを駆動する主な要因は以下の通りである。
- 人材の確保:有資格の技術者や熟練技能者を確保する上で、企業買収は最も直接的かつ迅速な手段となっている 41。
- 技術・能力の強化:大手企業が、海洋土木やBIM/CIMといったデジタル技術など、自社にない専門能力を持つ企業を買収し、事業領域を拡大する動きが活発化している 41。
- 地理的展開:有力な地場企業を買収することで、新たな地域市場へ効率的に参入する戦略も多く見られる 40。
- 事業承継問題の解決:経営者の高齢化と後継者不足(後継者難)に悩む多くの中小企業にとって、M&Aは事業と従業員の雇用を維持するための有力な選択肢となっている 18。
かつては機会主義的な動きと見なされがちだったM&Aは、今や人材不足と技術革新の必要性という二つの避けられない課題に対応するための、中核的な経営戦略へとその重要性を増している。このトレンドは、業界がより集約され、多様な能力を持つ大規模なプレーヤーが主導する形へと再編されていく未来を示唆している。
4.2 構造の根幹に挑む:重層下請構造の改革
建設業界の長年の課題である重層下請構造は、生産性の低下や、末端の技能労働者の処遇悪化の温床と指摘されてきた 23。下位の下請企業ほど価格交渉力が弱く、賃金や経費が中間段階で搾取されやすい構造となっている 23。
この根深い問題に対し、国土交通省は本格的な改革に乗り出している。
- 透明性と公正性の向上:改正建設業法では、元請企業に対し、下請契約において労務費相当額を著しく下回る契約とならないよう配慮する「配慮義務」が新たに課された 45。また、賃金の目安となる「標準労務費」を国が勧告できる仕組みも導入される 45。
- 不要な中間業者の排除:契約上は存在するものの、実質的な施工管理を行わない企業をサプライチェーンから排除する方針が明確化されている 44。
- 下請次数の制限:一部の地方自治体では、公共工事において下請次数を2次や3次までに制限する試みが始まっており、施工体制の明確化や下請企業の利益向上といった効果が報告されている 46。
- 監督と実態調査の強化:国土交通省は、重層下請構造の実態を正確に把握し、今後の政策立案に活かすため、全国的なアンケート調査を実施するなど、監視体制を強化している 47。
これらの政策は、業界の健全な発展のためには下請企業の経営安定が不可欠であるという政府の強い認識を反映している。特に労務費に関する新たな規制は、元請と下請の間の力関係を是正し、第2章で指摘した「機能不全に陥ったコスト算定モデル」を根本から修復しようとする重要な試みである。これは、伝統的で時に一方的であった受発注関係のあり方を、より公正で持続可能なパートナーシップへと転換させることを目指す、業界構造への直接的な介入と言える。
4.3 サプライチェーンとビジネスモデルの調整
企業レベルでも、外部環境の変化に対応した戦略的な調整が進んでいる。
- サプライチェーンの強靭化:世界的な供給網の混乱を受け、多くの製造業が生産拠点を国内に回帰させる動きを見せており、これが新たな工場建設の需要を生み出している 2。建設業界内部でも、プレキャスト部材の規格化などを通じて、サプライチェーンの効率化を図る動きが見られる 49。
- 維持・改修市場へのシフト:日本の社会インフラや建築ストックの老朽化に伴い、新設工事と並んで、補修・改修(リフォーム)工事の市場が著しく成長している 2。この分野は、景気変動の影響を受けにくい安定した収益源となる可能性があり、多くの企業が事業の柱として強化を進めている。
なお、提供された資料からは、建設資材の共同購入といった具体的なコスト削減策が業界内で広く普及しているかについての詳細な事例やデータは確認できなかった。この種の協力体制は他産業では見られるものの 51、建設業界におけるその動向は不明である。
第5章 テクノロジーという責務:人手不足への回答としての設備投資とDX
慢性的な人手不足と生産性向上の要請に直面する建設業界にとって、テクノロジーの積極的な導入はもはや選択肢ではなく、生き残りと成長のための必須戦略となっている。本章では、政府主導のビジョンから、BIM/CIMのような基盤技術、そしてAIやドローンといった最先端技術の活用事例まで、業界のデジタルトランスフォーメーション(DX)の現状を詳述する。
5.1 政府のビジョン:i-Construction 2.0
国土交通省が推進する「i-Construction 2.0」は、業界のDXを主導するトップダウンの国家戦略である。その中核的な目標は、人口減少社会においても持続可能なインフラ整備を可能にすることであり、具体的には「建設現場のオートメーション化」を通じて、2040年度までに生産性を1.5倍(=3割の省人化)に向上させることを目指している 25。これは、日本の人口動態という不可避な変化に対する直接的な回答である 54。
この戦略は、以下の三つの柱で構成されている 54。
- 施工のオートメーション化:遠隔操作や自律走行が可能な建設機械、AIによる施工支援、建設ロボットなどを活用し、現場作業の自動化・省人化を図る。
- データ連携のオートメーション化:設計から施工、維持管理に至る全プロセスでデジタルデータを一気通貫で活用する。その中核をなすのが、後述するBIM/CIMの原則適用である。
- 施工管理のオートメーション化:デジタルツールやドローンによる遠隔臨場、データ分析を駆使して現場管理を効率化し、書類作業の削減や事務所からの遠隔監督(オフサイト化)を推進する。
5.2 基盤技術:BIM/CIMの導入
i-Construction 2.0の根幹をなすのが、BIM/CIM(Building/Construction Information Modeling, Management)である。これは、構造物の3次元デジタルモデルに、形状情報だけでなく、部材、コスト、工程といった多様な属性情報を統合する仕組みである 59。
BIM/CIMの導入は、建設プロセスに革命的な変化をもたらすことが実証されている。
- フロントローディングの実現:設計の初期段階で、3次元モデル上で部材の干渉チェックや施工上の問題点を事前に洗い出すことができる。これにより、現場での手戻りや設計変更といった、コストと時間の浪費を劇的に削減できる 59。
- 合意形成の円滑化:3次元モデルは、発注者や地域住民、協力会社など、すべての関係者にとって直感的で分かりやすい「唯一の正しい情報源(Single Source of Truth)」となる。これにより、認識の齟齬を防ぎ、円滑なコミュニケーションと迅速な意思決定を促進する 60。
- 生産性の向上:導入事例では、BIM/CIMの活用によって地元説明会や協議の時間が半減したり、設計変更にかかる作業時間が3分の1に短縮されたりするなど、具体的な効果が報告されている 60。
国土交通省は、公共工事においてBIM/CIMの原則適用を段階的に進めており、その導入を強力に後押ししている 62。
5.3 最先端技術の応用:AI、ドローン、ロボティクス
BIM/CIMというデジタル基盤の上で、AIやドローンといった最先端技術が具体的な生産性向上ツールとして実装され始めている。
ドローン:測量、進捗管理、検査といった領域で広く活用されている。従来は数日を要した広範囲の測量作業が数時間で完了するなど、効率と安全性を飛躍的に向上させている 64。
AI(人工知能):AIの画像認識技術は特に応用範囲が広い。
- 施工管理:ドローンや定点カメラの映像をAIが解析し、資機材の在庫を自動で把握(鹿島建設の事例では作業時間を75%削減)、工事の進捗を管理し、ヘルメット未着用などの危険行動を自動で検知する 64。
- 品質管理:コンクリートのひび割れや配筋検査などをAIが自動で行い、品質を均一化するとともに、検査時間を最大60%短縮した事例もある 64。
- 設計:建物のファサードデザイン案を自動生成するなど、設計プロセスを支援するAIも登場している 64。
ロボティクス:鉄筋結束(大成建設の事例では作業効率を20%向上)のような反復作業や、危険区域の巡回などを、自律走行ロボットや遠隔操作ロボットが担い始めている 58。
これらのテクノロジーは、もはや単なる補助的なツールではない。BIM/CIMを使いこなし、AIやドローンを業務プロセスに深く組み込む能力そのものが、企業の競争優位性を決定づける時代に突入している。これらの技術を統合し、現場の物理的な状況とリアルタイムで連動する仮想空間モデル「デジタルツイン」を構築すること 54。それがi-Construction 2.0が目指す究極の姿であり、建設管理を「現場での事後対応型」から「データに基づく予測・遠隔管理型」へと根本的に変革する可能性を秘めている。
表5:i-Construction 2.0の取り組みと目標成果の概要
| オートメーション化の柱 | 主要な取り組み・技術 | 具体的な研究事例 | 目標成果 |
|---|---|---|---|
| 1. 施工のオートメーション化 | ・建設機械の遠隔操作・自律施工 ・AIによる施工支援 ・建設ロボットの導入 | ・自律走行式の鉄筋結束ロボット ・山岳トンネル工事での自動施工の試行 | ・現場作業員の削減 ・労働災害リスクの低減 ・熟練技能への依存度低下 |
| 2. データ連携のオートメーション化 | ・BIM/CIMの原則適用 ・設計から維持管理までの3次元データ一元化 ・デジタルツインの構築 | ・3次元モデルを契約図書として活用 ・3次元モデルと2次元図面の連動ルール策定 | ・手戻り・設計ミスの撲滅 ・関係者間の円滑な情報共有 ・ライフサイクルコストの最適化 |
| 3. 施工管理のオートメーション化 | ・ウェアラブルカメラ等による遠隔臨場 ・AI画像解析による進捗・安全・品質管理 ・書類作成の自動化 | ・ドローンとAIによる資機材管理システム ・AIによるコンクリート打継面の自動評価 | ・現場監督業務のリモート化・オフサイト化 ・検査業務の効率化と高度化 ・ペーパーレス化の推進 |
出典: 25 のデータを基に作成。
第6章 統合的考察と戦略的展望
本レポートで分析してきた通り、日本の建設業界は、コスト上昇と人手不足という構造的な圧力の下で、淘汰と再編を伴う大きな変革期にある。この最終章では、これまでの分析を統合し、業界の未来像を展望するとともに、各ステークホルダーが取るべき戦略的指針を提示する。
6.1 不可避の二極化:成功と淘汰の企業像
今後の建設業界では、適応能力の差によって企業の運命が明確に分かれる「二極化」が一層進行するだろう。
「未来に対応する企業」のプロファイル:
今後10年で成功を収める建設企業は、以下の特徴を持つと考えられる。
- 規模と財務力:短期的なコストショックを吸収し、大規模な技術投資を継続できる財務基盤を持つ。
- 技術的優位性:BIM/CIM、データ分析、現場の自動化技術を単なるツールとしてではなく、中核的な業務プロセスとして深く統合している。
- 選ばれる雇用主:安定した給与体系、安全で現代的な労働環境、明確なキャリアパスを提供し、希少な人材を惹きつけ、定着させる能力を持つ。
- 協調的パートナーシップ:旧来の受発注関係から脱却し、公正で透明性の高い、強靭なサプライチェーンを構築している。
「リスクに瀕する企業」のプロファイル:
一方で、経営難に陥る、あるいは市場から退出する可能性が高い企業は、以下の特徴を持つ。
- 小規模・脆弱な資本:利益圧縮に対する耐性が低く、未来への投資余力がない。
- アナログな事業運営:労働集約的で生産性の低い、伝統的な手法に依存し続けている。
- 魅力のない雇用主:賃金や労働条件で競争できず、常に人材確保に苦慮している。
- サプライチェーンにおける弱者の立場:上位企業からの価格圧力に抗えず、コスト上昇分を転嫁できない。
6.2 ステークホルダーへの戦略的提言
この変革期を乗り切るためには、各主体が自らの役割を再定義し、能動的に行動する必要がある。
- 建設企業:デジタルトランスフォーメーションを、コストではなく生存のための投資と位置づけ、経営の最優先課題として取り組むべきである。人事部門を単なる管理部門から、人材獲得と育成を担う戦略機能へと昇華させる必要がある。規模の経済と新たな能力を獲得するため、M&Aや戦略的提携を積極的に検討すべきである。
- 発注者(デベロッパー・施主):デフレ時代の安価な建設コストは過去のものであると認識を改める必要がある。資材価格の変動リスクを建設会社のみに負わせるのではなく、公正なリスク分担の仕組みを契約に盛り込むことが、自らのプロジェクトの成功とサプライチェーン全体の健全性維持に不可欠である。
- 政府・政策当局:i-Construction 2.0による技術導入の推進と、重層下請構造の改革という二つの柱を引き続き強力に推進すべきである。同時に、BIM/CIMやデータサイエンスを使いこなせる次世代の建設技術者を育成するため、教育・訓練プログラムの抜本的な強化が求められる。
6.3 結論的展望:変革後の産業像
現在業界を襲っている圧力は、一過性の嵐ではなく、恒久的な気候変動である。今後数年間で、業界の集約はさらに進むだろう。その結果として現れる未来の建設業界は、企業数こそ減少するものの、より技術集約的で、生産性が高く、そして持続可能な産業へと変貌を遂げているはずである。この移行プロセスは多くの企業にとって痛みを伴うものとなるが、縮小する労働力で日本の未来のインフラ需要に応えていくためには、避けては通れない進化の道程である。
引用文献
- 最近の建設産業行政について – 厚生労働省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001566406.pdf
- 【2025年版】建設業界の最新市場動向を徹底分析!中小企業が取るべき経営戦略とは?, 11月 2, 2025にアクセス、 https://mkensetu.jp/latest-market-trends/
- 国土交通省調査、8月の建設業界は増加傾向で民間土木が19.2%の大幅増、堅調に推移, 11月 2, 2025にアクセス、 https://news.build-app.jp/article/37922/
- 【2024年度・大手50社】建設工事受注高が4年連続増加!サービス …, 11月 2, 2025にアクセス、 https://kensetsu-data.co.jp/blog/blog_detail.php?id=629
- 2. 企業経営 | 建設業の現状 – 日本建設業連合会, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.nikkenren.com/publication/handbook/chart6-2/index.html
- 建設業の価格転嫁 ~資材の高騰を受けて~ – 建設 IT NAVI, 11月 2, 2025にアクセス、 https://process.uchida-it.co.jp/itnavi/column/20231220/
- 最近の建設業を巡る状況について【報告】 – 国土交通省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001734007.pdf
- 建設業界の今後は?現状や2024問題から課題まで徹底解説, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.kentem.jp/blog/construction-fromnow-on/
- 建設業界の2024年問題とは?独自調査結果や事例をもとに課題 …, 11月 2, 2025にアクセス、 https://andpad.jp/columns/0052
- 資材価格が歴史的な高騰、なお注目が必要 – 建設物価調査会, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.kensetu-bukka.or.jp/chousa_report/10758/
- 【2025年最新】建築資材の高騰と市場動向・今後の対応策も解説 | Grid – エルライン, 11月 2, 2025にアクセス、 https://lline-group.co.jp/magazine/building-materials-prices-soaring/
- 建設資材価格の高騰と公共投資への影響について – 内閣府, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www5.cao.go.jp/keizai3/shihyo/2022/1212/1293.pdf
- 公共工事設計労務単価、12年連続の引き上げ – 建設物価調査会, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.kensetu-bukka.or.jp/article/13429/
- 【2024年】建設業の賃上げは5%以上。取り組みや助成金を紹介 – 現場クラウド Conne, 11月 2, 2025にアクセス、 https://conne.genbasupport.com/tips-9664/
- 公共工事設計労務単価、13年連続の引き上げ – 建設物価調査会, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.kensetu-bukka.or.jp/article/15002/
- 知っておくべき!建設業 労務単価の実際と2026年度予測【業界情報】, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.arc-navi.shikaku.co.jp/column/details.php?column_id=3753
- 建設業をとりまく現状と課題, 11月 2, 2025にアクセス、 https://tekitori.or.jp/files/libs/1943/202506191417465727.pdf
- 最近の建設業を巡る状況について – 国土交通省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001493958.pdf
- 【最新版】建設業の職人不足を解消する10の対策|原因やICT化の事例もご紹介します! – リコー, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.ricoh.co.jp/service/remote-field/column/article-construction-industry-eliminate
- 建設業2024年問題とは?概要や課題、建設業の働き方改革について解説 – Buildee, 11月 2, 2025にアクセス、 https://service.buildee.jp/workstyle/ws_mag004/
- 建設業の2024年問題とは?背景や影響、労働環境改善に繋がる対応方法を解説 – Japan-build, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.japan-build.jp/hub/ja-jp/column/kdx/03.html
- 「建設業の経営分析(令和5年度)」 (概要版) 1. 調査の概要, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.ciic.or.jp/wp-content/uploads/2025/01/bunseki_R05_gaiyouban.pdf
- 重層下請構造の改善に向けた 取組について – 国土交通省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mlit.go.jp/common/001236203.pdf
- 「建設業」倒産動向調査(2024年)|株式会社 帝国データバンク …, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tdb.co.jp/report/industry/20250121-kensetsutousan/
- 建設業界の最新動向2025 ~市場概況、制度改正、建設コストの …, 11月 2, 2025にアクセス、 https://process.uchida-it.co.jp/itnavi/info/c20250317/
- 2024年問題は「人手不足」の建設会社の経営にどう影響するのか …, 11月 2, 2025にアクセス、 https://souken.craft-bank.com/analisys/tenshoku2024/
- 建設業の2024年問題に関する動向調査:2024年版 | クラフトバンク株式会社のプレスリリース, 11月 2, 2025にアクセス、 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000025.000080019.html
- 建設業界の採用戦略にSNSを活用する理由とは?効果的な進め方や成功事例を紹介, 11月 2, 2025にアクセス、 https://marugotoinc.jp/blog/kensetsu_sns/
- 採用に悩む建設会社のためのWEB・SNS活用戦略を解説!, 11月 2, 2025にアクセス、 https://legacy-jp.com/posts/393
- 建設業界における効果的なSNS採用戦略:人材不足を解決する最新アプローチガイド, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.hey-create.jp/post/20250623
- 【建設業界のSNS戦略】採用活動と社員教育を強化する方法 – 現場ラボ, 11月 2, 2025にアクセス、 https://genba-lab.com/2024/07/03/social-media-strategy/
- 建設業の魅力向上 – 東京都インフラポータルサイト, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.infura.metro.tokyo.lg.jp/attraction.html
- 建設産業・不動産業:【過去の取組】建設産業における女性の定着促進に向けた取組について, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_tk2_000001_00040.html
- 性活躍 援に取り組む – 地域ネットワーク 事例集, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.kensetsu-kikin.jp/woman/wp-content/themes/woman_network/pdf/chiiki-network_2016.pdf
- 株式会社竹中工務店 (建設業) – 女性の活躍推進や両立支援に積極的に取り組む企業の事例, 11月 2, 2025にアクセス、 https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/practice/detail?id=42
- 建設業の外国人材、24年に15万人突破 特定技能は倍増―厚労省 | 新建ハウジング, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.s-housing.jp/archives/396780
- 建設業で働く外国人労働者は約18万人で前年比22.7%増。ベトナム人が約7万人で最多【厚生労働省】 – 総合資格navi, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.arc-navi.shikaku.co.jp/column/details.php?column_id=3671
- 特定技能制度の現状について – 法務省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.moj.go.jp/isa/content/001397709.pdf
- 【全建】技能実習生多い/外国人材の活用状況 – 日本工業経済新聞社, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.nikoukei.co.jp/news/detail/539421
- 【2025年最新】建設・土木業界のM&A動向 | M&A仲介・アドバイザリーのご相談はストライク, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.strike.co.jp/ma_trend/construction/
- 建設コンサル業界のM&A動向(2025年)メリットデメリット/事例/成功のポイントを解説, 11月 2, 2025にアクセス、 https://cinc-capital.co.jp/column/industry/construction-consulting-ma
- 【最新動向】建設業界におけるM&Aの現況とデータ分析 – 村上事務所|, 11月 2, 2025にアクセス、 https://mkensetu.jp/news/ma/
- 建設業のM&A動向と売却・買収事例15選!メリットや成功へのポイントも解説!【2025年最新】, 11月 2, 2025にアクセス、 https://masouken.com/%E5%BB%BA%E7%AF%89%E6%A5%AD%E3%81%AEM&A
- 重層下請構造の問題点, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mlit.go.jp/common/001132804.pdf
- 【建設業法改正】元請の「努力義務」とは?標準労務費と労働者の処遇改善への影響, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.kendweb.net/tip/456048/
- 【下請次数制限】 8府県で取り組み進む/重層構造改善に効果あり – 建設資料館, 11月 2, 2025にアクセス、 https://kd-file.jp/wp/7987/
- 【アンケートを終了しました】国土交通省 「重層下請構造の実態調査」へのご協力のお願い – PwC, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.pwc.com/jp/ja/news-room/2025/mlit-research.html
- 2025/06/26 国交省/重層下請構造でアンケート開始、元下双方から実態・課題把握, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.wise-pds.jp/news/2025/news2025062601.htm
- 建設現場におけるサプライチェーン マネジメントの導入, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mlit.go.jp/common/001176466.pdf
- 建材・住宅設備サプライチェーンにおける物流効率化に向けた 2030年までのアクションプランに – 経済産業省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/mono/jyutaku/20240423_02.pdf
- 共同購買とは?共同購買はハードルが高い購買方法とされる4つの理由 – 購買管理 ビズネット, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www2.biznet.co.jp/column/887/
- 4. 共同調達の可能性, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.tokyo23-kuchokai-kiko.jp/report/docs/r01_04shibuya_h104.pdf
- 共同調達・購入カルテルに関する競争法上の考察 – 慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA), 11月 2, 2025にアクセス、 https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/download.php/AA1203413X-20160825-0003.pdf?file_id=115098
- i-Construction 2.0 – ~建設現場のオートメーション化に向けて – 内閣府 沖縄総合事務局, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.ogb.go.jp/-/media/Files/OGB/Kaiken/kyoku/about/gikan/setumeikai/R06/PDF_R060501_04_shiryou_3.pdf
- 国交省発表「i-Construction 2.0」2025年度の取組予定を解説!〜 建設現場のオートメーション化による省人化(生産性向上)加速へ!~ | デジコン, 11月 2, 2025にアクセス、 https://digital-construction.jp/column/1895
- 国土交通省における i-Construction 2.0 の推進 – 建設マネジメント技術, 11月 2, 2025にアクセス、 https://kenmane.kensetsu-plaza.com/bookpdf/314/fa_10.pdf
- i-Constructionとは?i-Construction2.0との違い、取り組むメリットとデメリットも解説, 11月 2, 2025にアクセス、 https://kensetsu-data.co.jp/blog/blog_detail.php?id=623
- i-Constructionとは?3つの柱で進化する建設業のICT | 株式会社アスク, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.ask-corp.jp/biz/column/i-construction.html
- BIM/CIMとは - 目的や効果、原則適用について解説 | CAD Japan.com(大塚商会), 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.cadjapan.com/topics/cim/about.html
- BIM/CIM 事例集 ver.1, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/usecase/bimcimExamplesR1.pdf
- BIM CIMの違いと導入メリットを徹底比較|活用場面、国土交通省による推進内容, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.abkss.jp/blog/26
- 国土交通省における BIM/CIMの取組と今後の展開, 11月 2, 2025にアクセス、 https://ocf.or.jp/pdf/cim/seminar2019/OCFseminar2019_1_MLIT.pdf
- BIM/CIMの現状と今後, 11月 2, 2025にアクセス、 https://jacicloud.jp/study/2.torikumi.pdf
- 空からの革新:建築におけるドローンの活用事例とAIが拓く未来|プランテック – note, 11月 2, 2025にアクセス、 https://note.com/plantec/n/n980175285caf
- 建設業でのドローン活用法を紹介!活用事例や導入メリットを徹底解説!, 11月 2, 2025にアクセス、 https://drone-school-navi.com/column/drone-use-purpose-construction/
- 建設業におけるドローン活用|効率アップと省力化による作業効率改善 – Safie(セーフィー), 11月 2, 2025にアクセス、 https://safie.jp/article/post_18815/
- 建築・建設業界におけるAI活用事例20選!施工効率や安全管理に貢献 | ニューラルオプト, 11月 2, 2025にアクセス、 https://neural-opt.com/construction-ai-cases/
- ③ドローン※技術 – 国土交通省, 11月 2, 2025にアクセス、 https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/content/001887571.pdf